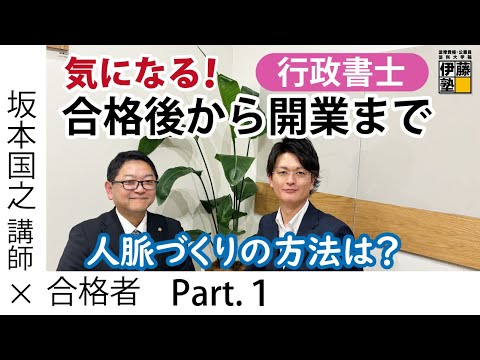行政書士は実務経験ゼロでも大丈夫?必要なスキル・経験を学ぶ5つの方法
キャリア
2025年09月10日

「行政書士試験に合格したけど、実務経験がないまま開業して大丈夫だろうか…」
このような不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
そんな方にまずお伝えしたいのが、法律上、行政書士の開業に実務経験は求められていないということです。実際、多くの先輩が未経験から開業して、現在は最前線でご活躍されています。
とはいえ、実際には実務経験がないことによる心配もあるでしょう。「失敗したらどうしよう」「相談されても自信を持って対応できない…」という悩みは尽きないものです。
そこで、本記事では、実務経験ゼロで開業した方の体験談を交えながら、開業前に身につけておきたいスキルや、経験を積む具体的な方法をご紹介します。
「経験がないから…」と悩んでいる方は、ぜひ最後までお読みください。きっと、あなたの不安を解消するヒントが見つかるはずです。
【目次】
1.行政書士の開業に実務経験は必要?
1−1.開業要件として、実務経験は求められていない
法律上、行政書士として開業するために、実務経験は必要ありません。
同じ士業でも、たとえば税理士の場合、「2年以上の実務経験」が登録要件として定められています。税理士事務所などでの実務経験がなければ、試験に合格しても税理士として登録はできません。
しかし、行政書士にはこのような制限が一切ありません。試験に合格し、各都道府県の行政書士会で登録手続きを完了すれば、すぐに行政書士として業務を開始できます。
実際に、伊藤塾で学ばれた方の中にも、会社員から転職して実務経験ゼロで開業し、現在では専門分野で活躍されている方が数多くいらっしゃいます。
1−2.実務経験ゼロによるリスク・不安はある
とはいえ、実務経験なしでの開業には、やはりリスクや不安が伴います。
実際に開業した方からも、「実務経験がなくて本当に不安だった」「初めて仕事を受けたときは手が震えた」という声をよく聞きます。行政書士として仕事を受けた瞬間から、「プロの専門家」として扱われるため、プレッシャーを感じるのは当然でしょう。
もっとも、リスクという面では、分からない点は役所の担当者に確認したり、先輩行政書士に相談したりすれば解決できるので、そこまで恐れる必要はありません。「まずは飛び込んでみて、やりながら覚えていく」というスタンスで十分でしょう。
それより問題なのが、自信のなさが顧客に伝わってしまうことです。つい、「やったことがないので…」と正直に伝えてしまったり、自信のない対応をしたりして、信頼を失うケースがよくあります。
こうした不安を解消し、自信を持って開業するための準備方法については、4章で詳しく解説します。
2.合格者に聞いた!実務経験ゼロから開業するまでの流れ
ここで、実際に実務経験ゼロから開業された方がどのような流れで開業まで進んだのか、体験談をご紹介します。お話を伺ったのは、伊藤塾で学んで2023年度の行政書士試験に合格された掛水さんです。
合格発表後から開業に至るまでのお話をお聞きしました。
2−1.開業を決意したきっかけ
私は、合格後すぐに開業すると決めていたわけではありません。
しかし、行政書士を進めてくれた先輩から「資格を取ったなら早く始めた方がいい」とアドバイスを受けたことが後押しになりました。
逆に、妻からは「子どもがまだ学校に通っているので会社勤めはやめないでほしい」と言われてしまったので、家庭とのバランスを取りつつ緩やかに開業することにしました。
2−2.合格後、経験ゼロで開業できたのは人脈を広げたから
合格発表後、「どうやって開業していくのか」「実際にどうやって仕事をしていくのか」という点が分かりませんでした。
「周りにヒントがない」と悩んでいたところ、既に開業して5〜10年が経つ先輩方から声をかけていただき、開業のお話を伺うことができました。そのとき、受験勉強と実務の違いなども教えていただきました。
2−3.開業場所はレンタルオフィス
開業時、事務所はどうしようかと悩んでいたのですが、先輩行政書士から「都内の一等地で、2人で事務所を出している」という話を伺いました。「すごいな」と思ってさらに聴いてみたら、はじめは低価格のレンタルオフィスでオープンしたと教えてもらえたのです。
そこで、私も真似をしてレンタルオフィスでスタートしました。そのあたりのアドバイスを、実際に先輩方からもらえたことが、非常に参考になりました。
2−4.合格して次のステップを考えている方へのメッセージ
行政書士試験の勉強と、開業(実務)にはかなりのギャップがあると思います。
ですが、基本的なことは先輩たちに学びながら進めていけば大丈夫です。1段1段、階段を登っていくように進んでみてください。
※こちらの記事もあわせて読まれています。
3.必須ではないが、行政書士の実務で求められるスキル・経験
冒頭でもお伝えしましたが、行政書士として開業するのに実務経験は必要ありません。しかし、できれば開業前に身につけておきたいスキル・知識はあります。
・許認可申請などの基本知識
・マナー、心づかいなどのビジネススキル
・業界特有の慣習、お作法
・マーケティング、経営などの知識や経験
・同業者との人脈
以下、詳しくご説明します。
3−1.許認可申請などの基本知識
まず必要なのが、許認可申請などの基本知識です。
許認可要件の基本的な考え方、必要書類について法令等の何をどのように見ていくべきかなど、土台となる知識は押さえておきましょう。
特に、行政書士実務の「王道」と呼ばれる建設業務などの許認可業務、近年ニーズの高い国際業務、遺言相続業務の基本は押さえておくべきです。開業直後は、幅広いジャンルの仕事を扱うので、どこかのタイミングで相談を受ける可能性が高いです。
完璧である必要はありませんが、「こんなのあったな…」程度の手がかりをもっておくだけで、かなりの安心材料となります。
3−2.マナー、心遣いなどのビジネススキル
知識よりも先に、依頼者が判断するのは「この人に任せて大丈夫か」という安心感です。
清潔感のある見た目、丁寧な言葉遣い、相手の不安に寄り添う姿勢。こうした「マナー」や「心遣い」ができているかどうかで依頼者の印象は大きく変わります。
役所の担当者とのやり取りでも、心遣いのある態度ひとつで、手続きがスムーズになることは多いです。
3−3.業界特有の慣習やお作法、地域性など
できれば、業界特有の慣習やお作法、地域性などにも触れておきたいところです。
法律事務は、法律や規則に書かれた通りにやれば十分と思われがちです。しかし、実際には「暗黙の了解」や「地域性」「お作法」があります。
たとえば、官公署によって求められる書類は違いますし、担当者によって指摘される内容も違います。「同じ申請なのに、都道府県によって許認可の基準が違う…」なんてこともザラにあります。A県ならいけるけど、B県はダメ、といった具合です。
全てを知っておく必要はありませんが、法律の世界でも、こういった慣習・地域性があると知っておけば、実務に出たときに大いに役立ちます。
3−4.マーケティング、経営などの知識や経験
開業する場合は、マーケティング、資金繰りなど、経営者としてのスキルも必要です。
「法律知識」だけでなく「どうやって仕事を得るか」「どうやって利益を残すか」を考えなければ、経営を維持できません。最低限、集客の方法(マーケティング)、資金繰りや損益計算、料金設定の方法などは学んでおきましょう。
行政書士に限った話ではありませんが、「士業だから営業しなくても依頼が来る」という時代はもう終わっています。やってみないと分からない部分はありますが、基本的な知識だけでも開業前に押さえておくべきです。
3−5.同業者との人脈
開業後の行政書士が最も苦労するのは、未知の案件にぶつかったときです。
自分ひとりで解決できない問題に直面したとき、相談できる先輩や同期の存在は大きな助けになります。さらに、同業者同士で案件を紹介し合うケースも多く、ネットワークを持っているかどうかが収入にも直結します。
支部の勉強会や懇親会、SNSでの交流を通じて、同世代の仲間や経験豊富な先輩とつながりを作っておきましょう。特に、同じタイミングで合格した同期とのつながりは、互いに成長できる関係になりやすく、一生の財産になります。
こうした人脈は一朝一夕では築けないため、開業前から少しずつ広げておきましょう。
※こちらの記事もあわせて読まれています。
4.行政書士が実務で必要なスキル・経験を身につける方法は?
ここまで、行政書士が開業前に身につけておきたいスキル、知識を紹介しました。では、上記のようなスキル、経験はどのように身につけていけばいいのでしょうか。
主に、次の5つの方法が考えられます。
以下の表で、それぞれの方法でどんなスキルが身につくかを整理しました。それぞれの方法について、さらに詳しく説明します。
| 許認可申請 などの 基本知識 |
マナー・ 心づかい |
業界慣習 ・お作法 |
経営者 スキル |
同業者 との人脈 |
|
| 事務所で働く | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ |
| 書籍・手引き で学ぶ |
△ ※理解の補助 にはなる |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 行政書士会の 研修を受ける |
◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ |
| 受注してみる | △ ※断片的に 身につく |
△ ※徐々に 身につく |
△ ※徐々に分 かっていく |
✕ | ✕ |
| 先輩から 教わる |
△ ※部分的 に聞ける |
✕ | ◯ | △ ※断片的 に学べる |
◯ |
4−1.行政書士事務所で働く
まず考えられる方法が、行政書士事務所で働くことです。
行政書士事務所のスタッフとして採用されれば、許認可申請の基本から接客、慣習まで、実践的なスキルを学べます。同業者との人脈ができるのも大きなメリットでしょう。
欠点は、求人数が少ないことです。そもそもスタッフを募集している事務所自体が少なく、条件にあった求人を見つけるのは簡単ではありません。
なお、もし開業する意思があるなら、応募時に必ず伝えておきましょう。ほとんどの事務所は、「新人に修行させたい」と考えているのではなく、長期的に働けるスタッフを求めています。開業の意思を隠して応募すると、後々トラブルになり信用を失ってしまいます。
4−2.書籍やインターネットを活用する
建設業許可の手引きや相続手続きのマニュアル本など、専門書は数多く出版されています。
さらに、許認可申請によっては、所管する都道府県が許認可申請の手引きを出している場合もあります。これらを活用すれば基本的な知識は身につくでしょう。
ただし、実務経験がない状態で書籍やネットの情報を読んでも、「結局どうすればいいの?」という壁にぶつかるケースが多いです。
あくまでも、実務に取り組むときの補助として考えるのをおすすめします。
4−3.行政書士会の研修に参加する
行政書士会や支部が開催する研修は、実務に直結する内容が多いです。
特定分野の第一人者や、実務の最前線で活躍されている方など、普段会えない方から直接話を聞けるチャンスがあります。同じ地域の先輩行政書士と知り合える機会にもなります。
ただし、行政書士として登録・開業していないと参加できない研修がほとんどです。開催頻度も限られているため、自分が学びたいタイミングで受講できるとは限りません。
4−4.先輩行政書士に教えてもらう
近くに相談できる先輩行政書士がいれば、その人に教えてもらうのが一番でしょう。
もっとも、信頼できる師匠(メンター)を見つけて、教えを乞うには時間がかかります。支部の研修や懇親会に参加すれば、実績ある行政書士には会えますが、忙しい先輩方にとって、新人を指導する時間を割くのは簡単ではありません。
「教えを乞いたい」という人が見つかったら、ぜひ自分から積極的に貢献してみてください。時間をかけて信用を積み重ね、「この人なら教えてもいい」と思ってもらえるような努力が必要です。
教えてもらえるまでに、ある程度の時間がかかることは覚悟しておきましょう。
4−5.まずは1件受注して、実務をこなしながら覚える
もっとも手っ取り早いのは、「習うより慣れろ」の精神で、とにかく1件受任してみることです。実際、多くの先輩行政書士がこの方法で実務経験を身につけています。
分からないことは行政庁の担当者に確認したり、支部の先輩に相談したりしながら進めれば、致命的なミスは避けられるでしょう。
ただし、どうしても経験がない状態で実務をこなすことになるため、プレッシャーは相当なものです。
以上、5つの方法をご紹介しました。お気づきのとおり、どれも一長一短です。
できれば、行政書士事務所に就職して経験を積むのが望ましいですが、先ほどご説明したとおり、求人数はあまり多くありません。
就職せずに経験を積もうとしても、そもそも行政書士として登録・開業していないと、研修に参加できず、受任もできないのでできることは限られています。
そこで、そのような合格者の方々の声を受けて開講したのが、伊藤塾の行政書士実務講座です。
5.実務が不安な方におすすめなのが伊藤塾の行政書士実務講座
行政書士実務の不安を払しょくし、実務に向けてしっかりと準備をしたいと考えている方におすすめなのが、伊藤塾の「行政書士 実務講座」です。
「行政書士実務講座」では、約1年間じっくりと時間をかけて、行政書士実務に必要となる基礎知識から、最新の情報や技能、対応力までを幅広く、実践的に学んでいきます。
行政書士実務の「王道」と呼ばれる建設業務を中心とする許認可業務はもちろん、近年ニーズの高い国際業務、遺言相続業務など幅広い分野を学習していきます。実務講座で身につけた行政書士実務の確かな「基礎知識」と「柔軟な対応力」をもってすれば、安心して業務対応することができることでしょう。
また、行政書士実務の知識以外で、事務所の経営やマーケティング、更にマナーについて、実際に開業し収益を上げていく方法についても学んでいきますので、独立・開業した際の事務所経営面についての不安も解消することができます。
さらに、質問会やスクーリング、懇親会等を通じて、これから開業していく上での仲間づくりや、先輩実務家とのネットワークも構築していくことができます。
行政書士試験に合格後、不安なく独立・開業を始め、スタートダッシュをかけたいとお考えの方は、ぜひ、伊藤塾の「行政書士 実務講座」をご活用ください。
※2026年 行政書士実務講座≪15期≫は、2025年11月より募集開始予定です。開講まで、今しばらくお待ちください。下記動画は、2025年行政書士実務講座≪14期≫の説明動画です。実務講座に興味をお持ちの方は「参考」としてご視聴ください。
6.行政書士の実務経験がなくても安心して独立・開業できる方法とは
本記事では、行政書士として開業するにあたり、実務経験は必要なのか、また身につけておくと良いスキルや経験について解説しました。
以下にポイントをまとめます。
◉行政書士として開業するにあたり、法律上、実務経験は必須ではありません。
◉開業前に、必須ではないものの身につけておくと良いとされるスキルや経験は以下の通りです。
・許認可申請などの基本知識
・マナー、心遣いなどのビジネススキル
・業界特有の慣習やお作法、地域性
・マーケティング、経営などの知識や経験
・同業者との人脈
◉これらのスキルや経験を身につける方法としては以下の5つの方法が考えられます。
・行政書士事務所で働く
・書籍やインターネットで学ぶ
・行政書士会の研修に参加する
・先輩行政書士に教えてもらう
・まずは1件受注して実務をこなしながら覚える
◉しかし、どの方法にも一長一短があり、特に行政書士として登録・開業していないと参加できない研修や、受任ができないといった制限があります。
◉実務経験ゼロの不安を解消し、開業に向けてしっかりと準備をしたい方には、伊藤塾の「行政書士 実務講座」が特におすすめです。本講座を受講することで、以下の知識やスキルが得られます。
・約1年間かけて、行政書士実務に必要となる基礎知識から最新の情報や技能、対応力までを幅広く、実践的に学習できます。
・行政書士実務の「王道」である建設業務や、近年ニーズの高い国際業務、遺言相続業務など、幅広い分野の実務を体系的に学べます。
・事務所の経営やマーケティング、マナーについても実践的に学ぶことができ、独立・開業後の経営面に関する不安も解消されます。
・質問会やスクーリング、懇親会等を通じて、これから開業する仲間や先輩実務家との貴重な人脈やネットワークを構築することができます。
以上です。
行政書士試験に合格後、不安なく独立・開業を始め、スタートダッシュをかけたいとお考えの方は、ぜひ、伊藤塾の「行政書士 実務講座」の受講をご検討ください。
※2026年 行政書士実務講座≪15期≫は、2025年11月より募集開始予定です。開講まで、今しばらくお待ちください。