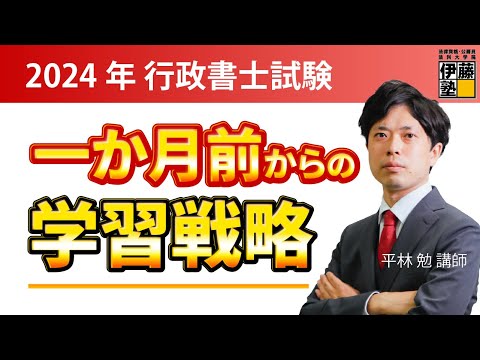行政書士試験の持ち物リスト&当日の疑問を一気に解消するQ&A
試験詳細
2025年10月08日


行政書士試験の当日。受験票を忘れて焦ったり、腕時計の電池が切れていて時間配分に苦労したり、会場の空調が寒すぎて集中できなかったり…。
そんな「防げたはずのトラブル」で、実力を発揮しきれなかったという声は少なくありません。
そこでこの記事では、行政書士試験に必要な持ち物を分かりやすくまとめました。前日と当日朝にこの記事で確認すれば、忘れ物の心配はゼロになります。
さらに、あると便利な持ち物や、当日の服装、昼食の取り方など、知っておくと役立つポイントも具体的に解説します。
初めて受験する方も、再チャレンジの方も、ぜひ最後までお読みください。
【目次】
1.【一覧】行政書士試験の当日に必要な持ち物リスト
行政書士試験の当日に必要な持ち物を、ひと目で分かるリスト形式でまとめました。
試験の前日にこのリストを見ながら準備をすれば、当日は安心して試験に臨めます。
■行政書士試験で必須の持ち物
・受験票
・筆記用具
・腕時計
・本人確認書類
・(土足厳禁の試験会場のみ)「上履き」と「下履きを入れる袋」
■行政書士試験であると便利な持ち物
・使い慣れたテキスト、要点ノートなど
・問題用紙に使う蛍光ペン
・マスク、ハンカチ、ポケットティッシュ
・飲み慣れた薬
・ひざ掛け・上着など体温調節できるもの
・飲み物や昼食
1−1. 行政書士試験で必須の持ち物
行政書士試験で必須の持ち物は、受験票・筆記用具・腕時計・本人確認書類・(土足厳禁の試験会場のみ)「上履き」と「下履きを入れる袋」、などです。
● 受験票
当日の試験会場(◯号講義室など)や、受験する席は、受験票の番号に沿って決められています。忘れても受験はできますが、本人確認が必要になります。
何より、受験票を忘れたという焦りや不安が、当日のパフォーマンスに大きく影響してしまいます。前日の夜にカバンに入れたら、朝もう一度確認しておきましょう。
● 筆記用具
行政書士試験では、BまたはHBの黒鉛筆(シャープペンシル可)とプラスチック製の消しゴムが指定されています。
鉛筆を使うなら最低でも2本、できれば3本以上は用意しておくと安心です。
シャープペンシルを使う場合は、替え芯も忘れずに持参しましょう。消しゴムも2個以上準備しておけば、落としたり紛失したりしても慌てずに済みます。
● 腕時計
試験室内に時計の用意はないので、腕時計は必須アイテムです。
おすすめは、シンプルなアナログ時計です。試験中は脳にかなりの負荷がかかるので、一目で時間が分かるものを選びましょう。電池が切れかかっていないか、遅れが発生していないか等も確認が必要です。
なお、スマートウォッチや計算機能付きの時計などの使用は固く禁止されています。
◉チェックポイント
「時計の使い方も工夫できる」
腕時計は、試験開始時刻である「13時00分」に合わせて使うのが基本です。
ただ、合格者の中にはあえて「0時00分」にセットして使うという人もいました。0時から始めると、時計をちらっと見ただけで「今、試験開始から何分経ったか」が分かり、時間の計算で頭を使わずに済む、というのが理由だそうです。
人によって合う・合わないがある方法ですが、もし興味があれば模試などで試してみるのも良いでしょう。
● 本人確認書類(運転免許証など)
万が一、受験票を紛失したり、忘れたりした場合は、本人確認書類(運転免許証等)が必要となります。運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、公的機関が発行したものを持参しましょう。
● 土足厳禁の試験会場のみ、「上履き」と「下履きを入れる袋」
試験場によっては、土足が禁止されている場合があります。土足厳禁の試験場で受ける方は、スリッパなどの室内履きと、脱いだ靴を入れるためのビニール袋を持参しましょう。
土足厳禁の試験場は、「一般財団法人行政書士試験研究センター」のホームページに明記されています。
※令和7年度試験では、山陽学園中学校・高等学校(岡山県)、高知中学高等学校(高知)が対象です。
1−2. あると差がつく!便利な持ち物
ここからは、必須ではありませんが、本番で実力を発揮するのに役立つアイテムを紹介します。
● 使い慣れたテキスト、要点ノートなど
試験開始前の休憩時間に、最終確認をするための教材を持参しましょう。
持っていく教材は、「これさえ見れば安心できる」というものに絞り込むことが大切です。
あまり多くの教材を持参しても、限られた時間では見きれません。自分が最も使い込み、要点がまとまっているテキストや自作のノートなどを1〜2点だけ選んで持っていきましょう。
● 問題用紙に使う蛍光ペン
蛍光ペンも、ぜひ持参して活用しましょう。ケアレスミスを防ぎ、「+4点〜8点」を確保するための非常に有効なアイテムです。
最近の行政書士試験は、「妥当なものはどれか」という問題と、「妥当でないものはどれか」という問題が混在しており、受験生のミスを誘発するつくりになっています。おそらく、答練などで問題文の読み間違いによる失点を経験した人も多いはずです。
マーカーを使って、自分なりの色分けルール(例:肯定文はピンク、否定文は黄色など)を作っておくと、問題を視覚的に把握できるので、問題文の読み間違いによる失点を防げます。
ただし、本番でいきなり使うのではなく、普段の勉強や模試の段階から、やりやすい方法を試しておきましょう。
● マスク、ハンカチ、ポケットティッシュ
マスクやハンカチ、ティッシュは、基本的なエチケットであると同時に、試験中の集中力を維持するためのアイテムです。会場の空調による乾燥や、不意の咳、くしゃみ、鼻水などでペースを乱されないように準備しておきましょう。
● 飲み慣れた薬
試験という特別な環境では、極度の緊張から頭痛や腹痛が起きることがあります。
そのような事態に備え、普段から飲み慣れている薬を持参しておきましょう。あくまで「お守り」として持っておくだけでも、精神的な負担が軽くなります。
ただし、試験当日に初めて飲む薬は、予期せぬ副作用が出る可能性もあるので避けてください。
● ひざ掛け・上着など体温調節できるもの
試験会場の空調は、席によって効き方が違うことが多く、席によって暑いと感じたり、寒いと感じたりするケースがあります。
対策として、カーディガンやパーカーなど、着脱しやすい上着を一枚持っていくことをおすすめします。足元の冷えが気になる方は、ひざ掛け(ブランケット)もあるとよいでしょう。
● 飲み物や昼食
飲み物や昼食(会場で取る場合のみ)は、事前に準備して持参しましょう。会場周辺の飲食店やコンビニは混雑が予想されます。
なお、昼食を食べる時間やメニューは、模試などで一度試しておきましょう。
「試験の何時間前に食べたら眠気が出ないか」「何を食べるのがよいか」など、本番と同じ状況で確認しておくと、当日最大のパフォーマンスを発揮できます。
1−3. これはNG!使用や着用が禁止されているもの
行政書士試験では、以下のものの使用や着用が禁止されています。
・スマートフォンやスマートウォッチなどの電子機器
・六法
・帽子やフード
・耳栓 など
これらのルールを守らないと、最悪の場合、不正行為と見なされ失格になることもありますので、十分注意してください。
2.行政書士試験当日の行動スケジュール
持ち物の準備が整ったら、当日の行動スケジュールも具体的にイメージしておきましょう。
当日午前中の過ごし方、会場到着から試験開始までの過ごし方、試験中のルール、試験後の流れなどに分けて、それぞれ説明します。
2−1. 当日午前中の過ごし方
試験当日の朝は、普段通りに起床し、いつも通りのリズムで過ごすことが大切です。
特別なことをしようとすると、かえって緊張が高まってしまいます。朝食は消化の良いものを適量とり、エネルギー補給をしっかり行いましょう。
稀に、午前中にしっかり勉強するつもりの人もいますが、基本的にはできないと思っておいたほうがいいでしょう。会場までの移動時間、到着時刻などを考えると、思ったほど時間がとれないケースが大半です。
何より、本番までに疲れてしまうと本末転倒です。勉強するとしても1〜2時間程度、使い慣れたテキストで軽い復習をする程度にとどめましょう。
2−2. 到着から試験開始までの過ごし方(トイレ・最終確認)
会場には、集合時間の30分前から1時間前に到着するのが理想的です。
早めの到着を心がければ、交通機関の遅延や会場の混雑といった不測の事態にも対応できます。精神的な余裕を持つことで、落ち着いて試験に臨めるというメリットもあります。
会場に着いたら、まずトイレの場所を確認し、試験開始前に必ず済ませておきましょう。
試験開始までは使い慣れたテキストで最終チェックをする人が多いです。ただ、「勉強は一切しない」と決めて心を落ち着かせるのも1つのやり方です。
2−3. 試験時間中のルール(途中退室など)
行政書士試験では、試験開始後の90分と試験終了前の10分間は途中退室できません。
つまり、基本的にトイレによる途中退室が認められるのは、14時30分〜15時50分までの80分間のみです。
ちなみに、試験中にトイレに行くかは人によって異なります。
試験時間を最大限に使うためにできるだけ行かないと決めている人もいますし、行き詰まったときなどに、トイレに行って深呼吸をする人もいます。
2−3−1. 机上に置けるもの、カバンにしまうもの
試験中に机上に置けるのは以下のものだけです。
【机上に置けるもの】
・受験票
・筆記具
・プラスチック消しゴム
・鉛筆削り
・蛍光ペン
・腕時計(懐中時計を含む)
・マスク
・ハンカチ
・ポケットティッシュ
・目薬及び点鼻薬
特に、スマートフォンは、電源を完全に切ってから、配布される封筒に入れる必要があります。
マナーモードでも振動音が鳴ると、不正行為とみなされる可能性があるので注意してください。
カバンは座席の下や指定された場所に置きます。試験中は触れないので、必要なものは事前に机上に準備しておきましょう。
2−4. 行政書士試験終了後の流れ(正解発表・自己採点など)
試験が終わったら、問題用紙は持ち帰って自己採点に使えます。
試験問題の正解は、試験日から1〜2週間後に、一般財団法人行政書士試験研究センターのホームページに掲載されるのがここ数年の流れです。
ただ、当日の夜には、受験指導校などが解答速報を公開するケースが多いです。
複数の解答を参考にすれば、ある程度正確な自己採点ができるでしょう。なかには、成績診断サービスを提供している指導校もあるので、他の受験生と比べてどうだったのかなども確認できます。
正式な合格発表は例年1月下旬、令和8年試験では「1月28日(水)」の予定です。
※伊藤塾の本試験択一成績診断はこちらから事前登録できます。
3.持ち物以外で受験生が気になるQ&A9選
最後に、多くの受験生が共通して抱く持ち物以外の細かい疑問について、Q&A形式で回答します。試験当日の不安を少しでも減らすために、ぜひ参考にしてください。
Q. 試験当日の服装は何を着ていけばいいですか?
試験当日の服装は、普段着慣れているリラックスできる服装がベストです。
席によって空調の効き方が違うケースもあるので、自分で体温をコントロールしやすいような工夫もあるとよいでしょう。たとえば、脱ぎ着しやすいカーディガンやパーカー、シャツの重ね着などがおすすめです。
スーツである必要は全くありませんので、最も試験に取り組みやすい服装を選んでください。
Q. 午前中の過ごし方はどうすればいいですか?
リラックスすることを最優先し、新しい知識を詰め込むのは避けましょう。
試験当日に新しい問題に触れると、かえって知識が混乱し、精神的な焦りを生む原因になります。
いつも通りの時間に起きて、消化の良い朝食をとる。そして、これまで自分が使い込んできたテキストやまとめノートを軽く見返す程度に留め、「これだけやってきたんだ」と自信を持って会場に向かいましょう。
Q. 昼食は何を食べるのがおすすめですか?
A. 午後の試験で眠くならないよう、消化が良く手軽に食べられるおにぎりなどがおすすめです。満腹になるまで食べるのは避け、腹八分目に抑えることが大切です。
また、直前に食べると眠気が出やすいので、模擬試験などで「何を・何時間前に食べる」と最もパフォーマンスが良いかをチェックしておきましょう。
Q. 会場で配られる予想問題は見るべきですか?
A. 試験会場の入口などで、予想問題が配布されていますが、基本的に見る必要はありません。当日知らない問題を見ても、自信をなくしたり、知識が混乱したりするだけだからです。
これまで自分が信じて使い込んできた教材を見直すだけで十分です。周りがもらっていても気にせず、自分のペースを貫きましょう。
Q. 会場にはどの教材を持っていくべきですか?
A. 要点をまとめたノートや判例六法、使い込んだテキスト1〜2冊などに絞って持参しましょう。
多くの教材を持ち込んでも、限られた休憩時間ですべてを見ることは不可能です。かえって「あれも見なきゃ、これも確認しなきゃ」と焦りを生む原因になります。
理想的なのは、「これを見れば全体を思い出せる」という自分だけの最終確認ツールです。
暗記事項をまとめたノートや、苦手分野の要点集など、短時間で効率的に確認できるものを選びましょう。
Q. 試験会場は下見に行くべきですか?
A. 下見は必須ではありませんが、心配な人は一度会場の最寄り駅などまで行って、ルートや所要時間を確認しておくと良いでしょう。当日の精神的な余裕につながります。
ただし、試験会場の敷地内や建物の中の下見は禁止されていますので、絶対に行わないでください。
Q. 試験中、本当にマーカーを使ってもいいのですか?
A. はい、問題用紙へのマーカーの使用は認められています。
行政書士試験研究センターの公式ページにも、「その他持参し、試験時間中に使用することができるもの」として、「問題用紙に用いる蛍光ペン(複数使用可)」とはっきりと記載されています。
ただし、解答用紙(マークシート)へのマーカー使用は禁止されていますので、絶対に行わないように注意してください。
(出典:行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験のご案内」)
Q. 本試験問題の正解はいつ分かりますか?
A. 例年、試験日から2週間程度で行政書士試験研究センターのホームページに公開されます。
ただし、実際には試験当日の夜から1週間ほどで、各受験指導校が「解答速報」を公表することが多いです。これらはあくまで参考解答なので、指導校によって解答が割れることもありますが、大まかな目安にはなります。
Q. 自己採点はどのタイミングですればいいですか?
A. 自己採点は、試験当日の夜から数日中に、受験指導校の解答速報などで行う人が多いです。
ただし、当日はとても疲れているので、自分を労ってあげることも必要です。
当日はゆっくり休んで、自分を労ってあげた後、記憶が新しいうちに自己採点まで終わらせましょう。
4.行政書士試験まで残り一か月の学習戦略とは?
最後に、行政書士試験まで残り一か月の学習戦略を伊藤塾行政書士試験科の平林講師による解説をお届けします。
1ヶ月前〜2週間前、2週間前〜1週間前、1週間前〜2日前、試験前日などに細分化して、試験までの学習の組み立てやポイント、当日の流れなどもお伝えします。動画は2024年試験に向けたものですが、年度による大きな違いはありません。
試験当日、最高のパフォーマンスを発揮するために、初受験・経験者問わず是非ご覧ください。
5.行政書士試験の持ち物&当日の疑問 まとめ
本記事では、行政書士試験当日に実力を発揮するために必要な持ち物リスト、あると便利なアイテム、および当日の行動スケジュールやルールについて解説しました。
以下に本記事のポイントをまとめます。
- 必須の持ち物と注意点
行政書士試験で必須の持ち物として、受験票、筆記用具(BまたはHBの黒鉛筆/シャープペンシルとプラスチック製消しゴム)、腕時計、本人確認書類が挙げられます。特に、スマートウォッチや計算機能付きの時計の使用は固く禁止されています。また、試験場によっては「上履き」と「下履きを入れる袋」が必要です。 - 便利な持ち物
試験中に実力を発揮するために、使い慣れたテキストや要点ノート(1〜2点に絞る)、問題用紙に使う蛍光ペン、ひざ掛けや上着など体温調節ができるもの、飲み慣れた薬、飲み物や昼食(腹八分目の量)などを持参することが推奨されます。 - 禁止されているもの
スマートフォンやスマートウォッチなどの電子機器、六法、帽子やフード、耳栓などの使用・着用は禁止されています。スマートフォンは電源を完全に切ってから、配布される封筒に入れる必要があります。 - 試験当日の行動
当日は普段通りに起床し、消化の良い朝食を適量とり、リラックスすることを最優先にします。会場には集合時間の30分前から1時間前に到着することが理想的です。 - 試験中のルール
試験中に机上に置けるのは、受験票、筆記具、消しゴム、鉛筆削り、蛍光ペン、腕時計、マスク、ハンカチ、ティッシュ、目薬、点鼻薬などに限定されます。 - 途中退室
試験開始後の90分間と終了前の10分間は途中退室できません。トイレによる途中退室が認められるのは、基本的に14時30分から15時50分までの80分間のみです。 - 直前の学習
当日、会場などで配布される予想問題は見る必要はなく、これまで使い込んだテキストやまとめノートを軽く見返す程度に留めましょう。 - 自己採点
試験終了後、問題用紙は持ち帰ることができ、正解は試験日から1〜2週間後に公表されますが、当日の夜には受験指導校が解答速報を公開することが多いです。自己採点は記憶が新しいうちに行いましょう。
行政書士試験で最高のパフォーマンスを発揮するために、当日の準備を万全に行うことはもちろん大切ですが、合格を確実なものとするためには日々の効率的な学習戦略が不可欠です。
過去10年間で4,000名を超える行政書士試験合格者を輩出するなど、法律系難関資格で圧倒的な実績を誇る伊藤塾では、2025年行政書士試験を受験する方に向けて「直前対策講座」を開講中です。
また、2026年行政書士試験を受験予定の方向けの「2026年合格目標!行政書士 合格講座」では、初めて法律を学ぶ方から、法律学習経験者まで、それぞれのレベルに合った講座を選択でき、戦略的カリキュラムと、質問制度・スクーリングなど充実したフォロー体制で、合格までしっかりと伴走します。
本気で合格を目指す方は、ぜひ伊藤塾への入塾をご検討ください。
伊藤塾は、あなたのチャレンジを力強くサポートさせていただきます。