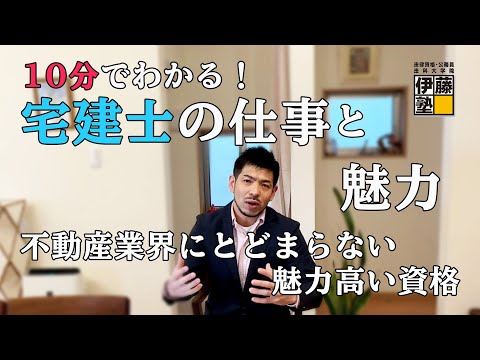宅建士は仕事がないって本当?将来性や資格の活かし方を解説
キャリア
2025年09月04日


国家資格の中でも人気が高い宅建士ですが、一方で「宅建士の資格を取っても仕事がない」「資格を持っていても就職や転職に役立たない」という声を聞いたことがあるかもしれません。
確かに、資格取得者が増えたことや不動産業界の特性から、そのような印象を持たれやすい面はあります。
しかし実際には、不動産取引を行う上で宅建士は欠かせない存在であり、将来性も十分にある資格であることは間違いありません。
本記事では、「宅建士は仕事がない」と言われる理由や、資格の価値や将来性、さらに宅建士として活躍し続けるためのポイントまで詳しく解説していきます。
【目次】
1.宅建士は仕事がないと言われる理由
宅建士は不動産取引に欠かせない資格ですが、一部では「意味がない」「仕事がない」などと言われることもあります。その背景を理解しておくことで、資格の実際の価値を正しく判断することができます。
1-1. 資格取得者が多く希少性が低い
宅建士は国家資格の中でも合格者数が多く、登録者数は100万人を超えています。そのため、他の難関資格のように「取得者が少ないから特別扱いされる」という状況にはなりにくいのが現実です。
背景として、毎年約3万人が新たに合格しており、資格保持者は年々増加しています。資格保持者が多い分、企業から見れば「宅建士資格は持っていて当然」という認識になりやすいといえるでしょう。
例えば、不動産会社の求人を見ると「宅建士必須」と記載されているケースは数多くありますが、「資格を持っているだけで給与が大幅に上がる」といった条件は少なくなっています。資格があることで応募の最低条件を満たせても、それ自体が大きな差別化につながらないことが多いのです。
1-2. 資格を取得しただけでは評価されにくい
宅建士の資格は不動産取引に欠かせませんが、取得しただけで高く評価されるわけではありません。不動産業界では「資格を持っていること」がスタートラインであり、即戦力と見なされるには実務経験やスキルが求められます。
例えば、不動産会社の営業職では、顧客と信頼関係を築くコミュニケーション力や、契約をまとめる交渉力が成果に直結します。資格を持っていても、実際に顧客対応や契約手続きを経験していなければ、現場では戦力として十分に評価されにくいのが現実です。
このように、宅建士資格は業界で働くうえでの大きな武器ではあるものの、資格だけでは十分に力を発揮できません。現場で経験を積み、実務スキルを磨いてこそ、その真価を活かせる資格だと言えるでしょう。
1-3. AI・IT化による将来への不安
不動産業界でもAIやITの導入が進んでおり、物件検索システムや自動応答チャット、電子契約の仕組みが広がっています。このような変化を受けて、「宅建士の仕事もいずれAIに奪われるのでは」と心配する声があります。
特に、不動産の契約書作成や物件情報の管理などはシステム化によって効率化されやすく、従来のように人が行っていた作業の一部が不要になるのではないかと懸念されています。
さらに、2022年の法改正で重要事項説明や契約書の交付に電子化が認められたことで、「人が直接対応しなくてもいいのではないか」という印象を持つ人も増えました。
このように、IT化や電子化の進展によって宅建士の役割が縮小してしまうのではないか、という将来への不安が「宅建士は仕事がない」と言われる一因になっています。
2.宅建士が将来性ある魅力的な資格である5つの理由
宅建士は「仕事がない」と言われることもありますが、実際には今後も必要とされ続ける魅力ある資格です。ここでは、宅建士が将来性を持つと言える5つの理由を解説します。
2-1. 不動産業界の需要が安定している
宅建士が将来性を持つ大きな理由は、不動産業界そのものの需要が安定している点にあります。
不動産の売買や賃貸は、人が生活する上で欠かせない取引です。人口減少が進んでいる日本でも、都市部では再開発や新築住宅の需要が続いており、地方でも相続や住み替えに伴う不動産取引が発生しています。つまり、不動産取引は景気の影響を受けやすい部分はあるものの、完全になくなることはないということです。
不動産取引の場面では必ず専門的な知識を持つ人材が必要になるため、宅建士の存在が欠かせません。
このように、不動産は生活インフラに近い性質を持つため、取引を支える宅建士の需要も安定的に続いていくと言えるのです。
2-2. 空き家問題や配置義務により宅建士の需要が拡大
宅建士の需要が高まっている背景には、社会的な課題と法律上の仕組みの両方があります。
まず大きな要因が「空き家問題」です。総務省の住宅・土地統計調査によると、日本の空き家率は右肩上がりに増加しています。
空き家は防犯や景観の問題を引き起こすため、売却や賃貸に出す動きが広がっています。こうした空き家取引の仲介や管理を担える宅建士へのニーズは今後さらに強まるでしょう。
加えて、不動産会社には「従業員5人につき1人以上の専任の宅建士を置かなければならない」という配置義務が宅建業法で定められています。社員数20人の会社であれば最低4人の宅建士が必要となるため、企業は常に資格者を確保し続けなければなりません。
このように、社会問題としての「空き家対策」と法律による「配置義務」の両面から、宅建士の需要は拡大傾向にあります。宅建士資格を持っていれば長期的に必要とされ続ける人材になれるのです。
2-3. 不動産取引に必須の独占業務がある
宅建士が将来性を持つ最大の理由は、法律で定められた独占業務を担っている点です。
宅建士には、不動産取引における「重要事項説明」と「契約書への記名」という二つの独占業務があります。重要事項説明とは、不動産の購入者や賃貸住宅の借主に対して、物件の権利関係や法的制限、周辺環境など取引に影響する重要な情報を説明する業務です。
例えば、土地に建築制限があることを説明しなかった場合、購入後に買主が家を建てられず大きな損害を被るケースも考えられます。
こうした事態を防ぐために、宅建業法は宅建士に説明を義務付けており、顧客は資格者による説明を受けて安心して契約できるようになります。
このように、不動産取引の公正さと安全性を担保する役割を担うのが宅建士です。独占業務が存在する限り、宅建士の必要性がなくなることはなく、資格の価値は今後も続いていくことになるでしょう。
※宅建士の独占業務については、こちらの記事で詳しく解説しています。
2-4. 幅広いキャリアに応用できる
宅建士の資格は不動産会社だけでなく、金融・建設・保険など多くの分野で活かすことができます。宅建士が学ぶ不動産関連の法律や契約知識は、不動産業界以外でも評価されやすいからです。
例えば、銀行では住宅ローンを扱う部署があり、顧客に融資を行う際に不動産の知識を持つ担当者は信頼されやすくなります。保険会社や建設会社でも、不動産取引に関わる知識は顧客への提案に役立ちます。
宅建士は「不動産会社で働くための資格」という枠を超えて、幅広いキャリアの可能性を広げてくれる資格です。将来の転職やスキルアップを考えたときにも、大きな武器となります。
※こちらも読まれています。
2-5. 独立・開業にもつながる
宅建士の大きな魅力の一つは、資格を活かして独立や開業を目指せることです。
不動産会社で経験を積んだ後に、自分で事業を立ち上げる道を選ぶ人も少なくありません。売買仲介や賃貸仲介、物件管理など、宅建士の知識を土台に幅広いビジネスモデルを組み立てることが可能です。資格を持っていれば信用力も高まり、取引先や顧客からの信頼を得やすくなります。
例えば、大手不動産会社で培った営業スキルをもとに、地元で独立して地域密着型の不動産事業を展開することも可能でしょう。独立後は、自らの裁量で経営方針を決められ、地域のニーズに合わせた柔軟なサービスを提供することもできます。
宅建士は会社員として働くだけでなく、自分で事業を起こす選択肢を持てる点で、将来性の高い資格といえます。キャリアの幅を広げたい人にとって、独立可能性は大きな魅力になるでしょう。
※宅建士の独立開業については、こちらの記事で詳しく解説しています。
3.宅建士として長期的に活躍するための重要ポイント
宅建士の資格を取得しても、それだけでその後の活躍が約束されるわけではありません。資格をどう活かし、どのように成長していくかが重要です。
ここでは、宅建士として長期的に活躍するための3つのポイントを紹介します。
3-1. 営業スキルやコミュニケーション力を磨く
宅建士として安定した成果を出すためには、資格の知識だけでなく営業力や対人スキルが欠かせません。
不動産取引は高額であり、顧客は大きな不安を抱えています。そのため「この人なら任せられる」と思ってもらえる信頼関係を築くことが重要です。顧客の要望を丁寧に聞き取り、適切な物件や契約プランを提案できる力が成果につながります。
例えば、同じ条件の物件を紹介しても、説明の仕方や対応の細やかさによって契約が決まるかどうかは大きく変わります。
顧客の立場に立ち、不安を一つずつ解消する姿勢が長期的な信頼とリピートにつながります。
3-2. ITスキルやデジタルツールを活用する
近年の不動産業界では、IT化やオンライン化の流れが急速に進んでいます。
国土交通省の規制緩和によって、重要事項説明もオンラインで実施できるようになり、電子契約の普及も拡大しています。これらに対応できる人材は企業にとって大きな戦力となります。
例えば、顧客がスマートフォンで契約を完結させたいと希望する場合、デジタルツールを使いこなせる宅建士であればスムーズに対応できます。
一方、ITに不慣れな担当者だと業務効率が落ち、顧客満足度の低下にもつながりかねません。
今後は不動産DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進も加速すると予想されるため、ITスキルを習得しておくことは宅建士として長く働くための必須条件と言えるでしょう。
3-3. ダブルライセンスで専門性を磨く
宅建士の資格を基盤に、関連する資格を組み合わせることで専門性を高め、長期的なキャリアを築くことができます。
不動産は法律・税金・資産運用など多方面に関わる分野です。そのため、ファイナンシャルプランナー(FP)、賃貸不動産経営管理士、マンション管理士、不動産鑑定士などの資格を併せて取得すると、顧客に総合的な提案ができるようになります。
例えば、FPを取得すれば、相続に伴う不動産売却の場面で取引をサポートするだけでなく、税金や資産運用の相談にも対応できます。顧客にとって「ワンストップで頼れる存在」となれば、他の宅建士との差別化につながります。
宅建士を起点にダブルライセンスを組み合わせることで、将来のキャリアの選択肢を広げ、安定した専門職として活躍できる可能性が高まります。
※宅建士のダブルライセンスについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
4.スムーズに宅建士資格を取得したいなら伊藤塾の「宅建士合格講座」がお勧め
宅建士試験に合格するためには効率的な学習が欠かせませんが、独学では学習範囲が広く、途中で挫折してしまう人も少なくありません。その点、伊藤塾の「宅建士合格講座」は、初学者から再挑戦者まで幅広く対応できるカリキュラムが用意されており、効率的に合格を目指すことができます。
講座には標準的に全科目を学べる「スタンダードコース」、特に難易度の高い権利関係(民法)の講義を強化した「スタンダードコースプラス」、そして法律知識をすでに持っている人向けの「法律既修者コース」の3種類があり、自分の学習状況に合わせて選択できます。
講義は一コマ約30分とコンパクトで、2倍速再生にも対応しており、通勤や移動中のスキマ時間を活用して効率的に学習できます。
また、過去問演習や模擬試験を通じて実践力を高める仕組みが整っており、さらにアプリを使った一問一答形式の学習や、オンライン質問会・個別カウンセリングなどのサポート体制も充実しています。
大手受験指導校ならではの分析に基づいた出題傾向の解説と、疑問を解消できるフォロー環境によって、合格に必要な知識を無理なく積み上げられるのが特徴です。
短期間で確実な合格を目指したい方にとって、伊藤塾の宅建士合格講座は独学では実現できない最適な学習環境が整っているといえるでしょう。宅建士の資格取得に興味がある方は、ぜひ伊藤塾で一緒に合格を目指してみませんか?
※こちらも読まれています。
5.宅建士は仕事がないと言われていることに関するQ&A
Q1. 宅建士の仕事は将来AIに奪われてしまう?
A. 宅建士の独占業務である「重要事項説明」や契約に関する責任は、法律で宅建士にしか認められていません。
顧客の疑問に答え、不安を解消しながら信頼関係を築く役割はAIにはできないため、この点で宅建士の価値は今後も失われることはありません。
Q2. 宅建士資格を取っても未経験では転職できない?
A. 宅建士の資格があれば、未経験でも不動産業界に転職することは可能です。資格を持っていることで応募条件を満たせる求人が増えるため、転職のチャンスは広がります。
ただし、不動産業界は営業職が中心のため、成果を出すにはコミュニケーション力や積極性が重視されます。そのため「資格だけ」では採用に直結しにくく、コミュニケーションスキルや営業力を伸ばしていく必要があるでしょう。
Q3. 宅建士資格は転職市場でどのくらい評価される?
A. 不動産業界においては宅建士資格の評価は非常に高く、求人票でも「必須」または「歓迎」と明記されていることが多いです。特に人材不足の傾向がある中小企業や地方の不動産会社では、資格者は即戦力として重宝されやすいでしょう。
一方、異業種への転職では資格だけで採用が決まることは少なく、業界経験や営業スキルが加わることでより評価されます。したがって、資格取得と並行して「どの分野で活かしたいのか」を明確にすることが重要です。
6.宅建士は「仕事がない」どころか将来性ある魅力的な国家資格
本記事では、「宅建士は仕事がない」と言われる理由と宅建士の実情や将来性について、さらに長期的に活躍するためのヒントなどを解説しました。
以下にポイントをまとめます。
・宅建士は「仕事がない」と言われることがありますが、実際には不動産取引に不可欠の資格であり、将来性も十分にある魅力的な国家資格です。
・「仕事がない」という印象は、資格取得者が多いことによる希少性の低さ、資格取得だけでは実務経験やスキルが評価されにくいこと、AI・IT化による将来への不安などが背景にあります。
・しかし、宅建士は、人が生活する上で欠かせない不動産業界の安定した需要に支えられ、空き家問題の増加や不動産会社への配置義務により、その需要は拡大傾向にあります。
・特に、不動産取引の公正さと安全性を担保する重要事項説明や契約書への記名という独占業務があるため、その必要性がなくなることはありません。
・また、不動産分野だけでなく、金融、建設、保険など幅広い業界で応用可能であり、独立・開業の道も開けるため、キャリアの可能性を大きく広げられる資格です。
・宅建士として長期的に活躍するためには、資格知識に加えて営業スキルやコミュニケーション力を磨き、ITスキルやデジタルツールを活用し、ファイナンシャルプランナーなどのダブルライセンスで専門性を高めることが重要です。
以上です。
宅建士試験の合格には効率的な学習が不可欠ですが、独学では挫折しがちな広い学習範囲も、伊藤塾の「宅建士合格講座」なら効率的に合格を目指す最適な学習環境が整っています。初学者から再挑戦者まで対応したカリキュラム、コンパクトな講義、充実した演習問題、アプリ学習、オンラインサポートなど、疑問を解消しながら無理なく合格に必要な知識を積み上げられる万全の体制で、あなたの挑戦を力強く後押しします。
宅建士として輝かしいキャリアをスタートさせたいとお考えなら、ぜひ伊藤塾で私たちと一緒に合格を目指してみませんか?