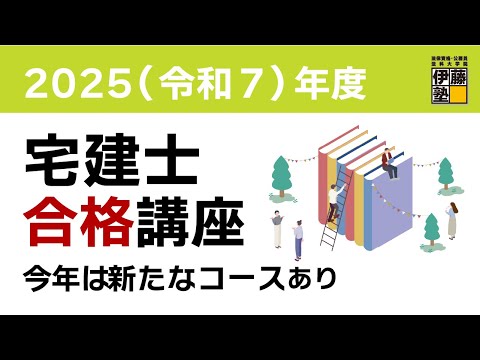宅建に合格するとすごい?一発合格は可能?宅建のリアルを解説
基本情報
2025年09月15日


「なぜ宅建士に合格するとすごいと言われるの?」
こんな疑問を聞くことがありますが、宅建士試験に合格することは本当にすごいことなのでしょうか。本記事では、
・宅建士試験の合格がすごいと言われる理由
・宅建士試験の合格はすごいと思わない人の意見
などについて取り上げました。宅建士に対する世間の評価を知りたい方は、是非ご一読ください。
※宅建士の資格の詳細については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
→【完全版】宅建とは?試験の詳細や宅建士の仕事内容など資格のすべてを徹底解説!
【目次】
1.宅建士の合格がすごいと言われる理由
宅建士に合格すると、周囲から「すごい」と言われることが多いです。その理由は様々ですが、よく挙げられる理由は次の5つです。
・受験者の「82%」は不合格になるから
・国家資格だから
・業務独占資格だから
・資格手当がもらえるから
・長時間の勉強が必要だから
それぞれの理由を、詳しく見ていきましょう。
1-1.受験者の82%が不合格になるから
宅建士は、受験者の「82%」以上が不合格になる難関国家資格です。
【宅建士試験の合格率】
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
| 受験者数 | 226,048 | 233,276 | 241,436 |
| 合格者数 | 38,525 | 40,025 | 44,992 |
| 不合格者数 | 187,523 | 193,251 | 196,444 |
| 合格率 | 17.0% | 17.2% | 18.6% |
| 不合格率 | 83.0% | 82.8% | 81.4% |
上の表からも分かるとおり、毎年24万人近くが宅建士に挑戦しているものの、そのうち19万人は不合格となっているのです。
「10人のうち8人以上」が落ちる試験に合格することは、決して簡単ではありません。少なくとも、資格の「難易度」という視点から考えると、宅建士の合格は確実にすごいと言えるでしょう。
※宅建士試験の合格率については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 宅建士試験の合格率が低い理由は?合格率を高めるポイントも解説!
1-2.「国家資格」だから
国に認められた「国家資格」であることも、宅建士に合格するとすごいと言われる理由です。文部科学省によれば、国家資格とは次のように定義されています。
国家資格とは、国の法律に基づいて、各種分野における個人の能力、知識が判定され、特定の職業に従事すると証明される資格。法律によって一定の社会的地位が保証されるので、社会からの信頼性は高い。
(引用:文部科学省 国家資格の概要について)
つまり、宅建士(国家資格)へ合格すると、国によって「不動産取引に従事する能力や知識がある」と保証されたことになるのです。民間資格とは比較にならない程の社会的信頼につながります。
さらに、宅建士は、不動産業界で最も知名度の高い資格だと言っても過言ではなく、多くの人から「不動産取引のプロ(国家資格)」だと認知されています。このように、いくつもの信頼が積み重なっているため、宅建士に合格すると「すごい」と評価されるのです。
※国家資格である宅建の魅力については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→宅建士は国家資格ではないと言われるのはなぜ?宅建の魅力を深堀り解説
1-3.「業務独占資格」だから
あまり知られていませんが、国家資格は次の4種類に分けられます。
| 名称 | 特徴 |
| 業務独占資格 | 有資格者以外は禁止されている業務を独 占的に行える資格。 専門的なスキルが必要なものが多く、試 験の難易度も高め。(医師、弁護士、司法 書士、行政書士など) |
| 名称独占資格 | 有資格者以外は、その名称を名乗ること が禁止されている資格。 「業務独占資格」とは異なり、資格を 持っていなくても、業務自体は行うこと ができる。(栄養士や保育士など) |
| 設置義務資格 (必置資格) | 法律で設置が義務づけられている資格。 (学芸員、衛生管理者など) |
| 技能検定 | 業務知識や技能などを評価するもの |
宅建士は、この中でも特に難易度が高い「業務独占資格」に分類されています。
「重要事項の説明」「重要事項説明書への記名」「契約書の記名」などは、宅建士だけに認められた独占業務です。
これらの不動産取引に欠かせない業務を、独占的に行えることが、宅建士に合格するとすごいと言われる理由となっているのです。なお、宅建業者には「宅建士の設置義務」が定められているため、「業務独占資格」であると同時に「設置義務資格」としての一面も持ち合わせています。
「業務独占資格」かつ「設置義務資格」であることが、宅建士に対する強いニーズの要因です。
※宅建士の独占業務については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
→ 宅建士を取得すると何ができる?独占業務など資格のメリット5選
1-4.資格手当がもらえるから
多くの不動産会社では、宅建士を取得した社員に「資格手当」を支給しています。同じ会社に勤めていても、宅建士の資格を持っている社員と持っていない社員では、給与に差がつくケースが多いのです。
会社が資格手当を支給するのは、宅建士が会社にとって価値があり、必要とされている証拠です。「宅建士を取得してほしい」という会社の期待に応えて、難しい試験を突破するのは、簡単なことではありません。会社から必要とされ、評価される資格を取得することは、それだけですごいことだと言えるでしょう。
1-5.合格に「300〜500時間」の勉強が必要だから
宅建士の合格には、一般的に「300〜500時間」もの勉強が必要とされています。
仕事や学業と両立しながら、これだけの時間を勉強に充てるのは、並大抵のことではありません。例えば、独学かつ半年で宅建士試験に合格しようとすると、毎日「2〜3時間」程度の勉強を休まずに続ける必要があります。「合格するまでは頑張る」という強い意志と覚悟がなければ、宅建士の合格は難しいでしょう。合格までの道のりは決して楽ではありません。しかしだからこそ、宅建士に合格すると「すごい」と言われるのです。
※宅建士試験の勉強時間については、次の記事で詳しく解説しています。
→【500時間必要?】宅建士試験の合格に必要な勉強時間について徹底解説!
2.宅建の合格がすごいと思わない人の理由は?
一方で、宅建士の合格をすごいと思わない人もいます。そのような意見を持つ人の理由としては、主に次の3つが挙げられます。
・取り組みやすい試験形式であること
・不動産業界では宅建士を持つことが当然だとされていること
・法律系国家資格の中では比較的合格しやすいこと
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1.取り組みやすい試験形式だから
宅建士試験は、多くの人が取り組みやすいと感じる試験です。四肢択一式のマークシート方式で行われる上、他の法律試験のように、記述式の問題が出題されないからです。
また、選択肢の数が4つしかないため、当てずっぽうで回答しても「25%」の確率で正解できることも、挑戦しやすいと感じるポイントでしょう。このような試験形式の特徴から「宅建士試験は合格しやすい」と考え、合格しても「すごいと思わない」と感じる人がいるのです。
ただし、前述のとおり、宅建士試験の合格率は例年「17%」程度しかありません。本当に合格しやすい試験なのかは、しっかりと考える必要があります。
2-2.不動産業界では宅建士の資格が必須だから
不動産業界で働く人にとって、宅建士の資格を取得することは当然のことだと考えられています。宅建士の資格がないと不動産取引ができず、業務に支障が出るケースもあるからです。そのため、不動産業界の人からすれば、宅建士の合格は「すごいこと」ではなく、業界で活躍するために「当然のこと」だと感じるのです。
実際、多くの不動産企業では、宅建士の資格を持つ人を優先的に採用したり、入社後に宅建士を取得することを前提に採用したりしています。宅建士を持つことが一般的となっており、資格だけで自分の希少性を高めることは難しくなっているのです。
しかし、だからといって宅建士の合格に価値がないわけではありません。確かに、不動産業界で働く人にとって宅建士を取得することは当たり前のことかもしれません。しかし、その「当たり前」の状態に至るまでには、相当の努力が必要です。業界で宅建士の合格が当然視されていることと、その合格がすごいことであることは、別問題だと考えるべきでしょう。
2-3.法律資格の中では合格率が高いから
宅建士は、法律系の国家資格の中では、比較的受かりやすい試験だと言われています。
「司法書士」や「行政書士」などと比べると、試験の合格率が高く、比較的短い勉強でも合格できるからです。そのため「宅建士の合格はそれほどすごいことではない」と考える人もいます。
【法律系国家資格の合格率・勉強時間】
| 資格 | 合格率 | 勉強時間 |
| 宅建士 | 15%〜18% | 300〜500時間 |
| 行政書士 | 10%〜12% | 600〜1,000時間 |
| 司法書士 | 4%〜5% | 3,000時間 |
| 司法試験 (予備試験) | 3%〜4% | 2,000時間〜5,000時間 |
| 社労士 | 5%〜6% | 500時間〜1,000時間 |
確かに、法律系国家資格の中では、宅建士は比較的取得しやすい部類だといえるでしょう。ただし、これはあくまでも「他の法律系国家資格と比べると」という話であって、決して簡単に合格できる訳ではありません。
働きながら「300〜500時間」の勉強時間を確保し、「10人中8人」が落ちる試験に合格するためには、相当の努力が必要です。
3.【ケース別】宅建の合格がすごいと言われやすいのは?
宅建士の合格がすごいと言われるかどうかは、状況によっても異なります。
特に、不動産業界で働いている人とそうでない人では、宅建士の合格に対する評価が大きく分かれるでしょう。ここでは、宅建士の合格がすごいと言われやすいケースを2つ紹介します。
3-1.大学生が宅建士に合格するとすごい
大学生が宅建士試験に合格すると、周囲からすごいと言われることが多いです。その理由は、大学生の宅建士合格者が非常に少ないからです。
宅建士試験合格者(令和6年度)の職業構成を見ると、学生はわずか「11.4%」となっています。つまり、合格者のうち大学生は「10人に1人」程度しかおらず、希少性が非常に高いのです。一方で、在学中に宅建士の資格に興味を持つ大学生は一定数います。
しかし、多くの大学生にとっては、宅建士試験の勉強は優先順位が低く、なかなか取り組めないのが実情でしょう。大学の授業やサークル活動、アルバイトなどで忙しい中、宅建士の勉強に時間を割くのは容易ではないのです。だからこそ、大学生で宅建士を取得すると「すごい」と言われます。就職活動などでも、宅建士の資格は強力な武器になるでしょう。
※大学生が宅建士の資格をとるべき理由は、こちらの記事で詳しく解説しています。
→【宅建士になれば就活無双?】大学生が宅建士を目指すべき理由とは
3-2.銀行員も宅建士に合格するとすごいと言われやすい
銀行員も宅建士に合格すると、周囲からすごいと言われることが多いです。宅建士の資格を取得する銀行員は、あまり多くないからです。銀行は不動産業界ではないため、かなり珍しいと言えるでしょう。
しかし、宅建士の知識は、銀行業務でも大いに役立ちます。不動産担保の調査や住宅ローンの審査など、様々なシーンで、専門知識を発揮できるでしょう。さらに、資格手当などがもらえたり、人事考課でプラスになったりすることもあります。宅建士は、銀行員の実務にも直結する資格なのです。
とはいえ、銀行員が働きながら勉強時間を確保することは、簡単ではありません。不動産業界とは異なる分野の業務に就いているため、学習面でのハードルも高いでしょう。そのため、宅建士を取得する銀行員は少ないのが現状です。しかしだからこそ、宅建士に合格した銀行員は、周囲から「すごい」と評価されます。日々の業務をこなしつつ、宅建士に挑戦する銀行員の姿勢が、高く評価されているのです。
※宅建士資格は不動産以外でも活かせることについて、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 宅建は就職や転職に有利?未経験もOK?不動産以外で活かせる仕事も紹介
4.宅建士試験に一発合格するのはすごいこと?
宅建士試験に一発合格するのは、非常にすごいことだと言えるでしょう。その理由は、宅建士試験の合格率の低さにあります。
前述のとおり、宅建士試験の合格率は「18%」程度しかありません。つまり、受験者の「82%」が不合格になっているのです。特にここ数年は、受験生全体のレベルが向上しています。このような難易度の高い試験に、一発で合格するのは並大抵のことではありません。
宅建士試験に一発で合格したい場合は、受験指導校の活用も検討してみましょう。受験指導校では、プロ講師の分かりやすい講義や、効率的なカリキュラムによって、最短で宅建士試験合格を目指すことができます。
徹底した分析により、本試験で出題されやすいテーマを中心に対策することで、300時間よりはるかに短い勉強時間で、一発合格している受講生も多数います。プロのサポートを受けながら、効率的に学習することで、一発合格の可能性を大きく高めることができるでしょう。
※こちらも併せてお読みください。
→ 宅建の通信講座はなぜ伊藤塾がおすすめなのか?宅建士合格講座の魅力を徹底解説
5.まとめ
最後に、今回の記事のポイントをまとめます。
◉ 宅建士は、合格率が低く相当の勉強が必要な資格
◉「国家資格」「業務独占」などすごい要素がたくさんある
◉ すごくないと言われる理由は「希少性の低さ」など
◉ 大学生や銀行員が宅建士を取ると、希少性も高い
宅建士の合格を「すごい」と考えるかは、人によって異なります。ただし、簡単に取得できないことは確かで、合格には相当の努力が必要です。
粘り強く努力して、宅建士に合格することが、称賛に値することは間違いありません。
不動産業界で働く人、違う業界で働く人など、状況は様々ですが、いずれのケースでも宅建士を活かして活躍することで、周囲の評価も高めることができるでしょう。
宅建士試験の対策には、ぜひ法律資格専門の指導校である伊藤塾をご活用ください。
「今年はさらにバージョンアップしたコースをご用意!!「2025年合格目標 宅建士合格講座」 のご紹介です!」