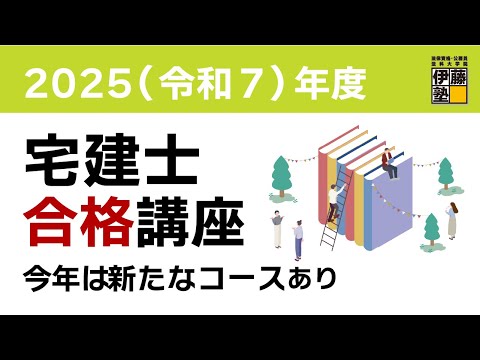宅建士試験初心者の勉強方法を6つのステップで解説!科目別の攻略法も
勉強法
2025年09月15日


ゼロから宅建士試験を目指す場合、何をどのように勉強すれば良いのでしょうか?
「初心者から宅建士試験に合格したい」
「まずは何から勉強すればいいの?」
こういった疑問をお持ちの方も多いでしょう。
約6人に1人しか合格できない宅建士試験を突破するには、正しい勉強法が欠かせません。間違った方向性で勉強すると、いつまで経っても合格できない結果につながります。
そこで本記事では、宅建士試験の初心者に向けて、ゼロから取り組んで欲しい勉強法を分かりやすく解説します。
◉この記事を読んで分かること
・初心者にオススメの勉強法
・宅建士試験の科目別の勉強法
・独学か受験指導校(予備校)かを判断するポイント
初心者から宅建士試験の合格を目指している方は、是非ご一読ください。
【目次】
1.宅建士試験初心者は何から始める?オススメの勉強法
宅建士試験は、合格率16%〜17%程度の難関試験です。合格には戦略的な勉強が欠かせません。特に、働きながら勉強する人や、試験までの時間が少ない人ほど、効率的な学習が必要です。
そこで、初心者から宅建士試験に合格するための勉強法を、6つのステップに分けて解説します。
1.まずは試験科目を知る
2.目標とする点数を決める
3.具体的な戦略を立てる
4.全体像を理解する
5.テキストと過去問を何度も往復する
6.模試でシミュレーションをする
出題傾向を分析し、科目ごとの特性を理解して勉強を始めましょう。
正しい学習方法を実践し、着実に力をつけていけば、初心者からでも十分に合格を狙えます。それでは、各ステップごとに説明します。
1-1.【ステップ①】まずは試験内容を知る
宅建士試験を目指すと決めたら、最初に行って欲しいのは試験内容を知ることです。まずは敵を知ることが、試験に合格する第一歩となるのです。
| 試験内容 | 問題数 | 科目 |
| 権利関係 | 14問 | 1.土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、 構造及び種別に関すること。 2.土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する 法令に関すること。 3.土地及び建物についての法令上の制限に関すること。 4.宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。 5.宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関する こと。 6.宅地及び建物の価格の評定に関すること。 7.宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。 |
| 宅建業法 | 20問 | |
| 法令上の 制限 | 8問 | |
| 税・その他 統計等 (免除科目) | 8問 | |
| 合計 | 50問 |
宅建士試験では、不動産取引に関する法律知識を中心に全50問が出題されます。出題形式は、すべて四肢択一のマークシート形式で、記述式問題は出題されません。
試験内容は、権利関係が14問、宅建業法が20問、法令上の制限が8問、税・その他と統計等(免除科目)が8問の合計50問です。それぞれの特徴や勉強法は、2章で詳しく解説します。
1-2.【ステップ②】合格に必要な点数を知る
次に、合格に必要な点数を把握しましょう。
宅建士試験は、毎年の合格点数が異なる相対評価の試験です。その年の受験者数、問題の難易度、ライバルの点数などによって合格ラインは変わってきます。直近10年間の合格点から推定される合格ラインは「36問/50問」以上が目安です。
【宅建士試験の合格ライン】
| 年度 | 合格点 |
| 令和6年度 | 37点 |
| 令和5年度 | 36点 |
| 令和4年度 | 36点 |
| 令和3年度 (12月) | 34点 |
| 令和3年度 (10月) | 34点 |
| 令和2年度 (12月) | 36点 |
| 令和2年度 (10月) | 38点 |
| 令和元年度 | 35点 |
| 平成30年度 | 37点 |
| 平成29年度 | 35点 |
| 平成28年度 | 35点 |
| 平成27年度 | 31点 |
(出典:(一財)不動産適正取引推進機構|試験実施概況(過去10年間))
かつては、35点得点できれば安心だと言われていた時代もありました。
しかしここ数年、合格点は上昇傾向です。その年の難易度によっても異なりますが、35点を下回ると合格は難しくなります。満点を狙う必要はありませんが、毎年の合格点より少し高めを目標にすると良いでしょう。
1-3.【ステップ③】科目ごとの目標点を設定する
宅建士試験の合格には、最低でも「36問/50問」以上の得点が必要です。
それでは、どうやって「36問/50問」の得点を取得すればよいのでしょうか。さらに細分化して、科目ごとの目標点数を説明します。
【科目ごとの目標点数】
| 科目 | 目標 |
| 権利関係 | 14問中9問 |
| 宅建業法 | 20問中17問 |
| 法令上の制限 | 8問中5問 |
| 税・その他 | 3問中2問 |
| 統計等(免除科目) | 5問中3問 |
権利関係は「14問中9問」、宅建業法は「20問中17問」、法令上の制限は「8問中5問」、税・その他は「3問中2問」、統計等(免除科目)は「5問中3問」の正答を目標にすると良いでしょう。
ここで最も意識して欲しいのが、各科目の出題数です。主要3科目である権利関係、宅建業法、法令上の制限だけで、50問中42問(全体の84%)を占めていることが分かります。そうすると、これらの科目をいかに効率的に攻略できるかが、合否に大きく影響します。
主要3科目の中でも、特に力を入れて勉強して欲しいのは「権利関係(民法)」です。権利関係(民法)は、法律的な考え方の基本となる科目です。これを得意にできれば、他の科目の得点力アップにもつながります。
1-4.【ステップ④】全体像を理解する
宅建士試験の勉強では、全体像を理解することが大切です。これができなければ、膨大な量の暗記が必要になり、すぐにパンクしてしまいます。
「いくら知識を覚えても、本試験で得点が伸びない」
「見たことのない問題が出ると、途端に正答できなくなる」
「過去問は解けるのに、あと一歩で合格ラインに届かない」
こういった悩みを抱える人は多いですが、大半は「暗記」に偏った勉強が原因です。宅建士のような法律系の資格試験では、「暗記」ではなく「理解」できているかが、合否に大きな影響を与えます。
一見遠回りに思えても、まずはかみ砕いて、全体像を理解する。
そうすることで、頭の中に法律の体系を構築する。
これを徹底することが、法律系の資格試験全般に共通した合格の秘訣です。力技で暗記するのではなく、あくまでも理解して、脳のキャパオーバーを防ぐことが宅建士試験に合格するポイントだと言えるでしょう。
1-5.【ステップ⑤】テキストと過去問を何度も往復する
全体像のイメージが掴めたら、テキストと過去問を何度も往復して、正確な知識を身につけていきます。このとき注意して欲しいのが、テキストと過去問、どちらに偏ってもダメなことです。
多くの人が陥りやすいのが、次のような失敗です。
【勉強法のNG例】
・ひたすらテキストばかり読み込んで、過去問を軽視する。
・テキストを軽視して、過去問ばかり取り組んでしまう。
どちらの勉強法も、効率的な得点力アップには結びつきません。特に、過去問ばかり取り組んでいる受験生は多いため、十分な注意が必要です。
合格者の中には、「過去問だけで合格できたよ!」と語る人もいますが、これは必ずしも正確ではありません。実際には、合格者の多くは過去問をやった後、テキストに戻っています。
【勉強法の正しい例】
・テキストで暗記した知識を、演習に活かしてアウトプットする
・演習で身につけた知識を、テキストに転記してインプットする
これを何度も何度も繰り返して、正確な知識を習得しましょう。
1-6.【ステップ⑥】模試でシミュレーションをする
試験間近になったら、模試を受験して、当日のシミュレーションを行います。
・時間配分はどうすればいいか
・自分が弱点としている科目、分野はどこなのか
・ライバルが正答できているのに、自分だけ取りこぼしている問題はないか
・イージーミスを防ぐにはどう対策すればよいか 等
模試を利用して、本試験当日に向けた最終チェックを行いましょう。ただし、模試を受験した後、復習に時間をかけ過ぎるのはおすすめできません。
模試はあくまでも「模擬」試験です。自分の弱点や実力を分析するための、判断材料に過ぎません。もちろん予想が的中する場合もありますが、基本的に合否に影響しないケースが大半を占めています。最終的にはテキストや過去問に戻って、基本的な知識を中心に復習を進めましょう。
2.科目別に解説|宅建初心者向けの勉強法
宅建士試験は、大きく4科目に分かれます。まずは各科目の概要を掴み、その上で、自分に合った勉強法を見つけましょう。
「権利関係(民法など)」「宅建業法」「法令上の制限」「税その他、統計等(免除科目)」に分けて、初心者向けの勉強法を解説します。
2-1.権利関係のポイント
宅建士試験で、最も重要な科目の1つが権利関係です。「全50問中14問」を占めており、試験の合否を左右する科目と言えるでしょう。
出題の中心は民法で、契約や権利義務に関する法律知識が問われます。苦手意識を持つ人が多いですが、法律の基本的な考え方が身につくため、14問という配点以上に力を入れるべき科目です。権利関係が得意になれば、他の科目の理解にもつながります。
勉強のポイントは、とにかく立ち止まらずに一周してみることです。最初は全体像を掴むのが難しく、理解できないと感じる人も多いですが、諦めずに進めていきましょう。毎日5分でも構いません。とにかく、民法を敬遠せず、日々触れ続けることが大切です。そうすると、全体像が頭に入ってきて、突然理解できる瞬間が訪れます。
分からなくなったら、事案を図で書いてみて、整理することも効果的です。立ち止まるのではなく、まずは手を動かして考えましょう。何度も繰り返すうちに、自然と民法の考え方が身に付いていきます。
※ 権利関係(民法)の学習のポイントについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 宅建の権利関係(民法)が苦手な方へ!得点力アップの秘訣を教えます
2-2.宅建業法のポイント
宅建士試験で最も配点が大きく、得点源とするべき科目が宅建業法です。全体の40%を占めており、この科目で高得点を取ることが合格のカギを握っています。
宅建業法のポイントは、「法律の目的」を常に意識して勉強することです。
宅建業法の目的 → 消費者を保護すること
不動産取引において、宅建業者と一般消費者は、必ずしも対等な立場とは言えません。専門的な知識や経験を持つ宅建業者に対して、一般消費者のほとんどは、不動産取引に不慣れだからです。そうすると、宅建業者を規制して、一般消費者を保護するためのルールが必要となります。
そこで作られた法律が「宅建業法」です。つまり、宅建業法の条文は「消費者保護」という目的を達成する手段として書かれているのです。
この視点を持って学習を進めれば、条文が頭に残りやすくなります。単に暗記するのではなく、「法律の目的」を意識した勉強を行いましょう。条文の趣旨を理解することが、得点を伸ばすためのポイントです。
2-3.法令上の制限のポイント
主要3科目の1つである法令上の制限では、50問中8問が出題されます。
都市計画法や建築基準法など、不動産の利用を制限する法律を学んでいく科目です。専門用語が多く、初心者に取っつきにくい部分もありますが、過去問が繰り返し出題されます。
従って、まずは過去問を解けるようになることが重要です。ある程度の暗記は必要ですが、逆に言えば、暗記だけでも一定の得点が期待できる科目だと言えるでしょう。用語の意味をしっかり理解し、過去問を通じて、頻出分野を重点的に演習することが効果的な勉強法です。
※法令上の制限」の攻略法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 宅建士試験「法令上の制限」の攻略法!覚え方や勉強法を解説
2-4.税・その他、免除科目のポイント
税・その他、統計等(免除科目)では、不動産に関する税制や、統計などの基本的な知識を学習します。主要3科目ほど時間をかける必要はありませんが、基本的な知識は身に付けておきましょう。
難問・奇問は捨てても構いませんが、簡単な問題で他の受験生に差をつけられると、合格は難しくなります。出題傾向を把握し、基本的な問題や頻出論点について、確実に得点することを目標に勉強しましょう。
実務経験によっては、「登録講習」を受けることで免除される場合もあります。すでに宅建業者で働いている方は、チェックしてみましょう。いずれにしても、必要以上に時間をかけ過ぎるべきではありません。ある程度の割り切りは必要な科目だと考えてください。
3.宅建初心者にオススメなのは独学?受験指導校?
宅建士試験の勉強法で最も迷うのが、「独学と受験指導校のどちらを選ぶべきか」という点ではないでしょうか?インターネット上にも様々な情報が乱立しており、多くの受験生が疑問を抱えているはずです。
「宅建士試験は、独学でも合格できる?」
「最初から、受験指導校を利用した方が良い?」
結論としては、「人によって異なる」が正解といえるでしょう。
勉強に充てられる時間や、学習環境、法律の学習経験によって、どちらを選ぶべきかが変わってくるからです。例えば、行政書士や司法書士に合格している人であれば、独学でも合格できるかもしれません。一方で、そもそも勉強が苦手な人の場合、独学ではあまりに時間がかかり、挫折してしまうかもしれません。独学で問題ない人もいれば、受験指導校を利用した方が良い人もいるのが実情です。
3-1.独学 or 受験指導校を判断するポイント
独学か受験指導校かで迷ったら、「法律の学習経験」で判断すると良いでしょう。
宅建士試験の法律科目…中でも権利関係(民法)は、独学での習得が難しい科目です。ゼロから1人で学習すると「大量の暗記をしたのに得点が伸びない…」という結果になり兼ねません。
特に最近は、本試験の問題が難しくなっていると言われています。法律的な考え方を身に付けない限り、大きく得点は伸ばせないでしょう。過去問を何度も解いたのに、本試験で対応できなかったという人は多いはずです。
受験指導校では、過去問の知識を覚えるのではなく、背後にある考え方(解き方)を教わることができます。そうすると、知らない問題が出てきても、その場で考えれば正答を導くことができるようになります。
民法の解き方が理解できれば、法律科目の得点は目に見えて上がっていくでしょう。「民法を制する者は、宅建士試験を制する」と言っても過言ではありません。
伊藤塾では「2025年合格目標 宅建士合格講座」から、権利関係(民法)の学習を手厚くした「スタンダードコースプラス」を新たに開講しています。この講座では「権利関係」をしっかりと攻略することで、宅建士試験の全ての科目を得点源とすることを目指しています。
「これまで法律を学んだことがない」「権利関係の得点が伸びずに悩んでいる」という方は、ぜひ受験指導校の利用も検討してください。
※こちらも併せてお読みください。
→ 宅建の通信講座はなぜ伊藤塾がおすすめなのか?宅建士合格講座の魅力を徹底解説
【宅建士】今年はさらにバージョンアップし、2つのコースをご用意!!「2025年合格目標 宅建士合格講座」 のご紹介です!
4.まとめ
最後に、今回の記事のポイントをまとめます。
◉初心者から宅建士試験に合格する勉強法
1.まずは試験科目を知る
2.目標とする点数を決める
3.具体的な戦略を立てる
4.かみ砕いて全体像を理解する
5.テキストと過去問を何度も往復する
6.模試でシミュレーションをする
◉宅建士試験でメインとなる科目は「権利関係(民法)、宅建業法、法令上の制限」
◉主要3科目だけで「42問/50問(84%)」を占めている
◉中でも権利関係(民法)を理解できるかは合否のカギを握っている
◉独学が難しいと感じたら、受験指導校を利用することも検討するべき
以上です。
宅建士試験は、決して簡単な試験ではありません。しかし、正しい勉強をすれば、初心者からでも十分に合格できる試験です。
本記事が参考になった、役に立ったと感じたら、ぜひ法律資格専門の指導校である伊藤塾をご活用ください。