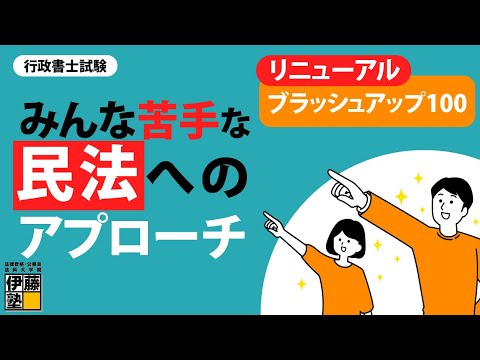なぜ行政書士試験の民法は覚えられないのか?難しいと悩む前に試してほしい思考法
試験詳細
2025年09月12日


行政書士試験の中でも、民法はトップクラスに苦手とする人の多い科目です。
「勉強量が多すぎて覚えられない」
「難しくて得点が伸びない」
このような壁にぶつかって悩んでいる受験生も多いのではないでしょうか?
民法が難しいのは、単に覚える量が多いからではありません。実は、問題の解き方が誤っていることが大きな要因なのです。正しい思考法が身につかない限り、いくら知識を覚えても民法の得点を伸ばすことはできません。
本記事では、民法が難しい・覚えられないと感じている方に向けて、ぜひ取り組んで欲しい対策をご紹介します。
◉本記事で分かること
・民法が難しい、覚えられないと感じる原因
・得点力を伸ばすための、具体的な対策
・民法で失敗しないための注意点
・民法への具体的なアプローチ方法
行政書士試験の民法が苦手な方は、是非ご一読ください。
※民法の勉強法については、こちらの記事でも詳しく解説しています。併せてご覧ください。
【目次】
1.民法が難しいのは「覚えられない」からではない!
行政書士試験の民法が難しいのは、単に量が多くて覚えられないからではありません。大半は、正しい思考プロセス(解き方)が身に付いていないことが原因です。
民法が「難しい」と感じる人は、おそらく次のような勉強をしているのではないでしょうか。
「毎日、数十問〜100問以上の過去問に取り組んでいる」
「思考プロセスを軽視して、事例と結論だけを覚えている」
「世界史や日本史のようなイメージで、ひたすら知識の量を増やそうとしている」
これに心当たりがあるなら、民法への取り組み方が誤っています。
民法を始めとした法律試験では、単に覚えれば得点が取れるわけではありません。ほぼ全ての問題で、次のような思考プロセスが必要です。
① まずは問題文を読んで、何を聞かれているか(テーマ)を把握する
② テーマ(論点)が分かったら、そこから覚えた条文、判例などを「想起」する
③ 最後に、問題文に書かれているケースを当てはめて、正誤の判断を行う

この流れが身につかない限り、いくら覚えたからと言って、民法の得点を伸ばすことはできないのです。
1-1.民法の正しい思考の流れ|94条(虚偽表示)のケース
それでは、正しい思考の流れを具体的に見ていきましょう。
例えば、「民法総則(94条(虚偽表示)」では、「第三者に当たる者、当たらない者」という問題がよく出題されます。そして、民法が苦手な人の多くは、「一般債権者は第三者にあたらない、差し押さえをした者は第三者に当たる」という結論を、知識として覚えてしまっています。
しかし、これが民法が難しいと感じる大きな要因なのです。実際には、「なぜそうなるのか」を毎回考えて、あてはめによって結論を導かなければいけません。

①テーマの把握
なるほど…通謀虚偽表示の第三者に当たるかが聞かれているんだな。
②想起
通謀虚偽表示の第三者の定義はなんだっけ? 確か…「虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であつて、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者」だったな。
③あてはめ
今回のケースを、「第三者の定義」にあてはめるとどうなるんだろう? まず、虚偽表示の目的は土地。そして、一般債権者は「債権」を持っているだけで、虚偽表示の目的(土地)については、利害関係を有していない。そうすると、第三者には当たらないな。
一方、差押をした者は、土地を差し押さえたので、虚偽表示の目的について利害関係を持っている。そうすると、「虚偽表示の目的(土地)につき法律上利害関係を有する(差し押さえ)に至った者」と言える。だから、第三者に当たりそうだ。
つまり、覚えるべきポイントは「虚偽表示の第三者の定義(のみ)」なのです。結論を覚えるのではなく、第三者の定義だけ覚えて「あてはめ」によって正解を出すことが正しい方法です。
全ての問題をこの考え方で解けるようになれば、民法の得点力が大きくアップします。最小限の知識を覚えるだけで、未知の問題にも対応できるようになるでしょう。
2.行政書士試験の民法が「覚えられない」と感じる原因
行政書士試験の民法が「覚えられない」と感じる最大の原因は、「何を覚えるべきか」が分かっていないことです。条文や判例、過去問を全て丸暗記しようとする受験生は多いのですが、すぐにパンクしてしまいます。
大切なのは、「覚えるべきポイントは覚える、覚えてはダメなポイントは覚えない」という意識を徹底することです。
| 覚えるべき知識 |
| ・条文の趣旨、要件と効果 ・第三者の定義 ・判例の基本的な考え方 ・結論にいたる理由 ・イレギュラーな結論となっている判例 ・その他、理屈で導けないもの など |
| 覚えてはダメな知識 |
| ・事例と結論 ・過去問の答え ・条文、判例の丸暗記 ・めったに出題されないマイナー知識 ・その他、理屈で導けるもの など |
民法が苦手な人に多いのが、「得点が伸びない=知識不足が原因」と考えて、いくつもの教材や問題集に手を出してしまうケースです。しかし、そもそも民法は条文だけでも1000以上ある法律で、判例もたくさん蓄積されています。いくら教材を増やしたからといって、これらを全て覚えることは不可能でしょう。
あなたを合格に導くのは、「100個のあやふやな知識」ではなく「5個の正確な知識」です。やみくもに覚えるのではなく、覚えるべきポイントを絞って、覚えた知識を使えるようになることが大切なのです。
3.民法が難しい・覚えられないと感じる方に試して欲しいこと
民法が難しい、覚えられないと感じている方は、ぜひ「図を書く」「推測で答えを出すトレーニングをする」「毎日少しずつ触れる」などの方法を試してみてください。
これらを実践することで、民法の理解度と得点力を確実にアップさせることができるでしょう。それぞれ詳しく説明します。
3-1.まずは図を書くクセを付ける
民法を得意科目にするには、とにかく図を書くクセをつけることが大切です。
問題文を読んだら、まずは「誰が、誰に請求しているのか」を矢印で結んで、状況を整理する練習をしてみてください。一見複雑な状況に見えても、図を描くことで、実は基本的な内容であることに気付くケースも多いです。
図を描くときのコツは、できる限り簡素化して、パターン化することです。テキストのような図を描く必要はないので、自分なりに工夫してみましょう。
【図を描くときのポイント】
・①、②などの数字を使って時系列を示す
(どの順番で契約関係に入ったのか)
・登場人物の位置は、必ず毎回同じ場所に描く
(例:債権者を左側、債務者を右側にするなど)
・契約内容は、アルファベット等で簡素化して表記する
(例:売買契約を「s」、賃貸借契約を「l」、登記を「㋣」など)
※売買:sell,賃貸借:lend
民法が得意な人ほど、まずは図を描いて事案を把握することを大切にしています。そうすることで、状況を整理し、何が問われているのか(テーマ)を的確に掴んでいるのです。逆に、民法が難しいと感じている人は、図を描くことを怠って、頭だけで考える傾向が強いです。
ぜひ、図を描いて考えるクセを付けることから始めてみてください。民法の理解が格段に深まるはずです。
3-2.民法の考え方(価値観)から、答えを推測するトレーニングをする
民法の考え方から、推測で答えを出すトレーニングもしてみましょう。
行政書士試験では、必ず未知の問題が出題されます。そのため、条文や判例を網羅的に覚えるだけでは限界があるのです。
全く見たことがない問題が出題されても、民法の考え方(価値観)さえ分かっていれば、推測で答えを出せる可能性が高くなります。
例えば、あなたと仲の良い友人の性格や考え方を思い浮かべてみてください。その友人が日常生活の中でどのような行動をとるか、どういった価値観をもっているのか、ある程度予測できるのではないでしょうか?
実は、これと同じことが民法にも言えるのです。民法の基本的な考え方が分かれば、初めて見る問題であっても、ある程度の予測が可能になります。過去問や判例で次のようなポイントを確認し、「民法がどういった考え方(価値観)をしているのか」を考えてみてください。
・関係者(本人、相手方など)が同意していたのか
・お互いの帰責性はどの程度か
・強行法規なのか、任意法規なのか
・保護する必要性、許容性があるのか
まずは自分なりに答えを推測し、そして解説を見て、「自分の考え方(価値観)」と「民法の考え方(価値観)」を比べてみましょう。比較していくうちに、様々なことが見えてくるはずです。
「自分は債務者を保護するべきだと思ったけど、民法はこう考えるのか」
「民法って、ものすごく本人の意思を尊重するんだな(私的自治の原則)」
「なるほど、こうやって利害関係を調整するのか」 など
この過程を繰り返すことで、民法の考え方が徐々に身についていきます。
3-3.1日3問だけでいいので「毎日」触れる
民法の学習では、とにかく毎日継続することが大切です。「難しい」「覚えられない」という意識が強くなるほど、民法から遠ざかりたくなる気持ちが強くなるでしょう。しかし、民法から遠ざかるほど、合格からも遠ざかってしまいます。
1日3問程度でいいので、必ず毎日問題に触れるようにしてください。
たった3問でも、3ヶ月続ければ270問です。着実に「わかる」問題が増えていくはずです。知識を定着させることはもちろん、問題に慣れることができて、苦手意識も格段に低下するでしょう。
合格者の中には、Excelを作成して、毎日解く問題の計画を立てたり、自分が解いた民法の問題数を記録したりしていた人もいました。こういったちょっとした工夫が、モチベーションのアップにも貢献したようです。たとえ10分でも、毎日積み重ねることを意識してみてください。そうすることで、民法の理解は格段に深まっていくはずです。
4.直前期になるほど注意|民法で失敗するポイント
行政書士試験では、直前期になるほど、民法の勉強で失敗しやすくなります。
民法から離れてしまったり、新しい知識を詰め込もうとしたりと、学習の方向性を見失ってしまう受験生が珍しくありません。失敗しやすいポイントと対策について説明します。
4-1.(✕)難しいからといって民法から離れる
直前期になるほど、民法から離れがちになる人が増えてきます。
その原因は様々ですが、いずれも大きな失敗につながってしまいます。
【民法から離れる原因】
・行政法の勉強に集中して、民法の時間が取れない
・難しいので手を付けたくないと感じ、無意識に遠ざけている
・過去問を覚えて、できたつもりになっている
・今更やっても無駄だと考えている など
民法は行政法に次いで配点が高く、合否を分ける重要な科目です。民法を捨てて、行政書士試験に合格することはできません。
どれだけ民法が苦手でも、必ず毎日触れる時間を作りましょう。地道に勉強していけば、突然、全体がはっきりと分かるようになるタイミングが訪れるはずです。毎日少しでも民法の問題に触れることが、合格への近道となるのです。
4-2.(✕)新しい知識を覚えようとする
直前期に新しい知識を覚えようとすることも、多くの受験生が失敗するポイントです。
思うように得点が伸びない原因が「知識不足」であると考えて、とにかく知識を広げようとする受験生は珍しくありません。しかし曖昧な知識をいくら増やしても、得点をアップさせることはできません。それどころか、逆に知識が空洞化して伸び悩みにつながってしまいます。

この画像は、民法の知識の絞り込みの方法をイメージしたものです。
基本的に「重要基本事項(赤)」の部分さえ覚えておけば、知識の量としては十分です。合格レベルの知識があるので、それ以上知識を増やす必要はありません。しかし実際には、多くの受験生が水色の箇所まで手を広げようとして失敗します。
【広げすぎて、失敗する知識の具体例】
・模試で間違えたマイナー知識
・SNSで見かけた直前予想
・合否に影響しない難しい論点 など
これらを無理に覚えようとすると、合否に影響しない知識ばかりが増えて、本当に大切なポイント(重要基本事項)が抜けてしまいます。例えば、模試では良い点が取れていたのに、本番で失敗するのが、直前期に手を広げて知識が空洞化してしまったケースの典型例でしょう。
繰り返しお伝えしますが、行政書士試験の民法で大切なのは、「覚えるべきポイントを絞って、覚えた知識を使えるようになること」です。むやみに新しい知識を覚えても、民法の得点を上げることはできないのです。
5.難しい民法へのアプローチ!本試験問題の特徴と対策
ここまでの内容で、民法が難しいのは「基本的な考え方が分かっていないこと」が原因だとお伝えしました。いくら大量の知識を覚えても、これが解決されない限り、民法を得意にすることは難しいです。
では、民法の考え方を身につけるには、どのように勉強していけば良いのでしょうか?
次の動画では、民法の本試験の特徴や、具体的なアプローチの方法について、伊藤塾の藤田講師が解説しています。
【行政書士試験】みんな苦手な民法へのアプローチ~超・リニューアルした「ブラッシュアップ100」~
6.まとめ
最後に、今回の記事のポイントをまとめます。
◉民法が難しいのは「覚えられない」からではない
◉難しいと感じる原因は、正しい思考プロセスが身についていないこと
◉民法の正しい思考の流れ
① まずは問題文を読んで、何が聞かれているか(テーマ)を把握する
② テーマ(論点)が分かったら、そこから覚えた条文、判例などを「想起」する
③ 最後に、問題文に書かれているケースを当てはめて、正誤の判断を行う
◉「覚えるべき知識」と「覚えてはいけない知識」を区別することも大切
・覚えるべき知識 → 条文の趣旨、要件と効果、第三者の定義など
・覚えてはいけない知識 → 事例と結論、過去問の回答、理屈で導けるもの など
◉民法が難しい・覚えられないと感じる方に試して欲しいこと
・図を書く習慣をつけて、問題の状況を整理する
・民法の考え方を理解し、分からない問題でも推測で答えを出すトレーニングをする
・毎日少しでも民法に触れる時間を作る
◉直前期に民法から離れたり、新しい知識を詰め込もうとするのはNG
◉重要基本事項だけを覚えて、覚えた知識を使えるようにすることが必要
以上です。
行政書士試験の民法は難しく、なかなか得点が伸びないと感じる方も多いかもしれません。
しかし、覚えるべきポイントを絞って、基本的な考え方さえ習得できれば、必ず合格への道が開けるはずです。
行政書士試験に挑戦したい方は、ぜひ法律資格専門の指導校である伊藤塾へご相談ください。伊藤塾では、法律を初歩からしっかり学習していくことができる「行政書士合格講座」を開講しています。
夢の実現に向けて、ぜひ一歩を踏み出してみてください。伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。