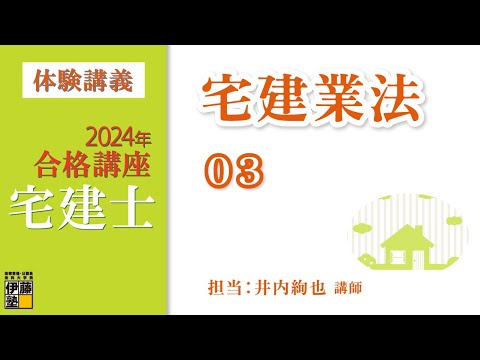宅建業法とは?宅建士試験で満点を目指すコツを解説
勉強法
2025年10月06日


宅建士試験では、宅建業法という法律から毎年20問出題されます。不動産取引を業務として行う場合の規制に関する法律ですが、例年難易度はそこまで高くありません。
基本的な知識を問う問題であり、かつ過去に出題されたことのある知識を聞かれることも多いので、正しい方向で勉強を進めれば、必ず9割から満点を安定して取れるようになる科目でもあります。
法令上の制限のように取り組みにくい科目でもないので、法律初学者が学習しやすいのもこの法律の特徴です。
この記事では、宅建業で満点を取るためのコツについてわかりやすく解説していきます。
宅建業法で満点を取れれば一気に宅建士試験合格が近づくので、ぜひ最後までご覧ください。
【目次】
1. 宅建業法とは
宅地建物取引業法(宅建業法)は宅地や建物などの不動産取引の場面における規制に関する法律です。
高額な不動産を取引する際に、知識のない消費者が不利益を被らないように保護することを主な目的としています。例えば、次のような規制が規定されています。
・宅地建物取引業を営むためには、国土交通大臣もしくは都道府県知事の免許が必要である
・消費者の誤解を招くような誇大広告の禁止
・宅建取引業者が受けられる報酬には上限がある
・宅建取引業者の宅建士設置義務
他にも、クーリングオフ制度や契約時の重要事項説明に関する規定など、一般の消費者を守るために様々な規定があります。これらの法律は、実際に宅建士として働く上でも重要な規制です。また、仮に宅建士を足がかりに他の資格にチャレンジする場合でも、宅建業法で学んだ法律の考え方は必ず役に立つといえます。
なお、宅建士試験について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
→【500時間必要?】宅建士試験の合格に必要な勉強時間について徹底解説!
→ 宅建に合格するとすごい?一発合格は可能?宅建のリアルを解説
→ 宅建士試験はどれくらい難しい?偏差値60相当?合格への道筋を解説
1-1. 宅建士試験では宅建業法の配点が最も高い
宅建士試験の出題科目及び出題範囲は、以下の通りです。
| 試験科目 | 問題数 |
| 権利関係 (民法等) | 14問 |
| 宅建業法 | 20問 |
| 法令上の制限 | 8問 |
| 税・その他 | 3問 |
| 免除科目 | 5問 |
試験形式は四肢択一のマークシート形式で、配点は1問につき1点です。50点満点の試験なので、宅建業法だけで全体の4割が出題されることになります。
宅建士試験の合格基準点は、例年35点〜38点前後で推移しています。令和6年度に実施された宅建士試験の合格基準点は37点だったため、宅建業法で満点を取れればそれだけで合格基準点の半分は得点できる計算になります。
2. 宅建業法の出題範囲
宅建士試験で出題される法令等については、宅建業法7条および8条で次のように規定されています。
・土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
・土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
・土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
・宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
・宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
・宅地及び建物の価格の評定に関すること。
・宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
※ 出題の根拠となる法令は、試験を実施する年度の4月1日現在施行されているものです。
参照:宅建試験の概要|一般財団法人 不動産適正取引推進機構
宅建業法については特に試験範囲が限定されていないので、規定されている内容については全て試験範囲として本番で出題される可能性があります。
とはいえ、宅建業法の条文全てを暗記する必要はありません。毎年出題される規制や頻出分野に絞って勉強すれば、効率よく本番で高得点を取れるだけの実力を身につけることができるでしょう。
出題の可能性が低い部分を重点的に勉強しても得点力は身につかないので、注意してください。
3. 宅建業法の難易度
宅建業法の難易度は、他の科目と比べてもそこまで高くありません。例えば、令和5年度の宅建士試験では、次のような問題が出題されています。
【問 28】 宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。
ア Aの従業員Bが、Cが所有する戸建住宅の買取りを目的とした訪問勧誘をCに対して行ったところ、Cか ら「契約の意思がないので今後勧誘に来ないでほしい」と言われたことから、後日、Aは、別の従業員D に同じ目的で訪問勧誘を行わせて、当該勧誘を継続した。
イ Aの従業員Eは、Fが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をFに対して行った際に、不実の ことと認識しながら「今後5年以内にこの一帯は再開発されるので、急いで売却した方がよい。」と説明 した。
ウ Aの従業員Gは、Hが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をHに対して行おうと考え、23 時頃にHの自宅に電話をかけ、勧誘を行い、Hの私生活の平穏を害し、Hを困惑させた。
エ Aは、Jとの間でJが所有する戸建住宅を買い取る売買契約を締結し、法第37条の規定に基づく書面をJ に交付したが、Aの宅地建物取引士に、当該書面に記名のみさせ、押印させることを省略した。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
引用:令和5年度 問題 問28|REITO 一般財団法人不動産適正取引推進機構
この問題は、アイウの3つが間違いとなり正解は3になるのですが、宅建業法を勉強したことがない方でも、感覚的に間違いの肢を選択できるのではないでしょうか。
エについては、「37条書面への宅建士の押印義務はない」という知識が必要になりますが、近年、契約書の電子化等が進み実際に印鑑を押さない場面も増えてきていることから、令和4年5月から開始された37条書面(契約書面)への押印義務の廃止についても覚えやすいかと思います。
このように、宅建業法で出題される内容は基本的な知識を問う問題が多いです。「なぜそのような規制が施されているのか」を常に意識して勉強すると、本番で見たことがない問題が出題された際に、適切な回答を選択する力が身につきます。
3-1. 宅建業法は満点を目指すべき
宅建業法は、宅建士試験の中で最も配点比率が高い科目です。得意・不得意はあるかもしれませんが、満点を目指すのが正しい受験戦略と言えるでしょう。稀に意地悪な問題も出題されますが、その問題は正解できなかったとしても、できれば9割以上の得点率は維持したいところです。
民法や法令上の制限などに比べると問題の難易度も低く、比較的取り組みやすい科目です。宅建業法で満点もしくは9割以上得点しておけば、他の科目での失点をカバーできます。過去問学習を通して安定して得点できる力を身につけましょう。
4. 宅建業法で満点を取るためのコツ
とはいえ誰にでも得意・不得意はあるので、いくら勉強してもなかなか得点に結びつかないこともあるでしょう。法律を初めて学ぶ方にとっては、「法律」というだけで難しく感じてしまうこともあるかもしれません。
ここでは、宅建業法で満点を取るための5つのコツについて解説していきます。
・過去問で出題された部分を重点的に学習する
・周辺知識まで完璧に覚えようとしない
・法改正があった部分をチェックしておく
・表や図を使って繰り返し学習する
・ただの暗記ではなく理解を伴った学習をする
4-1. 過去問で出題された部分を重点的に学習する
宅建業法について学習する際は、過去問で出題された分野を重点的に学習することを心がけてください。
宅建士試験では、過去に出題された問題が角度を変えて繰り返し出題されている傾向にあります。そのため、過去問を中心に学習し、出題された問題とその周辺知識を学ぶように学習すれば、効率良く得点力を身につけることができます。出題範囲を絞れば、出題される分野を重点的に学習するなどメリハリをつけた勉強もできるようになるでしょう。
特に、次の分野については重点的に学習しておくことをお勧めします。
| ・35条書面(重要事項説明書) ・37条書面(契約書) ・自ら売主制限(8種制限) ・免許 |
不動産取引を取り扱う専門家になるための試験なので、契約時における重要事項説明や契約書に関する知識は必要不可欠です。また、専門的知識のない一般消費者が損害を被らないためにも、クーリングオフや違約金等の定めに関する知識も身につけておく必要があります。
4-2. 周辺知識まで完璧に覚えようとしない
宅建士試験は、全体の75%程度得点できれば合格できる試験です。過去問を解く際には、周辺知識を完璧に覚えようとしすぎないよう注意しましょう。
確かに、過去問で出題された問題に対する回答だけでなく、その周辺知識も覚えていけば知識量は増えていきます。しかし、全てを完璧に覚えようとすると結局全ての知識が中途半端になり、本番で得点に結びつかない可能性があります。
過去問を繰り返し解いて基礎的な知識が十分身についてから、周辺知識まで手を広げるようにしましょう。100の曖昧な知識より、10の正確な知識を身につけるよう心がけましょう。
4-3. 法改正があった部分をチェックしておく
宅建業法に限らず、法律は定期的に改正されます。宅建業法についても例外ではないので、改正された法律についてもしっかりチェックしておきましょう。
直近の法改正を見てみると、「重要事項説明の対象となる建物状況調査の結果について、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等に限り、調査実施後2年以内(改正前は1年以内)のものが対象」に変更となりました。
「電磁的方法による提供」に関する改正など、近年行われた法改正についても繰り返し問われる可能性があるので、問題を通して改正点を確認しておきましょう。
4-4. 表や図を使って繰り返し学習する
宅建業法を勉強する際は、表や図を使って比較しながら覚えることも重要です。
例えば、宅地建物取引業者および宅地建物取引士に対する処分後の公告の要否につき、次のような表作成が有効です。
【処分後の公告の要否】
| 処分の 相手方 | 指示処分 | 業務停止 処分 | 免許取消 処分 |
| 宅地建物 取引業者 | 不要 | 必要 | 必要 |
| 宅地建物 取引士 | 不要 | 不要 | 不要 |
覚え方は人それぞれですが、表を作成して比較することで、処分後に公告が必要な場合について整理することができます。
◉指示処分を受けても業務を行うことは可能なので、わざわざ公告する必要はない
◉宅建士個人が業務停止処分や免許取消処分を受けても、他の宅建士が業務を引き継げるので、公告しなくても消費者に不足の損害を生じさせない
などと理由も合わせて覚えるようにすると、理解が深まり記憶が定着します。
表や図は、既存のものでも自分で作成したものでも構いません。
受験指導校のテキスト等に書かれているものを使えば、正確な情報を落とし込めるだけでなく、作成時間をかけることもありません。
4-5. ただの暗記ではなく理解を伴った学習をする
宅建業法では細かい数字が問われることもありますが、基本的に「なぜそのような規制がされているのか」を常に考えながら勉強することが大切です。
例えば、令和5年に行われた宅建士試験では、次のような問題が出題されました。
【問 39】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合における手付金の保全措置に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、当該契約に係る手付金は保全措置が必要なものとする。
1 Aは、Bから手付金を受領した後に、速やかに手付金の保全措置を講じなければならない。
引用:令和5年度 問題 問28|REITO 一般財団法人不動産適正取引推進機構
選択肢1は誤りとなるのですが、「買主から手付金が支払われたら、とにかく保全措置を講じる必要がある」とだけ覚えていると、正しい回答を導くことはできません。
手付金の保全措置が必要な理由は、手付金が返還されない事態を防ぐことで弱い立場である消費者を守ることにあります。例えば、宅地建物取引業者が一般の方と売買契約を結んだ後に、業者が倒産して手付金が返還されない、という事態を防ぐことにあります。
「手付金をもらってから保全措置を取ればいい」とすると、悪質な業者が保全措置を怠り消費者に不足の損害が発生する可能性があります。したがって、「保全措置は手付金をもらう前に施す必要がある」ということになるのです。
このように、法律で規制されている内容には全て理由(趣旨)があります。
単純な暗記が必要になる部分もありますが、その場合には自分が納得できるような理由を自分でつけることで、長期的に覚えることができるようになります。
また、覚える際は具体的な場面をイメージするとわかりやすいです。家を買う場面や賃貸をする場面などを具体的に想像しながら覚えていくと、規制の内容や対象を覚えやすくなるでしょう。
5. 質の高い講義とテキストを使い、宅建業法で満点を獲得しよう!
宅建業法で満点を取ることができれば、宅建士試験合格に一気に近づきます。どんな問題が出題されても安定して9割以上得点できるようにするためには、受験に特化した受験指導校のテキストを使って勉強することをお勧めします。
宅建士試験は、基本的に重箱の隅をつつくような問題は出題されず、資格取得の難易度はそこまで高くありません。しかし、法律の試験であることに変わりはなく、法律の初学者が独学で勉強を開始しても、法律用語や専門用語が多く何を言っているのか理解できない場合も多いのも事実です。
「なぜそのような規制になっているのか」まで記載されていない参考書も多いので、暗記ベースの勉強法になってしまい長期的に覚えられない知識になってしまう可能性も高いでしょう。
受験指導校では、暗記だけの勉強にならないようわかりやすく噛み砕いて内容を説明してくれるため、理解を伴った知識を身につけることが可能です。
覚え方のポイントや満点を取るコツ、頻出分野や出題予想等についてもアドバイスをもらえるので、「講義を聞いていれば宅建士試験で合格するために必要な知識を身につけられる」という安心感も得られます。
いち早く宅建士試験に合格して次のステップに進むためにも、ぜひ受験指導校の活用を検討してみてください。
※こちらも併せてお読みください。
→ 宅建の通信講座はなぜ伊藤塾がおすすめなのか?宅建士合格講座の魅力を徹底解説
6. まとめ
宅建業法は満点を取ることができる科目です。
満点を取るコツとして以下の5つについて解説しました。
◉過去問で出題された部分を重点的に学習する
◉基礎的な知識が定着する前から、周辺知識まで完璧に覚えようとしない
◉法改正があった部分をしっかりチェックしておく
◉表や図を使って繰り返し学習する
◉ただの暗記ではなく理解を伴った学習をする
宅建士試験では、宅建業法に関する問題が20問出題されます。
満点を取ることができればそれだけで合格基準点の半分以上は取れることになるため、他の科目で失点してもカバーすることができます。
基礎的な出題も多く「法令上の制限」よりも取り組みやすい内容なので、合格者が比較的高得点を取っている科目でもあります。
安定して得点するためには、曖昧な知識ではなく正確な知識をいかに身につけられるかがポイントです。単純暗記ではなく、規制の趣旨や目的を常に意識して勉強しましょう。
宅建士試験に合格すれば、今後の人生を大きく変えられる可能性があります。
宅建士試験対策には、ぜひ法律資格専門の指導校である伊藤塾をご活用ください。
伊藤塾の「宅建士合格講座」は、2025年からバージョンアップし、よりカリキュラムが充実しました。
「宅建士合格講座」の内容・特長について井内絢也講師がお伝えしていますので、初めての法律資格試験として、宅建士試験を目指そうとしている方、行政書士試験、他資格などのWライセンス取得を目指している方は、是非ともご視聴ください。