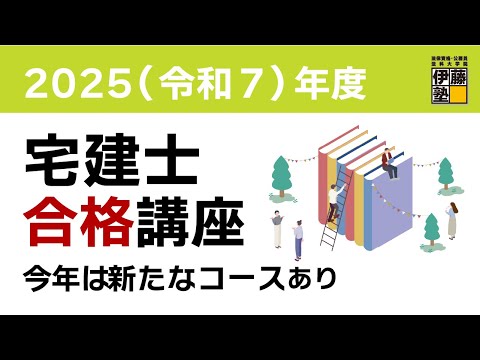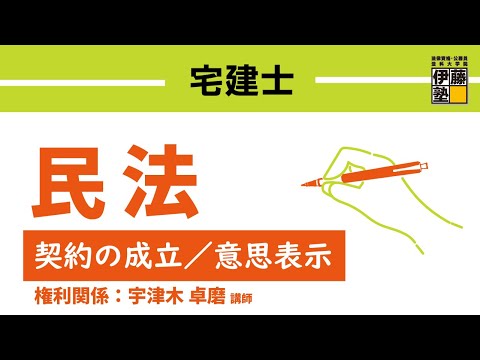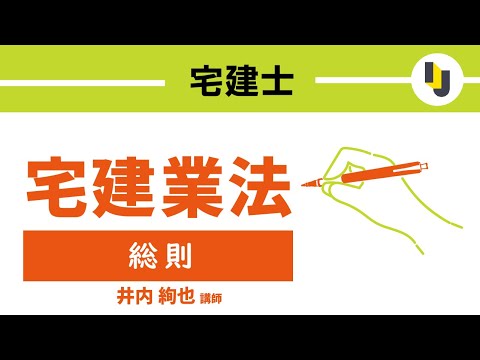宅建に3ヶ月で合格は無理?最短合格のポイントと注意点を解説
勉強法
2025年10月06日


「仕事や家事で忙しく、勉強時間は3ヶ月ほどしか取れない」「短期間で一発合格を狙いたい」という方の中には、「本当に3ヶ月で合格できるのだろうか」と不安を感じる方も多いでしょう。
宅地建物取引士(宅建士)は、毎年20万人以上が挑戦する人気の国家資格です。取得するとキャリアアップや転職に大きな武器となるため、多くの方が合格を目指しています。
しかし、宅建士試験は法律系の国家資格であり、初めて学ぶ方の場合は半年から1年程度かけてじっくり勉強するのが一般的です。そのため、3ヶ月という短期間で合格を目指すには、効率的に学習を進めて確実に得点力を伸ばすことが不可欠です。
本記事では、宅建士試験に3ヶ月で合格するための現実的な学習方法やスケジュール、注意点などをわかりやすく解説します。
【目次】
1. 宅建士試験に3ヶ月で合格は無理?
結論としては、限られた時間を無駄なく効率的に使えば、3ヶ月で宅建士試験に合格することは可能です。実際に仕事や家事の合間に毎日コツコツと勉強時間を確保し、スキマ時間を賢く活用して短期間で合格を掴み取る方も少なくありません。
3ヶ月合格の最大のポイントは、「限られた時間をいかに効果的に使うか」です。漫然とテキストを読むだけでは時間が足りず、短期間での合格は難しいでしょう。過去問の出題傾向をしっかり押さえ、合格に直結する重要分野に絞って学習を進めることが欠かせません。
適切な学習計画を立て、集中して取り組めば、3ヶ月でも合格圏内に届きます。これから紹介する勉強法やスケジュールを活用して、最短合格への第一歩を踏み出しましょう。
2. 宅建士試験に3ヶ月で合格するための勉強スケジュール
3ヶ月という短期間での合格を目指すなら、事前にしっかりと学習スケジュールを立てることが欠かせません。
宅建士試験の出題範囲は広く、闇雲に勉強していては時間切れになる恐れがあります。効率良く合格ラインを突破するには、「いつまでに、何を、どのくらい学ぶのか」を明確にしておく必要があります。
勉強スケジュールは人によって異なりますが、勉強スケジュールの一例をご紹介します。
【1ヶ月目】基礎知識のインプット
1ヶ月目は、基本テキストを使って全体像をつかみ、重要な法律用語や基礎知識を習得する期間に充てます。
多少分からない部分があっても、とにかく前に進むことを意識してください。全体を学んだ後に分からない部分に戻ることで、不明点が分かるようになるケースもあるからです。
使用する教材は、信頼できるテキスト1冊に絞り込みましょう。いろいろな教材に手を出すと学習効率が落ち、3ヶ月では間に合わなくなります。
特に重点的に学ぶべき科目は、配点が高い「宅建業法」や「権利関係(民法等)」です。まずはこれらの科目から優先的に進めるのがポイントです。
【2ヶ月目】過去問演習+理解の深化
2ヶ月目は、過去問を中心に演習し、得点力を養う期間となります。
宅建士試験は出題傾向が比較的安定しており、過去問学習の効果が高いため、ここで過去5年分の問題を繰り返し解きましょう。
問題を解いた後は、間違えた箇所や曖昧な知識をテキストに戻って復習し、理解を深めていきます。特に宅建業法は配点が高いため、ミスを減らし確実に得点できるように仕上げていくことが重要です。
最初のうちは正答率も低いかもしれませんが、問題を解いて解説を理解していくことで、知らぬ間に解ける問題数も増えていきます。解説などで示される図解や表などをノートやスマホなどに保存しておくと、スキマ時間に見返すことができて効果的です。
【3ヶ月目】総仕上げと試験対策
3ヶ月目は、総復習と本番対策に集中する重要な時期です。
まずは引き続き過去問演習を行い、解答スピードや正答率の向上を目指しましょう。宅建士試験は50問を2時間で解く必要があるため、1問あたりの時間配分を意識し、本番で時間切れにならないように訓練することが大切です。
また、公開模試を受験したり、時間を計って予想問題集を解く訓練などを取り入れるのも効果的です。本番に近い形式で問題を解くことで、苦手分野を最終チェックできるほか、試験当日の緊張感や雰囲気に慣れることができます。
さらに、試験で未知の問題に直面した際の解答テクニックも身につけられます。どの選択肢を選べば正解に近づけるかといった判断力を養うことが、合格を左右する重要なポイントです。
3. 宅建士試験に3ヶ月で合格するためのポイント
3ヶ月という短期間で合格を目指すには、効率の良い学習が不可欠です。そのためには「何をどこまで学ぶか」「どんな順序で学ぶか」を明確にし、ムダな学習や時間の浪費を避けることが重要です。
そこで、短期合格を実現するための5つの重要なポイントを以下にまとめてみました。
・インプット教材は最小限に抑える
・過去問中心の学習を行う
・スキマ時間を有効活用する
・試験科目ごとにメリハリをつけて勉強をする
・各科目で目標点数を設定する
順に解説していきます。
3-1. インプット教材は最小限に抑える
インプットに使用する教材は、信頼できる1冊に絞り込むことが成功の最大のポイントです。
宅建士試験の参考書や問題集は市場に多数ありますが、複数の教材を手当たり次第に使うと、内容が重複したり混乱したりして効率が落ちます。
特に3ヶ月という限られた勉強期間では、あれこれ手を広げる余裕はありません。「これさえあれば大丈夫」という1冊の教材を選び、繰り返し読み込むことで基礎知識を確実に身につけましょう。繰り返しのインプットが理解を深め、記憶の定着につながります。
また、同じ教材を使い続けることで、学習の進み具合や理解度が把握しやすくなり、弱点の発見や対策もスムーズに行えます。教材選びは、分かりやすさや最新の法改正に対応しているかも重視してください。
限られた時間の中で効率的に学習するためには、教材の絞り込みが欠かせません。信頼できる1冊を徹底的に活用し、短期間での合格を目指しましょう。
3-2. 過去問中心の学習を行う
宅建士試験に合格するためには、過去問を中心に学習することが非常に効果的です。
宅建士試験では、過去の問題と似た形式・内容の問題が毎年繰り返し出題されています。過去問が解けるようになれば、それだけである程度の得点は取れるようになるでしょう。
基本的な知識をテキストで身につけたら、できるだけ早い段階で過去問に取り組み、出題者が何を問いたいのか、その意図を理解することが得点力アップにつながります。
具体的には、過去5年分の過去問を繰り返し解きましょう。間違えた問題や苦手な分野は重点的に復習し、知識を確実なものにしていくことが重要です。過去問演習を重ねるうちに、試験でよく出るテーマやパターンが自然と頭に入ってきます。
過去問中心の学習を行うことは、知識のインプットとアウトプットを効率よく両立させる学習法でもあります。特に短期間で合格を目指す場合は、過去問中心の学習スタイルを基本と考え、集中して取り組みましょう。
3-3. スキマ時間を有効活用する
3ヶ月という短期間で宅建士試験に合格するためには、毎日のスキマ時間をいかに活用するかが大きなポイントとなります。
まとまった学習時間を確保するのが難しい場合でも、通勤や移動の合間、昼休み、家事の合間などのスキマ時間を上手に使うことで、1日あたりの総学習量を増やせます。
例えば、スマホやタブレットで講義動画を視聴したり、一問一答形式のアプリで問題を解いていくのが効果的です。また、耳からの学習も有効です。音声教材や講義をイヤホンなどで流しておけば、移動中や手が離せない作業中でも学習時間に変えることができます。
1日単位で見るとわずかな時間でも、積み重ねれば大きな差になります。短期合格を目指すなら、スキマ時間を最大限に活用する意識を持ちましょう。
3-4. 試験科目ごとにメリハリをつけて勉強をする
宅建士試験の出題は大きく分けて「権利関係」「法令上の制限」「宅建業法」「税・その他」の4分野に分かれています。科目ごとに得点配分が異なるため、メリハリをつけた学習が大切です。
【宅建業法】
宅建士試験の中で最も配点が高く、得点源となる宅建業法は重点的に学びましょう。毎年出題傾向が安定しているため、比較的得点しやすい科目です。ここでしっかり得点を確保できれば、合格が一気に近づきます。
【権利関係】
「権利関係」は範囲が広く難易度も高めですが、全問を完璧にする必要はありません。頻出テーマや得点しやすい問題を優先的に学び、確実に取れる問題を押さえておくことが重要です。
【法令上の制限】【税・その他】
「法令上の制限」や「税・その他」については出題数が限られているため、頻出分野を中心に効率的に学習しましょう。2ヶ月から3ヶ月目でまとめて知識を詰め込む方法も、短期合格を目指す場合には有効な方法です。
短期合格のためには、科目の特性や自分の得意・不得意を見極め、学習の優先順位を明確にして勉強を進めることが大切です。「どの科目で点を稼ぎ、どこを最低限に抑えるか」を意識することが、短期合格の近道になります。
3-5. 各科目で目標点数を設定する
宅建士試験で3ヶ月合格を目指すなら、科目ごとに目標点数を明確に設定することが大切です。
宅建士試験は50問出題され、合格ラインは年度によって若干の変動はあるものの、概ね36点前後(72%程度)となっています。そのため、どの科目で何点を取るのか、具体的な目標を決めて学習を進めると効率的です。
例えば、出題数や得点しやすさを踏まえて、以下のような目標配分が考えられます。
| ・宅建業法(20問) :16~18点を目標 ・権利関係(14問) :7~9点を目標 ・法令上の制限(8問):5~6点を目標 ・税・その他(8問) :5~6点を目標 |
こうして各科目の目標を明確にしておけば、勉強の進捗管理や弱点補強がしやすくなります。また、本番で全問正解を狙う必要はなく、合格ラインに届く得点を計画的に目指すことが現実的な戦略です。
限られた時間の中で最短合格を目指すなら、闇雲に全科目を詰め込むのではなく、目標点数を意識しながら学習のメリハリをつけることが重要です。
4. 宅建士試験に3ヶ月で合格を目指す場合の注意点
3ヶ月という短い期間で宅建士試験の合格を目指す場合、効率的な勉強法だけでなく、いくつか意識すべき注意点もあります。無計画に勉強を始めてしまうと途中で挫折したり、試験本番に間に合わなくなったりする可能性もあります。
ここでは、3ヶ月で合格を目指す際に押さえておきたいポイントや注意点をまとめてみました。
・合格までに必要な勉強時間を確保する
・満点での合格を目指さない
・実現可能な勉強計画を立てる
・確実に得点できる問題を落とさないようにする
・苦手分野に固執しすぎない
・途中でモチベーションが切れない工夫を
・生活リズム・体調管理にも気を配る
それぞれ具体的に解説していきます。
4-1. 合格までに必要な勉強時間を確保する
宅建士試験に合格するために必要な勉強時間は、一般的に300〜500時間程度といわれています。ただし、必要な時間は人それぞれで、過去の学習経験や法律知識の有無、受験指導校活用の有無によっても異なります。
3ヶ月という短期間で合格を目指す場合は、自分の目安に応じて勉強時間をしっかり確保することが大切です。仮に300時間を目標とするなら、1日平均で約3時間半〜4時間程度の学習が必要になります。500時間を目指すなら、平日は3〜5時間、休日はさらに多めに勉強時間を取る必要があるでしょう。
仕事や家事との両立でまとまった時間が取りにくい場合は、通勤時間や昼休み、家事の合間などのスキマ時間を活用して、日々コツコツ積み上げていく工夫が欠かせません。週末や休日にはまとまった時間を使って、理解が難しい箇所の復習や模擬試験に取り組むことが効果的です。
4-2. 満点での合格を目指さない
宅建士試験の合格ラインは、年度によって若干の変動はあるものの、概ね36点前後(50問中)です。つまり、合格するためには全問正解を目指す必要はありません。
3ヶ月という短い期間で合格を狙う場合、限られた時間内で全範囲を完璧に理解しようとすると学習が非効率になってしまいます。試験範囲の知識を網羅的に覚えて満点合格を目指すのではなく、合格ラインを確実にクリアすることを目標にしましょう。
出題頻度の高い分野や得点源となる科目を優先的に学び、難易度が高く出題頻度が低い問題は、ある程度割り切って学習時間のバランスを取ることが大切です。
限られた期間の中で「合格する」という目標に集中し、無理に満点を狙わない意識を持つことが、結果的に合格への近道となります。
4-3. 実現可能な勉強計画を立てる
3ヶ月という短い期間で宅建士試験の合格を目指すなら、「自分にとって実現可能な勉強計画」を立てることが非常に重要です。
最初にやりがちなのが、張り切って無理なスケジュールを立ててしまい、途中で消化不良になって挫折してしまうパターンです。例えば「平日は毎日5時間、休日は10時間勉強する」といった計画は、仕事や家庭の都合を考えると現実的ではない場合も多いでしょう。
まずは自分の生活リズムや仕事・家事の予定を確認し、「平日は何時間確保できるか」「週末にまとまった学習時間が取れるか」といった現実的な見通しを立ててから、スケジュールを作成しましょう。
また、最初から完璧な計画を立てようとする必要はありません。週ごとや月ごとに進捗を確認し、必要に応じて柔軟に修正していくことも大切です。
3ヶ月という限られた時間を最大限に活用するためにも、実現可能で無理のない計画作りを意識しましょう。
4-4. 確実に得点できる問題を落とさないようにする
短期間で合格を目指す場合は、「確実に得点できる問題を確実に取る」ことが非常に重要です。
宅建士試験では、毎年の出題傾向が安定している分野や、比較的難易度が低く正答率が高い問題も多く含まれています。こうした「取りこぼしてはいけない問題」をしっかり得点することが、合格ライン突破の鍵になります。
逆に、難易度の高い応用問題や出題頻度の低い特殊な問題は、時間をかけすぎず、割り切る判断も必要です。全問正解を目指すのではなく、自分が確実に正解できる問題を積み重ねていくことが大切です。
過去問演習を通じて「よく出る問題」「自分が間違えやすい問題」を把握し、重点的に復習しておきましょう。本番でも見直しの時間を確保してケアレスミスを防ぐ工夫が必要です。
3ヶ月という限られた時間の中では、こうした戦略的な取り組みが結果に直結します。合格に必要な得点を着実に積み上げていきましょう。
4-5. 苦手分野に固執しすぎない
短期間での合格を目指す場合、苦手な分野に時間をかけすぎるのは避けた方が良いでしょう。
なぜなら、全体の学習バランスを崩してしまい、得意な分野や得点源となる分野の対策が不十分になってしまうリスクがあるからです。
苦手な分野もある程度は押さえておく必要がありますが、「時間をかけた分だけ得点につながるか」という視点で優先順位をつけることが大切です。限られた学習時間を有効に活用するためには、まずは出題頻度が高く得点しやすい分野をしっかり固め、全体の合格ラインをクリアすることを第一に考えましょう。
苦手分野を「完璧に克服しよう」と考えるより、「最低限押さえておくべきポイントを理解する」程度の割り切りも、短期合格のためには必要な判断と言えます。
4-6. 途中でモチベーションが切れない工夫を
3ヶ月という短期間で集中的に勉強するには、高いモチベーションを維持することが欠かせません。最初は意気込んでスタートしても、思うように勉強が進まなかったり、疲労がたまったりして途中で気持ちが切れてしまうこともよくあります。
そこで意識したいのが「小さな成功体験を積み重ねる」ことです。例えば「今週は過去問を30問解く」「宅建業法の1章を読み終える」など、達成可能な小さな目標を立ててクリアしていくことで、達成感が得られ、次への意欲につながります。
また、勉強記録をアプリや手帳に書き残すのも効果的です。自分の努力が「見える化」されることで、自信がつき、やる気が持続しやすくなります。
さらに、家族や友人に宅建士試験の勉強をしていることを宣言してみるのも一つの方法です。周囲の応援や励ましを受けることで、自分へのプレッシャーが程よい刺激となり、途中で投げ出しにくくなります。
「3ヶ月後に必ず合格している自分を想像する」といったポジティブなイメージを持つことも大切です。うまくモチベーションをコントロールしながら、最後まで学習を継続していきましょう。
4-7. 生活リズム・体調管理にも気を配る
宅建士試験に短期間での合格を目指すためには、効率的な学習だけでなく、健康管理も欠かせません。特に3ヶ月という集中期間中は、生活リズムを整え、体調を良好に保つことが合格への大きなポイントとなります。
不規則な生活や睡眠不足は集中力や記憶力を低下させ、勉強の効率を大きく下げてしまいます。毎日同じ時間に起きて寝る「規則正しい生活リズム」を意識し、質の良い睡眠を確保することが重要です。
また、適度な運動やバランスの良い食事も、体調を維持し精神面の安定につながります。疲れがたまった時は無理せず休息を取り、ストレス解消やリフレッシュの時間を設けることも効果的です。
生活リズムや体調管理を疎かにせず、心身ともにベストな状態で勉強に取り組むことが、3ヶ月での合格を現実的にするポイントです。
5. 宅建士試験に3ヶ月での合格を目指すなら受験指導校の活用を
宅建士試験に短期間で合格を狙う場合、効率的な学習方法と明確な計画が必要不可欠です。
独学で短期間に必要な知識と解法を身につけることは不可能ではないものの、簡単なことではありません。そのため、多くの受験生が「受験指導校」の利用を検討しています。
受験指導校の最大のメリットは、試験内容に精通したプロの講師から直接学べることです。各講師は試験の出題傾向や頻出ポイントを熟知しており、独学では見落としがちな重要テーマや効率の良い勉強法を具体的に教えてくれます。これにより、限られた学習時間で重点的に対策すべきポイントが明確になり、無駄なく合格に必要な知識を吸収できます。
例えば、伊藤塾の宅建士合格講座では、最新の試験傾向や法改正を反映したテキストを使用し、重要事項はもちろん、頻出テーマなど受験生が把握しておくべき論点を重点的に学習していきます。
また、スキマ時間での学習に有効な「一問一答形式のWEBのドリル」を使い、インプットした知識を定着させていくほか、過去問演習の指導や公開模擬試験などを通して、短期間で着実に合格に必要な得点力を身につけるカリキュラムが組まれています。
さらに、個別カウンセリングやオンライン質問会などのサポート体制も整っているため、法律初学者でもつまづくことなく学習を進めていくことができます。
もちろん、オンライン講義ですから、自分のライフスタイルにあった学習が可能です。
※詳しくは、こちらをご覧ください。
→ 宅建の通信講座はなぜ伊藤塾がおすすめなのか?宅建士合格講座の魅力を徹底解説
このように、受験指導校の活用は、特に3ヶ月という短期間で宅建士試験合格を目指す場合に、効率的かつ計画的な学習を支える大きな助けとなります。独学での勉強で不安を感じている方は、ぜひ積極的に活用して合格への近道を進んでください。
6. 宅建士試験に3ヶ月で合格するのは無理?に関連するQ&A
Q1. 独学で宅建士試験に3ヶ月で合格することは可能?
A. 独学で宅建士試験に3ヶ月で合格することは不可能ではありませんが、かなり厳しいと考えておくべきでしょう。
独学の場合、どこに重点を置いて学習すればよいか迷いやすく、重要ポイントの見落としや非効率な勉強になりがちです。また、疑問点があってもすぐに解決できず、理解が深まらないまま時間だけが過ぎてしまうこともあります。
短期間での合格を目指すなら、独学に頼らず受験指導校の力を借りることをお勧めします。
Q2. 民法などの権利関係は3ヶ月でマスターできる?
A.「権利関係(民法等)」は宅建士試験の中でも特に難しい科目とされていますが、3ヶ月でも基本的な理解は十分可能です。
重要なのは、すべての細かい論点を完璧に理解することではなく、過去に頻出の基本問題を中心に押さえ、応用問題に時間をかけすぎないことです。
基礎的な法律用語や判例を理解した上で過去問演習で出題パターンを把握することで、合格に必要な力を効率よく身につけられます。
Q3. 宅建士試験に3ヶ月での合格を目指すなら1日どれくらい勉強すればいい?
A. 宅建士試験に3ヶ月での合格を目指す場合、一般的には合計で約300~500時間の勉強時間が必要とされています。これを90日で割ると、1日あたり3~5時間の学習が目安となります。
ただし、必要な勉強時間には個人差があります。法律学習経験者や不動産の知識がある方、受験指導校を利用している方は比較的短い時間で合格ラインをクリアできる一方、法律初学者で独学の場合、より多くの時間を要することもあります。
重要なのは勉強の「量」だけでなく「質」です。効率的な学習計画を立て、過去問演習を中心に重点的な対策を行うことで、短時間でも効果的に理解を深められます。
Q4. 宅建士試験の過去問は何年分やればいい?
A. 宅建士試験の過去問は、一般的に直近5年分を重点的に繰り返し学習することが効果的とされています。直近5年分は最新の試験傾向や法改正を反映しているため、しっかりと取り組むことが大切です。
Q5. 試験まで時間がない場合、どの科目から優先的に勉強すればいい?
A. 3ヶ月で合格するためには、まず「権利関係」と「宅建業法」に重点を置くことが効果的です。
これらの科目は試験の配点が高く、得点源となるため優先的に対策すべきです。
ただし、権利関係の中でも特に民法は範囲が広く難解なため、時間をかけすぎて他の重要分野が疎かにならないよう注意が必要です。基本的な重要ポイントを押さえ、過去問を繰り返し解くことに集中しましょう。
7. 宅建士試験に3ヶ月で合格することは可能だが簡単ではない
最後に、本記事の内容をまとめます。
◉宅建士試験に3ヶ月で合格することは可能であり、そのためには過去問を中心とした効率的な学習と、明確な学習計画が不可欠です。
◉短期合格のためのポイント
・インプット教材は最小限に抑える
・過去問中心の学習を行う
・スキマ時間を有効活用する
・試験科目ごとにメリハリをつけて勉強する
・各科目で目標点数を設定する
◉3ヶ月で合格を目指す上での注意点
・必要な勉強時間の確保
・満点を目指さない
・実現可能な勉強計画を立てる
・確実に得点できる問題を落とさない
・苦手分野に固執しすぎない
・モチベーション維持
・生活リズム・体調管理の重要性
以上です。
宅建士試験に3ヶ月で合格することは可能です。しかし、初学者が独学で短期合格することは簡単なことではありません。もし、あなたが短期間での合格を目指しているのなら、ぜひ受験指導校の活用をご検討ください。
伊藤塾では現在、2025年合格目標 宅建士合格講座を開講中です。
伊藤塾の「宅建士合格講座」は、2025年からバージョンアップし、よりカリキュラムが充実しました。
「宅建士合格講座」の内容・特長について井内絢也講師がお伝えしていますので、初めての法律資格試験として、宅建士試験を目指そうとしている方、行政書士試験、他資格からWライセンス取得を目指している方などは、是非ともご視聴ください。
「今年はさらにバージョンアップしたコースをご用意!「2025年合格目標 宅建士合格講座」 のご紹介です!」
法律知識ゼロの方でもわかりやすい講義で、短い学習時間で効率よく合格できる「宅建士合格講座」から、「権利関係」の民法「契約の成立・意思表示」の体験講義をご視聴いただけます。
是非、テキストとあわせてご覧ください。担当:宇津木 卓磨 講師
宅建業法「総則」の体験講義です。ぜひご覧ください。担当:井内 絢也 講師
伊藤塾は、宅建士試験に本気で挑む受験生を全力で応援しています。