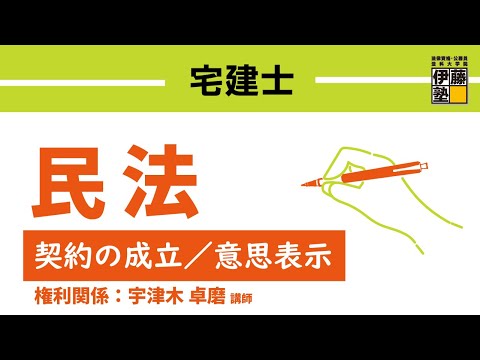【2025年】宅建の法改正まとめ!改正点や試験で得点するためのポイント
試験詳細
2025年10月06日


2025年(令和7年)の宅建士試験を控え、宅建業法をはじめとする様々な不動産関連の法改正が施行されました。本試験では最新の法改正が反映されるため、これらの変更点をしっかりと把握することが合格への重要なポイントとなります。
法改正に基づく出題は、単なる知識を問うだけでなく、実務に直結する重要な問題が多く含まれています。宅建士資格取得後に実務で活躍するためには、改正法に関する深い理解が必要不可欠です。
本記事では、2025年の宅建士試験に関連する法改正を網羅的に解説し、試験対策に役立つポイントを分かりやすくお伝えします。
【目次】
1. いつまでの法改正が宅建士試験で出題される?
宅建士試験では、試験実施年度の4月1日現在で施行されている法令が出題範囲となります。つまり、2025年(令和7年)10月に実施される試験では、2025年(令和7年)4月1日までに施行された法改正が対象となります。
試験範囲にはそれ以前に施行された法改正も含まれますが、直近の法改正は特に出題される可能性が高いため、重点的に学習することが重要です。
2. 【2025年】宅建士試験に関係のある最新の法改正一覧
2025年(令和7年)に実施される宅建士試験で抑えておきたい最新の法改正は、以下の通りです。
・従業者名簿における記載事項の変更(令和7年4月1日施行)
・宅建業者名簿における登載事項の変更(令和7年4月1日施行)
・宅地建物取引業者票(標識)における記載事項の変更(令和7年4月1日施行)
・指定流通機構(レインズ)への登録事項の追加と説明義務の強化(令和7年1月1日施行)
・国土交通大臣免許業者の免許申請等における申請先の変更(令和6年5月25日施行)
・建築確認の対象となる建築物の範囲の拡大(令和7年4月1日施行)
以下、それぞれ重要となるポイントを解説していきます。
2-1. 従業者名簿における記載事項の変更(令和7年4月1日施行)
従業者名簿には、従業員の住所、生年月日、性別などの個人情報が記載されていましたが、改正後はこれらの情報の記載が不要となります。
従業者名簿は、従業者だけでなく取引関係者も閲覧可能です。従業員のプライバシーを保護するために、これら個人情報の記載が廃止されました。
変更後の従業者名簿には、職務内容や勤務開始日など業務に関連する基本的な情報が記載されることになります。
2-2. 宅建業者名簿における搭載事項の変更(令和7年4月1日施行)
改正前は、宅建業者名簿に専任である宅地建物取引士(専任宅建士)の氏名を搭載することが義務付けられていましたが、個人のプライバシーなどへの配慮から、改正後は氏名の記載は不要となります。
2-3. 宅地建物取引業者票(標識)における記載事項の変更(令和7年4月1日施行)
これまでは事務所に掲示する標識に「専任の宅地建物取引士の氏名」を記載することが求められていましたが、改正後は、その氏名を記載する必要がなくなり、代わりに「専任の宅地建物取引士の人数」「事務所の代表者氏名」「宅地建物取引業に従事する者の数」を記載することになりました。ここでいう「代表者」とは、通常、店長や政令使用人を指します。
この改正により、事務所の標識には実務と関連性の高い情報が反映されることとなりました。
2-4. 指定流通機構(レインズ)への登録事項の追加(令和7年1月1日施行)
令和7年1月1日施行の改正では、指定流通機構(レインズ)への登録事項が追加されました。これにより、売主側の仲介業者は、取引状況に関する情報をより詳細に登録しなければならなくなりました。
具体的には、指定流通機構への登録事項に「当該宅地または建物の取引の申込みの受付に関する状況」が追加されています。この変更は、主に売主側の仲介業者が両手仲介(不動産会社が売主と買主の両方から仲介を依頼され、両者から仲介手数料を受け取る取引)を狙う場合に、虚偽の取引状況を登録して他の業者による取引を妨げる行為を防止するための措置です。取引状況が事実と異なる場合、監督処分(指示処分)の対象となる可能性があります。
この改正により、仲介業者は取引状況を正確かつ適切に登録する義務が強化され、取引の透明性が向上することが期待されています。
2-5. 国土交通大臣免許業者の免許申請等における申請先の変更(令和6年5月25日施行)
宅建業者が国土交通大臣免許を受けるための申請は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行われていましたが、改正後は、直接国土交通大臣(各地方整備局等)に申請を行うことになります。
また、都道府県知事免許から国土交通大臣免許への変更も同様に、申請先が直接国土交通大臣(各地方整備局等)に変更されることになりました。
これにより、免許申請手続きの流れが簡素化され、効率的な処理が進むことが期待されています。
2-6. 建築確認の対象となる建築物の範囲の拡大(令和7年4月1日施行)
令和7年4月1日施行の改正により、建築確認の対象となる建築物の範囲が拡大されました。これまでは、建築確認が必要な建物について、木造と非木造で要件が異なっていましたが、改正後は、都市計画区域外においても、建物の階数が2以上または延べ面積が200m²を超える場合、構造に関わらず建築確認が必要となります。
これにより多くの建物が建築確認を受けることとなり、建物の安全性や法令順守がより厳格に求められるようになります。
3. 押さえておきたい近年の重要な法改正
最新の法改正ではないものの、宅建士試験に関連する法改正で抑えておきたいものを4つピックアップしています。本試験でまだ出題されていない分野もあるので、改正のポイントを抑えて得点力をアップさせましょう。
3-1. 重要事項説明の対象となる建物状況調査結果の範囲(令和6年4月1日施行)
改正前は、建物状況調査結果が調査から1年以内であれば重要事項説明の対象となっていましたが、改正後は、共同住宅(RC造やSRC造)については調査から2年以内の結果も重要事項説明の対象とされるようになりました。木造戸建ての場合は調査実施から1年以内、共同住宅の場合は2年以内に行った建物状況調査結果が、重要事項説明の対象となります。
これにより、木造戸建てと共同住宅の取り扱いに違いが生まれ、より正確な説明義務が求められることとなりました。
3-2. 標準媒介契約約款におけるあっせん「無」における理由の記載(令和6年4月1日施行)
令和6年4月1日施行の改正により、標準媒介契約約款であっせん「無」の記載方法が変更されました。改正前は「あっせんを行わない」と記載するだけで済んでいましたが、改正後は、あっせんを実施しない理由を記載することが求められるようになりました。
また、あっせんの限界(瑕疵の有無を判断しないこと等)についても明記する必要があります。これにより契約内容が明確化され、トラブルの回避が期待されています。
2024年(令和6年)の宅建士試験では、次のような問題が出題されました。
【問 32】 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
4. Bが当該中古住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合は、Aは同項に規定する書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。
この選択肢では、「あっせんしない場合でも『無し』と記載は必要」ということが分かれば、「誤り」という正誤判定ができる問題でした。
今後の試験では、あっせんをしない理由やあっせんの限界に関する事項についても記載しなければならない点に、注意が必要です。
3-3. 空き家等に関する媒介報酬規制の見直し(令和6年7月1日施行)
令和6年7月1日施行の改正により、空き家等の媒介報酬に関する規制が見直されました。これまでは、不動産の売買価格が400万円以下の場合、不動産業者が受け取る仲介手数料と現地調査などの実費を合わせた最大額は18万円(税抜)でした。しかし、改正後は、売買価格が800万円以下の物件に対して、最大30万円(税抜)までの受領が可能となっています。
この変更により、特に低価格帯の物件の取引が促進され、不動産業者が積極的に仲介業務を行いやすくなることが期待されています。
3-4. 相続登記の義務化および相続人申告登記制度の創設(令和6年4月1日施行)
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。これにより、不動産の所有権を相続した相続人は、相続開始から3年以内に相続登記を申請する義務を負うことになりました。相続登記を怠った場合、最大10万円の過料が科される可能性があります。
また、相続登記ができない場合に備えて、新たに相続人申告登記制度が創設されました。この制度は、遺産分割協議が未完了でも、相続人が自らが相続人であることを登記することができるものです。相続人申告登記を行うことで、相続登記の申請義務を履行することが可能となります。
この改正により、相続登記を放置することがなくなり、土地や建物の所有権が明確化され、トラブルが防止されることが期待されています。
なお、相続人申告登記制度は、複雑な相続で遺産分割協議がまとまらない場合など、期限内に相続登記ができない場合に行う手続きです。申告登記後に相続人間での話し合いがまとまった場合には、改めて相続登記を行う必要があることに注意が必要です。
4. 宅建士試験の法改正に関する問題を落とさないための方法
宅建士試験では法改正に関する問題が頻繁に出題されます。改正部分のみに力を入れて他の重要な基礎項目の学習が疎かになるのは得策ではないため、効率良く改正ポイントを頭に入れていくことが試験対策上有効になります。
法改正情報に敏感になり、年明けから春先にかけて発表される改正情報を早期にキャッチアップすることが重要です。漏れなく情報を入手し確実に理解するためには、受験指導校の講座などを有効活用して、最新情報を効率的に学ぶとよいでしょう。
改正点について学ぶ際は、ただ改正法を丸暗記するのではなく、改正の背景や意図、改正前後で何が変わったのかを深く理解することが大切です。過去問との比較を行い、出題の仕方がどう変わるかをシミュレーションしておくと、本試験で改正法に関する問題が出題されても慌てずに対処できます。
予想問題集や模擬試験などを活用して、改正点を反復学習する方法も効果的です。改正法に関する問題を繰り返し解くことで、知識が確実に身につき、試験本番でも自信を持って臨むことができるようになります。
改正法に関する不安がなくなれば、他の科目を勉強する際にも余裕を持って取り組むことができ、全体の学習効率が向上するでしょう。
※こちらの記事も合わせて読まれています。
→ 宅建士試験に独学で合格するための効率の良い勉強法とは?後悔しないための注意点も解説
5. 2025年における宅建士試験の法改正に関するQ&A
5-1. 令和7年(2025年)の宅建試験には、どの法改正が出題されますか?
2025年(令和7年)に実施される宅建士試験は、2025年4月1日までに施行された法改正が出題範囲になります。どの改正法に関する知識が問われるかは明言できませんが、宅建士試験に関連する法改正の数はそこまで多くないので、改正のポイントを押さえて覚えることが重要です。「なぜそのような改正が行われたのか」という視点を持っておくと、本試験で出題された場合にも柔軟に対応できるようになります。
5-2. 令和7年(2025年)の宅建士試験に関する法改正をまとめたテキストはありますか?
令和7年(2025年)の宅建士試験に関連する法改正をまとめたテキストは、多くの受験指導校や書店で販売されています。特に、法改正に特化したテキストや問題集は、試験に出題される可能性の高い改正点をピックアップしているため、試験対策において非常に有効です。
しかし、テキストだけでは法改正の背景や実務への影響を十分に理解することが難しいことがあります。受験指導校の講義では、講師が改正の意図や実務での適用方法について詳しく解説してくれるため、理解が深まり、試験対策がより効果的になります。法改正対策としては、市販の参考書だけではなく、受験指導校の講義を活用することをお勧めします。
5-3. 細かい法改正を全て暗記しなければ合格できませんか?
試験に出題される可能性が低い、細かい法改正まで全て暗記する必要はありません。宅建士試験対策という意味では、重要な改正点に焦点を当てて学習することが大切です。過去問や予想問題集、予備校の講義などを活用して、どの改正が試験に出やすいかを見極め効率的に対策を進めましょう。
6. 法改正に不安があるなら、伊藤塾の「宅建士合格講座」で総合的な学習を
宅建士試験では法改正に関する問題が頻繁に出題されますが、独学で重要な法改正について網羅的に学ぶのは非常に難しく、重要な改正点を漏らしてしまう可能性があります。
法律系資格試験において圧倒的な合格実績を持つ伊藤塾が提供している「宅建士合格講座」では、最新の法改正に対応したカリキュラムを使い、改正の背景や目的まで深く理解しながら学習を進めることができます。これにより、単なる暗記に頼ることなく、試験で出題される改正内容を実務にも役立つ形で習得できるという特徴があります。
また、法改正だけでなく、宅建業法や権利関係(民法等)などの重要分野や、苦手意識を持つ人も多い法令上の制限、統計問題などについても、試験を知り尽くした講師による講義を活用することで、深く網羅的に知識を習得し、効果的に得点力を身につけることができます。
法改正に不安がある方や、試験全体をしっかり学びたい方は、法律知識ゼロの方でも、短い学習時間で効率よく合格できる伊藤塾の「宅建士合格講座」をぜひご活用ください。
※こちらの記事も読まれています。
→ 宅建の通信講座はなぜ伊藤塾がおすすめなのか?宅建士合格講座の魅力を徹底解説
※伊藤塾「宅建士合格講座」の無料体験動画をぜひご視聴ください。
※動画で使用しているテキストはこちらからご覧ください。
7. 2025年の宅建士試験に影響する法改正のポイント
本記事では、2025年(令和7年)の宅建士試験に出題される可能性のある法改正について解説しました。
ポイントを以下にまとめます。
◉2025年(令和7年)の宅建士試験では、令和7年4月1日までに施行された法改正が出題範囲となります。
◉特に重要な最新の法改正
・従業者名簿、宅建業者名簿、宅地建物取引業者票(標識)における記載事項の変更(いずれも令和7年4月1日施行)
・指定流通機構(レインズ)への登録事項の追加(令和7年1月1日施行)
・国土交通大臣免許業者の免許申請等における申請先の変更(令和6年5月25日施行)
・建築確認の対象となる建築物の範囲の拡大(令和7年4月1日施行)
◉近年の重要な法改正
・重要事項説明の対象となる建物状況調査結果の範囲見直し(令和6年4月1日施行)
・標準媒介契約約款におけるあっせん「無」の場合の理由記載義務化(令和6年4月1日施行)
・空き家等に関する媒介報酬規制の見直し(令和6年7月1日施行)
・相続登記の義務化および相続人申告登記制度の創設(令和6年4月1日施行)
◉宅建士試験の法改正問題で得点するためには、単に改正法を暗記するだけでなく、改正の背景や意図、改正前後で何が変わったのかを深く理解することが重要です。
◉全ての細かい法改正を暗記する必要はなく、重要な改正点に焦点を当てて効率的に学習することが合格への鍵となります。
以上です。
独学での法改正対策に不安がある方や、効率良く短期間での合格を目指している方は、ぜひ伊藤塾の「宅建士合格講座」をご活用ください。
伊藤塾では「合格後を考える」を理念として、合格することのみならず、「実務家」としての活躍も視野に入れた指導を行っています。資格は合格がゴールではなく、そこからがスタートです。
合格後、即戦力として活躍したい方は、ぜひ、伊藤塾で本当の実力を身につける学びを始めてみませんか?
伊藤塾は、あなたのチャレンジを全力で応援いたします。