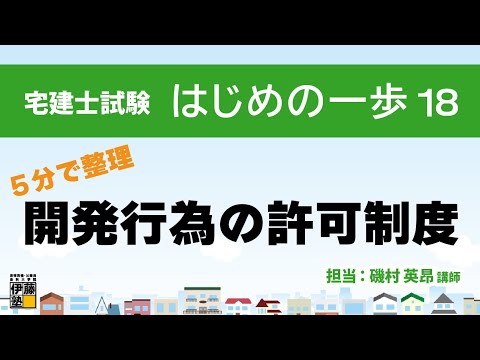宅建の開発許可を攻略!図表・ゴロ合わせで苦手意識を払拭し得点源に
勉強法
2025年10月10日


宅建士試験の「法令上の制限」で多くの受験生がつまずくのが、都市計画法の「開発許可」です。
「どの区域で、何㎡以上だと許可がいるの?」
「許可が不要になる例外が多すぎて覚えられない…」
そんな悩みを抱えていませんか?
本記事では、複雑な開発許可のルールを3つのステップで整理し、図解や表を使って視覚的にわかりやすく解説します。
さらに、試験で狙われやすい「許可不要の例外パターン」は、ゴロ合わせで楽しく記憶することができるように工夫しました。
最後に、過去問で力試しをして、あなたの知識を「わかる」から「解ける」レベルへと引き上げていきます。
本記事を読むことで、開発許可への苦手意識が少しでも払拭でき、自信を持って臨めるようになれば幸いです。ぜひ最後までお読みください。
【目次】
1.そもそも開発許可とは?目的を知れば理解が深まる
開発許可とは、一言でいうと「街づくりのルールを守るための許可」です。
もし誰もが好き勝手に土地を造成して建物を建ててしまうと、どうなるでしょうか。
道路が狭くて消防車が入れなかったり、下水道が整備されていなかったり、日当たりの悪い家が密集したりと、無秩序で住みにくい街になってしまいます。
そうした事態を防ぎ、計画的で安全な街づくりを進めることが開発許可制度の目的です。
具体的には、主として「建築物の建築」や「特定工作物の建設」を目的として行う「土地の区画形質の変更」に対して、都道府県知事等の許可を求める制度です。
少し難しい言葉が出てきましたが、要は「家などを建てるために、土地をいじる工事」には、原則として許可が必要だと考えてください。
| 用語 | かんたんな説明 |
| 開発行為 | 建物を建てる目的で、土地の形状など を変更する工事のこと |
| 土地の区画 形質の変更 |
道路を新設したり、土地を削ったり (切土)、盛ったり(盛土)すること |
| 許可権者 | 都道府県知事、または指定都市・中核 市・施行時特例市の長 |
2.【図解】開発許可が「いる?いらない?」を判断する3ステップ
開発許可の問題を解くカギは、正しい順番で検討することです。
どんなに複雑に見える問題でも、以下の3つのステップで考えれば、必ず答えにたどり着けます。
この思考フローをマスターしてしまいましょう。
【ステップ1】どの「区域」で開発するのか?
↓
【ステップ2】その工事は「開発行為」にあたるか?
↓
【ステップ3】区域ごとの「面積要件」を超えているか?
この3ステップをクリアすると、原則として開発許可が必要になります。
ただし、宅建士試験で最も重要なのは、この原則にあてはまっても許可が不要になる「例外」です。
まずはこの3ステップの原則をしっかり押さえましょう。
ステップ1. どの「区域」で開発するのか?
開発許可のルールは、場所によって厳しさが異なります。
都市計画法では、土地を大きく4つのエリアに分けています。
開発予定地がどのエリアにあるのかを、最初に確認するのが鉄則です。
| 区域の種類 | 特徴 | 開発へのスタンス |
| 市街化区域 | すでに市街地である か、概ね10年以内に 市街化を図るべき区 域 |
積極的に街づくり を進めたいエリア |
| 市街化 調整区域 |
市街化を抑制すべき 区域。自然環境など を守りたいエリア |
原則として開発は させたくない エリア |
| 非線引き 都市計画区域 |
市街化区域と市街化 調整区域の区分がな い都市計画区域 |
どちらとも言えな い、ゆるやかな規 制のエリア |
| 都市計画 区域外 |
上記のいずれでもな い区域。いわゆる「田舎」のイメージ |
規制は最もゆるや か |
ステップ2. 「開発行為」にあたるか?(特定工作物もチェック)
次に、行おうとしている工事が「開発行為」に該当するかをチェックします。
開発行為とは、「建築物の建築」または「特定工作物の建設」を目的とした「土地の区画形質の変更」のことです。
上記のいずれかの要素が欠けていれば、開発行為にはあたりません。
例えば、単に土地を駐車場にするために砂利を敷くだけ(建築物も特定工作物も建てない)なら、開発行為ではありません。
また、建物の建築目的がなく、登記上で土地を分筆するだけの場合も、区画形質の変更にはあたらないため開発許可は不要です。
ここで注意したいのが「特定工作物」です。
これらは建物ではありませんが、周辺への影響が大きいため、建設目的の開発行為には許可が必要となります。
| 特定工作物 の種類 |
具体例 | ポイント |
| 第一種 特定工作物 |
コンクリートプラント アスファルトプラント など |
周辺の環境に影響 を及ぼす施設 |
| 第二種 特定工作物 |
ゴルフコース・1ヘクタール以上の野球場・ テニス場・墓苑など |
大規模な集客施設 やレジャー施設 |
特に、第二種特定工作物は試験で狙われやすいポイントです。
ゴルフコースは面積に関わらず特定工作物にあたりますが、野球場や墓苑は1ヘクタール(10,000㎡)以上の場合に限られる点を区別して覚えましょう。
ステップ3. 区域ごとの「面積要件」を超えているか?
最後に、開発する土地の面積が、区域ごとに定められた基準を超えているかを確認します。
この面積基準は、暗記必須の超重要ポイントです。
下記のような「語呂合わせ」を使って覚えることも有効な記憶術のひとつでしょう。
| 区域 | 開発許可が必要 となる面積 |
覚え方の ゴロ合わせ |
| 市街化区域 | 1,000㎡ 以上 | 市街地でセンス ある開発! (1,000) |
| 市街化 調整区域 |
面積に関わらず 原則として許可 が必要 |
調整区域は 例外なし! |
| 非線引き 都市計画区域 |
3,000㎡ 以上 | 非線引き、 みんなで開発! (3,000) |
| 準都市 計画区域 |
3,000㎡ 以上 | 準都市も みんなで開発! (3,000) |
| 都市計画 区域外 |
10,000㎡(1ha) 以上 |
区域外は イチから開発! (1ha) |
市街化調整区域は、市街化を抑制するエリアなので、面積の大きさに関わらず、原則として開発が厳しく制限されているのが最大の特徴です。
【補足知識】
・三大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)の一部では、市街化区域の基準が 500㎡ 以上に強化される場合があります。
・都道府県の条例により、非線引き都市計画区域などの基準が 300㎡ まで引き下げられることがあります。
3.試験で頻出!開発許可が「不要」になる例外パターン
ここからが宅建士試験で最も問われる「許可不要の例外」です。
3ステップの原則にあてはまっても、これから紹介するケースに該当すれば開発許可は不要になります。
数が多くて大変ですが、グループに分けて理解すれば頭に入りやすくなります。
| 例外のカテゴリ | 具体的な内容 |
| ①農林漁業関連 | 農林漁業用の建築物(畜舎・温室な ど)や、その従事者の住宅の建築目 的の開発行為 |
| ②公共・公益関連 | 公益上必要な建築物(図書館、鉄道 施設など)の建築目的の開発行為 |
| ③国や自治体関連 | 国や地方公共団体などが行う開発行 為(知事との協議成立が必要) |
| ④事業・緊急時 関連 |
都市計画事業や土地区画整理事業な どの施行として行う開発行為 |
| 非常災害のために必要な応急措置と して行う開発行為 |
|
| ⑤小規模・軽易な もの |
面積要件に満たない小規模な開発行為 |
| 通常の管理行為、軽易な行為 (仮設建築物など) |
例外①:農林漁業用の建築物とその従事者の住宅
市街化調整区域は、農業などを守り育てるエリアでもあります。
そのため、農業や林業、漁業を営むために必要な建築物(例:畜舎、温室、サイロなど)や、そこで働く人たちが住む家のための開発行為は、許可が不要とされています。
ただし、非常に重要なひっかけポイントがあります。
この例外は、市街化区域には適用されません。
市街化区域で農家の家を建てるために1,000㎡以上の開発行為を行う場合は、原則通り開発許可が必要です。
| 市街化 調整区域 |
市街化区域 | |
| 農林漁業用 の建築物 |
許可不要 | 原則通り(1,000㎡以上 なら)許可必要 |
| 農林漁業者 の住宅 |
許可不要 | 原則通り(1,000㎡以上 なら)許可必要 |
例外②:公益上必要な建築物(駅舎・図書館など)
地域の人々の生活に欠かせない、公益性の高い建築物のための開発行為も許可は不要です。
どのような建物が該当するか、具体例でイメージを掴みましょう。
- 駅舎などの鉄道施設
- 図書館
- 博物館
- 公民館
- 変電所
以前は学校や病院、社会福祉施設も許可不要でしたが、法改正により現在は原則として許可が必要となっています。
試験対策としては、「駅舎や図書館は許可不要」と覚えておけば十分です。
例外③:国や地方公共団体が行う行為
国や都道府県、市町村といった公的機関が行う開発行為は許可申請をする必要はありません。
ただし、無条件で開発できるわけではありません。
これらの機関が開発行為を行う際は、あらかじめ許可権者である知事と協議をする必要があり、その協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなされます。
- 民間の開発 → 知事への許可申請
- 国や自治体の開発 → 知事との協議
例外④⑤:その他おさえておくべき例外(事業施行、軽易な行為など)
最後に、その他の重要な例外をまとめて確認します。
- 都市計画事業等の施行として行うもの
もともと大きな都市計画に基づいて行われる工事なので、個別の開発許可は不要です。 - 非常災害のため必要な応急措置
地震や水害の後に、仮設住宅を建設するなどの緊急的な開発行為は、許可を待ついとまがないため不要です。 - 通常の管理行為、軽易な行為
車庫や物置の設置、工事用の仮設建築物など、ごく小規模で一時的な行為は許可不要です。
4.開発許可の手続きは「申請→審査→工事→完了」
開発許可の手続きの細かい部分まで覚える必要はありませんが、大まかな流れを知っておくと理解が深まります。
1.事前協議・申請
開発者は、公共施設の管理者などと協議し、同意を得た上で知事に申請書を提出します。
2.審査・許可
知事は申請内容を審査し、問題がなければ許可を出します。
3.工事の施工
開発者は許可内容に従って工事を行います。
4.工事完了の届出
工事が完了したら、知事に届け出ます。
5.完了検査・公告
知事は検査を行い、合格すれば検査済証を交付し、工事が完了したことを公告(世間に知らせる)します。
この流れで特に重要なのが、工事完了の公告後でなければ、原則として建物を建てたり、土地を使ったりできないという「建築制限」です。
| タイミング | 建築制限の内容 |
| 工事完了公告 の前 |
原則、建築物の 建築は不可 |
| 工事完了公告 の後 |
許可された予定 建築物以外の建 築は原則不可 |
ただし、工事用の仮設建築物や、知事が支障ないと認めた場合などは、許可不要の例外措置が適用されます。
「公告があって、はじめて建物が建てられる」という原則をまずは押さえましょう。
5.知識を定着させる!開発許可の過去問にチャレンジ
それでは、実際の試験問題で知識を確認してみましょう。
【令和4年 宅建士試験問題 問16】
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1.市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2.区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
3.自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。
4.市街化調整区域内における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがあるかどうかにかかわらず、都道府県知事は、開発審査会の議を経て開発許可をすることができる。
(出典:宅建試験の問題及び正解番号表|不動産適正取引推進機構)
【正解と解説】
正解:2
1.誤:市街地再開発事業としての開発行為は、区域・面積を問わず、開発許可は不要です(都市計画法29条1項)。
2.正:公益上必要な一定の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、区域・面積を問わず、開発許可は不要です(都市計画法29条1項)。
3.誤:開発行為を行うのに適当でない区域として災害レッドゾーンは原則として開発区域に含まないことを規定しています(都市計画法第33条第1項第8号)。災害レッドゾーンに該当するのは、災害危険区域・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域・土砂災害特別警戒区域・浸水被害防止区域であり、問題文の「土砂災害警戒区域」は該当しません。
4.誤:調整区域で許可を出すには「市街化を促進するおそれがないこと」が要件の一つであり、そのおそれを無視して許可できるとは言えません(都市計画法34条14号)。
6.宅建士試験の開発許可に関するよくある質問(FAQ)
Q. 市街化調整区域では建物を建てられないのですか?
A. 原則として建築は制限されますが、以下は例外的に可能です。
- 農林漁業用の建築物(農家の住宅、畜舎など)
- 公益上必要な建築物(駅、図書館、変電所など)
- 開発許可を受けて建築したもの
- 都市計画事業の施行として建築するもの
Q.「区画形質の変更」とは具体的に何をすることですか?
A. 具体的には、土地に以下の変更を加えることです。
- 区画の変更:道路・水路等で土地を分割・統合すること
- 形の変更:切土・盛土で土地の形状を変えること(1m超の造成等)
- 質の変更:農地を宅地に、林地を宅地に変更すること
Q. 開発許可後の用途制限とは?
A. 工事完了公告後も用途制限は継続します。
- 開発許可で定められた予定建築物以外は建築不可
- 用途変更には知事の許可が必要
- 違反すると罰則あり
例:住宅用として許可を受けた土地に、勝手に店舗は建てられない
7.開発許可を得意科目にするなら伊藤塾がおすすめ!
宅建士試験の中で、多くの受験生が苦手意識を持つ科目のひとつが、本記事のテーマでもある開発許可を含む「法令上の制限」です。
都市計画法・建築基準法・農地法など複数の法律が絡み、条文・制度を忘れやすいこと、用語・数字など覚えることが多いことなどが苦手意識を感じる大きな原因となっています。
「何度テキストを読んでも、さっぱり覚えられない!」
もし、あなたがそんな悩みをお持ちでしたら、ぜひ当コラムを運営している伊藤塾にご相談ください。
伊藤塾は、法律資格専門の受験指導校であり、開塾以来30年にわたり、司法試験を始めとする難関資格において圧倒的な合格実績を挙げ続け、多くの法律家を輩出してきました。
そのノウハウを詰め込んだ 伊藤塾の「宅建士 合格講座」は、法律のプロフェッショナルである講師陣によるわかりやすい講義ときめ細かいサポート体制で、初めて法律を学ぶ方でも無理なく安心して学習を進めることができるよう設計されています。
法律用語に慣れていない方、独学は厳しいと感じている方、一発合格をしたい方、短期間で合格したい方は、ぜひ伊藤塾をご活用ください。
あなたの新しいキャリアの実現を力強くサポートさせていただきます。
※こちらも読まれています。
講義は、分かりやすく丁寧で、 不動産について完全に素人の私でも、内容がスッと頭に入ってきました。
教材は、一見するとシンプルな印象を受けますが、 合格に必要な内容に絞り込まれており、不足はありませんでした。
講師の方々は、講義が分かりやすいのはもちろん、本試験で狙われやすいところ、引っかけのポイント等を 的確に教えてくださるため、とても頼もしい存在でした。 実際に不動産業をされている先生も講義をされるため、 実務の話を講義で聞くことができることは、合格後をイメージできて良かったと思いました。
8.宅建士試験の開発許可 まとめ
本記事では、多くの受験生がつまずきやすい都市計画法の「開発許可」についてわかりやすく解説しました。
以下にポイントをまとめます。
- 開発許可とは、計画的で安全な街づくりを進めるため、主に「建築物の建築」や「特定工作物の建設」を目的とする「土地の区画形質の変更」に対して、原則として都道府県知事等の許可を求める制度です。
- 開発許可が必要かどうかの判断は、「区域」「開発行為の該当性」「面積要件」の3ステップで検討することが鍵となります。
- 開発行為に該当するのは、「建築物の建築」または「特定工作物の建設」を目的とした「土地の区画形質の変更」です。特定工作物のうち、ゴルフコースや1ヘクタール(10,000㎡)以上の野球場・墓苑は第二種特定工作物です。
- 区域ごとの面積要件は、市街化区域は1,000㎡以上、市街化調整区域は面積に関わらず原則許可が必要、都市計画区域外は10,000㎡(1ha)以上が許可の原則です。
- 宅建士試験で最も重要なのは、原則にあてはまっても許可が不要となる「例外」です。例外には、農林漁業用の建築物(市街化区域を除く)、駅舎や図書館などの公益上必要な建築物、国や地方公共団体などが行う開発行為(知事との協議が必要)、都市計画事業などの施行として行う行為 などがあります。
- 開発許可の手続きでは、工事完了の公告後でなければ、原則として建物を建てたり土地を使ったりできないという建築制限が存在します。
- 工事完了公告後も、開発許可で定められた予定建築物以外の建築は原則不可であり、用途変更には知事の許可が必要です。
開発許可は宅建士試験で毎年出題されている重要テーマです。「覚えられないから捨てる」ではもったいないです。
伊藤塾で学べば、苦手意識は払拭され、開発許可が「得点源」へと変わります。
法律が難しいと感じている方は、ぜひ、伊藤塾の「宅建士 合格講座」をご活用ください。
伊藤塾があなたのチャレンジを力強くサポートさせていただきます。