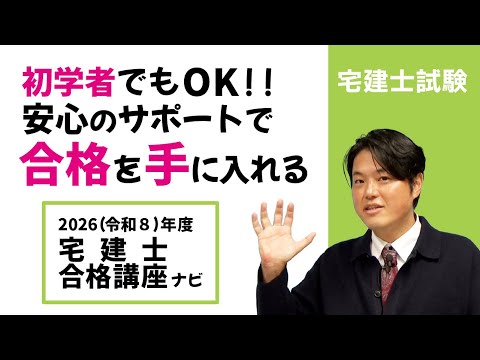宅建の建築基準法とは?覚え方や得点するコツをわかりやすく解説
勉強法
2025年11月05日


宅建士試験で出題される「建築基準法」は、法令上の制限に関する分野の中でも暗記項目が多く、受験生の多くが苦手意識を持つテーマです。
出題数は例年2問と限られていますが、出題傾向を押さえて勉強すれば確実に得点できる“狙い目科目”でもあります。
建築基準法では、用途規制や建蔽率・容積率、建築確認など、建物を安全かつ適切に建てるためのルールが問われます。数字や規制を丸暗記するだけではなく、「なぜそう定められているのか」という趣旨を理解することで、記憶に残りやすくなります。
本記事では、宅建士試験における建築基準法の概要から頻出分野、覚え方のコツ、さらには得点戦略までをわかりやすく解説します。
法令上の制限の中でも特に建築基準法に苦手意識を持っている方は、ぜひ最後までご覧ください。
※法令上の制限については、こちらの記事で詳しく解説しています。
【目次】
1. 宅建士試験で出題される建築基準法とは
不動産取引に関連する法律の中でも、「建築基準法」は宅建士試験において重要な位置づけにあります。建築基準法は、建物を建てる際に守るべき最低限のルールを定めた法律であり、安全で快適な街づくりを目的としています。
本試験では、建築基準法の全条文が問われるわけではなく、不動産取引に関連する部分――たとえば「用途地域ごとの建築制限」「建蔽率・容積率」「防火・準防火地域」「建築確認の要否」などが中心です。
聞き慣れない言葉も多く苦手意識を持つ受験生も多いですが、細かい数字を整理して覚えてしまいさえすれば得点源にしやすい科目です。
1-1. 建築基準法の概要
建築基準法とは、「建築物の敷地、構造、設備、用途などに関する基準」を定めた法律です。
目的は、建物の安全性を確保し、火災や地震などの災害から人命を守ること、そして都市の美観や環境を守ることにあります。
この法律には、大きく分けて「単体規定」と「集団規定」の2種類があります。
単体規定:建物そのものに関する基準
(例:構造強度、防火・避難設備、採光・換気など)
集団規定:建物同士の関係や都市計画上の配置に関する基準
(例:用途地域、建蔽率・容積率、高さ制限など)
単体規定は全国一律に適用されますが、集団規定は地域によって適用される制限が異なります。
宅建士試験では、特にこの「集団規定」に関する問題を中心に出題されます。
【出題例(令和6年度宅建士試験より抜粋)】
【問 18】 次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 客席部分の床面積の合計が300㎡の映画館については、第二種住居地域内において建築することはできないが、準住居地域内においては建築することができる。
➡︎ ✕ 準住居地域内で建築できる映画館の大きさは200㎡未満に限られます。
2 特定用途誘導地区内において、都市計画で建築物の高さの最高限度が定められていたとしても、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該最高限度を超えてよい。
➡︎ ◯ 建築基準法60条の3第2項
3 計画しようとする建築物の天空率が、道路斜線制限、隣地斜線制限又は北側斜線制限に適合する建築物の天空率未満であれば、これらの制限は適用されない。
➡︎ ✕ 天空率”未満”ではなく”以上”です。
4 都市計画で建蔽率の限度が80%に指定されている区域かつ防火地域内にある耐火建築物について、建蔽率の限度を超えるためには、特定行政庁による許可を得る必要がある。
➡︎ ✕ このケースでは建蔽率の制限は適用されません。
出典:令和6年度本試験 第18問|一般財団法人 不動産適正取引推進機構
1-2. 宅建士試験における出題数
建築基準法からの出題数は例年2問です。「法令上の制限」に関する分野全体(8問前後)の4分の1を占める形で出題されます。出題数こそ多くありませんが、毎年似たパターンの問題が繰り返し出題されるため、過去問対策の効果が非常に高い分野です。
1-3. 出題傾向・頻出分野
建築基準法で特に出題頻度が高いのは、以下の分野です。
【用途地域による建築制限】
地域ごとに建てられる建物の種類を制限する制度です。第一種低層住居専用地域では3階建て以上の建物や店舗付き住宅が制限されるなど、地域の性格に応じた建築ルールを理解しておきましょう。
【建蔽率・容積率】
敷地面積に対する建物の占有面積や延べ面積の割合を定めたものです。角地緩和や前面道路の幅員制限など、細かい数字を正確に覚えておくことが重要です。
【斜線制限・日影制限】
建物の高さや配置を制限して、採光や通風を確保するためのルールです。特に「道路斜線」「隣地斜線」「北側斜線」の違いを整理して覚えましょう。
【道路規制(接道義務・道路内の建築制限)】
建築物は原則として「幅員4m以上の道路に2m以上接していること」が条件です。また、道路内に建物を建てることは原則禁止とされます。
【単体規定など】
建築物の構造・敷地・建築設備などに対してさまざまな角度から制限が加えられています。過去問を中心に、地方公共団体による個別的な規制・緩和があるケースや、建築協定などに関する問題に一通り触れておきましょう。
【建築確認】
原則としてすべての建築物に建築確認が必要ですが、10㎡以下の増築や仮設物は不要です。確認が必要なケースと不要なケースを区別できるようにしておくと安心です。
これらの分野は暗記中心で比較的得点しやすい一方、数字や例外規定が多いため混乱しやすいのも事実です。ただし、出題傾向が安定しているため、過去問を繰り返し学習すれば短期間でも得点アップが狙えるコスパの高い分野と言えます。
2.建築基準法の覚え方・得点するコツ
建築基準法は数字や制限が多く、「建蔽率60%」「前面道路の幅員が…」など、一見すると複雑です。しかし、出題パターンははっきりしているため、正しい順序で学習すれば安定した得点源になります。
最も重要なのは、「なぜ、そのルールがあるのか?」という制度の趣旨を先に理解し、それから過去問で頻出パターンを掴み、最後に細かい数字を整理することです。丸暗記に頼らない「納得できる理解」こそが、合格への近道です。
2-1. 【最重要】「なぜ?」という制度の趣旨から考える
建築基準法の学習で一番やってはいけないのは、いきなり数字を丸暗記しようとすることです。まず、「そのルールが、誰の何を“守る”ためにあるのか」を考えましょう。
例えば、「建蔽率(けんぺいりつ)」で考えてみます。
◉丸暗記の例
「建蔽率60%」「角地(かどち)は+10%緩和だ」
◉「趣旨」から考える例
【目的】 なぜ建蔽率があるのか? → 土地いっぱいに家が建つと、火事が燃え広がりやすく、日当たりや風通しも悪くなる。 → そこで、あえて「空き地」を確保させ、防火や住環境を守るのが目的。
【ルールの理解】 なぜ「角地」は+10%緩和される? → 角地は、土地の二方が広い道路に面している。 → ということは、最初から「防火」や「風通し」の目的が達成しやすい「優等生」な土地である。 → 「それなら、ご褒美にルールを緩めて(+10%)、少し家を広く建ててもOK」
このように、目的から理解すれば「角地緩和」のルールを忘れることはありません。
これは、日影制限(「北側のお隣さんの日当たりを守るため」)や、接道義務(「消防車や救急車が入る道幅を確保するため」)など、すべてのルールに共通します。まず「制度の趣旨(目的)」を掴めば、応用が利くようになります。
2-2. 過去問で「問われ方」を知り、頻出分野を押さえる
制度の趣旨(目的)を大まかに理解したら、次に過去問を解きます。 建築基準法の出題内容は毎年大きく変わらず、論点は限られています。過去問は「制度の趣旨が、本試験でどう問われるか」を知るための最良のツールです。
頻出分野である「用途地域による建築制限」「建蔽率・容積率」「建築確認」「接道義務」などは毎年のように出題されています。
過去5年分を最低3回は繰り返しましょう。その際、「なぜこの選択肢は正しいのか(間違っているのか)」を、2-1で学んだ「趣旨」に立ち返って説明できるかを確認しながら進めると、知識が定着します。
2-3. 最後に、細かい「数字」を表で区別して整理する
趣旨を理解し、問われ方を掴んだら、最後の仕上げとして細かい数字を整理します。試験では、この数字の「すり替え」で失点することが多いからです。
◉例1:「容積率」
前面道路の幅員制限で、住居系地域は「幅員 × 0.4」、その他の地域は「幅員 × 0.6」
◉例2:「日影規制」
低層住居専用地域(5m/3m)、中高層住居専用地域(10m/5m)など
これらの数字は、丸暗記ではなく、必ずノートや表を使って「比較」しましょう。テキストの図やイラストを活用し、視覚的に「違い」を区別して覚えることが、混乱を防ぎ、得点を確実にするカギとなります。
3.宅建で建築基準法の問題は難しい?捨てるのはアリ?
建築基準法は条文数が多く、専門的な用語や数値の暗記が必要なため、「難しい」「時間がかかる」と感じる受験者が少なくありません。特に、用途地域による建築制限や斜線制限など、数字や条件の組み合わせで出題される問題は、混乱しやすい分野です。
そのため「建築基準法は捨て科目にして他で稼ぐ」という考え方をする人もいますが、完全に捨てるのはお勧めできません。毎年2問出題される上、過去問を繰り返せばパターン化できる問題が多いからです。
3-1. 暗記が得意な方は確実に得点できる科目
建築基準法の問題は、理論的な応用よりも知識をそのまま問う形式が中心です。用途規制や建蔽率・容積率などに関する問題などは、制度の趣旨(目的)を理解したうえで、制限の対象や種類、細かい数値を覚えておけば確実に点を取れます。
また、過去問の出題パターンが似通っているため、重要な数字や制限内容をまとめた表を使って繰り返し覚えると効果的です。暗記が得意な受験者にとっては、むしろ得点源にしやすい分野と言えるでしょう。苦手意識を持たずに、範囲を絞って「取れる2問」を狙う戦略が有効です。
※宅建士試験の暗記のコツについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
3-2. 捨て問とせず、少なくとも1問は正解できるよう対策を
宅建士試験では、全50問中37点前後が合格ラインの目安とされています。つまり、全ての科目で満点を狙う必要はなく、自分の得意・不得意に応じて配分を考えることが大切です。
建築基準法の出題数は毎年2問程度なので、どうしても苦手であれば「2問中1問は捨てる」といった割り切りも現実的な戦略です。
ただし、建築基準法は都市計画法などの法令と関連する部分も多く、基礎知識として理解しておくと他の分野にも活かせます。完全に捨て問として無視するのではなく、少なくとも1問は正解する問題として押さえておくことが合格への近道です。
※都市計画法の勉強法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
4. 建築基準法を学ぶなら伊藤塾の宅建士合格講座がおすすめ
このように、建築基準法は、正しい学習法で取り組めば、確実に得点できる「狙い目科目」となります。
確実な合格のためには、単に数字やルールを丸暗記するのではなく、「なぜ、その制限があるのか」という制度の趣旨(目的)から理解することが重要です。これにより、記憶に定着しやすくなるだけでなく、試験本番で未知の問題にも対応できる応用力が身につきます。
伊藤塾の「宅建士 合格講座」では、宅建士の実務家でもあるプロの講師が、具体的な事例をふんだんに用いながら「趣旨から考える思考法」を徹底的に解説します。
また、数字や例外規定が多く混乱しやすい建築基準法の特性に対し、写真・表が豊富なオリジナルテキストを用いて視覚的に情報が整理され、さらに条文や数値を語呂合わせで楽しく覚えるなど、無理なく楽しく学んで合格してしまう工夫が満載です。
この体系的なアプローチにより、確実に得点できる力を効率的に身につけることができます。
建築基準法を「捨て問」にせず、楽しく、効率よく得点源に変えたいとお考えであれば、ぜひ伊藤塾の「宅建士 合格講座」をご検討ください。
◉楽しく学んで、合格してしまう 伊藤塾の【宅建士 合格講座】
●何のための制度・手続きなのかを徹底解説
→ 制度趣旨を理解することで、未知の問題にも強くなる!
●実務家の講師による「実務談義」が豊富
→ リアルな実務談義によって、難解な条文もイメージしやすく覚えやすい!
●語呂合わせによる暗記術を活用
→ 覚えるのが苦手な方でも無理なく楽しく覚えられる!
●伴走型の参加イベント(スクーリング、オンライン質問会、オンライン座談会など)を多数用意
→ 充実したサポートで、最後までやり遂げられる!
●写真・表・データが豊富でわかりやすいテキスト・問題集・補助レジュメ・学習アプリ・模試まで揃ってインプットもアウトプットも万全
→合格するために必要十分かつ適切な教材が全部セット!
●他の受験生と「一番差がつく」権利関係を手厚くカバー
→ 多くの受験生が苦手としている権利関係を得点源に!
これら合格に必要なものが全て揃って、受講料は追加料金なしの
39,800円
5. 宅建の建築基準法に関するQ&A
Q. 建築基準法にどれくらい時間をかければ安定して得点できるようになりますか?
A. 安定して得点できるようになるのに必要な勉強時間は人によりますが、暗記が得意な人であれば比較的短期間で得点源にすることも可能です。
関連性のある都市計画法と結びつけて学ぶことで、理解が深まり勉強時間も短縮できます。また、安定した得点力を身につけるためには過去問演習で頻出分野を抑えることが重要です。
Q. 建築基準法に関する法改正の一覧表はどこで確認できますか?
A. 最新の法改正情報は、国土交通省の公式サイトや「e-Gov法令検索」などで確認できます。
国土交通省のページでは、改正の概要や施行日、目的などが整理されており、過去の改正履歴も閲覧可能です。また、e-Gov法令検索では最新の条文内容をすぐに確認できるため、法改正点を正確に把握する際に便利です。
Q. 用途規制や建蔽率・容積率の細かい数値はどのように覚えればいいですか?
A. 数字や条件を丸暗記するよりも、「なぜその制限があるのか」という目的とセットで覚えるのが効果的です。たとえば、建蔽率は「火災時の延焼防止」、容積率は「人口密度や交通量の調整」と関連づけると記憶に残りやすくなります。表・図・語呂合わせを使って繰り返し整理すると定着しやすいです。
6.宅建の建築基準法の覚え方や得点するコツまとめ
本記事では、宅建士試験における建築基準法の覚え方と得点するコツについて解説しました。
以下にポイントをまとめます。
- 宅建士試験で例年2問出題される分野であり、出題傾向が安定しているため、正しい対策をすれば、確実に得点できる「狙い目科目」です。
- 不動産取引に関連する部分、特に用途地域による建築制限や建蔽率・容積率、道路規制など、都市計画上のルールを定めた「集団規定」が中心に出題されます。
- 細かい数字の丸暗記から入るのではなく、「なぜ、その制限があるのか」という制度の趣旨(防火、安全、採光など)から理解することが、記憶の定着と応用力育成の鍵となります。
- 建築基準法は毎年似たパターンの問題が繰り返し出題されるため、過去問を解きながら、「問われ方」を知り、細かい数字をノートや表、図などを活用して視覚的に比較整理することが、本試験での混乱や失点を防ぐために重要です。
- 建築基準法は完全に「捨て問」にせず、最低でも2問中1問は正解することを目指して対策を行うことが、合格ラインを超えるための近道となります。
建築基準法という難解な分野を短期間で得点源に変えるには、体系的な学習と「趣旨から考える思考法」の習得が不可欠です。
伊藤塾の「宅建士 合格講座」では、プロの実務家講師がこの「趣旨から考える思考法」を徹底的に伝授し、難解な制度をリアルな事例や語呂合わせを用いて楽しく解説します。
楽しく学んで無理なく合格してしまう 伊藤塾の「宅建士 合格講座」をぜひご検討ください。