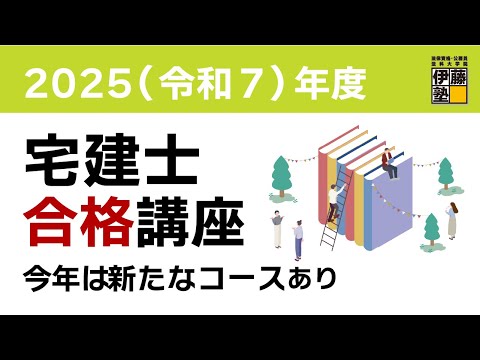宅建士試験に独学で合格するための効率の良い勉強法とは?後悔しないための注意点も解説
勉強法
2025年08月27日


「独学で宅建を目指したい」
「だけど、勉強方法が分からない」
「というか、そもそも独学でも合格できるの?」
独学で宅建を目指す方の多くが、このような悩みを抱えています。
確かにとても不安なポイントですよね。
せっかく勉強するなら、少しでも合格率を高めたいのが正直なところ。
しかしながら、宅建士試験の合格率は、毎年「15〜17%」程度。6人に1人しか合格できない宅建士試験に、独学で合格するには、正しい方法で勉強を進めていくことが必要不可欠です。
正しい勉強法や、注意点を把握して勉強をスタートしないと、後々後悔することにもなりかねません。そこでこの記事では、法律専門指導校である伊藤塾において蓄積されたノウハウを元に、
◉ 宅建に独学で合格するための効率の良い勉強法
◉ 合格率を上げるためのコツや注意点
◉ 独学に向いていない人の特徴
について解説します。
この記事を読めば、独学で失敗する可能性を大幅に低下させることができるでしょう。
※宅建士の資格の詳細については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
→【完全版】宅建とは?試験の詳細や宅建士の仕事内容など資格のすべてを徹底解説!
【目次】
1.宅建に独学で合格することはできる?
宅建は、独学で挑戦する人も少なくない試験です。書店に多くの種類のテキストが販売され、気軽に学習を開始できそうなことなどが、多くの人が独学で学習を始める主な理由でしょう。
それでは、実際のところ、独学でも宅建に合格できる可能性は高いのでしょうか?結論から言いますと、独学で宅建に合格することは不可能ではありません。
ただし、宅建士試験の合格率が、毎年「15〜18%」程度しかないこともまた事実です。しかも、この合格率には、受験指導校を利用している人も数多く含まれているため、独学のみで計算すると、合格率は更に低下することになるでしょう。
【令和6年度 宅建士試験の合格率】
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 241,436 | 44,992 | 18.6% |
この数字からも分かるように、宅建は決して簡単な試験ではありません。
宅建に独学で合格するためには、しっかりと対策を考えて、勉強を進めていく必要があります。合格するための具体的な勉強法については、次章で詳しく解説します。
2.独学で宅建に合格するための効率の良い勉強法
それでは、どのような流れで勉強を進めていけば、独学で宅建に合格することができるのでしょうか?ここでは、独学で宅建合格を目指す場合の効率の良い勉強の手順や、合格率を上げるためのコツについて解説します。
2-1.効率の良い勉強の手順
独学で宅建合格を目指す場合、以下の5つのステップで効率よく勉強を進めていくことが王道です。
ステップ① 必要な合格ラインを理解する
ステップ② 勉強の計画を立てる
ステップ③ テキストでインプットを行う
ステップ④ 過去問を利用してアウトプットする
ステップ⑤ 答練、模試などを利用して直前演習をする
順番にみていきましょう。
【ステップ①】必要な合格ラインを理解する
まずは、宅建に必要な「合格ラインを理解する」ことが先決です。ゴール設定が曖昧だと、必要な勉強量を見積もることができないからです。敵を知ることが、合格への第一歩だと心得ましょう。
なお、宅建士試験の合格ラインは、概ね「36点前後」となることが多いです。50点満点中の36点が必要となるため、問題全体の正答率で言い換えると「72%程度」が必要な計算となります。
※宅建士試験の「合格率」や「合格点」については、以下の記事で詳しく解説しています。
→ 宅建士試験の合格率はなぜ低い?合格点や難易度をデータをもとに徹底解説!
【ステップ②】勉強スケジュールを立てる
次に、合格ラインに到達するための勉強スケジュールを立てましょう。
・試験日から逆算して、勉強期間を設定する
・出題範囲を確認し、科目ごとに勉強時間を割り当てる
・1ヶ月・1週間・1日に必要な勉強時間を計算する
などの流れで、具体的なスケジュールを設定していきます。
配点の高い科目には、より多くの時間を充てるなど、メリハリをつけることが重要です。
また、働きながら受験する人に多いのが、「仕事後に、必ず毎日3時間勉強する!」などの非現実的なスケジュールを設定してしまい、途中で挫折してしまうケースです。本当に実現できる勉強スケジュールになっているのかは、しっかりと検討する必要があるでしょう。
※宅建の合格に必要な勉強時間については、以下の記事で詳しく解説しています。
社会人が、必要な勉強時間を確保する方法についても解説しているので、ご一読ください。
→【500時間必要?】宅建士試験の合格に必要な勉強時間について徹底解説!
【ステップ③】テキストでインプットを行う
計画が作成できたら、テキストを使ったインプット学習を始めます。宅建士試験の出題範囲は広いため、まずは基本的な法律知識を身につけることを目指しましょう。
なお、法律初学者の場合、難解な法律用語に慣れるだけでもかなりの時間がかかります。モチベーションを切らさないためには、一緒に勉強できる仲間を作ったり、こまめに休憩してリフレッシュする等の工夫が必要です。
【ステップ④】過去問を利用してアウトプットする
テキストで学んだ知識を定着させるためには、アウトプットが欠かせません。ある程度のインプットが終わったら、過去問を利用して問題演習を行いましょう。
過去問を解く際は、以下のポイントを意識してください。
・答えを暗記するのではなく「理解」する
・解き終わったら解説を確認し、テキストに戻って復習する
テキストと過去問を何度も往復して、知識の定着を図っていきましょう。
【ステップ⑤】答練、模試などを利用して直前演習をする
試験直前は、答練や模試を活用して、本番に向けた演習を行います。答練や模試では、以下のようなことを確認しましょう。
・時間配分が適切にできているか
・苦手分野の克服ができているか
・ケアレスミスを防ぐ対策ができているか
受験指導校が開催する模試では、自分に不足している点が分かるだけでなく、ライバルの立ち位置も把握することができます。本番さながらの演習を行い、時間配分の感覚をつかむとともに、試験当日に向けた最終チェックを行いましょう。
2-2.合格率を上げるには?勉強法の2つのコツ
更にいくつかのポイントを意識して勉強することで、宅建の合格率を飛躍的に高めることができます。ここでは、合格率を上げる勉強法のコツについて、2つ紹介します。
2-2-1,出題頻度の高いテーマから優先的に勉強する
宅建士試験では、特定のテーマが頻繁に出題される傾向があります。そのため、過去問を自分で徹底的に分析し、出題頻度の高いテーマを把握することで、効率よく得点力を上げることができます。
例えば「権利関係」を例に説明すると、
| ・制限行為能力者 ・抵当権 ・賃貸借 ・相続 |
等のジャンルはほぼ毎年出題されています。
このような頻出ジャンルを確実に得点できることは、合格に必要不可欠だといっても過言ではありません。限られた時間の中で合格点を取るために、勉強する内容に優先順位をつけることが大切です。過去問を分析し、頻出テーマに重点を置いて、勉強を進めていきましょう。
2-2-2,分からない点は人に教わる
独学で宅建士試験の勉強を進める上で、理解しにくい点が出てくることは避けられません。複雑な制度の仕組みなど、テキストを読んでみても、なぜそうなるのか理解することが難しい場合も多いでしょう。
そのような場合は、一人で抱え込まずに、人に教わることが大切です。身近に宅建士試験の合格者がいれば、理解しにくいことを質問してみましょう。試験に合格した人からのアドバイスは、学習を進めるうえで、とても参考になるはずです。
もしも身近に質問する相手がいない場合は、受験指導校を利用することも検討するべきでしょう。
理解しにくい点を放置しておくことは、全くおすすめできません。理解が不十分な状態で学習を続けると、後々の学習に支障をきたすだけでなく、試験当日の、思わぬ失点にも繋がるからです。
3.独学が向いていない人の特徴
前述の流れやポイントを意識して勉強すれば、独学で宅建に合格できる可能性は飛躍的に高まります。しかし、独学で勉強をスタートした人の多くが、途中で挫折してしまったり、残念ながら不合格になってしまうこともまた事実。
実際のところ、独学が向いている人は、そう多くないというのが実情でしょう。そこでここでは、独学が向いていない人の特徴について解説します。
| ・自分を律するのが苦手 ・必要な情報を取捨選択できない ・法律を全く勉強したことがない |
上記のような特徴に当てはまる人は、独学は避けるのが無難かもしれません。
それぞれ見ていきましょう。
3-1.自分を律するのが苦手な人
宅建の試験勉強を、独学で進めていくには、高い自己管理能力が求められます。
計画通りに勉強を進め、誘惑に負けることなく、コツコツと努力を積み重ねていく必要があるからです。例えば、日々の仕事で疲れたり、家事が忙しかったりすることを理由に、勉強をサボってしまう人は要注意です。どれだけ合格する可能性の高い勉強計画を作成できたとしても、実行できなければ意味がありません。
一度勉強が滞ってしまうと、モチベーションは下がり、合格もどんどん遠のいてしまいます。忙しい毎日の中でも、自分を律して勉強を続けていく自信がない人は、独学の合格は難しいかもしれません。
3-2.必要な情報を取捨選択できない人
必要な情報を、自分で取捨選択する自信がない人も、独学には向いていないかもしれません。宅建士試験は出題範囲が広く、試験までに膨大な量の情報を扱うことになるからです。
情報の取捨選択ができない人は、細かい情報まで全て覚えようとしてしまい、最終的に「どこが重要で、どこが重要でないのか」が分からなくなってしまいます。一人でテキストを読み進めていった結果、袋小路に迷い込んでしまう受験生は少なくありません。こうなると勉強の効率は下がり、合格に必要な勉強時間も格段に長くなります。
情報を取捨選択する自信がない場合は、必要かつ十分な情報が揃っている受験指導校を利用することも一案です。
3-3.法律を全く勉強したことがない人
宅建の試験では、法律に関する専門知識が問われます。そのため、法律を全く勉強したことがない人にとって、独学は非常にハードルが高くなるでしょう。
例えば、宅建で超重要科目となる「民法」や「宅地建物取引業法」。これらの法律では、「瑕疵担保責任」や「善管注意義務」といった、日常的には使われない専門用語がいくつも登場します。法律を勉強したことがない人にとっては、こうした言葉に慣れるだけでもかなりの時間がかかります。
最初は、専門用語を見ただけで拒絶反応を示してしまう受験生も少なくありません。法律に苦手意識がある人は、独学は避けておくのが無難でしょう。
4.独学で勉強する場合の注意点
それでは、独学で勉強を開始する場合、どのような点に注意すると良いのでしょうか?実は、独学を選択した受験生が後で後悔しやすい理由は、ある程度パターン化されています。
例えば、
| ・想像以上に長期間の勉強が必要になった ・モチベーションの維持が難しかった ・法律の改正を見逃してしまった ・意外と費用がかかってしまった |
などです。
独学で勉強する場合、自分も同じ壁にぶち当たることを覚悟する必要があるでしょう。
それぞれ説明します。
4-1.長期間の勉強が必要になる
宅建士試験に独学で合格するには、相当な勉強時間が必要になります。
一般的には「300時間〜500時間」が目安だとも言われており、仕事や学業と両立しながら確保するのは簡単ではありません。例えば、試験までに半年間(6ヶ月)の勉強期間が残されているケースで考えてみましょう。
「500時間」を確保するためには必要な勉強時間は、以下のようになります。
・1ヶ月あたりの勉強時間=84時間(500時間÷6ヶ月)
・1週間あたりの勉強時間=21時間(84時間÷4週間)
土日どちらかで10時間、平日は毎日欠かさず2時間以上の勉強を半年間続けて、ようやく達成できるといったところでしょうか。実際は、仕事の都合等で勉強できない日も出てくるため、かなり厳しいスケジュールとなることは間違いありません。
コンスタントに勉強時間が取れないと、なかなか知識が定着しないため、合格に必要な期間もどんどん長期化していきます。
必要な勉強時間の確保が難しいと感じる人は、独学での受験は慎重に検討するべきかもしれません。
※宅建の合格に必要な勉強時間については、以下の記事で詳しく解説しています。
社会人が、必要な勉強時間を確保する方法についても解説しているので、ご一読ください。
→【500時間必要?】宅建士試験の合格に必要な勉強時間について徹底解説!
4-2.モチベーションの維持が難しい
モチベーションの管理を、大きな課題だと感じる人も少なくありません。ひたすらテキストを読み込みながら、一人で黙々と勉強を続けていくことは、簡単ではないからです。
特に、勉強が思うように進まない時期や、成果が出ない時期は、モチベーションが下がりやすくなります。そうなると勉強時間は減り、さらに合格から遠ざかってしまう可能性も否めません。
モチベーションを維持するには、明確な目標設定と、定期的な振り返りが大切です。また、家族や友人に協力してもらい、頑張りを認めてもらうことも効果的でしょう。
4-3.法律の改正を見逃すと命取りになることも
独学で宅建士試験の勉強を進めるうえで、注意しなければならないのが、法律の改正です。
宅建士試験は、不動産に関連する法律知識が問われる試験です。法律の改正に合わせて、出題内容も変更されていきます。法改正の動向は常にチェックし、最新の情報を把握しておく必要があるでしょう。
例えば、2020年には「民法」が、120年ぶりに大改正されました。そのため、過去問の解説の一部が、現行法と異なるケースも出てきています。法改正に気づかずに勉強を進めてしまうと、本番で思わぬ失点を喫してしまう可能性があります。独学で勉強をする場合は、常に法改正の情報にアンテナを張っておきましょう。
4-4.意外と費用がかかる場合がある
「独学なら費用が抑えられる」と考える人も多いかもしれません。しかし、独学でも意外とお金がかかる場合があるので注意が必要です。
例えば、
・「購入したテキストが自分に合わなかった」
・「他に分かりやすそうな参考書が見つかった」
・「1冊の問題集で十分なのかが不安」
・「模試だけを単独で申し込みたい」
等の理由から、いくつもの教材に手を出してしまい、結果的に2〜3万円の費用がかかってしまうケースは意外に少なくありません。一方、受験指導校を利用しても、宅建講座は比較的低価格で済む場合が多いです。例えば伊藤塾でも、早期申込割引などを上手く活用すれば、お得に受験指導校の講義を活用できます。
(2025年合格目標 宅建士合格講座)
【早期申込割引】
| 講座 | 受講料 |
| スタンダード コースプラス | 79,800円 |
| スタンダード コース | 64,800円 |
| 法律既修者 コース | 49,800円 |
【伊藤塾まこと会(同窓会)会員限定割引30%OFF 25/7/31まで】
| 講座 | 一般受講料 | まこと会 (i.total)会員 割引受講料 |
| スタンダード コースプラス | 79,800円 | 55,800円 |
| スタンダード コース | 64,800円 | 45,300円 |
| 法律既修者 コース | 49,800円 | 34,800円 |
【学生割引50%OFF 25/9/30まで】
| 講座 | 一般受講料 | 学割割引受講料 |
| スタンダード コースプラス | 79,800円 | 39,900円 |
| スタンダード コース | 64,800円 | 32,400円 |
もちろん、インプットやアウトプットに必要な教材は全て含まれているため、追加の費用は発生しません。
→ 2025年合格目標 宅建士合格講座はこちら!
5.受験指導校を利用すると勉強時間が大幅に短縮される
宅建士試験の合格を目指すうえで、独学で学習を進めていくことは容易ではありません。特に、限られた勉強時間の中で、試験範囲を全て学習するためには、相当な覚悟と労力が必要になるでしょう。
そんな時に頼りになるのが、プロの講師陣が在籍する受験指導校です。受験指導校では、宅建士試験に精通した講師陣が、受験生の目線に立って、丁寧に指導してくれます。質の高い講義を受けたり、洗練されたテキストを使用して効率よく勉強していけば、300時間もかからずに合格することも、決して難しくはありません。
たとえば、平日は仕事で忙しい社会人の方でも、週末の限られた時間を有効活用することで、スムーズに学習を進めていくことができるでしょう。
もちろん、受験指導校を利用するには一定の費用がかかります。しかし、それ以上に得られる学びの質の高さを考えれば、合格へのショートカットとして十分に価値があります。
独学で試行錯誤を繰り返すよりも、無駄のない質の高い学習教材で学べることで、タイパ的にもコスパ的にも最も効率良く学べることは間違いありません。
※こちらも併せてお読みください。
→ 宅建の通信講座はなぜ伊藤塾がおすすめなのか?宅建士合格講座の魅力を徹底解説
6.まとめ
この記事では、
◉ 宅建に独学で合格するための勉強法
◉ 独学に向いていない人の特徴
◉ 独学で後悔しやすいポイント
についてお伝えしました。
宅建士になりたいという強い想いがある方は、ぜひ法律専門指導校である伊藤塾をご活用ください。
「今年はさらにバージョンアップしたコースをご用意!!「2025年合格目標 宅建士合格講座」 のご紹介です!」