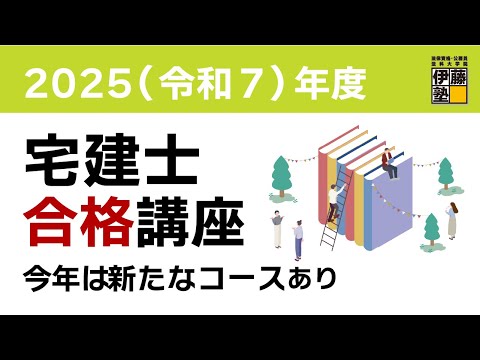宅建士試験は簡単すぎるってホント?実際の難易度を徹底検証!
勉強法
2025年08月29日


「宅建士試験は簡単すぎる」
こんな意見を耳にすることがあります。確かに、宅建士試験は法律資格の中では比較的チャンレンジしやすい試験です。
しかし「簡単すぎる」とまで言うことはできません。実際には、受験生の「6人に1人」しか合格することはできず、宅建士になるためには相当の努力が必要です。
そこで、今回は
・なぜ宅建士試験が簡単すぎると言われるのか
・宅建士試験の実際の難易度
・難易度を考えるときの大切なポイント
について取り上げました。宅建士試験の合格を目指す方は、是非ご一読ください。
※宅建士の資格の詳細については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
→【完全版】宅建とは?試験の詳細や宅建士の仕事内容など資格のすべてを徹底解説!
【目次】
1.宅建士試験は簡単に合格できる?
宅建士試験の難易度については、「簡単」と「難しい」の両方の意見があります。
確かに、他の法律関連の資格試験と比べるとチャレンジしやすいため、比較的取得しやすい印象を持つ人は多いです。また、マークシートによる出題のみという試験形式も、受験生にとっては取り組みやすいポイントでしょう。しかし簡単に合格できるかどうかは、個人の状況や努力によって異なります。
例えば、不動産業界での実務経験がある人にとっては比較的容易に感じることもあるかもしれませんが、初めて不動産について学ぶ人にとっては難しく感じる可能性があるでしょう。「短期間で合格できた」という声ばかりに耳を傾けて、宅建士試験を「簡単だ」と評価するのはあまりにもリスキーです。
実際には、膨大な量の法律知識を習得する必要があり、合格までに相当努力している受験生もたくさんいます。宅建士試験に簡単に合格するためには、試験の難易度を正しく理解し、適切な準備を行うことが重要です。
※宅建士試験の難易度については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 宅建士試験の合格率はなぜ低い?合格点や難易度をデータをもとに徹底解説!
2.宅建士試験が簡単すぎると言われる4つの理由
それでは、なぜ宅建士試験は簡単すぎると言われるのでしょうか。宅建士試験が簡単すぎると言われる主な理由を4つ紹介します。
・必要な勉強時間が短いから
・他の法律資格と比較して合格しやすいから
・四肢択一のマークシート形式だから
・合格している人の数が多いから
それぞれの理由について、詳しく見ていきましょう。
2-1.必要な勉強時間が短いから
宅建士試験が「簡単すぎる」と言われる最大の理由は、必要な勉強時間が比較的短いことです。一般的に、宅建士試験の合格に必要な勉強時間は「300〜500時間」程度だと言われています。これは、他の法律資格と比較すると、かなり少ない時間です。
例えば、司法試験の場合は「2,000〜5,000時間」、司法書士試験では「約3,000時間」の学習時間が必要とされています。つまり、宅建士試験はこれらの資格の「6分の1程度」の勉強で合格することができるのです。
そのため、宅建士試験では「3ヶ月〜6ヶ月」程度の学習期間でも、十分に合格を目指すことができます。行政書士試験などの受験経験があったり、受験指導校を利用したりしている場合は、さらに短期間で合格できる可能性もあるでしょう。他の法律資格と比較すると、短期間で合格を狙えるため「宅建士試験は簡単」だというイメージが広まっているのです。
ただし、働きながら「300〜500時間」の勉強時間を確保しようとすると、一定の努力は必要になります。確かにチャレンジしやすい資格ではありますが、簡単に合格できる試験とまではいえないでしょう。
※宅建士試験の合格に必要な勉強時間については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→【500時間必要?】宅建試験の合格に必要な勉強時間について徹底解説!
2-2.他の法律資格と比較して合格しやすいから
宅建士試験は、他の法律関連の資格試験と比べると、合格率が高い試験です。例えば、次の表は法律資格の合格率を比較したものです。
| 資格 | 合格率 |
| 宅建士 | 15%〜18% |
| 行政書士 | 10%〜12% |
| 司法書士 | 4%〜5% |
| 司法試験(予備試験) | 3%〜4% |
| 社労士 | 5%〜6% |
| 中小企業診断士 | 5%〜7% |
宅建士試験の合格率は「15%から18%」程度で、他の資格と比べると高いことがわかります。特に、司法書士や司法試験(予備試験)と比べると、その差は顕著です。
このように、他の法律資格と比較した際の合格率の高さが、「宅建士試験は簡単だ」という噂が広まる要因の一つとなっています。しかし、これはあくまでも相対的に比較した場合の話です。
絶対的に宅建士試験が簡単だと言えるわけではありません。合格率が「15%から18%」程度というのは、裏を返せば、受験者の「82%から85%」が不合格になっていることを意味しているからです。「6人中5人が落ちる」試験だと捉えると、簡単に合格できるという評価には、かなり無理があるでしょう。
2-3.四肢択一のマークシート形式だから
宅建士試験では、全ての問題が「四肢択一」のマークシート形式で出題されます。
この取り組みやすい試験形式が、宅建士試験が簡単だというイメージにつながっています。例えば行政書士試験では、同じマークシート形式でも、選択肢が1つ多い「五肢択一式」で出題されます。これと比べると、宅建士試験は「四肢択一式」で選択肢の数が少なく、記述式の問題もないため、一見すると簡単そうに見えるのです。
しかし、マークシート形式だからといって侮ることはできません。近年の宅建士試験では、出題形式に変化が見られるからです。具体的には、全ての選択肢の正誤を問う「個数問題」や、正答率が25%程度の難問が増加しており、試験全体が難化傾向にあるのです。
宅建士試験では、マークシート形式だからと言って安易に考えるのではなく、しっかりと対策を立てて臨むことが重要です。単に選択肢を選ぶだけでなく、その根拠となる知識をしっかりと身につけておかないと、合格は難しいでしょう。
2-4.合格している人の数が多いから
合格者数の多さも、宅建士試験が「簡単すぎる」と言われる理由の1つです。
年間約20万人が受験する宅建士試験では、毎年の合格者の数が、約4万人近くにのぼります。そのため、身近に宅建士の資格保有者がいるケースも多く「簡単に取得できるのかもしれない」という印象を持つ人が多いのです。
しかし、この印象は必ずしも試験の難易度を正確に反映しているとは限りません。合格者数が多いのは、単に受験者数自体が多いからに過ぎないからです。実際には、合格者の何倍もの人が不合格となっていることを忘れてはなりません。
宅建士試験の人気と規模の大きさは確かですが、それが即座に「簡単な試験」を意味するわけではないのです。「合格者数の多さ」という表面的な数字に惑わされることなく、試験の本質を見極めることが重要です。
3.宅建の実際の難易度は?忘れてはならない4つのポイント
前述のとおり、宅建士試験が「簡単すぎる」と言われる理由は、必ずしも正確ではありません。さらに、宅建士試験の難易度を考える上では、次の4つのポイントを踏まえることが必要です。
・未経験者ばかりではない
・そもそも勉強時間の確保が難しい
・問われる知識の量が多い
・宅建士試験は難化傾向にある
それぞれ説明します。
3-1.受験するのは未経験者だけではない
宅建士試験を受験する人の中には、不動産業界での実務経験がある人や、行政書士試験などの他資格で法律学習経験のある人もいます。すでに基本的な知識を持っている場合、未経験者に比べて有利に試験に臨むことができるでしょう。
このような一部の受験生の声が、「宅建士試験は簡単だ」というイメージを作り上げている可能性があります。しかし宅建士試験は、決して万人にとって簡単な試験ではありません。
試験では、民法や宅建業法など、広範囲かつ専門的な知識が問われるからです。知識の習得には多大な時間と努力が必要となるでしょう。また、実務経験者や他資格合格者であっても、宅建士試験特有の出題傾向に対応するには、試験に特化した学習が不可欠です。「宅建士試験は簡単」という言葉に惑わされることなく、それぞれの状況に合わせた学習計画を立てることが必要です。
3-2.そもそも勉強時間の確保が難しい
前述のとおり、宅建士試験では「300時間〜500時間」の勉強時間が必要だと言われています。これは、確かに司法試験などと比べると短いですが、社会人が簡単に確保できる時間ではありません。例えば、半年で「300時間」を確保しようと思うと、最低でも毎日「2時間」程度の勉強が必要となります。仕事をしながら毎日「2時間」の勉強をすることは、決して簡単なことではありません。
勉強時間を確保できたとしても、仕事で疲れ果ててしまい集中できないという日もあるでしょう。さらに、家庭を持っている人であれば、家事や育児に追われ、勉強どころではないという人も珍しくありません。このような状況で宅建士試験に合格するには、出題頻度の高いテーマを重点的に学習したり、要点を絞って効率的に勉強を進めたりする工夫が必要です。限られた時間の中で、宅建士試験に合格することは決して簡単なことではないのです。
※宅建士試験の合格に必要な勉強時間については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→【500時間必要?】宅建試験の合格に必要な勉強時間について徹底解説!
3-3.問われる知識の量が多い
宅建士試験は、不動産取引に関する幅広い知識が問われる試験です。
民法、宅建業法、借地借家法、都市計画法など、幅広い法律知識が出題される上、聞き慣れない専門用語もいくつも出てきます。法律の知識がない状態から学習を始める場合、用語に慣れるだけでも、かなりの時間がかかるでしょう。
単に暗記するだけでは、この膨大な知識を身につけることは困難です。宅建士試験に合格するためには、各法律がどのような目的で作られたのか、それぞれの法律がどのように関連しているのかといった、法律の全体像を把握することが重要になります。単に覚えるのではなく、法律の基本的な考え方をしっかりと理解し、実践的な問題にも対応できる応用力を身につける必要があるのです。
3-4.宅建士試験は難化傾向にある
近年、宅建士試験の合格点は上昇傾向にあります。
例えば、平成26年度の宅建士試験の合格点は「32点」でしたが、令和5年度試験では「36点」以上の得点がないと、合格することができませんでした。つまり、以前は約7割の正答率で確実に合格できる試験だったのが、最近では8割の正答率がないと厳しい試験となっているのです。
なお、合格点が上がった理由は、問題の難易度が下がったからではありません。実際、令和5年度試験では、正答率が25%を下回る難問の数が増えていました。むしろ、受験生のレベルが上がったことで、合格点が上昇している可能性があります。つまり、受験生全体のレベルアップに伴って、試験難易度が相対的に上昇しているのです。宅建士試験の合格を目指すなら、これまで以上に効率的かつ実践的な学習が求められます。
合格点の上昇と問題の難化、そして受験生のレベルアップに対応できるよう、戦略的に学習を進めていくことが重要です。
※宅建士試験の難易度については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 宅建士試験の合格率はなぜ低い?合格点や難易度をデータをもとに徹底解説!
4.合格が難しいと感じたら受験指導校もおすすめ
このように、宅建士試験は決して簡単な試験ではありません。膨大な量の法律知識を短期間で習得するためには、効率的な学習方法が不可欠です。
特に、法律の知識がない状態から学習を始める人にとって、何から手をつけていいのかわからないのが実情でしょう。働きながら勉強した結果、数年勉強しても合格できなかったという受験生も珍しくありません。
そんな時におすすめなのが、受験指導校の宅建士合格講座です。受験指導校では、宅建士試験に精通した講師陣によって、洗練された学習カリキュラムが組まれています。全50時間の講座によって、合格に必要なポイントだけを集中的に学習することができます。もちろん、受験指導校に通うためには一定の費用はかかります。
しかし、合格するための最短ルートだと考えれば、コストパフォーマンスは決して悪くありません。宅建士試験の合格を本気で目指すなら、選択肢の1つとして、受験指導校の利用も検討してみてはいかがでしょうか。
※こちらも併せてお読みください。
→ 宅建の通信講座はなぜ伊藤塾がおすすめなのか?宅建士合格講座の魅力を徹底解説
5.まとめ
最後に、今回の記事の要点をまとめます。
◉ 宅建士試験は、簡単に取れる資格ではない
◉ 一部の「簡単に合格できた」合格者の声が目立っているだけ
◉ ただし、法律資格の中でチャレンジしやすい試験ではある
◉ 合格には、ポイントを絞った効率的な学習が必要
宅建士試験は簡単ではありませんが、誰にでもチャレンジしやすい試験です。
宅建士に興味がある方は、ぜひ法律資格専門の指導校である伊藤塾をご活用ください。
「今年はさらにバージョンアップしたコースをご用意!!「2025年合格目標 宅建士合格講座」 のご紹介です!」