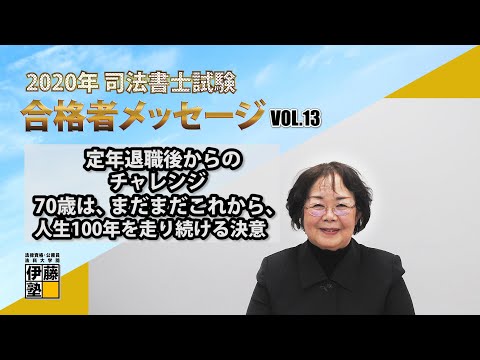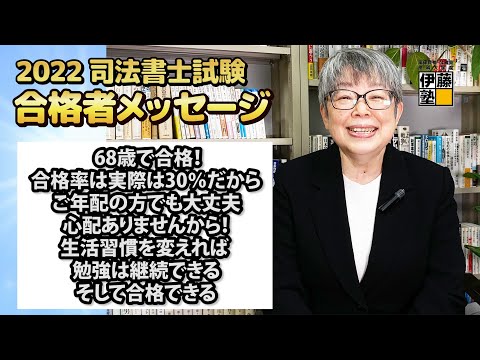「定年後の仕事どうしよう?」と悩む50〜60代が選べる7つの選択肢と選び方
キャリア
2025年09月08日


「定年後も働きたいけど、どんな仕事があるんだろう」
「60歳からの生活費、年金だけで足りるか不安…」
定年を目前にして、あるいは定年を迎えて、こんな気持ちになっていませんか。
長年会社のために働いてきたのに、急に「シニア」扱いされる。再雇用制度はあるけど、部下だった人が上司になるかもしれない。そんな現実を前にして、複雑な気持ちになるのは当然のことです。
でも、考えてみてください。今の60代は、ひと昔前の60代とはまったく違います。体力も気力も充実していて、まだまだ働ける。むしろ、これまでの経験を活かして、新しいことに挑戦したいと思っている人も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、定年後の仕事として考えられる7つの選択肢を紹介し、あなたの状況に合った働き方を見つけるお手伝いをします。再雇用、転職、起業、そして70歳、80歳まで現役で働ける道まで、幅広くお伝えしていきます。
ぜひこの記事を読んで、定年後の人生設計のヒントを見つけてください。あなたらしい「第二の人生」が、きっと見つかるはずです。
【目次】
1.定年後の仕事として考えられる7つの選択肢
定年後の仕事には、大きく分けて7つの選択肢があります。
① 今の会社で再雇用してもらう
② 資格や専門スキルを活かして開業する(士業、塾講師など)
③ これまでの経験を活かして同業の別会社へ転職する
④ シルバー人材センターを利用する
⑤ パートやアルバイトをする(警備員、スーパーやコンビニ店員など)
⑥ 自営業・起業する(タクシー、貨物ドライバーなど)
⑦ 短期・単発のスキマバイトをする(倉庫作業、清掃員など)
この中で基本的におすすめなのは、「①今の会社で再雇用」か「②専門スキルや資格を活かして働く」のどちらかです。どちらも多くの人にとって実現しやすく、これまでの経験を活かしやすいからです。他の選択肢も含めて、それぞれ詳しく解説していきます。
1−1.今の会社で再雇用してもらう
1つ目は、今まで働いていた会社で再雇用してもらうルートです。
高齢者雇用安定法によって、事業主には65歳までの雇用機会の確保が義務付けられています。この法律に基づいて、多くの企業で再雇用制度や勤務延長制度が導入されました。
こうした制度を使えば、定年後も新たな条件で働き続けたり、同じ条件で雇用を継続してもらえたりします。
【メリット】
・慣れた職場なので、新しいことを覚えるストレスがない
・長年の人間関係があるので、仕事がスムーズに進む
・転職活動をする必要がなく、確実に安定した収入が得られる
【デメリット】
・月収40万円が24万円になるなど、給与の額は大幅にダウンする
・「○○部長」から「○○さん」になり、立場の変化に戸惑う
・かつての部下が上司になり、指示を受ける側に回ることもある
1−2.資格や専門スキルを活かして開業する(士業、塾講師など)
2つ目は、士業などの資格や専門スキルを活かして働くルートです。
行政書士、司法書士、社会保険労務士といった士業は、実は50代、60代から始める人が多い仕事です。参考までに、行政書士試験や社労士試験の合格者の4人に1人は50代以上。「今さら資格なんて…」と思う必要はまったくありません。
こういった士業などには定年がないので、70歳、80歳まで現役で働けます。
士業以外にも、塾講師や語学講師、経営コンサルタントなど、これまでの知識や経験を活かせる道はたくさんあります。会社に頼らず、自分の力で稼げるようになれば、定年後の人生はもっと自由になるはずです。
【メリット】
・専門知識を活かせるため、時給換算で高い報酬を得られる
・人生経験が武器になるので、年齢がハンディになりにくい
・自宅でも開業できるなど、働き方の自由度が高い
【デメリット】
・資格や専門スキルがない場合、新たに取得する必要がある
・法改正や制度変更に対応するため、継続的な学習が必要
・定年がない分、引退のタイミングを自分で見極める必要がある
1−3.同業の別会社へ転職する
3つ目は、これまでの経験を活かして別の会社で働くルートです。
40年近く培ってきた専門知識や人脈があれば、同業他社で即戦力として活躍できる可能性があります。特に、営業職で顧客を持っている人や、技術職で特殊なスキルがある人は、意外と需要があるものです。
ただ、正規雇用の求人を見つけるのは簡単ではありません。総務省の統計によると、60歳を境目に正社員が激減し、ほとんどの方がパートやアルバイトでの採用となっています。
◉55歳以降の非正規雇用者の割合

(出典:内閣府|令和7年版高齢社会白書(全体版))
選択肢の一つとはなりますが、基本的には「経営に携わっていて、役員として迎えられた」あるいは「業界で実績があり、同業他社から声がかかった」といったケースに限られるでしょう。
【メリット】
・新しい環境で心機一転、第二の人生をスタートできる
・専門性が高い分野なら、定年前より良い条件で働ける可能性もある
・これまでのキャリアを活かせるので、やりがいを感じやすい
【デメリット】
・そもそも求人が見つかりにくい
・正規雇用での採用は難しく、多くの場合は非正規雇用になる
・特別な実績や人脈がない限り、給与や待遇が大幅に下がることが多い
1−4.自営業・起業する(個人タクシー、貨物ドライバーなど)
4つ目は、退職金を元手に自分でビジネスを始めるルート、つまり起業です。
個人タクシー、貨物ドライバー、飲食店の開業、コンサルティング会社設立など、選択肢は無限大です。成功すれば、会社員時代を超える収入も夢ではないでしょう。ただし、失敗すれば老後資金を失うリスクもあります。
【メリット】
・定年がなく、健康である限り何歳まででも働ける
・自分の裁量で仕事ができ、会社員時代とは違う充実感がある
・成功すれば、会社員時代を超える収入も可能
【デメリット】
・失敗すれば退職金を失い、老後資金が底をつくリスクがある
・安定収入を得るまでに時間がかかり、当面は赤字覚悟が必要
・肉体的、精神的な負担が大きい
1−5.シルバー人材センターを利用する
5つ目は、地域のシルバー人材センターに登録して仕事を受ける方法です。
シルバー人材センターは全国にあり、60歳以上なら誰でも会員になれます。センターが地域の企業や自治体、一般家庭から仕事を受注し、登録している会員に仕事を割り振ってくれる仕組みです。
ただ、仕事の内容は、草刈り、清掃、駐車場の管理、宛名書きなど、特別なスキルがなくてもできる軽作業がほとんどです。がっつり稼ぐというよりは、社会とのつながりを持つイメージになるでしょう。
【メリット】
・軽作業や短時間労働が中心なので、体力的に無理なく働ける
・地域社会や人とのつながりを持ちやすい
・特別なスキルがなくても、誰でも気軽に始められる
【デメリット】
・仕事の内容や量は選べず、希望通りの仕事が来るとは限らない
・短期・短時間の仕事が多く、安定した収入は期待できない
・スキルや経験を活かすという意味でのやりがいは感じにくい
1−6.パートやアルバイトをする(警備員、スーパーの軽作業など)
6つ目は、パートやアルバイトとして働く方法です。
コンビニ、スーパー、警備会社などを中心に、「60歳以上活躍中」「シニア歓迎」といった求人も多く、選択肢は意外とあります。週2〜3日だけ、午前中だけといった働き方もできるので、年金をもらいながら月数万円の収入を得たい人には最適です。
ただ、これまで管理職だった人でも、20〜30代の社員から指示を受けることになります。人によっては、プライドとの折り合いをつける必要があるでしょう。
【メリット】
・シフト制で働く日数や時間を調整でき、自分のペースで働ける
・職種が豊富なので、自分の体力や興味に合った仕事を選べる
・未経験でも採用されやすい求人が多く、仕事を見つけやすい
【デメリット】
・時給は最低賃金に近いことが多く、まとまった収入にはなりにくい
・20〜30代の若手社員から指示を受ける立場になることもある
・単純作業が中心で、仕事に変化や刺激が少ない
1−7.短期・単発のスキマバイトをする(倉庫作業、清掃員など)
7つ目は、スマホのアプリを使って好きな時だけ働く方法です。
「タイミー」「シェアフル」といったアプリに登録すれば、面接なしで明日からでも働けるバイトが探せます。倉庫のピッキング、清掃員、飲食店スタッフなど、1日単位の仕事がスマホで簡単に見つかる時代になりました。
月曜はアルバイトをして、火曜は孫と遊んで、水曜はゴルフ…といった自由な生活もできます。大きな収入は期待できませんが、社会とのつながりを保ちながら、マイペースで働きたい人には向いています。
【メリット】
・自分の都合に合わせて働く日を選べるので、自由度が高い
・さまざまな年代の人と交流できる
・いくつもの現場を経験できるので、新しい発見がある
【デメリット】
・仕事がない時期もあり、収入が不安定になる
・20〜30代の若手社員から指示を受ける立場になる
・職場が毎回変わるため、仕事に慣れたり、人間関係を築くのが難しい
2.定年後の仕事を選ぶ前に考えるべき3つのこと
ここまで、定年後の仕事として考えられる7つの選択肢を見てきました。
ただ、すぐに「どれにしよう」と決めるのは難しいでしょう。定年後の仕事選びは、単に「働き方」を選ぶだけでなく、「生き方」を選ぶことだからです。
あなたにとって最適な選択は、以下の3つによって変わってきます。
・どれくらいの収入が必要か
・何を優先したいか(お金、時間、やりがい)
・家族がどう考えているか
これらを明確にせずに選んでしまうと、後で後悔する可能性が高くなります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
2−1.どれくらいの収入が必要か
まず最初にやるべきは、毎月の出費を確認し、必要な収入額を把握することです。
年金だけで生活できるのか、それとも他に収入が必要なのか、必要だとしたら、月にいくら足りないのか、以下3つのステップで計算してみてください。
① 月々の支出を書き出す(住居費、食費、保険、趣味など)
② 年金受給額を確認する(ねんきん定期便でチェック)
③ 差額を計算する
(例:支出25万円 - 年金18万円 = 不足7万円)
この差額があなたの「必要収入」です。さらに、残りの人生でやりたいことも書き出してみましょう。海外旅行、子や孫への援助、趣味のお金、自宅のリフォームなどです。
これらの予算も加えて計算していけば、仕事選びでどの程度収入を重視するべきかが分かります。
2−2.何を優先したいか(お金、時間、やりがい)
次に考えるべきは、あなたが定年後の人生で何を大切にしたいかです。
これまで長年、会社のために時間を使ってきました。残りの人生は、もう少し自分の希望を優先してもいいはずです。
ただ、何を優先するかは人それぞれです。以下の項目で、特に当てはまるものをチェックしてみてください。
□ 老後資金に不安がある
□ 孫に何かしてあげたい
□ まだ自宅のローンが残っている
□ 趣味に時間を使いたい
□ 家族(配偶者)との時間を大切にしたい
□ 健康管理を最優先にしたい
□ まだまだ成長したい
□ 社会の役に立ちたい
□ 新しいことに挑戦したい
どこに多くチェックが入りましたか?
上から3つに多くチェックが入れば「お金重視」、真ん中3つなら「時間重視」、下3つなら「やりがい重視」です。
この傾向によって、あなたに適した仕事が変わってきます。
お金重視なら再雇用や転職で確実に稼ぐ、時間重視なら短期バイトやシルバー人材センターを利用する、やりがい重視なら新しい資格取得や起業という選択肢が考えられます。
もちろん「お金もやりがいも両方」という方もいるでしょう。その場合は、長く働ける仕事を選ぶことで、両方を実現できる可能性があります。
2−3.家族がどう考えているか
最後に、家族がどう思っているのかも聞いておきましょう。
意外と「毎日家にいられると困る」という配偶者や、「起業は絶対に反対」という子どもも多いです。家族としっかり話し合うことで、現実的な選択肢が見えてきます。
◉よくある家族の声
(妻の本音)
「正直、毎日家にいられると息が詰まる」
「でも体を壊すような働き方はしないで」
「週3日くらい、自分のペースで働いてくれるのが理想」
(子どもの意見)
「仕事を辞めて家にいるとボケそうで心配」
「やりたいこと、新しいことに挑戦して欲しい」
「たまに孫の面倒は見てもらえると助かる」
定年後の夫婦関係を良好に保つためにも、適度な距離感は大切です。
3.何を重視する?【タイプ別】定年後におすすめな仕事
前章で自分の状況を整理したら、次は具体的にどの仕事を選ぶかです。
「収入優先・時間などの自由度優先・やりがい優先」の3つのタイプに分けて、おすすめの仕事をご紹介します。
3−1.老後資金が足りない人(収入を優先したい人)
3−1−1.月5〜10万円以上の収入が必要な場合
今の会社での再雇用がおすすめです。現役時代より給料は下がりますが、最も確実に収入を維持できるからです。
ただし、まだ定年まで数年以上あるなら、資格なども検討する余地はあります。
再雇用は65歳で終わりますが、士業などであれば生涯現役で働けます。長期的にはこちらが有利かもしれません。
3−1−2.月1〜5万円程度の収入で十分な場合
パート・アルバイトがおすすめです。週2〜3日、1日5時間程度働けば達成できるでしょう。
求人ジャンルによってはシニア歓迎の求人も多いので、仕事を選ばなければすぐに始められます。
3−2.時間、場所などの自由度を大切にしたい人
スキマバイトをしたり、シルバー人材センターを利用したりするのがおすすめです。
これらは「明日だけ」「午前だけ」といった働き方ができるので、仕事以外の時間を大切にしやすいです。孫の運動会も、夫婦旅行も、自由に予定を組めます。収入は期待できませんが、自由度には代えられません。
もう一つ考えられるのが、自宅で開業するという方法です。
たとえば、士業などの資格職なら、自宅を事務所として開業できます。資格職でなくとも、家庭教師をしたり、ハンドメイド作品を販売したり、趣味のスクールなどを行う方法もあるでしょう。どれも通勤の必要がなく、働く時間・場所も自由です。
ただし、資格や専門スキルが必要なので、定年前から準備が必要です。
3−3.これまでのキャリアを活かし、やりがいをもって働きたい人
同業他社への転職か、専門職として独立するかの二択です。
ただ、転職は現実的に厳しいケースもあります。60歳を過ぎての正社員採用は少ないので、よほどの実績か人脈がない限り、非正規雇用になるでしょう。
それならいっそ、専門職として独立を考えてみるのも良いでしょう。40年の経験は必ず武器になります。経営コンサルタント、業界アドバイザー、または士業の資格を取って専門家として開業するなど、さまざまな道があります。
4.定年後、生涯現役を目指す方におすすめなのは法律系の資格
ここまで、定年後の仕事の全体像を見てきました。その中で、多くの人が気になっているのが「どれくらい長く働けるか」ではないでしょうか。人生100年時代、できれば70歳、80歳まで安定した収入を得たい。そう考える人が増えています。
では、生涯現役で働ける仕事とは何か、その選択肢の一つとしておすすめしたいのが、法律系の資格です。ここからは、なぜ法律系資格が定年後の仕事として最適なのかを3つのポイントから紹介していきます。
◉法律系の資格がおすすめな理由
・体力的な負担が少なく、定年がない
・未経験からでも挑戦しやすい
・これまでの人生経験を活かせる
それぞれ詳しく説明します。
4−1.体力的な負担が少なく、定年がない
法律系資格の魅力は、体力的な負担が少なく続けやすいことです。
専門知識を活かした書類作成や相談業務がメインなので、重い荷物を運んだり、立ちっぱなしで働いたりする必要はありません。自分のペースで、無理なく仕事を進められます。
さらに、開業が前提となるので、定年退職という概念がありません。会社員なら65歳で再雇用も終わりますが、士業なら70歳、80歳、さらには90歳まで現役で活躍している人もザラにいます。
4−2.未経験からでも挑戦しやすい
未経験からでも挑戦しやすいのも法律系資格の魅力です。
基本的に受験資格がないので、これまでの経歴にかかわらず挑戦できます。行政書士、司法書士、社労士など、年齢、学歴、職歴に関係なく、誰でも受験できるのです。医師や薬剤師のように大学に行く必要もありません。
さらに、合格者の平均年齢も高めです。行政書士試験・社労士試験の合格者の4人に1人は50代以上、司法書士試験でも同様の傾向があります。実際、伊藤塾では60代でこれらの試験に合格している人も多く、70歳で司法書士試験に合格した人もいます。
※以下の動画で、60代で司法書士になられた方々のお話を伺っています。
「2020年司法書士試験合格者Vol.13~定年退職後からの受験チャレンジ、70歳は、まだまだこれから、人生100年を走り続ける決意~」
「2022年司法書士試験合格~68歳で合格!合格率は実際は30%だから、ご年配の方でも大丈夫、心配ありませんから!生活習慣を変えれば勉強は継続できる、そして合格できる。~」
4−3.これまでの人生経験を活かせる
法律系の仕事で求められるのは、実は専門知識だけではありません。
同じくらい大切なのが、お客様の悩みを聞き取る「傾聴力」、相手に分かりやすく説明する「コミュニケーション力」、そして人生経験によってにじみ出る「人間力」です。
これらはまさに、長年の会社員生活で培ってきた能力そのものです。そのため、人生経験の浅い20〜30代よりも、さまざまな経験を積んだシニア世代の方が信頼されやすいことが多々あります。
さらに、法律とまったく関係ない業界の専門性が活きるケースも多くあります。たとえば、建設会社出身なら行政書士の建設業許可で、人事畑を歩んできたなら社労士の労務管理で発揮される、といった具合です。
法律系の仕事では、50代・60代という年齢がハンディではなく、むしろ強みになるのです。
5.定年後の仕事として、行政書士資格を選んだ人の声
とはいえ、「本当に50代、60代からでも大丈夫?」と不安な方もいるでしょう。
そこで、実際に定年後の仕事として法律資格を選んだ人の声を紹介します。
今回は一例として、法律資格の中でも短期間で目指しやすい行政書士試験の合格者をピックアップしました。
(2024年度 行政書士試験合格者 阿部 豊彦さん(60代))
65歳で会社員人生を卒業し、セカンドライフを行政書士としてスタートします。
個人事業主として事務所を構え、近隣住民の皆様のお困りごとに寄り添える行政書士を目指します。
弟、父、母家族3人を看取った経験から、相続手続きのお手伝いが主になりそうです。が、国際業務や任意後見にも興味あり、まずは実務講座を受講していく中で固めていきます。
(2024年度 行政書士試験合格者 高橋 千文さん(50代))
50代になり定年後を考えたとき、開業できる資格であることと業務範囲の広さに魅力を感じ行政書士を目指そうと思いました。
受験する前は会社員として定年後も雇用延長して過ごそうと考えていましたが、定年した方々と今も交流があり、皆さん口を揃えて仕事はずっとした方がいいと話されています。
定年後も人の役に立てる仕事をしたいと思い行政書士を目指しました。
(2023年度 行政書士試験合格者 岡本 吉裕さん(50代))
50代後半になり家族を養う身であるにもかかわらず、退職後の選択肢がないことに不安を感じたことです。そこでネクタイを締めて働ける、そして何か独占業務を与えられた資格を手に入れようと考えました。行政書士に目標を定めたのは、私が大学に入学した40年前には、行政書士試験と宅建は誰でも受かると揶揄されていたことから、受かりやすいかもと思い行政書士を選びました。3年前のことです。
(2023年度 行政書士試験合格者 石田 昭彦さん(60代))
家族の介護も予想されるため、自宅での仕事を考えて独立開業できる行政書士を57歳の時に目指そうと考えました。その当時は地方銀行に勤務しており、いよいよ介護が必要となってきたため、59歳で会社を定年退職し介護と家事を行いながら勉強を続けました。
※こちらの記事もあわせて読まれています。
ご覧のように、多くの方々が定年後の仕事として行政書士を目指し、見事に合格しています。
50代で将来への不安を感じた人、介護と両立しながら勉強した人、会社での経験を活かしたいと考えた人、それぞれ理由は違いますが、皆さん定年後の仕事として行政書士を目指して、実際に合格されています。
もしあなたが「65歳以降も安定して働きたい」「自分のペースで仕事をしたい」「これまでの経験を活かして社会に貢献したい」と考えているなら、ぜひ法律系資格を選択肢の一つとして検討してみてください。
最後に、上記の合格者の方々が利用していた伊藤塾についてご紹介します。
6.法律系の資格を目指すなら伊藤塾がおすすめ
もし、定年後の仕事として法律資格に興味を持たれたなら、ぜひ当コラムを運営する伊藤塾にご相談ください。伊藤塾は、1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出してきた法律資格専門の受験指導校です。特に、司法試験、司法試験予備試験、司法書士試験などの難関法律資格で、圧倒的な実績を誇っています。
・司法試験 :合格者1,592名中1,436名が伊藤塾を利用(合格者占有率 90.2%)
・予備試験 :合格者449名中405名が伊藤塾を利用(合格者占有率 90.2%)
・司法書士試験 :合格者737名中433名が伊藤塾を利用(合格者占有率 59%)
伊藤塾を利用して難関法律試験に合格しているのは、一部の限られた人だけではありません。
法律初学者からでも、定年後から勉強を始めた方でも、あるいは介護や家族の世話と両立しながらでも、多くの方が難関法律試験に合格しています。50代、60代の合格者も多数輩出しており、年齢を不安に感じる必要はありません。
さらに、合格後をサポートする様々な取り組みを実施していることも伊藤塾の特徴です。
合格したOB・OG同士の同窓会設立など、「法曹」「司法書士」「行政書士」「社会保険労務士」といった士業の方々がつながれる機会を積極的に提供し、合格後の活躍をサポートしています。
※こちらの記事も読まれています。
7.定年後の仕事に関するよくある質問
Q1. 50代・60代で定年後に正社員として働くことは、現実的に可能なのでしょうか?
A. 60歳を境に正社員の求人は大幅に減り、多くの場合、パートやアルバイトといった非正規雇用での採用になるのが現状です。同業の別会社へ転職する場合も、特別な実績や人脈がない限り、正規雇用での採用は難しいとされています。ただし、「経営に携わっていて役員として迎えられた」り、「業界で実績があり同業他社から声がかかった」りするような特定のケースでは、正社員としての転職も考えられます。
Q2. 法律系の資格取得を目指す場合、どのくらいの期間や勉強時間が必要ですか?
A. 法律系の資格の中でも行政書士試験は「短期間で目指しやすい」医師や薬剤師のように大学に通う必要がなく、未経験からでも挑戦しやすいという特徴があります。
Q3. 定年後の仕事における一般的な収入の目安について教えてください。
A. 定年後の仕事における収入は、選択肢によって大きく異なります。
再雇用の場合、現役時代と比較して月収が大幅にダウンすることがデメリットですが、最も確実に収入を得られる方法です。
パートやアルバイト、 シルバー人材センターの仕事では、まとまった収入にはなりにくい傾向があります。
一方、資格や専門スキルを活かした開業(士業など)会社員時代を超える収入も夢ではないとされています。
8.定年後の仕事探しの選択肢と選び方・まとめ
本記事では、定年後の仕事探しに悩む50代・60代の方へ、具体的な選択肢と成功のためのヒントを紹介しました。
以下に本記事のポイントをまとめます。
・定年後の仕事には、①今の会社での再雇用、②資格や専門スキルを活かした開業、③同業の別会社への転職、④シルバー人材センターの利用、⑤パート・アルバイト、⑥自営業・起業、⑦短期・単発のスキマバイト の7つの選択肢があります。
・特に、①今の会社で再雇用 か ②専門スキルや資格を活かして働くことが、多くの人にとって実現しやすく、これまでの経験を活かしやすい点で基本的におすすめです。
・仕事を選ぶ前に、「どれくらいの収入が必要か」「何を優先したいか(お金、時間、やりがい)」「家族がどう考えているか」の3つの視点から、自身の状況を明確にすることが重要です。
・老後資金が不足し収入を優先したい場合は、希望額が大きい方は「再雇用」、数万円程度で大丈夫なら「パート・アルバイト」、時間や場所の自由度を大切にしたい場合は「スキマバイト」や「シルバー人材センターの利用」、または「自宅での開業」、キャリアを活かしてやりがいをもって働きたい場合は「同業他社への転職」や「専門職としての独立」がそれぞれ適しています。
・人生100年時代において、70歳、80歳まで長く安定して働きたいと考える方には、法律系の資格取得が特におすすめです。法律系の資格は体力的な負担が少なく定年がなく、未経験からでも挑戦しやすく、これまでの人生経験を強みとして活かせるという魅力があります。実際に、行政書士試験の合格者には50代・60代の方々も多くいます。
以上です。
定年後のセカンドキャリアを充実させるためには、自身の状況と希望に合った選択をすることが大切です。もし、定年後も長く活躍できる法律資格に興味を持たれたなら、ぜひ伊藤塾にご相談ください。
伊藤塾は、1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、司法試験や司法書士試験などの難関法律資格で圧倒的な実績を誇っています。
法律初学者の方や、定年後から勉強を始めた方、介護や家族の世話と両立しながらの方でも、50代・60代を含め多くの方が難関法律試験に合格しています。また、合格後の活躍をサポートする同窓会設立など、士業の方々がつながれる機会も積極的に提供しています。
あなたの「第二の人生」の第一歩を、伊藤塾が全力でサポートいたします。