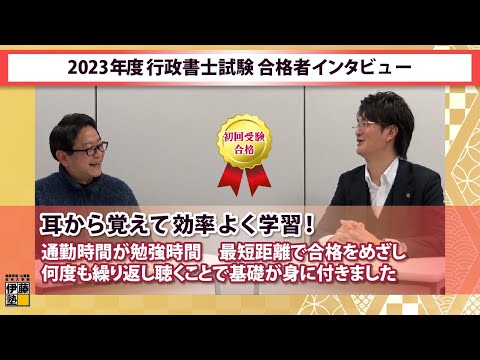行政書士試験の勉強スケジュールは?いつ始める?合格者の勉強法も公開
勉強法
2025年09月03日


「行政書士試験に合格するための勉強スケジュールが知りたい」
「試験勉強はいつからスタートするべき?」
「毎日どれくらいの勉強時間は必要?」
行政書士試験の受験生から、こんなご質問をいただくことは少なくありません。忙しい受験生が、限られた時間の中で試験合格を目指すためには、正しい勉強スケジュールの作成が必要不可欠です。
しかし、勉強スケジュールの作成は意外に難しいもの。
・社会人、主婦、学生…
・法律初心者、学習経験者…
それぞれの環境や経験に応じて、試験の戦略も大きく変わってきます。勉強の方向性を間違えると、いくら勉強を続けても、合格できないという事態にもなりかねません。
本記事では、毎年多くの行政書士試験合格者を輩出している当塾が
◉ 行政書士試験の勉強をスタートする時期
◉ 開始時期別の勉強スケジュール
◉ スケジューリングのコツ
について解説します。効率的な勉強スケジュールを作成するために、是非ご一読ください。
【目次】
1.行政書士試験の勉強はいつから始める?
行政書士試験が毎年11月に実施されるのに対し、試験を目指そうと思って学習を開始するタイミングは人それぞれです。
また、学習開始のタイミングによって、学習戦略も異なります。例えば、次のようなポイントによって、合格に必要な学習期間は大きく変わってきます。

一般的には、「早く始めれば始めるほど良い」と言われますが、一概には言えません。早くスタートしたものの、途中で中だるみしてしまったり、モチベーションが低下してしまう人もいれば、逆に、スタートが遅くなったとしても、短期ゆえにモチベーションを切らすことなく、最後まで駆け抜けて合格する人もいます。
学習開始時期に応じた正しい勉強方法で効率的に学習を進めていけば、短期間の学習でも、十分に合格点に達することができます。例えば、独学時代に毎年多くの勉強時間を費やしたものの、何年かけても不合格だった受験生が、受験指導校で、適切な学習方法を教わったことにより、少ない学習時間でも合格できたというケースがたくさんあります。
① 8月から本格的に勉強を開始して、3ヶ月で合格したNさん
行政書士試験は、一度だけ独学で受験し不合格。
その後しばらく勉強を中断していたものの、8月に伊藤塾の「合格講座 速修生」に入塾して、初めて本格的に勉強を開始しました。
勉強に充てられる時間は少なかったものの、プロのアドバイスに従って、重要なポイントのみを抽出して勉強した結果、3ヶ月という超短期間での合格を実現できました。
※関連動画 合格者インタビュー
「短期合格を実現した”時短学習法”~独学から一番変えたこと~」
② 4度目のチャレンジで合格したOさん
独学で勉強を進め、行政書士試験に3回チャレンジしましたが、いずれも不合格でした。
独学時代は、どれだけ勉強しても、思ったように得点を伸ばすことができませんでしたが、今思えば、そもそも勉強の方向性が間違っていたように思います。
必要な問題の取捨選択が全くできておらず、受験指導校の講師の方から、「ここは出ない」「この知識はいらない」と言われて、衝撃を受けたことを覚えています。
※関連動画 合格者インタビュー
「4回目の受験は今までと違った手応えでした!」
結局のところ、「今からでは勉強時間が足りないのでは・・・」といったように、勉強開始のタイミングにこだわるのではなく、残された期間から逆算して、戦略的に学習を進めていくことが大切だと言えるでしょう。
1-1.行政書士試験に必要な勉強時間
行政書士試験に合格するためには、一般的には「600〜1,000時間程度」の勉強時間が必要だと言われています。ただし、この勉強時間はあくまでも目安であり、個人差が大きいです。
例えば、法律系資格の勉強経験があったり、受験指導校などを利用して効率的に学習を進めた場合、600時間以下の勉強時間で合格できる可能性があります。
一方、独学で行政書士試験の勉強を始める場合、法改正の情報収集など、勉強以外の部分でも時間を取られてしまい、勉強時間も増えてしまいがちです。特に、法律の初学者にとって、参考書を読んで理解するまでにはかなりの時間がかかるため、2〜3年もの歳月を要してしまうことも珍しくありません。
試験に確実に合格するためには、学習開始時期に応じた学習戦略のもと、それに沿った勉強スケジュールを計画し、日々継続して学習を進めていくことが大切です。
※行政書士試験の合格に必要な勉強時間については、こちらの記事で詳しく解説してます。
2.行政書士試験の勉強スケジュールをシミュレーション
それでは、行政書士試験に合格するためには、具体的にどのように勉強スケジュールを作成すればよいのでしょうか?この章では、行政書士試験の勉強スケジュールについて、勉強を開始する時期別に、実際にシミュレーションしていきます。
①11月からスタートするケース
② 1月からスタートするケース
③ 4月からスタートするケース
それぞれ見ていきましょう。
2-1.11月からスタートするケース
まずは、学習期間を1年(12ヶ月)とした場合の勉強スケジュールです。この場合、比較的余裕を持って勉強時間を確保することができます。早期スタートの利点を活かし、基礎からしっかりと土台を構築していきましょう。
伊藤塾の受講生を見る限りでは、全科目について基本からしっかりと学習することで、確実に合格しています。ただし、モチベーション管理が難しいと感じる人も多いため、ペース配分に気をつけて学習を進めていきましょう。
2-1-1. 時期ごとの勉強スケジュール
【11月〜2月:スタート期】
テキストを中心に、基礎知識のインプットを重点的に行いましょう。「憲法」からスタートし、「民法」、「行政法」といった重要度の高い科目を中心に勉強を進めていきます。
【3月〜8月:中期】
基礎の構築が終わったら、問題演習に重点を置いて、学習を進めていきましょう。テキストと問題を何度も往復し、しっかりとした土台を作りましょう。
【9月〜11月:直前期】
直前期には、本番に即した形で、実践的な演習を進めていきます。記述式問題の演習、模擬試験などを活用して、本番に向けた対策を行いましょう。
2-2.1月からスタートするケース
次に、学習期間を9ヶ月とした場合のシミュレーションです。
この時期から開始しても、スキマ時間などを上手く活用すれば、必要な勉強時間を確保することができます。主要科目を中心に、しっかりと学習を進めていきましょう。
確実に合格するためには、試験の頻出テーマを押さえて、効率的な学習戦略を作成することが重要です。
2-2-1. 時期ごとの勉強スケジュール
【1月〜3月:スタート期】
テキストを中心に、基礎の構築を重点的に行いましょう。インプットに充てられる時間が少ないため、ポイントを絞って学習を進めることが必要です。
【4月〜8月:中期】
基礎の構築が終わったら、積極的に問題演習を進めていきましょう。テキストと問題を何度も往復することで、効率的に知識を定着させることができます。
【9月〜11月:直前期】
直前期には、実践的な演習を進めていきましょう。記述式問題の演習、模擬試験など、本番に即した形で、問題を解くスピードを鍛えていきます。
2-3.4月からスタートするケース
最後に、学習期間を半年(6ヶ月)とした場合のシミュレーションです。
11月〜1月にスタートしたライバルと比べると、勉強に充てられる時間は少なくなってしまいます。もっとも、正しい試験戦略を立てて、効率的に勉強を進めていくことさえできれば、合格は決して難しくありません。
例えば、「民法」や「行政法」などの配点の高い科目を、確実に得点することで、合格に大きく近づくことができます。勉強時間が足りないと感じる場合は、受験指導校の講座も検討してみましょう。
2-3-1. 時期ごとの勉強スケジュール
【4月〜8月:スタート期】
憲法・民法・行政法の主要3科目を中心に、テキストと演習を反復して学習していきます。最小限の労力で目標を達成するために、頻出テーマに的を絞って対策を進めていきましょう。
【9月〜11月:直前期】
記述式問題の演習や、模擬試験を活用して、実践的な演習を進めていきます。試験の予想問題等も使用して、学習の総仕上げと最終確認を行いましょう。
3.スケジューリングのコツ
行政書士試験においては、勉強スケジュールを適切に設定できるかが、合格の鍵を握っているといっても過言ではありません。しかし、実際に作成してみると、スケジューリングは意外に難しいものです。
そこでここでは、スケジューリングのコツを3つ紹介します。

3-1.ゴールから逆算する
行政書士試験に合格するためには、まずは明確なゴール設定が重要です。残された時間や、合格に必要な点数から逆算して、日々の具体的な計画を立てていきましょう。
例えば、「来年11月の行政書士試験に合格する」というゴールを設定したら、そこから逆算して、半年後、3ヶ月後、1ヶ月後までにどこまで勉強を進めるべきかを明確にします。
期限を区切ることで、モチベーションを維持しながら、着実に学習を進められるでしょう。目標達成のために、自分のペースでコツコツと勉強を継続していきましょう。
3-2.目標を細かく設定する
次に、大まかな目標をさらに細分化し、具体的な行動レベルまで落とし込みます。
例えば、「行政法の過去問集を1ヶ月で1周する」といった目標に対し、1日あたり何問進めていくのかを決めます。1日10問進める計画を立てれば、30日で300問の過去問を演習することができます。
目標を細かく設定し、毎日の行動目標を細分化していくことで、日々の学習が継続しやすくなります。ただし、あくまでも最終的な目標は、合格に必要な知識を身につけることです。「何周するか」「何問解くか」が学習の目的にならないように注意しましょう。
3-3.計画は定期的に見直す
一度立てた勉強計画は、定期的に見直すことが大切です。予定した計画通りに進まないことは、決して珍しいことではありません。
テキストを理解することに予想以上に時間がかかってしまったり、逆にペースが上がったりと、学習の進捗状況は日々、変化していきます。そのため、1週間や1ヶ月といった区切りで、定期的に計画の進捗を振り返ることが必要です。進捗を確認し、目標やスケジュールを調整することで、効率的に学習を進めていくことができます。
4.忙しい社会人が勉強の効率を上げる方法
個人差が大きいとはいえ、一般的に「600〜1000時間」の勉強時間が必要だといわれている行政書士試験。毎日2〜3時間の勉強時間を働きながら確保することは、決して簡単ではありません。
忙しい社会人が、行政書士試験に合格するためには、勉強の効率を上げることが必要不可欠だといえるでしょう。この章では、社会人が勉強の効率を上げるための方法について解説します。

4-1.スキマ時間を活用する
仕事や家事で時間を奪われてしまう社会人にとって、まとまった勉強時間を確保することは難しいかもしれません。そのような場合は、スキマ時間を有効活用しましょう。
通勤電車の中や昼休みなど、わずかなスキマ時間でも勉強に充てることで、着実に知識を身につけることができます。
例えば、
・テキストや一問一答の問題集を持ち歩いて復習する
・スマートフォンを活用して、倍速で講義動画を再生する
など、スキマ時間を活用する方法は、いくらでも存在します。1回10分のスキマ時間でも、6回繰り返せば「1時間」の勉強時間に相当します。スキマ時間を活用して、継続的に学習を進めていくことで、合格に大きく近づくことができるでしょう。
4-2.科目ごとの優先順位を付ける
行政書士試験の科目は多岐にわたるため、全てを均等に勉強するのは非効率的です。限られた時間で合格するには、科目ごとに優先順位を付けて学習することが必要です。
例えば「憲法」「民法」「行政法」などの配点の高い主要科目を重点的に学習していくことで、最小限の労力で目標点数に到達することが可能となります。
さらに、主要科目の中でも、本試験で問われやすい頻出テーマの優先順位をあげて学習を進めることが大切です。「どの科目で何問づつ得点することで180点の合格基準点を突破する」、といった学習戦略をしっかり立てることが、勉強の効率を上げるためにも重要となります。
4-3.受験指導校を利用する
合格に必要な勉強時間を大幅に短縮するためには、受験指導校を利用することも一案です。受験指導校には
◉ 合格実績に裏付けされた学習戦略と効率的な勉強スケジュール
◉ 出題傾向を踏まえたメリハリのある講義
◉ プロの講師陣による分かりやすい講義
◉ 合格に必要な知識だけをまとめた洗練された教材
など、最短で合格するために必要なノウハウや環境が整っています。
プロのアドバイスを受けながら、状況に応じて勉強スケジュールを修正していくことで、限られた学習期間でも、格段に合格率を高めることができます。特に仕事や家事で忙しい社会人にとって、受験指導校は心強い味方となるでしょう。
5.行政書士合格者の勉強スケジュールや勉強法を大公開
最後に、実際に行政書士試験に合格した受講生の、「勉強スケジュール」や「勉強法」を紹介します。行政書士試験の合格に必要なノウハウが詰まっているので、ぜひ参考にしてください。
5-1.4月末からスタートして、半年で一発合格したKさん
【勉強の開始時期について】
試験6ヶ月前の「5月」から本格的に勉強を開始しました。半年間の勉強で、独学で合格することは難しいと感じたため、伊藤塾の「合格講座 速修生」を利用しました。
働きながらの勉強だったので、講義の配信に追いつくのが大変でしたが、毎日の通勤時間が片道1時間程かかっていたため、電車の中で片道1コマを目安に、講義を受講するようにしていました。加えて、朝1時間だけ早く起きて勉強したり、昼休みを利用したりすることで、無理なく勉強を進めることができました。
【勉強方法で工夫した点】
スキマ時間を活用して、重要項目を耳から学習することを意識していました。特に「速修生」の復習アシスト講義は、1回20分で重要項目を復習できるため、歩いている時間を利用して、100回以上も繰り返し聞きました。
これによって、本来膨大な時間がかかるはずの民法や行政法を、ハイスピードで習得できたことが、勉強時間を大幅に短縮できたポイントだと思います。
5-2.2回目の受験で合格したMさん
【1回目の受験時のスケジュール】
1回目の受験時は、独学で、市販のテキストや1問1答の問題集を利用して勉強していました。専業で勉強していたため、1日の勉強時間は7〜8時間。直前期については朝から晩までずっと勉強をしていました。
しかし、思ったように成績が伸びず、本試験は惨敗。記述式に至っては「4点」しか得点することができませんでした。テキストを読みながら、ひたすら過去問を解いていくという独学の勉強に限界を感じ、受験指導校を利用することにしました。
【2回目と1回目の違い】
受験指導校の講師のメリハリのある説明と、具体例を交えた分かりやすい講義で、合格に必要な基礎力が一気に高まりました。得点も、前年が嘘のように一気に伸びて、模試の頃には基礎力は万全と自信をもって言える状態になりました。
勉強スケジュールについては、週単位で目標を設定して進めていました。特に、夏以降の直前期については、週の中でも日毎に分けて、細分化して進めていきました。
受験指導校の講師が言っていた「合格者というのは、予定が全て決まっている」という言葉が今でも印象に残っています。合格から逆算して、目標を細分化し、徹底的に予定通りに過ごせたことが合格につながったのかなと思います。
6.まとめ
最後に、今回の記事の要点をまとめます。
◉ 行政書士試験の勉強を開始するタイミングに正解はない
◉ 長期間学習しても不合格になる人がいる一方で、短期間でも合格できる人もいる
◉ 学習期間よりも、勉強の方向性(戦略)が合否を大きく左右する
◉ 受験を決めたタイミングに応じて、正しい勉強スケジュールを立てることが大切
限られた勉強時間でも、正しい戦略を立てて勉強を進めていけば、行政書士試験に合格することは決して難しくありません。勉強の方向性に不安を感じたら、ぜひ法律専門指導校である伊藤塾へご相談ください。
伊藤塾の「行政書士合格講座」は、法律を初歩からしっかり学習していくことができる講座です。
→ 行政書士合格講座はこちら
夢の実現に向けて、ぜひ一歩を踏み出してみてください。
伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。