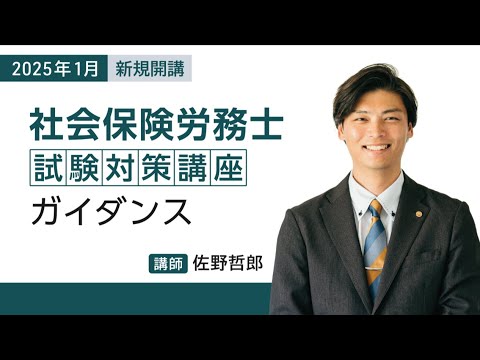社労士資格を活かした副業とは?仕事内容や成功のポイントを徹底解説
キャリア
2025年10月21日


「副業」「ダブルワーク」という言葉が特別ではなくなり、多くの人が本業以外での新しいキャリアや副収入を求めるようになりました。
今、その選択肢の一つとして、社会保険労務士(以下、社労士)資格が注目を集めています。その理由として、専門性を活かして高単価な案件を獲得できる点や、時間や場所に縛られない柔軟な働き方が実現できる点が挙げられます。
しかし、実際に社労士資格を副業として活用するためには、業務に関する基礎知識を持ち、自分に合った働き方を選択することが重要です。
本記事では、なぜ社労士が副業に適しているかを詳しく解説した上で、具体的な副業スタイルや仕事の見つけ方、必要なスキルについて詳しく説明していきます。
副業としての社労士の可能性を探っている方は、ぜひ参考にしてください。
【目次】
1. 社労士資格が副業に最適な理由
社労士資格が副業に適している理由として、主に以下の3つのポイントが挙げられます。
| ・独占業務がある ・高単価な副業も見込める ・在宅ワークに適している |
1つずつ、詳しく説明をしていきます。
1-1. 独占業務がある
社労士には、社労士として登録した人のみが行うことができる独占業務があります。社会保険関係の書類作成や提出代行、就業規則の作成などがこれにあたります。
社労士だけに行うことができる業務があることにより、競合相手の数が限られ、一定の需要を見込めます。そのため、誰でも参入できる一般的な副業と比べて、仕事を獲得しやすい環境にあると言えます。
1-2. 高単価な報酬も見込める
社労士の業務は専門性が高いため、一般的な副業と比べて報酬が高く設定される傾向にあります。
例えば、ライティングを副業として行うとします。社労士という肩書きを持った人が行う案件と、資格を持たない人が行う案件を比較した場合、ライティングの能力が同レベルであれば、基本的には前者の方が高額な案件となりがちです。
さらに、労務相談や就業規則の作成など、専門性の高い業務においては、高額な収入となりやすいです。
このように、高単価な業務を請け負うことで、限られた時間で効率よく収入を得られる可能性があるため、副業に適していると言えます。
1-3. 在宅ワークに適している
社労士の業務は主に書類作成や相談対応などが中心で、これらはパソコンとインターネット環境さえあればどこでも行うことができます。そのため、自宅で手軽に始めることができ、特定のオフィススペースを確保する必要がありません。さらに、一人で完結できる業務が多いことから、自分のペースで作業を進められるのも魅力の1つです。
場所や時間にとらわれず、本業の勤務時間の前後や休日など、自分の都合に合わせて柔軟に業務を進められるため、副業に適していると言えます。
※社労士の年収については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 社労士の年収はどれくらい?稼げる社労士の特徴を解説
2. 社労士の副業スタイル
社労士の副業には、主に次の3つのスタイルがあります。
| ・独占業務での副業 ・コンサルティング業務での副業 ・知識を活かしたその他業務 |
1つずつ詳しく説明をしていきます。
2-1. 独占業務での副業
まず1つめとして、社労士の独占業務分野で副業を展開することです。
2-1-1. 具体的な業務内容
社労士の具体的な独占業務は次の通りです。
◼︎書類作成と提出代行
社会保険に関連する書類の作成と行政機関等への提出を、事業主に代わって行うことができます。従業員が入退社した際の手続きや、育休や産休中の手続きなど、代行できる業務の幅は多岐に渡ります。
中小企業や人事部がない会社の場合、社会保険の手続きに詳しい人が不足していることが多く、社労士の需要が高くなります。
◼︎帳簿書類の作成
労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、就業規則など、法令で定められた帳簿書類の作成を行うことができます。
例えば、就業規則は従業員が10人以上いる場合には作成と届出が義務付けられています。トラブルを防げるような過不足のない就業規則を作るには、労働関係法の専門的な知識が必要となるため、ここでも社労士の役割が重要となります。
※社労士の独占業務については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 社労士の独占業務とは?1号業務・2号業務の詳細と今後の展望を解説
2-1-2. 仕事の見つけ方
社労士の独占業務を活用した副業は、主に以下のような方法で見つけることができます。
◼︎クラウドソーシングサイトの活用
最も手軽に始められる方法であり、自分から業務を提示したり、クライアントが提示する依頼に応募したりすることができます。まずは提示された業務を受注し、実績を積むことが重要です。こうしてサイト内での信頼を高めることで、将来的には自分が提示した業務に対する依頼も増え、選ばれやすくなります。
◼︎人脈の活用
知人や取引先からの紹介、前職の関係者からの依頼などにより案件を獲得できる方法です。社労士の業務は個人情報など重要なデータを扱うことも多いため、信頼関係がある状態で業務の代行をすることが望ましいと言えます。
紹介により獲得した業務の場合、ある程度お互いの素性がわかるため、安心して業務を進めることができます。
2-1-3. 必要なスキル
社労士の独占業務を副業として行う場合には、主に以下のスキルが必要となります。
・最新の法令知識
労働や社会保険に関する法令は細かな法改正が多いため、常に最新の知識が必要です。
・文書作成の注意力
数字を扱う作業や、行政機関への書類作成などを正確に行う必要があります。
2-2. コンサルティング業務での副業
2つめのスタイルは、社労士としてのコンサルティング業務による副業です。
2-2-1. 具体的な業務内容
コンサルティングとは、企業の抱える問題を解決するための立案や業務プロセスの改善提案を行うことを指します。社労士に解決が求められる内容としては、主に以下の内容になります。
◼︎労務相談
従業員の離職や継続雇用などに関する相談に対して、改善案を提示します。
◼︎職場環境改善
ハラスメント対策など、従業員の働きやすい環境作りのための相談や提案を行います。
◼︎人事評価制度や賃金体系の見直し
従業員に不満が募らないよう、適切な人事制度の構築を援助します。
コンサルティング業務は独占業務ではないため社労士でなくても行うことができます。しかし、専門的な知識に基づいて行う必要があるため、社労士資格を持っていることで信頼性が高まり、依頼を得やすくなります。
2-2-2. 仕事の見つけ方
コンサルティング業務を依頼されるためには、労働関係の知識だけでなく、問題解決の経験やお互いの信頼関係が重要になります。短期間で結果が出ることではない課題が多いため、信頼関係がないと途中で関係が悪化したり、提案が実行されないまま終わってしまうなどのリスクがあります。
取引先や知人からの紹介は、すでに一定の信頼関係が構築されているため、仕事を獲得しやすい方法です。それ以外にも、以下のような方法で仕事を見つけることができます。
◼︎オンラインでの情報発信
ブログやSNSを活用して、労務関係の専門知識を発信することで、自身の考え方や人間性を示すことができます。特に、タイムリーな法改正の話題や具体的な事例を紹介することで、依頼をしてみようと感じてもらえるきっかけになります。
◼︎セミナーなどイベントの開催
労働関係のセミナーや無料講座を行うことで、顧客を得られる例もあります。多くの企業にとって需要のありそうな話題を取り上げることで、必要性を感じてもらい、新たな依頼につなげられる可能性があります。
2-2-3. 必要なスキル
コンサルティング業務を行うためには、まず大前提として社労士の知見を活かした問題解決の経験が必要不可欠です。加えて、以下のスキルが求められます。
・営業力
ただ知識や資格があるだけでなく、「信頼できそうだ」「この人に任せたい」と感じてもらえるよう、自分の経験値や価値を効果的に売り込む必要があります。
・傾聴力
相手の話をただ聞くだけでなく、その背景にある本質的な問題を理解し、課題を正確に把握する能力が必要です。
・問題解決力
トラブルに対して原因を的確に分析し、知識や経験に基づいて具体的で実行可能な解決策を提示する能力が求められます。
2-3. 知識を活かしたその他業務
前述した業務のほかにも、社労士を活用してできる副業があります。いくつか例を挙げて説明をしていきます。
2-3-1. 具体的な業務内容
◼︎ブログやオウンドメディアの記事執筆
社労士としての働き方や社労士の知識を活用し、記事の執筆を行います。
◼︎資格試験の講師
社労士試験の合格を目指す人の指導を行うこともできます。社労士試験は独学での合格が難しいと言われる難関資格であり、高度な専門知識と体系的な指導力を持つ講師は非常に重宝されます。
◼︎行政機関でのアルバイト
社労士登録を行うことで、行政機関などから単発の勤務依頼を受けることがあります。専門性を活かして働くことができるため、その後の開業ステップにつながる副業にもなり得ます。
2-3-2. 仕事の見つけ方
記事の執筆は、クラウドソーシングサイトで見つけるのが一般的です。
社労士試験の講師業は、一般的な求人サイトなどで募集がかけられていることや、社労士講座を行っている学校などのHPに募集情報が掲載されているケースが多くあります。
行政機関からの協力は、社労士登録をすることにより社労士会から案内を受け取ることができます。
2-3-3. 必要なスキル
業務の種類によって、必要なスキルが異なります。
・ライティングスキル
記事執筆をする際は、持っている知識をわかりやすくまとめ、読者に伝える文章を作成する能力が必要です。
・指導力
講師業をするのであれば、試験範囲全般にわたる高度で正確な専門知識はもちろんのこと、複雑な法制度や関連知識を生徒が理解しやすいように構造的に整理し、関連付けながら説明する能力が求められます。
また、試験までの限られた時間の中で、生徒が効率的に学習を進められるよう、計画の立て方、復習方法、問題演習の進め方など、具体的な学習方法を指導する能力も必要です。
・コミュニケーション力
行政協力では、主に行政機関の窓口や問い合わせ先で業務を行います。問い合わせに対して、相手の理解度やニーズに応じて、わかりやすく情報を提供することが求められます。
3. 副業を成功させるためのポイント
ここからは、本業と副業を両立するために大切なポイントを3つ説明していきます。
3-1. スケジュール管理をする
副業をする上で最も重要なことは、自分自身のスケジュール管理です。
業務ごとの納期を把握して管理することは当然のことですが、自分が副業に費やせる時間を把握することも非常に重要です。
そのためには、本業とプライベートに必要な時間を確保し、残りの時間から副業に充てられる現実的な時間を見極める必要があります。自分のキャパシティを超えた働き方をすると、副業をしていることが苦しくなり、継続が難しくなるためです。
3-2. 小さく始める
副業を始める際には、まず小規模からスタートすることが大切です。最初から大規模な事業や長期契約に着手してしまうと、うまくいかなかった場合や、途中で方向転換したいと思った際にトラブルが起こりやすくなり、本業にも悪影響を及ぼす可能性があります。
まずは単発の案件を引き受けたり、信頼できる知人からの紹介を受けることで、小さな実績を積むことができます。成功体験を重ねることで、自信がつき、評価も高めていけるため、より大きなスケールでの活動も視野に入れられるようになります。
3-3. 自分に合ったスタイルを考える
副業を長く続けるためには、自分の働きやすいスタイルを見つけることが不可欠です。
社労士を活用した副業は、ここまで説明した通り多岐にわたります。そのため、自分の持っているスキルや適性を見極めて、最適な働き方ができそうな副業を始めることが大切です。これにより、社労士資格を活かしながら、無理なく副業を続けることができます。
さらに、小さく始めることにより、働き方を柔軟に見直すこともできるため、自分に最適なスタイルを見つけやすくなります。
4. 副業を開始する注意点
最後に、副業を開始する上で重要となる3つの注意点をお伝えします。
4-1. トラブルを未然に回避する
副業を始める前に、まず確認すべきは本業の会社における副業規定です。会社によって副業に関する方針は様々ですので、就業規則などで確認し、会社のルールに違反することのないよう注意が必要です。
また、副業を行う中で業務に関するトラブルが発生した場合は、自分で対処しなければなりません。そのため、事前に契約書などによって、業務内容や報酬について詳細に明文化しておくことが重要です。これにより、後々のトラブルを未然に防ぎ、安心して副業に取り組むことができます。
4-2. 社労士会への登録をする
選択する業務によっては、資格を持っているだけでなく、社労士登録が必要となる場合があります。特に、社労士の独占業務である案件を取り扱う場合には、登録をしていないことで法律違反となってしまうため、必ず社労士会へ登録することが必要です。
また、行政協力などの案内を受けるためにも、社労士会への登録が必要となります。
ただし、登録には実務経験など必要な要件があり、手続きには一定の費用と時間がかかるため、計画的に進めることが重要です。
※社労士の独占業務については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 社労士登録は必要?費用や実務経験は? 4つの種別・登録手順をわかりやすく解説
4-3. 税に関する知識を持つ
副業を行う上で、税務に関する基礎知識は不可欠です。
例えば、一般的な会社員の場合、通常は年末調整で所得税が精算されますが、副業収入がある場合は確定申告が必要となることがあります。そのため、確定申告の方法や収入・支出の計上に関する知識を持ち、適切に納税することが求められます。
副業の種類が多岐に渡る場合や、収入が高額になる場合には、手続きが煩雑となる可能性があるため、税務署や税理士に相談をすることも検討する必要があります。
安定した副業を継続する上で、適切な税務手続きを行うことは重要な要素です。
5. 社労士資格で広がる副業の可能性
Q1. なぜ社労士資格は副業に適しているのですか?
A 社労士資格が副業に適している理由は主に3つです。
・独占業務がある
・高単価な副業も見込める
・在宅ワークに適している
Q2. 社労士の副業にはどのようなスタイルがありますか?
A. 主に以下の3つの副業スタイルが挙げられます。
・独占業務での副業
・コンサル業務での副業
・知識を活かしたその他業務(記事執筆、社労士資格試験の講師、行政機関での単発アルバイト)など
Q3. 社労士の副業の仕事はどのように見つけられますか?
A. 副業スタイルによって仕事の見つけ方は異なります。
・独占業務 → クラウドソーシングサイトの活用、知人や取引先、前職関係者からの紹介など
・コンサル業務 → 取引先や知人からの紹介、ブログやSNSでのオンライン情報発信、セミナーや無料講座の開催など
・記事執筆 → クラウドソーシングサイトなど
・試験講師 → 一般的な求人サイトや社労士講座を行う学校のHPなど
・行政機関のアルバイト → 社労士会からの紹介
Q4. 社労士が副業を成功させるためのポイントは何ですか?
A. 本業と副業を両立し、副業を成功させ継続するためには、以下のポイントが大切です。
・スケジュール管理をする
・小さく始める
・自分に合ったスタイルを考える
社労士資格は、これらの多様な副業スタイルに活用できるため、自分の生活スタイルに合わせて柔軟な働き方を選択する上で多くの魅力を持つ資格です。
Q5. 社労士として副業を始める際に注意すべき点はありますか?
A. 副業を開始する上で重要な注意点がいくつかあります。
・本業の会社の副業規定確認
・事前に契約書などで業務内容や報酬を詳細に明文化しておくこと
・社労士会への登録
・税に関する知識
ここまで説明してきた通り、社労士資格は副業として多くの魅力を持つ資格です。
独占業務や労務コンサルティング業務、知識を活かしたその他の業務など、多様な副業スタイルに活用できるため、自分の生活スタイルに合わせて働き方を柔軟に選択することができます。
副業を成功させ、そして継続していくためには、社労士が行う副業の基礎知識を持つことが不可欠です。業務ごとの特徴を理解して、自分に合った働き方を選択することで、副業の可能性を最大限に引き出すことができます。
伊藤塾では、2025年の合格を目指す方々に向けて、2025年合格目標 社労士試験合格講座を開講しています。
自分の理想の働き方を実現するために、ぜひ社労士になるための一歩を踏み出してみてください。伊藤塾が、あなたの夢の実現に向けて全力でサポートいたします。
【社労士】伊藤真塾長×持田裕講師~伊藤塾で「社労士」を目指す意味とは~