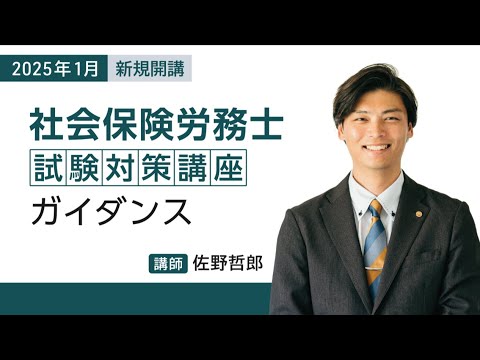社労士は本当に悲惨?やめとけと言われる理由とそれでも目指すべき価値を解説
キャリア
2025年10月21日


社会保険労務士(以下、社労士)資格について、インターネット上では「悲惨」「やめとけ」といったネガティブな評価を目にすることがあります。しかし実際には、社労士資格は現代社会において大きな可能性のある魅力的な資格であるといえます。
確かに、7%程度の低い合格率や、AI化による業務縮小への懸念から、社労士資格取得に不安を感じる声があります。ただし、これは社労士の一面だけを捉えた評価であり、AIで代替できない業務の需要の高まりやキャリアパスの広がり、自己成長の喜びや充実感を得られるなど多くの側面において、社労士は今後も価値のある資格として存続し続けるでしょう。
本記事では、社労士が「悲惨」「やめとけ」と言われる理由を解説したうえで、それを超える価値と可能性について、詳しく説明していきます。
社労士に不安を感じて挑戦を躊躇されている方は、ぜひ最後までご一読のうえ参考にしていただければ幸いです。
【目次】
1. 社労士は「悲惨」「やめとけ」と言われる理由
「社労士は将来が悲惨」「やめとけ」と言われる背景には、主に次の3つの理由があります。
・「社労士=高収入」ではない
・AIの活用により仕事がなくなる懸念がある
・試験合格までの道のりが過酷で挫折しがち
1つずつ、詳しく説明をしていきます。
1-1.「社労士=高収入」ではない
まず1つめとして、「社労士になれば高収入になれる」というイメージと、現実の社労士の年収との間にギャップがあることです。
社労士は国家資格の取得が必要な職業であり、年収が高いイメージがありますが、実際には資格を取得しただけで必ず高収入を得られるわけではありません。
社労士は幅広い働き方ができる資格であり、働き方や経験によって年収は大きく変動します。例えば企業に勤務する社労士の場合、資格を活かした専門性の高い業務ができなければ、一般の人事担当者と変わらない年収にとどまることも少なくありません。
そのため、年収の大幅アップだけを期待して資格を取得した場合、思ったような変化が得られず、社労士資格を取得したことを後悔する結果となり「社労士は悲惨。やめとけ。」などという発言に至った可能性があります。
1-2. AIの活用により仕事がなくなる懸念がある
次に、社労士の将来性について、AIが今後、現在の社労士の業務を代替する可能性があるという懸念があることです。
今まで社労士の主な業務であった給与計算や社会保険の手続きは、AIツールの活用により、専門知識がなくてもある程度は対応できるようになってきました。そのため、今後は社労士の需要が減少するため、将来的に仕事が無くなり、厳しい状況になるのではないかと懸念されています。
このような不安感が「社労士になっても将来が悲惨だ。」と言われる要因の1つと考えられます。
1-3. 試験合格までの道のりが過酷で挫折しがち
3つめの理由として、社労士が難易度の高い資格であり、合格までの道のりが険しいことです。
国家資格である社労士試験の難易度は非常に高く、合格率は例年わずか7%程度です。試験範囲が広く、専門的で幅広い内容を細かく学習しなければならないため、合格をするためには相当な時間と労力が必要です。
仕事や家事との両立をしながら合格を目指す場合、学習時間の確保が難しく、思ったように進められずに挫折してしまう人は少なくありません。
このような背景から、社労士試験に挑戦することに対して「やめとけ」という声も増えているのが現状です。
2. それでも社労士を目指すメリットとは?
しかし、「悲惨」「やめとけ」と言われる理由が存在する一方で、社労士を目指すことには大きな価値があることも明らかです。ここからは、社労士を目指すメリットとして挙げられる、以下の4つの魅力について解説します。
・働き方の幅が広がる
・年収の大幅アップを狙える
・AIでは補えない分野での需要が高まっている
・難関試験への挑戦を通して成長できる
2-1. 働き方の幅が広がる
1つめの魅力として、働き方の幅が広がることです。
社労士というと「開業して働く」というイメージを持つ人も多いですが、副業での展開や、企業内でのキャリアアップなど、開業以外でも自分のキャリアの幅を大きく広げることができる資格です。
具体的な働き方について、簡単に紹介をしていきます。
2-1-1. 独立開業
社労士の働き方として、最もイメージされやすいものが「独立開業」です。
社労士の独立開業の特徴として、初期投資が少ないことや、安定収入が得やすいことが挙げられます。
業務はパソコンとインターネット環境があれば行えるものが多いため、大規模な設備がなくても始めることができます。さらに、顧客とは月額で報酬が発生する顧問契約を結ぶことが一般的なため、安定した収入基盤を築きやすいです。
自身の専門知識を活かし、顧客との信頼関係を築いていけるため、非常にやりがいのある働き方です。
独立開業をするためには「試験合格」と「2年間の実務経験、または事務指定講習の修了」の要件を満たして社労士登録をする必要があります。
※社労士の独立開業については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 社労士は独立すべき?年収1000万も夢じゃない!開業後の実態を解説
※事務指定講習については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 社労士の事務指定講習は働きながら受講できる?落ちる可能性など詳しく解説
2-1-2. 企業内でのキャリアアップ
社労士資格は、企業内でのキャリアアップにも効果的です。
特に人事労務の担当者であれば、資格取得により専門性が証明され、社内での発言力や信頼性が高まりやすくなるため、より重要な業務を任される可能性があります。事務的な手続き以外にも、労務管理やコンプライアンス部門で活躍するチャンスが広がります。
専門性を活かして活躍をすることで、企業内での昇進や新たなポジションへ任命されるなど、キャリアアップの可能性が広がっていきます。
2-1-3. 副業
社労士資格を取得することで、副業の幅を広げることもできます。
副業に活用するために最適な資格の一つとして、社労士は注目されています。
具体的な副業の例としては、記事執筆や行政機関への協力などが挙げられます。さらに、社労士の知識を活用した副業は、一般的な副業と比べて時給単価が高い傾向があることも特徴です。
また、副業での実績を積み重ねることで、将来的な独立開業へのステップとすることもできます。副業からキャリアを発展させられる点も、社労士資格を活用することの魅力の一つと言えます。
※社労士の副業については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 社労士資格を活かした副業とは?仕事内容や成功のポイントを徹底解説
2-2. 年収の大幅アップを狙える
2つめの魅力が、年収が大きく上がる可能性がある点です。
前述した通り、社労士資格を取得しただけで年収が劇的に上がることは期待できませんが、資格を活かしたキャリア形成により、大きな収入アップを実現することが可能です。
例えば、企業の勤務社労士として活躍する場合、労務管理やコンプライアンス強化など、より専門性の高い業務を担当することで、人事労務のスペシャリストとしてのキャリアを築くことができます。
また、独立開業をした場合であれば、自らの営業などにより顧客を増やしたり、付加価値の高いサービスを提供することで、収入増加に直結させることができます。
自分の営業力や専門知識が直接収入に反映されるため、やりがいを持ってキャリアを築いていけます。
※社労士の年収については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 社労士の年収はどれくらい?男女別の年収や稼げる社労士の特徴を解説
2-3. AIでは補えない分野での需要が高まっている
3つめの魅力は、今後、AIでは代替できない分野において活躍の場が広がると予想されている点です。
AIが得意とするのは、定型的な事務作業や明確な答えのある知識・手続きに関する業務などです。一方で、現代の人事労務の業務においては、多様な働き方への対応・ハラスメント対策・メンタルヘルスケアなど、個々の状況に応じた柔軟な取り組みが求められています。
これらの課題を解決するためには、企業と従業員の双方の考えを理解した上で、適切なコミュニケーション方法やトラブル解決策を提案することが求められます。
このような、顧問先の状況に応じた柔軟な解決策やコミュニケーション能力が必要な業務は、現代のAIでは代替が難しく、社労士の需要が今後ますます増していくと考えられます。
2-4. 難関試験への挑戦を通して成長できる
4つめの魅力は、国家試験である社労士試験に挑戦をすることにより、人として大きく成長ができる点です。
社労士試験は、専門分野の幅広い知識を細かく習得する必要があり、その学習には忍耐力や持久力、ストレス管理などが不可欠です。
なぜなら、合格を掴み取るためには「長期間にわたる計画的な学習の継続」「仕事や家事と両立しながら学習時間の確保」「試験日までのモチベーション維持」が不可欠であるためです。
そのため、試験に本気で臨むことで、自己成長ができる大きなきっかけとなります。さらに、試験に合格することで達成感や自己肯定感を得られ、さらなる学習への意欲やより高いキャリアを目指す自信を身につけることができます。
社労士試験に挑戦することにより得られた成長は、その後の人生においても大きな助けとなります。
3. 「社労士は悲惨」を避けるためのポイント
ここまでご説明した通り、社労士資格は決して「悲惨」「やめとけ」と言われるようなものではなく、現代社会において大きな価値と可能性を秘めた資格だといえます。
社労士試験に臨んで後悔をしないためには、大切な3つのポイントがあります。
| ・生き方や働き方のビジョンを持つ ・求められる「社労士像」を知っている ・効率的な学習で合格を目指す |
ポイントについて、1つずつ詳しく説明していきます
3-1. 生き方や働き方のビジョンを持つ
まず1つめに、自分の生き方や働き方の明確なビジョンを持つことです。
社労士になることだけで、人生が突然ガラッと変わることはありません。そのため、「社労士になること」を目的にしてしまうと、社労士になってから何も変化が起こらずに、期待外れだったと考えてしまいがちです。
重要なのは、「なぜ社労士資格が必要なのか」という目的を明確にすることです。
「独立開業して、企業の労務課題を解決したい」
「勤務先で人事制度の改善をしたい」
「人事部門でより専門性の高い業務に携わりたい」
このように具体的な目標を設定することで、資格取得後の進むべき道が明確になり、着実にキャリアを築いていくことができます。
さらに、目標を達成するために必要となるスキルや経験も見えてくるため、計画的な準備が可能になります。
3-2. 求められる「社労士像」を知っている
AI活用の高まりなどにより、これからの社労士の需要は今までとは異なってくることが予想されています。
従来は給与計算や手続きなど、型にはまった業務からこれからは顧問先ごとの臨機応変な対応が必要となる、コンサルティング業務などが重要になると考えられています。
社労士になるためには専門的で幅広い知識が必要ですが、社労士として今後活躍するためには、知識をどのように活用をするかという問題解決能力、相手にわかりやすく伝えられるかといったコミュニケーションスキルも重要になります。
社労士になってから「こんなはずじゃなかった」とならないためには、今の社労士が求められる業務内容や、必要なスキルなどをしっかりと理解しておくことが大切です。
求められる社労士像を理解して資格取得を目指すことで、その後のキャリアもイメージしやすくなるでしょう。
3-3. 効率的な学習で合格を目指す
社労士試験の合格を掴み取るためには、効率的な学習が不可欠です。
社労士試験は合格率が例年わずか7%程度の難関試験であり、合格のためには膨大な試験範囲を攻略する必要があります。
実際に、多くの受験生が「どこから手をつければよいかわからない」「学習方法が間違っていないか不安」といった悩みを抱えており、結果的に挫折してしまうケースも少なくありません。
せっかくの学習時間を有効に活用し、確実に合格へと近づくためには、ただやみくもに勉強を進めるのではなく、試験範囲を体系的に学習し、適切なタイミングで専門家のアドバイスを受けられる学習環境を整えることが重要です。そのような環境で効率的に学習を進めることで、着実に実力を積み上げ、合格への道筋を立てることができます。
4.【Q&A】社労士についてよくある質問
Q1.社労士は年収が低いのですか?
A.社労士の年収は働き方や資格の活用方法によって大きく異なります。
例えば会社勤めの社労士の場合、年収600万円以上の層が全体の40%以上を占める一方で、300万円未満の層も20%程度存在するという統計結果となっています。経験や専門性を活かすことで、雇用される立場でも十分な収入を得られる職種といえます。
(参考:「2024年度 社労士実態調査」調査結果(詳細版))
Q2.社労士は需要がなくなっていますか?
A.いいえ、需要は減少しているのではなく、求められる業務内容が変化しています。
社労士に対して実施された統計によると、「労働及び社会保険に関する相談業務」は70%以上、「各種規程の作成・整備業務」は60%以上が、5年前と比較して需要が増加していると実感しています。
給与計算や助成金申請などの定型業務は減少を感じる人が一定数はいるものの、法改正への対応や労務管理の専門家として、社労士の需要は今後も継続すると考えられます。
Q3.社労士はやりがいのある仕事ですか?
A.はい、社労士は社会にとって重要な役割を果たすことができる、やりがいのある仕事です。
実際、80%以上の社労士が業務に対して「専門性を活かせる」「社会的責任が果たせる」「労働者や企業への貢献を実感できる」と実感しています。
企業と従業員の関係性を円滑にし、職場環境を整えることで社会をより良くする、非常に重要な役割を果たしています。
※こちらの記事も読まれています。
→ 社労士になれば人生変わるって本当?国家資格の専門家として生きる魅力を徹底解説
5. 社労士は本当に悲惨?やめておくべき職業なのか?
社労士は「悲惨」「やめとけ」と言われることがありますが、実際には大きな可能性を秘めた魅力的な資格です。
確かに、試験合格までの道のりは険しく、資格取得後も成功を収めるためには相応の努力が必要です。そのため、ネガティブな印象を持たれることもありますが、明確な目標を持ち、適切な準備をすることで、社労士資格は人生を豊かに変える大きなきっかけとなり得ます。
自身のキャリアビジョンを明確にし、現代社会で求められる社労士像を理解した上で、効率的な学習計画を立てることで、「悲惨」ではなく、むしろ「素晴らしい」キャリアの第一歩を踏み出すことができます。
伊藤塾では、試験対策に精通した講師陣による指導を通じて、要点を押さえた効果的な学習をご提供しています。
現在、2025年の合格を目指して、2025年合格目標 社労士試験合格講座を開講中です。
社労士試験に合格して人生を変える挑戦に臨みたい方は、ぜひ一歩を踏み出してみてください。伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。
【社労士】伊藤真塾長×持田裕講師~伊藤塾で「社労士」を目指す意味とは~