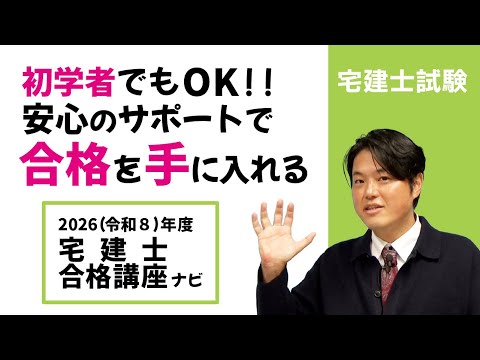宅建の合格点は何点必要?過去10年の推移からみる目標点数を解説
基本情報
2026年01月08日


「宅建士試験って、結局何点取れば合格できるの?」
「35点が目安って聞いたけど、本当にそれで大丈夫?」
「過去の合格点はどう推移しているの?」
まず結論からお伝えすると、宅建士試験に確実に合格するには38点以上が必要です。
かつては「35点あれば合格できる」と言われていましたが、現在の宅建士試験は以前よりも明らかに難化しています。受験生のレベルも上がっており、合格点36点以上が3年連続で続いた時期もありました。
この記事では、過去10年間(※)の合格点データをもとに「確実に合格するために必要な点数」を徹底解説します。点数別の合格可能性、科目別の目標点数、そして38点以上を取るための勉強法まで、合格に必要な情報をすべてまとめました。
(※直近10年度は、令和2・3年度が2回実施のため「計12回」で集計しています。)
目標点数を明確にして、戦略的に合格を勝ち取りたい人はぜひご一読ください。
【目次】
1. 宅建士試験に確実に合格するには「38点」が必要
まず結論からお伝えすると、宅建士試験合格の安全圏の目安は「38点/50点」以上です。
得点率でいえば、およそ8割になります。
以下では、過去のデータから点数別の合格可能性を見ていきます。
1-1.「35点」で合格点に達する可能性は五分五分
かつては、「宅建士試験は35点あれば合格できる」と言われていました。
しかし、近年は受験者全体のレベルが上がっており、同じ難易度の問題でも合格点が以前より高くなる傾向があります。
直近10年間の宅建士試験でいえば、「35点」で合格できた試験は12回中6回しかありません。そのため、35点を目標に置くより、もう一段上の得点を狙う設計にしておくのが安全です。以下は、過去10年間の合格点をもとに、得点が「35点」だった場合の合否をまとめたデータです。
| 年度 | 合格点 | 合否 |
| 令和7年度 | 33点 | 合格 |
| 令和6年度 | 37点 | 不合格 |
| 令和5年度 | 36点 | 不合格 |
| 令和4年度 | 36点 | 不合格 |
| 令和3年度 (12月) | 34点 | 合格 |
| 令和3年度 (10月) | 34点 | 合格 |
| 令和2年度 (12月) | 36点 | 不合格 |
| 令和2年度 (10月) | 38点 | 不合格 |
| 令和元年度 | 35点 | 合格 |
| 平成30年度 | 37点 | 不合格 |
| 平成29年度 | 35点 | 合格 |
| 平成28年度 | 35点 | 合格 |
| 合格可能性 | 50%(12回中6回) | |
※令和2年度・3年度は感染症拡大防止のため2回に分けて実施
出典:(一財)不動産適正取引推進機構|試験実施概況(過去10年間)
なお、令和7年度の合格点は33点と過去10年間で最低でしたが、これは問題の難易度が高かったためであり、「令和7年度が受かりやすい試験だった」というわけではありません。
※こちらの記事も読まれています。
1-2.「36点〜37点」あれば合格点に達する可能性は高い
下記表は、過去10年間の合格点と、それぞれの年で得点が36点の場合と37点の場合の合否をまとめたものです。
36点〜37点の得点があれば、宅建士試験に合格できる可能性はかなり高まることがわかります。
ただし、最近は36点でも合格点ギリギリになる年が多く、年によっては37点でも不合格になることもあります。確実に合格するなら、もう少し余裕が欲しいところです。
| 年度 | 合格点 | 36点 | 37点 |
| 令和7年度 | 33点 | 合格 | 合格 |
| 令和6年度 | 37点 | 不合格 | 合格 |
| 令和5年度 | 36点 | 合格 | 合格 |
| 令和4年度 | 36点 | 合格 | 合格 |
| 令和3年度 (12月) | 34点 | 合格 | 合格 |
| 令和3年度 (10月) | 34点 | 合格 | 合格 |
| 令和2年度 (12月) | 36点 | 合格 | 合格 |
| 令和2年度 (10月) | 38点 | 不合格 | 不合格 |
| 令和元年度 | 35点 | 合格 | 合格 |
| 平成30年度 | 37点 | 不合格 | 合格 |
| 平成29年度 | 35点 | 合格 | 合格 |
| 平成28年度 | 35点 | 合格 | 合格 |
| 合格可能性 | 83% (12回中8回) | 91% (12回中11回) | |
1-3.「38点」あればほぼ確実に合格点に達する
直近10年間に限れば、「38点」であれば確実に合格できています。
ただ、今後どうなるかは分からないため、合格点の目標としては、「80%(40点)」を念頭に勉強するとよいでしょう。
目標とするのはあくまでも「本試験で80%」取れる実力です。「過去問が8割できれば良い」というわけではありません。
「解いたことがある問題なら全問正解できる」レベルまで仕上げることで、初めて本番で40点が現実的になります。
2. 宅建士試験の合格点・合格率の過去10年間の推移
次に、宅建士試験の合格点・合格率について、過去10年間の推移を見ていきます。
【過去10年間の合格点の推移】
| 年度 | 合格点 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 |
| 令和7年度 | 33点 (最低点) | 18.7% | 245,462 | 45,821 |
| 令和6年度 | 37点 | 18.6% | 241,436 | 44,992 |
| 令和5年度 | 36点 | 17.2% | 233,276 | 40,025 |
| 令和4年度 | 36点 | 17.0% | 226,048 | 38,525 |
| 令和3年度 (12月) | 34点 | 15.6% | 24,965 | 3,892 |
| 令和3年度 (10月) | 34点 | 17.9% | 209,749 | 37,579 |
| 令和2年度 (12月) | 36点 | 13.1% | 35,261 | 4,610 |
| 令和2年度 (10月) | 38点 (最高点) | 17.6% | 168,989 | 29,728 |
| 令和元年度 | 35点 | 17.0% | 220,797 | 37,481 |
| 平成30年度 | 37点 | 15.6% | 213,993 | 33,360 |
| 平成29年度 | 35点 | 15.6% | 209,354 | 32,644 |
| 平成28年度 | 35点 | 15.4% | 198,463 | 30,589 |
| 平均合格点 | 35.5点 | |||
2-1. 合格点の最高は「38点」
直近10年間で、合格点が最も高かったのは、令和2年度(10月)試験です。
合格には「38点」が必要で、前年より「3点」も高い点数でした。
当時の宅建士試験では、35点〜36点あれば、高確率で合格できると言われていたため、多くの受験生が涙を飲むことになりました。
2-2. 合格点の最低は「33点」
一方で、合格点が最も低かったのは令和7年度試験で、33点でした。この年の合格率は18.7%と、直近10年間の中でも高めの水準となりました。なお、さらに遡ると平成27年度には31点で合格できた年もあります。
もっとも、合格点は年度によって大きく変動するため、低い年を基準に目標を設定するのは危険です。どんな年でも確実に合格できる38点以上を目指しましょう。
2-3. 合格点の平均は「35.5点」
過去10年間の合格点の平均は「35.5点」です。
年による変動が大きいため「35点」で合格できない年も多いです。
3. 科目別の目標点数と対策のポイント
宅建士試験で38点以上を取るには、科目ごとにメリハリをつけた学習が必要です。
すべての科目を満遍なく勉強するのではなく、得点しやすい科目で確実に点を稼ぐイメージで進めていきましょう。
以下では、科目別の目標点数を見ていきます。
| 科目 | 配点 | 目標の得点 | 目標の得点率 |
| 宅建業法 | 20点 | 16点以上 | 80% |
| 権利関係 | 14点 | 10点〜11点 | 70%〜80% |
| 法令上の制限 | 8点 | 5点以上 | 60%以上 |
| 税・その他 | 8点 | 5点〜6点 | 60%〜75% |
| 全体 | 50点 | 38点以上 | 76%以上 |
3-1. 宅建業法の目標点数は「16点以上/20点」
宅建業法では、最低でも16点、できればそれ以上の得点を目指しましょう。
例年20問が出題され、配点は全体の4割を占めています。宅建士試験において最大の得点源となる科目であり、ここで点を落とすと合格は厳しくなります。
近年は、「正しいものはいくつあるか」という個数問題が「11問/20問」出題されるなど、難化傾向にあります。すべての選択肢の正誤を正確に判断できる力が必要なため、一問一答形式での演習も効果的です。
また、35条書面(重要事項説明)と37条書面(契約書面)の共通点・相違点など、横断的な知識の整理も合否を分けるポイントになります。
※宅建業法の勉強法は、以下の記事で詳しく解説しています。
3-2. 権利関係の目標点数は「10〜11点以上/14点」
権利関係では10点〜11点を目標にしましょう。14問出題されるため、約70〜80%の正答率が必要です。難しい年でも最低9点は死守したいところです。
民法を中心に出題され、受験生の間で最も差がつく科目と言われています。
攻略のポイントは、丸暗記に頼らず「なぜそのルールがあるのか」という制度趣旨を理解することです。具体的な事例をイメージしながら、条文を当てはめる訓練を繰り返しましょう。
借地借家法、区分所有法、不動産登記法は比較的得点しやすい分野です。深入りしすぎず、基本事項を確実に押さえることを優先しましょう。
※権利関係の勉強法は、以下の記事で詳しく解説しています。
3-3. 法令上の制限の目標点数は「5点以上/8点」
法令上の制限では5点以上を目標に対策を進めましょう。8問出題されるため、約60%以上の正答率が目安です。
都市計画法や建築基準法など、用語の定義や具体的な数字を正確に覚える必要がある暗記科目です。近年は難易度がやや高めの傾向にあるため、まずは5点を確実に取ることを優先しましょう。
学習時間が限られている場合は、範囲が広い建築基準法よりも、都市計画法や農地法など他の分野を優先的に仕上げる戦略も有効です。各規制の目的や趣旨をつかんでおくと、記憶が定着しやすくなります。
※法令上の制限の勉強法は、以下の記事で詳しく解説しています。
3-4. 税・その他の目標点数は「5〜6点以上/8点」
税・その他の分野では5点〜6点を目指しましょう。8問出題され、約60〜75%の正答率が目標です。
固定資産税や不動産取得税などの税制、地価公示法、不動産鑑定評価基準など、幅広い分野から出題されます。税金の問題は「自分が不動産を取得・保有・売却する当事者になったら」という視点で考えると理解しやすくなります。
免除科目は過去問からの出題も多く、比較的パターンが決まっています。直前期にしっかり対策すれば得点源にしやすい分野です。
※税・その他の勉強法は、以下の記事で詳しく解説しています。
4. 宅建士試験の合格点は高すぎる?難しくなった?
「宅建士試験は難しくなった」という声を聞くことがありますが、これはそのとおりです。間違いなく以前よりも難しくなっています。
たとえば、令和7年度試験では「正しいものはいくつあるか」を問う個数問題が増え、宅建業法では20問中11問がこの形式でした。すべての選択肢を正確に判断する必要があるため、丸暗記では対応できません。同様に、過去問演習を繰り返すだけでは太刀打ちできないような、思考力を問われる問題も増えています。
本格的な法律系国家試験としての側面が強まり、「実務家として法律を使いこなせるか」が問われるようになったと言えるでしょう。
ただし、それでも合格点が高すぎるとまでは言えません。合格率は15〜18%の間で安定しており、試験が難しくなっても一定の割合で合格者が出る構造は変わっていないからです。正しい対策をした人は、ちゃんと受かっています。
試験が難しくなっても、基本的な問題を確実に取ることが合格の鉄則であることに変わりはありません。基本を固め、制度の趣旨を理解する学習を積み重ねれば、合格は十分に可能です。
5. 難化する宅建士試験で合格点を取るには?最新の傾向を踏まえた3つのアドバイス
前章では、宅建士試験は難しくなっているものの、正しい対策をすれば合格できるとお伝えしました。では、「正しい対策」とは具体的に何でしょうか。
ここからは、合格のための3つのポイントをお伝えします。
- 問題に優先度をつけて、メリハリのある勉強をする
- 知識をバラバラに覚えるのではなく、整理して「体系化」する
- モチベーションに頼るのではなく、学習を「習慣化」する
それぞれ詳しく見ていきます。
5-1. 問題に優先度をつけて、メリハリのある勉強をしよう
宅建士試験は満点を目指す必要はありません。問題に優先度をつけ、メリハリのある学習をすることが合格への近道です。
問題は重要度に応じて「A・B・Cランク」に分類できます。Aランクは合格者なら必ず正解する基本問題、Bランクは合格者でも正解率が5〜6割の問題で、ここでの得点力が合否を分けます。Cランクは難問やマイナーなテーマで、正解できなくても合否に直接影響しません。
例年の傾向では、Aランク問題を確実に得点し、Bランクで半分以上取れれば合格ラインに届きます。特に時間がない場合は、出題頻度の低いテーマには手をつけず、A・Bランクの重要テーマに集中しましょう。
※独学の勉強法について以下の記事で詳しく解説しています。
5-2. 知識をバラバラに覚えるのではなく、整理して「体系化」しよう
近年の宅建士試験では、単なる暗記では対応できない問題が増えています。こういった問題に対応するには、知識を「思い出せる形」に整理して体系化することが大切です。
ポイントは、「なぜそのルールがあるのか」を理解することです。
たとえば、35条書面と37条書面は混同しやすい論点です。しかし、35条書面は「契約前にお客さんが判断するための材料」、37条書面は「契約後に合意内容を確定させる証拠」という役割の違いがあります。こういった役割の違いを理解すれば、なぜその項目が必要なのかも自然と見えてきます。
このように「なぜ?」から考える習慣をつけると、知識が体系的につながり、記憶にも定着します。
※初心者の勉強法について以下の記事で詳しく解説しています。
5-3. モチベーションに頼るのではなく、学習を「習慣化」しよう
「やる気が出たら勉強しよう」では、合格は難しいです。やる気は日によって変動するからです。モチベーションに頼るのではなく、学習を「習慣」にまで落とし込むことが大切です。
やる気が起きない日でも、まずは「たった5分だけ」机に向かう、あるいはテキストを開くことから始めてみましょう。5分でも始めれば脳が切り替わり、自然と10分、30分と続けられるようになります。
以上、合格に必要な3つのポイントをお伝えしました。この3つを意識すれば、合格にぐっと近づきます。
ただ、「どの問題がAランクなのか」「どうやって体系化すればいいのか」「一人で習慣を続けられるか不安」という方もいるかもしれません。
次章では、そんな方がタイパ・コスパ良く確実に合格するための選択肢として、当コラムを運営する伊藤塾の「宅建士合格講座」を紹介します。
6. タイパ・コスパよく楽しく確実に合格するなら伊藤塾がおすすめ
ここまで読んで、
- 「制度趣旨を理解する勉強が大切なのはわかったけど、独学でできるか不安」
- 「A・B・Cランクの見分け方がわからない」
- 「忙しくて、まとまった勉強時間が取れない」
と感じた方もいるかもしれません。
そんな方には、法律資格専門の指導校である伊藤塾の「宅建士合格講座」がおすすめです。
6-1.「丸暗記」からの脱却。「なぜ?」がわかるから、忘れない。
5章でお伝えしたとおり、近年の宅建士試験は丸暗記では対応できません。「なぜそのルールがあるのか」を理解する勉強が必要です。
伊藤塾は司法試験など法律資格で圧倒的な実績を持ち、「法的思考力(リーガルマインド)」を育てることを重視しています。
- 「なぜそうなるのか?」を徹底解説
難しい法律用語を並べるのではなく、制度の趣旨や理由を丁寧に解説。「理由」がわかるから記憶に定着し、見たことのない問題が出ても現場で考え抜く力が身につきます。
- 「権利関係」に全講義の約半分を投入
多くの受験生が挫折する「権利関係」に、講義時間の約50%を割いています。この分野を得意にすることで、合否を分ける勝負所で圧倒的なアドバンテージを得られます。
6-2. 忙しいあなたに最適化された「30分完結」カリキュラム
「勉強する時間がない」という悩みは不要です。スキマ時間を徹底活用できる工夫が凝らされています。
- 1コマ30分の集中講義
講義は原則30分で区切られています。通勤中や昼休みなど、細切れの時間で着実に学習を進められます。2倍速機能を使えば、1コマわずか15分。復習の際もスムーズです。
- インプット即アウトプットの黄金サイクル
講義直後に「一問一答」で確認し、一通り学んだら「四肢択一」で実戦練習。このサイクルがカリキュラムに組み込まれているため、迷わず最短距離を走れます。
6-3. 「合格に必要なこと」だけに絞り込んだ教材
範囲が広い宅建士試験において、満点を目指す勉強は非効率です。伊藤塾は「合格点+α」を確実にとる戦略をとっています。
- 無駄を削ぎ落としたオリジナルテキスト
出題頻度が低いマニアックな知識はカット。逆によく出る重要ポイントは徹底的に厚く。メリハリの効いたテキストが、あなたの学習時間を無駄にしません。
- 本番想定の模試
予想問題: 本試験と同じ形式の模試が含まれており、知識の抜け漏れチェックはもちろん、本番での時間配分(2時間で解き切る力)も養えます。
6-4. 独学にはない「安心」のフォロー制度
通信講座でも、あなたは一人ではありません。
- 質問制度・カウンセリング
学習内容の疑問点はマイページから質問可能。さらに、講師や合格者スタッフによるカウンセリングもあり、学習計画の悩みや不安をすぐに解消できます。
- 学習のペースメーカー
Web講義は適切なタイミングで配信されるため、教室に通っているような感覚で、遅れることなく学習ペースを維持できます。
6-5. 合格に必要なすべてが入って、受講料は「39,800円」
初学者にも分かりやすい条文ベースのオリジナルテキスト&講義に加え、厳選した過去問題集、模擬試験、さらにスキマ時間でサッと使える学習アプリや万全のサポート体制も含めて、受講料は 「39,800円」です。
独学では学びきれない「なぜ?」を解決する 全てのツールがセットになっているので 事前準備不要、安心して学習を始めることができます。
法律初学者の方も、学習経験者の方も、伊藤塾の「宅建士合格講座」で楽しく学んで、タイパよくコスパよく合格を手にしてみませんか?
7.【Q&A】宅建士試験の合格点についてのよくある質問
Q. 宅建士試験の合格点はいつ分かりますか?
A. 宅建士試験の合格点は、合格発表日に「不動産適正取引推進機構」のHPに掲載されます。
ただし、正式発表の前に、報道機関などが正式発表に先んじて合格点を発表するのが例年の流れです(合格発表日の深夜0時頃)。
正式発表まで待てない方は、深夜0時以降にニュースサイトなどを確認してみてください。
Q. 過去問だけで合格点に達するのは可能ですか?
A. 過去問だけで合格したという話は一定数聞こえてきます。しかし、過去問演習だけで、テキストを一切使わずに合格したというケースは極めて稀です。
ほとんどの人は、テキスト等を活用して、しっかりと知識をインプットしながら、過去問に取り組んでいます。インプットとアウトプットのバランスや、学習の手順などに自信のない方は、受験指導校の「合格のために考え尽くされた効率的なカリキュラム」を活用されるとよいでしょう。
Q. 宅建士試験の合格点はどのように決めるのですか?
A. 宅建士試験の合格点(合格基準点)の決め方は、公表されていません。
ただし、合格率が「15%〜17%」の間で安定的に推移していることを踏まえると、一定の調整がなされている可能性が高いでしょう。
例えば、次のような影響を受けていることが考えられます。
・問題の難易度
・受験者の数
・受験者の平均点
・社会の情勢(宅建士を増やしたいのか、減らしたいのか)
基準が公表されていない以上、正確なところは分かりません。必要以上に合格点の決まり方を気にするのではなく、確実に合格できる点数を取れるように試験対策を行いましょう。
Q. 宅建士試験の勉強は何月から始めたらいいですか?
確実に合格を目指すなら、試験が行われる年の1月から開始するのが理想です。
ただし、短期集中型の人であれば、約3ヶ月前(7月頃)から勉強を開始して、その年の試験に受かるケースもあります。
試験の勉強は、思い立ったときが始めどきです。早すぎる・遅すぎるということはありません。まずは一歩を踏み出してみましょう。
8. 過去の推移から分析!宅建士試験の合格点 まとめ
本記事では、宅建士試験において確実に合格を勝ち取るための目標点数や学習戦略について解説してきました。
以下にポイントをまとめます。
- 現在の宅建士試験に確実に合格するには、38点以上(得点率約8割)を目指す必要があります。
- 過去10年間の合格点の推移を見ると、かつて目安とされていた「35点」での合格可能性は50%(6回/12回)に留まっており、受験生レベルの向上や試験の難化を考慮すると、35点を目標にするのは避けるべきです。
- 直近の令和7年度試験は合格点が33点と過去10年で最低でしたが、これは難易度が非常に高かったためであり、決して「受かりやすい試験」になったわけではありません。
- 科目別の戦略として、最大の得点源である「宅建業法」で16点以上、受験生の間で差がつく「権利関係」で10点〜11点を確実に得点することが宅建士試験合格への近道です。
- 単なる丸暗記ではなく、「なぜそのルールがあるのか」という制度趣旨(リーガルマインド)を理解することで、難化する本試験に対応できる応用力が身につきます。
- Aランクの問題(合格者なら必ず正解する基本問題)・Bランクの問題(合格者でも正解率が5〜6割の問題)を優先度高く集中して学習し、日々の勉強を習慣化することが、目標点数に到達するための鉄則です。
「独学で制度趣旨を理解できるか不安」
「仕事と両立しながら効率よく学びたい」
と感じている方は、ぜひ 伊藤塾の「宅建士合格講座」をご検討ください。
伊藤塾では、多くの受験生が苦手とする「権利関係」に講義時間の約半分を割き、「なぜ?」がわかる丁寧な解説で、初見の問題にも対応できる真の実力を養います。
1コマ30分の集中講義はスキマ時間の学習に最適で、インプット即アウトプットの黄金サイクルで回せるよう設計されています。
受講料は、オリジナルテキスト、問題集、模試、アプリ、万全のサポート体制がすべて揃って39,800円。
令和8年度宅建士試験での確実な合格を目指し、法律資格で圧倒的な実績を誇る伊藤塾で、効率的かつ楽しく学習をスタートさせましょう。
伊藤塾があなたのチャレンジを力強くサポートさせていただきます。