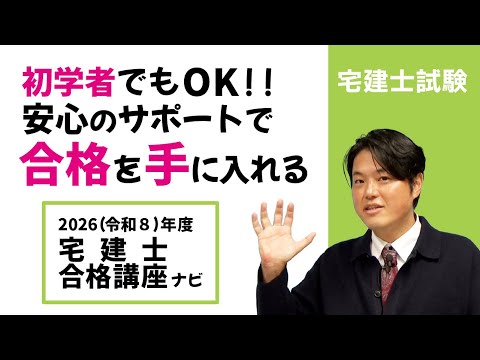宅建に落ちる人の特徴は?合格のポイントや試験本番で得点するコツを解説
基本情報
2025年11月04日


宅建士試験は毎年20万人以上が受験する人気国家資格ですが、合格率はわずか15〜18%前後に留まります。真面目に勉強していても結果が出ない人も多く、「自分には向いていないのか」と不安を感じるケースも少なくありません。
しかし、宅建士試験に落ちるのは努力不足というより、勉強法や試験対策の方向性が間違っているケースがほとんどです。正しい方法での勉強を継続できれば、本試験でどんな問題が出題されても必ず合格を掴み取ることができます。
この記事では、宅建に落ちる人の共通点を具体的に紹介し、合格を掴むための正しい学習法や本番で得点するコツを解説します。これから合格を目指す方や来年こそ合格したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
【目次】
1. 宅建士試験に落ちるのは恥ずかしいことではない
令和6年度(2024年度)に実施された宅建士試験の合格率は18.64%でした。つまり、受験者の約8割が不合格となったわけです。宅建士試験は決して簡単な試験ではなく、多くの人が一度や二度の失敗を経て合格を掴んでいるのが現実です。
試験の難しさの背景には、出題範囲の広さと出題形式の多様化があります。権利関係(民法、不動産登記法など)・法令上の制限(建築基準法、都市計画法など)・宅建業法・税その他の各分野を横断的に学ぶ必要があり、単なる暗記だけでは対応できません。
また、2025年(令和7年)の本試験ではいわゆる「個数問題」が例年よりも多く出題されました。個数問題とは、「正しいものはいくつか」「誤っているものはいくつか」と問う形式で、すべての選択肢を正確に判断しなければなりません。選択肢のうち1つの知識が曖昧だと失点につながるため、理解の深さや判断力がより重視される出題傾向となりました。
このように、試験傾向の変化や出題レベルの上昇も、不合格者が多い要因の一つです。しかし、不合格だったからといって実力がなかったわけではありません。宅建士試験は、正しい方向で努力を続ければ誰でも合格を狙える試験です。
落ちたという事実を恥じる必要はありません。むしろ、今回の経験を踏まえて勉強法を改善すれば、次こそ確実に合格を掴めるはずです。
※こちらも読まれています。
2. 宅建に落ちる人の特徴
宅建士試験は努力すれば誰でも合格できる試験ですが、勉強の方向性を誤ると得点につながりません。
ここでは、実際に不合格になった受験生によく見られる特徴をご紹介します。
1.勉強時間が足りていない
2.落ちるわけないと試験を舐めている
3.アウトプットを重視せずに勉強を進めている
4.試験に出題されにくい問題にフォーカスしすぎている
5.本試験でのペース配分を意識していない
6.複数の教材に手を出し1冊を完璧にできない
それぞれ詳しく解説していきますので、自分に当てはまる点がないか確認しながら、勉強法改善のヒントを掴みましょう。
2-1. 勉強時間が足りていない
法律系の国家資格である宅建士試験は、合格までにおおよそ300〜500時間程度の学習が必要だと言われています。
不合格者の多くは、勉強時間を「確保したつもり」で実際にはインプット中心になり、復習や演習の時間を取れていないケースが目立ちます。
少なくとも本試験の6か月前には学習をスタートし、平日は1〜2時間、休日は3〜4時間程度をコンスタントに積み上げていくことが理想です。勉強時間が不足していると、試験本番で「見たことがあるけれど正確に思い出せない」という場面が多発します。
量をこなすこと自体が目的ではありませんが、一定の学習量を確保しなければ、得点力は安定しません。まずは生活の中に「毎日勉強する習慣」を作ることが、合格への第一歩です。
※宅建士試験の合格に必要な勉強時間については、こちらの記事で詳しく解説しています。
2-2. 落ちるわけないと試験を舐めている
宅建士試験は、誰でも受験できる国家資格ということもあり、「少し勉強すれば受かるだろう」と軽く考える人が少なくありません。特に多いのが、「仕事で不動産に関わっているから知識はある」「短期間で暗記すれば大丈夫」と考えて勉強を後回しにするパターンです。
宅建士試験では、多岐に渡る法律から細かい制度の内容や数字などが問われます。そのため、知識をなんとなく理解している程度では得点に繋がりにくく、実務経験があっても試験対策を怠ると得点が伸びません。
また、2025年(令和7年)の本試験では個数問題が大幅に増えたこともあり、曖昧な記憶では得点できない出題が目立ちました。こうした形式の問題は、「正しい知識に基づく根拠をもって判断できるか」が問われるため、思い込みや経験則だけで解こうとすると失点しやすい傾向にあります。
2-3. アウトプットを重視せずに勉強を進めている
宅建士試験は、過去問演習を繰り返す中で「出題パターン」を把握することが極めて重要です。
アウトプット(問題演習)を通じて、知識を定着させることこそが得点力につながる勉強法です。
「テキストを読む」「講義を視聴する」といったインプット中心の勉強だけでは合格に届きません。
一見理解したように感じても、実際に問題を解こうとすると手が止まってしまう ── これは、知識を「使う練習」が足りていないことが原因です。
具体的には、過去5年分の過去問を繰り返し解くことを優先しましょう。
ただ答えを覚えるのではなく、「なぜこの選択肢が誤りなのか」「他の問題とどこが違うのか」を自分の言葉で説明できるようになることが大切です。こうした思考の積み重ねによって、出題パターンの変化にも柔軟に対応できるようになります。
また、間違えた問題は放置せず、「間違いノート」や「弱点リスト」にまとめて定期的に復習すると、知識の抜けを効果的に埋められます。
※こちらも読まれています。
2-4. 試験に出題されにくい問題にフォーカスしすぎている
宅建士試験は出題範囲が広いため、すべてを完璧に覚えようとすると時間が足りません。にもかかわらず、「他の受験生と差をつけたい」「細かい部分まで理解しておきたい」と考え、出題頻度の低い論点に時間をかけすぎてしまう人がいます。
しかし、宅建士試験は毎年似たテーマが繰り返し出題される傾向があり、マイナー論点の勉強に力を入れても得点には繋がりにくいのが現実です。例えば、権利関係では難解な民法の細部や例外規定にこだわるより、相続や不動産登記法、借地借家法などの基本分野を確実に押さえるほうが効果的です。
限られた勉強時間を有効に使うには、「出題の可能性が高い分野を確実に押さえる」という発想が不可欠です。まずは過去問分析や出題頻度表を確認し、得点に直結する問題から優先的に取り組みましょう。
2-5. 本試験でのペース配分を意識していない
宅建士試験は全50問を2時間で解答するため、時間配分のミスが合否を左右します。実力があっても、1問に時間をかけすぎて後半が手つかずになるケースは少なくありません。特に権利関係の長文問題に時間を使いすぎると、後半の宅建業法や法令制限の得点源を取り逃がすことになります。
普段の過去問演習や模試の段階から、本番と同じ時間制限で解く習慣をつけておくと、焦らず安定したペースで進められるようになります。
また、本番では「分からない問題は一旦飛ばす」判断も重要です。難問に固執して時間を浪費するより、解ける問題を確実に取る戦略が結果的に高得点につながります。
2-6. 複数の教材に手を出し1冊を完璧にできない
宅建士試験で伸び悩む人の多くが陥るのが、複数の教材に手を出してしまうことです。
「このテキストのほうが分かりやすそう」「この問題集も解いておいたほうが安心」と思い、次々と買い足してしまうと、学習の軸がぶれてしまいます。教材を変えるたびに内容や表現が微妙に異なるため、知識が整理できず、結果的にどれも中途半端な理解で終わってしまう可能性が高いのです。
宅建士試験の合格に必要なのは、数多くの教材に目を通すことではなく、1冊を完璧に仕上げる集中力と反復です。1冊のテキストを繰り返し読み、同じ過去問を何度も解き直すことで、知識が定着し「出題パターン」が自然と見えてきます。
理解が曖昧な箇所があれば、その都度テキストに戻って確認し、重要ポイントにはマーカーやメモを残して「自分仕様の1冊」に仕上げていきましょう。
次々と新しい教材に頼るより、手元の教材を信じてやり抜く方が、結果的に合格への最短ルートとなるのです。
3. 宅建合格に必要な正しい勉強法
宅建士試験に合格するためには、闇雲に長時間勉強することよりも「正しい方法で学ぶ」ことの方が重要です。
出題範囲が広いため、効率の悪い勉強を続けてしまうと、どれだけ時間をかけても合格点に届きません。
ここでは、合格者が共通して実践している5つの勉強法を紹介します。
1.各科目で目標点を決める
2.出題可能性の高い分野を重点的に学習する
3.過去問メインの勉強に切り替える
4.理解を伴った暗記を意識する
5.スケジュール管理とモチベーションの維持を徹底する
3-1. 各科目で目標点を決める
宅建士試験は、宅建業法(20問)・権利関係(14問)・法令制限(8問)・税・その他(8問)の4分野から構成されています。合格を狙うためには、「すべてで高得点を取る」のではなく、科目ごとの目標点を明確にする戦略が欠かせません。
目標点は人によって異なりますが、宅建業法で8割〜9割の得点を確保し、その他の分野でそれぞれ6〜7割程度の得点を目指すのがお勧めです。宅建業法は暗記中心で得点しやすく、権利関係は理解力を問う難問が多いため、得点配分に強弱をつけるのが効果的です。
このように「どこで確実に点を取るか」を明確にしておくことで、限られた時間を効率的に使えるようになります。
※こちらも読まれています。
3-2. 出題可能性の高い分野を重点的に学習する
宅建士試験では、すべての分野を完璧に仕上げることは現実的ではありません。限られた勉強時間の中で合格を目指すには、出題可能性の高い分野を中心に学習する戦略が欠かせません。
過去の出題傾向を分析すると、毎年のように繰り返し問われるテーマがはっきりしています。
例えば、宅建業法では「免許制度」「重要事項説明(35条書面)」「37条書面」「報酬額の上限」などが定番論点です。
こうしたテーマは、出題頻度が高いだけでなく、得点しやすい分野でもあります。まずはこれらを確実に正答できるレベルに仕上げることが、合格の土台になります。反対に、出題頻度が低い細かい判例やマイナー条文に時間をかけすぎるのは非効率です。
出題傾向を正しく見極め、学習の優先順位をつけることが、最短で合格点に届く最大のポイントです。
3-3. 過去問メインの勉強に切り替える
宅建士試験の最も効果的な学習法は、過去問を中心に学ぶことです。
宅建士試験は毎年出題傾向に大きな変化がなく、過去問を分析することで「よく出るテーマ」「出題パターン」「ひっかけ問題の特徴」が把握できます。つまり、過去問を制することが合格への最短ルートです。
最初の段階では、答えを覚えることよりも「なぜ正しいのか、なぜ間違いなのか」を理解することが重要です。2回目以降は、間違えた問題を重点的に復習し、選択肢の根拠を説明できるようにしましょう。さらに、同じ問題を3回以上繰り返すことで、知識が定着し応用力も身につきます。
また、問題を解く際は本試験と同じ時間配分(1問2分程度)を意識することも効果的です。制限時間内で解く練習を重ねると、実戦力が鍛えられます。
3-4. 理解を伴った暗記を意識する
宅建士試験は、単純な丸暗記では対応できない問題が増えています。数字や条文を覚えることも必要ですが、なぜその規定があるのか、どんな意図で作られたのかを理解しておくことで、応用問題にも対応できるようになります。
例えば、宅建業法は専門的知識の乏しい消費者を守るための法律です。その点を意識しておくと、重要事項説明(38条書面)や37条書面の記載事項、自ら売主制限などに関する規制内容も頭に入りやすくなります。
暗記を効果的に行うには、インプットとアウトプットを組み合わせることが大切です。テキストを読んだらすぐに過去問で確認し、「なぜそうなるのか」を自分の言葉で説明できるようにすると、記憶が長期化します。
理解を前提にした暗記は、ただの暗記よりも定着率が高く、学習効率も向上します。数字や文言を覚える際も、「根拠を説明できる暗記」を意識して取り組みましょう。
※宅建士試験の暗記については、こちらの記事で詳しく解説しています。
3-5. スケジュール管理とモチベーションの維持を徹底する
合格までにかかる時間は、人によって異なりますが、多くの受験生は半年から1年程度 学習することになります。そのため、合格できるかどうかは知識量だけでなく、計画的に学習を継続できるかどうかが大きく左右します。
まずは試験日から逆算し、1か月ごとの学習計画を立てましょう。特に時間のかかる権利関係や、得点比率の高い宅建業法を重点的に学習するのがポイントです。
また、学習を続けるうちにモチベーションが下がる時期もあります。そうしたときは、「合格後の自分」を具体的にイメージすることが有効です。資格取得後に転職や独立ができる、自信を持って仕事に臨めるなど、目的意識を持つことで学習の意欲を維持できます。
さらに、短時間でも毎日勉強を続ける「学習の習慣化」も合格者に共通する特徴です。疲れている日でも5分だけテキストを読む、5問だけ過去問を解くといった“途切れない学習”を心がけましょう。
※宅建士試験の勉強スケジュールについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
4. 確実に合格を掴むなら伊藤塾の「宅建士合格講座」の活用がお勧め
宅建士試験の合格を目指すなら、独学ではなく受験指導校の体系的な講座を活用するのが非常に有効です。
伊藤塾の「宅建士合格講座」では、合格に直結する学習設計が組まれており、忙しい社会人でも効率的に学べる環境が整っています。
講座の具体的な特徴は以下のとおりです。
1.権利関係を重点的に学習できる
2.プロの講師によるわかりやすい講義を受けられる
3.オンライン質問やカウンセリング制度でモチベーションを維持できる
4.楽しく学んで、合格してしまう
それぞれ詳しく解説します。
4-1. 権利関係を重点的に学習できる
本試験では、宅建業法(全50問中20問)及び権利関係(14問)の出題比率が高いため、この2科目の出来次第で合否が決まると言っても過言ではありません。中でも権利関係は、単純暗記では得点に繋がりにくく、多くの受験生が苦手意識を持ってしまう科目です。
伊藤塾の「宅建士 合格講座」は、この権利関係に厚みを持たせて構成されており、全体講義の約半分が「権利関係」に充てられています。
「通常講義」と「復習アシスト」の二本立てで、徹底的に理解を伴った学習が出来るため、初心者でも安心して学習を進めることができます。
4-2. プロの実務家講師によるわかりやすい講義を受けられる
伊藤塾の「宅建士 合格講座」では、宅建士の実務家でもあるプロの講師陣が、リアルな事例を交えながら、宅建士試験の基礎から応用までをわかりやすく丁寧に解説してくれます。
また、「何のための制度・手続きなのか」という「趣旨から考える思考法」を徹底的に身につけることができるのも大きな特徴です。この思考法を身につければ、試験本番で未知の問題に遭遇した際にも、落ち着いて対応ができるようになるはずです。
さらに、写真・表・データが豊富でわかりやすいオリジナルテキスト、厳選された過去問題集や学習アプリに加え、模擬試験までセットでついてくるため、「これだけやっていれば合格できる」と自信を持って本試験を迎えることができるでしょう。
4-3. オンライン質問やカウンセリング制度でモチベーションを維持できる
宅建士試験の学習では、「最初は順調でも途中で挫折してしまう」という悩みを抱く受験生が少なくありません。モチベーションの維持は、合格までの最大の課題と言えます。
伊藤塾の「宅建士 合格講座」では、学習を継続しやすい仕組みが充実しており、受講生の挫折を防ぐ工夫が随所に盛り込まれています。
年2回のスクーリング・オンライン質問会(Zoom)・有資格者によるカウンセリング制度など充実したサポート体制によって、モチベーションを保ち、最後まで諦めることなく学習を進めることができます。
4-4. 楽しく学んで、合格してしまう
そして、何と言っても伊藤塾の「宅建士 合格講座」の最大の特徴は、「楽しく学んで、合格してしまう」という点です。
宅建士試験の学習では、覚えなければならない条文や数値が多々あるのですが、当講座では語呂合わせ等を使って、無理なく楽しく覚えられるよう工夫がなされています。
また、難解な制度についても、実務家の講師が実例を用いて制度趣旨から具体的に解説してくれますので、イメージがしやすく、記憶にも定着しやすいという「楽しく学んで合格してしまう」工夫が満載の講座となっています。
楽しく学べて、合格に必要なすべてが揃っている伊藤塾の「宅建士 合格講座」の受講料は ¥39,800 。
もう、独学で苦しむ必要はありません。
楽しく学んで、無理なく合格を目指しましょう。
5. 宅建に落ちる人の特徴に関するQ&A
Q. 宅建に受かる気がしない……どうすればいいですか?
A. 宅建士試験は決して簡単ではありませんが、「正しい方法で続ける」ことで誰でも合格を狙えます。まずは、落ちた原因を客観的に分析することが大切です。勉強時間が足りなかったのか、出題傾向を把握していなかったのか、暗記と理解のバランスが取れていなかったのかを整理しましょう。
その上で、出題頻度の高い分野(宅建業法・権利関係)から学習を立て直すと効果的です。独学が不安な場合は、受験指導校の講義を活用して、ペースを整えるのも有効です。
Q. 受験指導校を活用すれば必ず合格できますか?
A. 受験指導校を利用することで、独学よりも合格へ近づけますが、「受講=自動的に合格」ではありません。講座はあくまで最短ルートを示してくれるナビゲーションです。学習の習慣化や復習の徹底など、受講生自身の努力も欠かせません。
とはいえ、講師による指導や質問制度、カウンセリングなどを活用すれば、学習の方向性を誤るリスクは大幅に減ります。初学者や再受験者にとっては、学習効率を飛躍的に高める手段と言えるでしょう。
Q. 宅建に2回以上落ちる人には共通点がありますか?
A. 2回以上不合格になる人の多くは、「同じ勉強法を繰り返している」という共通点があります。
過去問演習をせずインプット学習に偏っていたり、苦手分野の克服を後回しにしていたりするケースが目立ちます。
前回と同じ方法で挑戦しても結果は変わりません。模試の結果や苦手科目を分析し、「どこで失点しているのか」を把握した上で勉強法を修正しましょう。
Q. 勉強しても得点が伸びないのはなぜですか?
A. 知識のインプットばかりで、問題演習(アウトプット)をしていないことが大きな原因です。
宅建士試験は「知っている」だけでは得点につながりません。実際に過去問を解き、「なぜこの選択肢が正しい(誤り)なのか」を説明できるようにすることが重要です。
また、理解が浅いまま暗記を進めると、応用問題に対応できません。得点が伸び悩むときは、学習内容を声に出して説明したり、過去問の解説をノートにまとめたりして、理解を伴う学習へ切り替えましょう。
Q. 試験直前にやってはいけない勉強法はありますか?
A. 直前期は「新しい教材に手を出す」ことが最も危険です。これまで使ってきたテキスト・問題集に絞り、復習と苦手分野の補強に徹することが合格への近道です。
また、徹夜や詰め込み勉強も集中力を下げる原因になります。前日は軽めの確認に留め、十分な睡眠を取ることも本試験で実力を発揮するには大切です。
※試験直前の勉強法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
6. 宅建士試験に落ちる人の特徴と合格のための学習法 まとめ
当記事では、宅建士試験に落ちる人の特徴と宅建士試験の合格を目指す上で理解しておくべき点について解説しました。
以下にポイントをまとめます。
●試験の難易度と現状
宅建士試験の合格率は15〜18%前後であり、受験者の約8割以上が不合格となる現実があります。不合格は実力不足ではなく、勉強法や試験対策の方向性が間違っているケースがほとんどです。
●出題傾向の変化
特に2025年(令和7年)の本試験では「個数問題」が多く出題されるなど、単なる暗記だけでは対応できず、理解の深さや判断力がより重視される傾向にあります。
●不合格者の主な特徴
1.合格に必要な学習時間(300〜500時間程度)を確保できていない。
2.試験を軽視し、曖昧な記憶や思い込みで解こうとしている。
3.知識を「使う練習」であるアウトプット(問題演習)を重視せず、インプット中心の勉強に偏っている。
4.出題頻度が低いマイナー論点に時間をかけすぎており、「出題の可能性が高い分野を確実に押さえる」発想が欠けている。
5.本試験での時間配分を意識していない。
6.複数の教材に手を出し、1冊を完璧に仕上げる集中力と反復ができていない。
●合格のための正しい学習法
1.宅建業法で8〜9割、他の分野で6〜7割程度の得点を目指すなど、科目ごとに目標点を決める戦略が有効。
2.過去問分析に基づき、宅建業法の定番論点など、出題可能性の高い分野から優先的に学習する。
3.過去問演習をメインとし、答えを覚えるのではなく「なぜ正しいのか、なぜ間違いなのか」を理解する。
4.条文や数値を覚える際も、「なぜその規定があるのか」という理解を伴った暗記を意識する。
5.試験日から逆算して計画を立て、短時間でも毎日勉強を続ける「学習の習慣化」を徹底する。
独学で伸び悩んでいると感じている方は、ぜひ受験指導校の体系的な講座の活用をご検討ください。
伊藤塾の「宅建士 合格講座」は、多くの受験生が苦手意識をもってしまう「権利関係」に重点を置いた構成で、プロの実務家講師が「制度趣旨から考える思考法」を教え、受講生を合格に導きます。
さらに、オンライン質問会やカウンセリング制度など、学習の継続を支えるサポート体制も充実しており、楽しく学んで合格できる工夫が満載の講座です。
独学で勉強の方向性に迷っている方、次こそ確実に合格を掴みたい方は、伊藤塾とともに、楽しく学んで無理なく合格を目指しませんか。
伊藤塾があなたのチャレンジを力強くサポートさせていただきます。