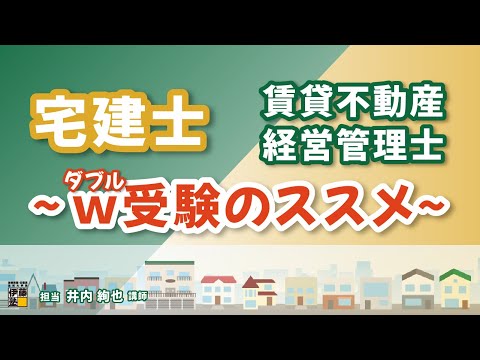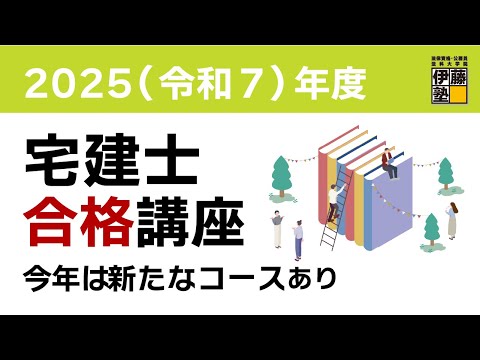宅建士を取得すると何ができる?独占業務など資格のメリット5選
キャリア
2025年08月29日


「宅建士になると何ができる?」
「どのようなメリットがあるの?」
こんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。実は、宅建士になってできることは、想像以上にたくさんあります。
・今よりも収入をアップさせたい
・時間に縛られずに働きたい
・副業で収入を増やしたい
・就職や転職したい
・出産や育児から仕事に復帰したい
など、様々な目標を実現できる可能性があるのです。本記事では、
・宅建士になるとできること
・取得するメリット
・宅建士が活躍できる業界
などについて取り上げました。宅建士になると何ができるのか知りたい方は、是非ご一読ください。
※宅建士の資格の詳細については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
→【完全版】宅建とは?試験の詳細や宅建士の仕事内容など資格のすべてを徹底解説!
【目次】
1.宅建士になると何ができる?できること5選
宅建士の資格を取得すると、様々なことができます。ここでは、宅建士になるとできるようになることを5つ紹介します。
・独占業務を担当できる
・就職や転職がしやすい
・副業として働ける
・独立開業できる
・女性がキャリア復帰できる
それぞれ見ていきましょう。
1-1.独占業務を担当できる
宅建士になると、独占業務を担当できます。次の3つの独占業務は、どれだけベテランの社員であったとしても、宅建士の資格を保有していないと行うことができません。
・重要事項の説明
・重要事項説明書の記名
・契約書の記名
いずれも不動産取引で必ず必要な手続きですが、宅建士以外が行うと、罰則を科せられてしまいます。
1-1-1.重要事項の説明
不動産を売買したり、賃貸借契約を結ぶ際は、取引の内容を分かりやすく説明することが欠かせません。買主・借主の大半は、不動産取引に必要な知識や経験を持っていないからです。そこで、専門家である宅建士が「重要事項説明」を行うことが決められています。
※重要事項とは?
買主・借主が、物件を選ぶために必要な情報です。
具体的には、登記の情報、法令による制限、電気やガス等のライフライン、手付金や敷金、契約の解除や損害賠償に関すること等が挙げられます。
専門家である宅建士が、必要な情報を分かりやすく伝えることで、買主・借主を守っているのです。
1-1-2.重要事項説明書の記名(35条書面)
重要事項を説明した後は、それを証明するために「重要事項説明書」への記名が必要です。この記名も、必ず宅建士が行わなければなりません。
「重要事項説明書」は、宅建士が説明した内容を、買主・借主が確認するための重要な書類です。宅建士が「重要事項説明書」に記名することで、説明した内容の責任を明確にしているのです。
1-1-3.契約書の記名(37条書面)
不動産取引が成立すると、契約に関する内容が記載された書面(37条書面)を相手に交付しなければなりません。実務上、契約書として扱われるケースも多い37条書面ですが、この書面についても宅建士が記名を行います。
※35条書面と37条書面については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 35条書面と37条書面の違いとは?比較表や覚え方のコツを解説
1-2.就職や転職がしやすい
宅建士の資格を取得すると、不動産業界をはじめとする様々な業界に就職や転職がしやすくなります。専門的な知識をアピールすることで、不動産会社や建設会社、金融機関などへ就職・転職しやすくなるのです。
業界未経験から、宅建士を取得して、これらの業界に転職する人もいます。例えば、飲食業界で働いていた人が、不動産業界へ転職するようなケースも珍しくありません。
実際に、求人情報を見てみると「宅建士歓迎」や「宅建士取得者優遇」などと記載された求人票が数多く存在します。
宅建士の資格は、就職や転職の際に大きなアピールポイントになるのです。宅建士によって、キャリアの選択肢が広がり、様々な業界で活躍できる可能性が高まります。
※宅建士の就職・転職については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 宅建は就職や転職に有利?未経験もOK?不動産以外で活かせる仕事も紹介
1-3.副業として働ける
宅建士を取得すると、副業の選択肢も広がります。本業を退職せずとも、不動産取引に関する専門知識を活かすことで、様々な形で働くことができるのです。
例えば、以下のような副業が挙げられます。
・土日や空いた時間を活用して、宅建士としてアルバイトをする(いわゆる週末宅建士)
・不動産関連のWebメディアで、宅建士の知識を活かした記事を執筆する
・予備校や専門学校で、宅建士講座の講師として指導をする
・専門的な知識を活かして、不動産活用のコンサルティングを行う
宅建士の資格を活かせば、本業とは異なる分野でも収入を得ることができます。さらに、副業で培ったスキルや人脈が、本業でも発揮されてキャリアアップにつながるケースもあります。
※宅建士の副業については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→宅建士資格を活かしたオススメ副業4選!在宅・土日のみ・未経験もOK
1-4.独立開業できる
宅建士の資格があれば、自分で不動産業を始めて、独立開業することもできます。ただし、独立開業は向き不向きがはっきりしているため、メリット・デメリットなどをしっかりと検討することが必要です。
| メリット | デメリット |
| ・在庫を持つ必要がない (比較的低リスク) ・必要な初期投資が少ない ・自分のペースで仕事ができる ・軌道に乗ると、高年収を狙える ・裁量が大きい ・やりがいを感じやすい | ・一定の開業資金は必要 ・全てを一人でこなす必要がある (集客、営業、事務作業など) ・安定した収入には時間がかかる |
独立開業には、開業資金の準備や事業計画の作成など、十分な準備が不可欠です。まずは不動産会社に勤務して実務経験を積み、人脈を築くことから始めるとよいでしょう。
宅建士の独立開業については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→【宅建士の独立開業】成功のコツと失敗しやすい4つの要因を解説
1-5.出産や育児からキャリア復帰できる
出産や育児で仕事を離れた女性にとって、宅建士になることは、キャリア復帰に有効な方法です。近年、不動産業界では女性の活躍が増えており、女性宅建士の数も年々増加しています。
不動産取引では、お客様と直接会って打ち合わせをすることが多いため、女性ならではのきめ細やかな対応が求められます。そのため、女性宅建士の需要が高まっているのです。例えば、物件の内覧や契約の説明など、お客様と対面する場面では、女性ならではの心配りや共感力、コミュニケーション能力が発揮でき、信頼関係を築きやすくなります。
出産をきっかけに退職したものの、宅建士になって仕事に復帰し、活躍している女性は珍しくありません。キャリアの中断があっても、宅建士の資格を取得することで、その能力を正当に評価してもらいやすくなるのです。宅建士という明確な指標があることで、一時的なブランクがあっても、スムーズにキャリア復帰できる可能性が高まります。
※宅建士が女性にもおすすめな理由は、こちらの記事でも詳しく解説しています。
→宅建士の年収とメリットは?女性にもおすすめな理由を徹底解説
2.宅建士の資格を取得するメリット
宅建士の資格を取得すると、できることが増える以外にも様々なメリットがあります。
ここでは、代表的なメリットを3つ紹介します。
・自分の市場価値が高まる
・収入のアップが期待できる
・昇進や出世に役立つ
それぞれ見ていきましょう。
2-1.自分の市場価値が高まる
宅建士の資格を取得することで、自分の市場価値を高めることができます。最も分かりやすいのが、不動産業界で働くケースです。
不動産業界では、宅建業法によって、宅建士の設置義務が定められています。宅建業者は「従業員5人につき1人以上」の宅建士を置かなければなりません。そのため、事業を拡大しようとすると、必然的に宅建士を増やすことが求められます。つまり、宅建士を持っているだけで、不動産業界での市場価値が上がるのです。
不動産業界以外でも、宅建士の資格は高く評価されています。金融機関や保険会社、建設会社などで、不動産に関する知識を持つ人材が求められているのです。このように、宅建士の資格を取得することで、自分の市場価値を高め、キャリアの選択肢を広げることができます。不動産業界だけでなく、様々な業界で活躍できる可能性が広がるでしょう。
2-2.収入のアップが期待できる
宅建士の資格を取得することで、収入のアップが期待できます。一般的に、資格を持っている人は、そうでない人に比べて、収入が高くなります。宅建士も例外ではありません。
例えば、宅建士を活かして不動産業界で働けば、高い給与を得られる可能性があります。不動産業界の平均年収は、全産業平均よりもかなり高い水準です。さらに、宅建士の資格を持っていれば、基本給とは別に月1〜5万円の資格手当が支給されるケースもあるのです。
仮に、本業で宅建士の知識を活かしづらい場合でも、資格を活かした副業で収入アップを目指せます。週末だけ宅建士の独占業務を請け負ったり、不動産関連のライターとして活動することで、本業とは別の収入源を確保できるでしょう。
さらに、将来的に独立開業すれば、収入は大きく増える可能性があります。事業が軌道に乗れば、年収1000万円以上を目指すこともできるのです。
宅建士を取得することは、様々な形で収入アップのチャンスを広げることにつながります。
2-3.昇進や出世に役立つ
宅建士の資格は、昇進や出世にも役立ちます。特に不動産業界で働いている人にとっては、宅建士の資格が、昇進の必須条件となっているケースが少なくありません。企業によっては、管理職へ昇進するための条件として、宅建士であることが求められているのです。
必須要件となっていない場合でも、宅建士を保有しているかが、昇進の際に考慮される場合は多いです。また、不動産業界以外でも、宅建士の資格が、昇進や出世に有利に働くことがあります。
例えば、銀行では、宅建士を持っていることが人事考課に影響を与えるケースが珍しくありません。地方公務員などでも、不動産関係の部署に配属された場合、高い評価につながる可能性があります。建築基準法や都市計画法など、宅建士の持つ法律知識が、公務員の実務でも役立つからです。宅建士を取得すると、様々な場面で、専門知識を持つ人材として高く評価されるでしょう。
3.宅建士を活かして活躍できる業界は?
宅建士を取得すると、様々な業界で活躍できる可能性が広がります。ここでは、宅建士のスキルを活かして活躍できる代表的な業界を4つ紹介します。
・不動産業界
・金融業界
・保険業界
・地方公務員
それぞれ見ていきましょう。
3-1.不動産業界
不動産業界は、宅建士を最も活かしやすい業界です。
・独占業務を担当できる
・取引シーンで専門知識を発揮できる
・宅建士が信頼の獲得に繋がる
など、宅建士の資格を存分に活かして活躍することができます。
給料とは別に資格手当が支給されたり、経験を積んで独立したりもできるため、宅建士にとって、非常に魅力的な業界といえるでしょう。
3-2.金融業界
金融業界も、宅建士の知識を活かして活躍できる業界の1つです。例えば、次のようなシーンでは、宅建士のスキルが役立ちます。
・動産担保ローンの審査
・不動産価値の評価
・投資のアドバイス
銀行や信用金庫、証券会社などで、宅建士保有者が求められているのです。
3-3.保険業界
保険業界でも、宅建士の知識が役立ちます。「火災保険」や「地震保険」などの保険商品を扱う場合、不動産に関する知識が欠かせないからです。不動産の価値やリスク評価など、様々なシーンで、宅建士のスキルが重宝されるでしょう。
また、マイホームの購入など、顧客のライフプランを作成する際も、宅建士が信頼の獲得に繋がります。
3-4.地方公務員
地方公務員でも、宅建士の知識を活かして活躍できます。「都市計画法」「建築基準法」など、宅建士が持つ法律知識は、自治体の不動産部署でも必要となるからです。
人によっては、宅建士取得後、自治体の「キャリア選択型人事制度」などを利用して、不動産行政のスペシャリストとして活躍する場合もあります。
4.ダブルライセンスを取得するとできることが増える
宅建士がダブルライセンスを取得すると、できることの幅が更に広がります。
複数の資格を持つことで、より専門性の高い業務に携わることができ、キャリアの幅が広がるのです。ここでは、宅建士と相性の良い資格として「賃貸不動産経営管理士」「行政書士」「司法書士」を紹介します。
4-1.賃貸不動産経営管理士
賃貸不動産経営管理士は、宅建士と非常に相性の良い資格の一つです。ダブルライセンスを取得すると、
① 宅建士として賃貸契約の「仲介業務」を行う
② 賃貸不動産経営管理士として、賃貸契約後の「管理業務」も引き受ける
といった形で、業務の幅を大きく広げることができます。
試験対策としても共通事項が多く、「約50%」の試験範囲が重なっていると言われています。そのため、同じ年に宅建士とダブル受験をする人も多い資格です。
※賃貸不動産経営管理士試験の難易度や試験日については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 賃貸不動産経営管理士の難易度は?合格率や合格点・合格ラインを解説
→【2024年度】賃貸不動産経営管理士の試験日は?申込方法・講習・過去問なども解説
※宅建士と賃貸不動産経営管理士のダブル受験については、こちらの動画で詳しく解説しています。
→ 宅建士・賃貸不動産経営管理士w受験のススメ
4-2.行政書士や司法書士
宅建士取得後に、行政書士や司法書士などに挑戦する人もいます。宅建士は、不動産に関する資格ですが、法律系国家資格の入口的な位置づけともなっている資格です。身につけた法律知識は、他の法律系国家資格でも十分に活用できるのです。
特に、独立開業を目指す場合は、行政書士・司法書士などの法律系国家資格を持つことが大きな武器になります。専門性が大きく高まる上、競合との差別化にもつながります。
※行政書士や司法書士とのダブルライセンスやトリプルライセンスについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 司法書士・行政書士・宅建士のトリプルライセンスが最強!難易度も解説
5.まとめ
最後に、今回の記事のポイントをまとめます。
◉ 宅建士になると、就職や転職、独立開業などができる
◉ 副業として、収入源を増やすこともできる
◉ 出産や育児などからのキャリア復帰にも役立つ
◉ 収入がアップしたり、昇進に影響したりする
宅建士になるとできることは、想像以上にたくさんあります。
現場で経験を積んだり、スキルアップしたり、ダブルライセンスを取得すれば、時間の経過と共にできることも更に増えていくでしょう。
宅建士試験の対策には、ぜひ法律資格専門の受験指導校である伊藤塾をご活用ください。
※こちらも併せてお読みください。
→ 宅建の通信講座はなぜ伊藤塾がおすすめなのか?宅建士合格講座の魅力を徹底解説
「今年はさらにバージョンアップしたコースをご用意!!「2025年合格目標 宅建士合格講座」 のご紹介です!」