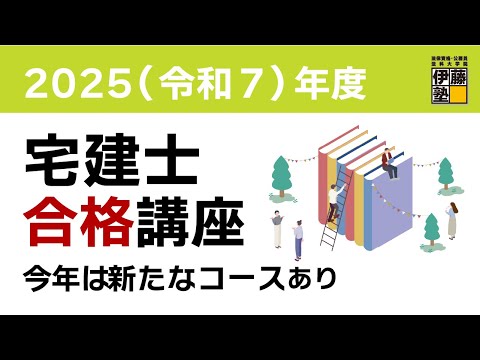宅建士は多すぎ?オワコンって本当?資格取得するメリットや選ばれる人材になる方法
キャリア
2025年10月06日


宅建士の資格に興味はあるものの、「宅建士は多すぎて、今さら資格を取っても役に立たないのでは?」と不安に思う方もいらっしゃることでしょう。
確かに、宅建士の登録者数は年々増加し、就職や転職において“差別化が難しい資格”という印象を持たれがちです。そのため、SNSなどでは「宅建士は多すぎてオワコン」といった声も聞かれます。
しかし現実には、宅建士は今も不動産業界で「なくてはならない国家資格」であり、法律で定められた独占業務を担う存在として必要とされています。資格の活かし方次第では、むしろ選ばれる人材になることも十分に可能です。
この記事では、宅建士を取り巻く現状と課題、将来性や資格の活かし方などについて解説していきます。宅建士資格に挑戦すべきか迷っている人は、ぜひこの記事を参考にしていただき、積極的な気持ちで資格取得にチャレンジしてください。
【目次】
1. 宅建士や宅建業者は本当に多すぎる?登録者数はどれくらい?
まずは、宅建士と宅建業者の登録数を客観的なデータから確認し、本当に“多すぎる”のかを検証していきます。
1-1. 宅建士の登録者数
最新の国土交通省の発表によれば、令和5年度における宅地建物取引士の総登録者数は約118万人となっています。このうち、新規登録者数は約2万9,000人であり、近年は新たに登録する人の数も増加傾向にあります。(参照:令和5年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について|国土交通省)
登録者が100万人を超えているという数字だけを見ると、「宅建士は多すぎるのでは」と感じるかもしれません。しかし、注意すべきはこの登録者数に「不動産業以外で働く人」や「資格保有のみで実務に従事していない人」も含まれている点です。つまり、登録者全員が宅建士として不動産業務に携わっているわけではないという事です。そのため、「登録者数が100万人以上いる=飽和状態」とは言えません。
1-2. 宅建業者の登録数
令和6年3月末時点における宅建業者数は、全国で約13万業者に上ります。前年度から979業者の増加となっており、これで10年連続で業者数が増加している状況です。
(参照:令和5年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について|国土交通省)
宅建業者数の増加は、不動産業界の活発さや多様化を象徴する変化と捉えることができます。資格者数が多いと感じる背景には、こうした業界の成長があることを押さえておく必要があるでしょう。
2. 宅建士の価値は下がっている?「オワコン」と言われる理由
宅建士は長年にわたって人気を保ってきた国家資格ですが、最近では「宅建士はもうオワコン」「資格を取得する意味がない」という声も聞かれます。
ここでは、宅建士の価値が下がっているのではないかと感じてしまう理由を3つの観点から整理し、実情を検証していきます。
2-1. 登録者数が増え続けているため希少性が薄れている
宅建士の価値が下がったと言われる一因として、登録者数の増加により希少性が低下したことが挙げられます。国家資格は一般に「限られた人しか持っていない=価値がある」という認識が根強く、その人数が増えれば「誰でも取れる資格」という印象になりやすい傾向があります。
実際、宅建士の登録者数は令和5年度において約118万人に達しており、年々増加を続けています。試験の合格者数も安定して多いため、他の資格と比べても“取得しやすい部類”と見られることもあるでしょう。
ただし、このような見方は一面にすぎません。数が多いこと=価値がないとは限らず、むしろ宅建士が社会的に必要とされているからこそ、資格者が増えているとも言えます。
資格そのものの信頼性は法律で保たれています。社会における役割が明確に存在する限り、宅建士の価値がゼロになることはありません。
2-2. 実務経験や営業スキルがないと活かしづらい現実がある
宅建士の資格を取得しても、「就職や転職で活かせなかった」「給料が上がらなかった」という声が見られる理由は、他の資格にも共通していえることですが、資格を持っているだけで即「採用される」「給料が上がる」とはなりにくい現実を表しています。
不動産業界では、宅建士として重要事項説明や契約書への記名押印を行うだけでなく、物件案内や顧客対応、契約交渉といった営業活動全般が業務の中心となります。そのため、実務経験や対人スキル、営業力や提案力などが重視される傾向にあります。
例えば、未経験の新人が宅建士の資格だけで不動産営業に飛び込んでも、成果を上げるには時間がかかるケースが多いものです。逆に言えば、実務力を身につければ、資格を持たない人との差は大きく広がります。
資格を「活かせるかどうか」は自分次第です。宅建士の資格取得は「ゴール」ではなく「スタート地点」として考えると、現実とのギャップに戸惑わずに済みます。
2-3. AIや不動産テックの進展により、将来の仕事が不安視されている
近年、「不動産業界にもAIの波が押し寄せている」「宅建士の仕事もいずれ自動化されるのでは」といった声が上がっています。確かに、不動産テックの発展は著しく、物件検索・査定・契約書の作成・電子署名など、かつて人間が行っていた業務がデジタル化されつつあります。
例えば、重要事項説明をオンラインで行える「IT重説」や電子契約の普及は、業務の効率化を進める一方で、「宅建士の存在意義が薄れていくのでは」と不安を感じさせる要因となっています。
しかし、AIやシステムが進化しても、不動産取引における全ての業務を機械に任せることは難しいのが現実です。顧客の感情に寄り添う提案、トラブル対応、契約内容の柔軟な説明など、AIに代用が難しい人間ならではの対応力は今後も需要がなくなることはないでしょう。
むしろ、テクノロジーを理解し使いこなせる宅建士は、時代に適応した「選ばれる存在」になれると言えます。未来を恐れるより、変化を味方につける姿勢が求められています。
3. 登録者数が多くても宅建士を取得すべき理由
宅建士の登録者数が100万人を超えていると聞くと、「今から取得しても遅いのでは?」と不安になるかもしれません。しかし、実際には宅建士の需要は今もなお安定しており、資格の価値は揺らいでいません。
ここでは、なぜ登録者が多くても宅建士を目指す意義があるのかについて、3つの視点から解説していきます。
3-1. 不動産業界で唯一の「独占業務」がある
宅建士が高く評価される最大の理由は、法律で定められた「独占業務」があることです。これは、宅建士にしか許されていない仕事が存在することを意味します。
具体的には、不動産売買や賃貸契約において、以下の3つの業務は宅建士の資格を持つ者でなければ行えません。
| ・重要事項の説明 ・重要事項説明書への記名 ・契約書(37条書面)への記名 |
これらは不動産取引の根幹にかかわる重要なプロセスであり、宅建士がいなければ不動産会社は合法的に営業を継続できません。
つまり、不動産取引が行われる限り、そこに宅建士としての需要が存在するということになります。
3-2. 不動産市場の拡大と求人ニーズの安定性
宅建士の資格は、不動産市場の拡大により安定した需要を維持しています。
都市部の不動産価格上昇や投資用不動産への注目により、大手企業に加えて副業・兼業での個人・法人参入が増加し、新規業者の設立が活発化しています。
地方都市や郊外でも、再開発事業や移住促進政策の影響で地元密着型不動産会社の新設が進んでおり、全国的に宅建業者が増加している状況です。不動産業は景気の影響を受けやすいものの、一定のニーズが継続的に存在し、業務拡大が全国規模で進展しています。
また、宅建業法では営業所ごとに「従業員5人に1人以上」の専任の宅建士配置が義務付けられており、従業員10人なら2人以上の専任の宅建士が必要です。この配置義務は全国共通で、業者数の増加に比例して宅建士の必要数も拡大する構造となっています。
このような現状から、宅建士資格が不要になるという見方は早計であり、不動産市場の拡大と宅建業者の増加は宅建士の継続的需要を強く裏づけています。
3-3. 宅建士の活躍フィールドはむしろ広がっている
近年、宅建士の活躍の場は不動産仲介業にとどまらず、様々な関連業界へと広がりを見せています。
例えば、大手不動産フランチャイズチェーンの展開に伴い、1社あたり数十店舗を構える企業も珍しくなくなりました。こうした店舗ごとに宅建士の配置が必要とされるため、大手企業の採用ニーズも継続しています。
また、不動産テックの発展により、スタートアップやIT企業でも不動産事業への参入が活発になっています。オンライン契約やIT重説、VR内見などの新サービスを展開する企業でも、法的要件を満たすために宅建士が必要とされる場面は依然として多く存在します。
さらに、建築業、リフォーム業、金融業界等でも不動産取引に関連する業務が増えており、宅建士資格を保有していることが「業界横断的な価値」として評価される場面も増えてきました。
このように、宅建士の資格は活躍のフィールドを選ばず、幅広い業界で応用できる汎用性の高いライセンスとなっています。登録者が多いからこそ、「どう活かすか」が問われる時代になっているとも言えるでしょう。
4. 宅建士が飽和する中で“選ばれる人材”になるには?
宅建士の登録者数は増加傾向にあるため、資格を持っているだけでは評価されにくい時代になりつつあります。実際、企業が求めるのは「宅建士の資格+実務力や人間力を備えた人材」です。だからこそ、資格取得後は“選ばれる宅建士”を目指す必要があります。
ここでは、資格取得後に実践すべき5つのポイントを紹介します。
4-1. 実務経験を積んで即戦力をアピールする
資格を取得しただけで満足してしまう人も多い中、実務経験を積むことは大きなアドバンテージになります。不動産業界では、現場での判断力や対応力が問われる場面が多く、資格よりも実務力が重視されることもあります。
物件案内、契約書作成、重要事項説明など、実務の流れを一通り経験している宅建士は、企業から即戦力として評価されやすくなります。未経験者よりも、入社後すぐに仕事を任せられる人材の方が重宝されるのは当然です。
まずはアルバイトやインターン、パート勤務でも構いません。小さな経験の積み重ねが、将来的な信頼につながります。
4-2. コミュニケーション能力や営業スキルを磨く
宅建士に求められるのは法律知識だけではありません。顧客との信頼関係を築くコミュニケーション能力や、ニーズを汲み取って提案につなげる営業力も重要です。
不動産業は高額な取引を扱うため、顧客は不安や迷いを抱えていることが多く、その心理に寄り添いながら丁寧に説明できるかが問われます。
同じ条件の物件を紹介しても、言葉の選び方や説明の順序一つで印象は大きく変わります。結果的に成約率や顧客満足度にも差が出るでしょう。
信頼される宅建士は、話す力・聞く力の両方を兼ね備えています。普段の会話や接客経験も、実は実務に直結する貴重なトレーニングになります。
4-3. SNS・ブログ等で情報発信してブランディングする
宅建士としての専門性を活かし、SNSやブログで情報発信を行うことも、自身のブランディングにつながります。
例えば、SNSで物件を紹介をしたり、法律改正のポイントをわかりやすく解説したりすることで、不動産に関心のあるフォロワーを増やせます。これにより「知識のある宅建士」「信頼できる人」という印象を築くことができます。
実際、SNS経由で内見予約や相談を受ける宅建士も少なくありません。情報発信を通じて、資格を“信頼”へと転換できるのです。
単に資格を持っているだけではなく、「誰に相談したいか」と選ばれる存在になるには、情報発信を通じた自己ブランディングがますます重要になっていくでしょう。
4-4. AIや不動産テックへの理解を深める
不動産業界で活躍するためには、AIや不動産テックへの理解が欠かせません。すでに現場では、オンライン契約、VR内見、AIによる価格査定などの技術が導入され、業務の効率化が進んでいます。
こうした新しいツールに対して苦手意識を持っていると、変化に対応できず、職場での評価やキャリアに影響を及ぼす可能性があります。反対に、ITリテラシーの高い宅建士は、変化に強い人材として社内外から信頼されやすくなります。
例えば、重要事項説明をオンラインで行う「IT重説」にスムーズに対応できれば、顧客対応の幅も広がり、利便性や信頼性をアピールできます。
テクノロジーを受け入れ味方につける姿勢こそが、これからの宅建士に求められる素養です。「知らないから避ける」のではなく、「理解して使いこなす」姿勢を身につけましょう。
4-5. 宅建+αで差別化する「ダブルライセンス」
宅建士として他と差をつけるには、宅建に加えてもう一つの専門スキルや資格を身につけることが効果的です。自分だけの+αを持つことで、企業や顧客から選ばれる存在になれます。
実際、不動産業務は宅建士の範囲にとどまらず、資金計画、物件管理、法律実務、相続や税金の知識など幅広い領域と関わりがあります。そのため、他分野の知識を備えている人材は、総合的な提案力を持つ人として重宝されます。
例えば、ファイナンシャルプランナー(FP)と組み合わせれば、住宅ローンやライフプランに関するアドバイスまで対応できるようになります。顧客の将来設計に寄り添った提案ができる宅建士は、相談される頻度も高まるでしょう。
また、賃貸不動産経営管理士やマンション管理士などを取得すれば、管理会社やオーナーとのやりとりもスムーズになり、現場の信頼も得やすくなります。
さらに、行政書士や司法書士など法律系の資格を持っていれば、相続や登記といった手続きにも対応でき、不動産に関するワンストップサービスを提供することも可能です。
このように、宅建を基盤としながら、自分の興味や進みたい方向に応じて他の資格を掛け合わせていくことで、より広い業務範囲に対応でき、専門性や信頼性を高めることができます。
資格を取得することがゴールではなく、どう組み合わせて活かすかが、今後の宅建士にとって重要な視点となるでしょう。
5. 宅建士を本気で目指すなら伊藤塾の「宅建士合格講座」がお勧め
宅建士試験に合格したいと本気で考えているなら、効率的かつ着実に力を伸ばせる伊藤塾の「宅建士合格講座」が最適です。
この講座では、法律を初めて学ぶ方でも安心して取り組めるよう、基礎を丁寧に解説した講義と、試験に出やすい論点を厳選した教材が用意されています。初学者には理解の難しい「権利関係等」や「法令上の制限」などの分野に関しても、講義を受けることで本試験で得点源にすることができるでしょう。
講義は1コマ30分と短く、倍速再生にも対応しているため、通勤・通学中などのスキマ時間を有効に活用できます。さらに、問題演習はスマホ対応の専用アプリでいつでも手軽に取り組めるのも大きなメリットです。
オンラインでの質問受付やカウンセリングといったサポートも充実しており、一人で抱え込まずに学習を進められる体制が整っています。「宅建士が多すぎて、資格を取得する意味がないかも」と不安になっても、カウンセリングを活用すれば、自分の目標や将来像に照らして資格取得の意義を整理することができます。業界の現状やキャリアの可能性について講師やスタッフからアドバイスを受けられるため、迷いや悩みを解消しながら学習に集中できます。
宅建士は受験者が多い試験ですが、確かな戦略と学習環境があれば、短期間でも十分に合格を目指せます。
法律初学者が短期間で合格を目指す場合には、伊藤塾の合格講座を積極的に活用することをお勧めします。
※こちらも読まれています。
→ 宅建の通信講座はなぜ伊藤塾がおすすめなのか?宅建士合格講座の魅力を徹底解説
6. 宅建士が多すぎることに関するQ&A
Q1. 宅建士として独立できる?
A. 宅建士の資格があれば、独立して不動産業を開業することも可能です。ただし、宅建士の資格だけで開業できるわけではなく、「宅地建物取引業」の免許取得が必要です。
また、資金調達や顧客獲得、物件情報の仕入れなど、営業や経営スキルも求められます。資格はスタートラインにすぎず、実務経験や人脈づくりが成功の鍵を握るでしょう。
Q2. 宅建士が多すぎて就職先がない?
A. 確かに宅建士の登録者数は年々増加していますが、それ以上に宅建業者の数も増えており、求人ニーズは安定しています。
特に営業所ごとに「5人に1人以上」の専任の宅建士が必要という法律上の配置義務があるため、業界全体として宅建士の需要は依然高い水準を保っています。
就職先がないというよりは、スキルや適性で差がつきやすい状況と言えるでしょう。
Q3. 宅建士の需要は今後も続くの?
A. 宅建士の需要は今後も続くと予想されます。
不動産取引は法的手続きを要するため、宅建士の関与が不可欠です。加えて、都市部を中心とした不動産価格の上昇や地方での移住促進、投資用不動産市場の拡大など、業界は多様な形で成長を続けています。
法改正やテクノロジーの進展があっても、「宅建士の独占業務」は現時点で代替されていません。
Q4. 宅建士が多いと転職で不利になる?給料は上がらない?
A. 宅建士の人数が多いことは事実ですが、実務スキルや営業力など「+αの強み」がある人材は、転職市場でも歓迎されます。
また、資格手当を支給する企業も多く、特に不動産会社では宅建士資格が昇進の前提条件となっていることもあります。
年収は勤務先や役職によって差がありますが、成果次第で一般の会社員以上を狙うことも十分可能です。
Q5. これから宅建士を目指しても意味がない?
A. 宅建士としての登録者数は多いものの、不動産業者の増加により宅建士の需要は拡大しています。
また、営業所ごとの宅建士配置義務や法律上の独占業務があるため、宅建士でなければできない仕事も存在します。重要なのは「数が多い」ことより、「どう活かすか」です。実務経験を積んだり、他資格と組み合わせたりすることで、自分だけの強みを築くことができます。宅建士は今後もキャリア形成の大きな武器となる資格です。
7.宅建士は多いけれどオワコンどころか今後も活躍できる資格だった
本記事では、宅建士が多すぎてオワコンなのでは?という不安について、多方面から検証してみました。
以下に検証結果をまとめます。
◉宅建士の登録者数は令和5年度で約118万人と多いものの、登録者全員が実務に従事しているわけではなく、また宅建業者数も10年連続で増加し約13万業者(令和6年3月末時点)に上っているため、ニーズは依然として高いといえます。
◉「宅建士は多すぎてオワコンではないか」と言われる背景には、登録者数の増加による希少性の低下、資格を取得しただけでは就職や昇給に繋がらなかった人もいる実情(就職や昇給にはヒューマンスキルの要素が重要)、AIや不動産テックの進展による将来への不安などがあります。
◉しかし、宅建士は不動産取引において法律で定められた「独占業務」(重要事項の説明、重要事項説明書・契約書への記名押印)を担うため、不動産取引が行われる限りその需要はなくなりません。
◉宅建業法により、営業所ごとに「従業員5人に1人以上」の専任宅建士配置が義務付けられているため、宅建業者数の増加に比例して宅建士の必要数も拡大しています。
◉宅建士の活躍フィールドは、不動産仲介業に留まらず、大手不動産フランチャイズ、不動産テック企業、建築業、リフォーム業、金融業界など、幅広い分野に広がっています。
◉多くの宅建士の中から「選ばれる人材」となるためには、資格取得を「スタート地点」と捉え、以下のようなプラスアルファの強みを身につけることが重要です。
・実務経験を積むこと
・コミュニケーション能力や営業スキルを磨くこと
・SNSやブログでの情報発信による専門家としてのブランディング
・AIや不動産テックへの理解
・他の専門スキルや資格を組み合わせた「ダブルライセンス」
以上です。
宅建士は、不動産市場の拡大と法的な配置義務により、今後も安定した需要が見込まれる国家資格です。この資格を最大限に活かし、キャリア形成の大きな武器とするためには、合格するだけではなく、合格後の活躍も見据えた学習と戦略が不可欠です。
伊藤塾の「宅建士合格講座」では、単に合格するためだけの知識の習得ではなく、実務で使える知識として定着させられるよう考え抜かれたカリキュラムとなっているため、実務に出てから活躍しやすいことも魅力のひとつです。
もしあなたが、宅建士試験への合格を本気で目指すのなら、ぜひ伊藤塾の「宅建士合格講座」をご活用ください。
伊藤塾は、あなたのチャレンジを全力で応援しています。