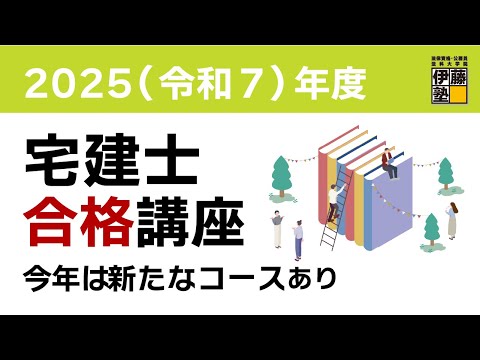宅建士はやめとけ?役に立たない?受験生が気になる宅建士のメリットとは?
キャリア
2025年08月28日


「宅建士資格を取るのはやめとけ」
「宅建なんて役に立たない」
こんな話を耳にしたことがあるかもしれません。しかし、詳しく検証してみると、その大半は誤ったイメージが先行しており、妥当性を欠いていることがわかります。
活用法さえ間違わなければ、宅建士は決して役に立たない資格ではなく、様々なメリットを享受できる魅力的な資格だからです。
この記事では、
◉ なぜ宅建士はやめとけと言われるのか
◉ 宅建士資格が、本当は役に立つ理由
◉ 知っておくべき宅建士の注意点
について解説します。宅建士の資格に不安を感じている方は、是非ご一読ください。
※宅建士の資格の詳細については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
→【完全版】宅建とは?試験の詳細や宅建士の仕事内容など資格のすべてを徹底解説!
【目次】
1.宅建は役に立たない資格ではない!現役宅建士が語る宅建の魅力
「宅建士はやめとけ」「宅建は役に立たない」などと言われることがありますが、実際のところどうなのでしょうか?現役の宅建士であり、実務家ならではの豊富な経験を有している伊藤塾の 井内絢也 講師に、宅建士の実態についてお聞きしました。
Q.そもそも、なぜ宅建士試験を受験されたのでしょうか?
父親の会社が倒産したことがきっかけです。
自分がなんとかしないといけないと思ったのですが、社会で必要な知識や経験が全く無いことに気づき、愕然としました(笑)
そんなとき、親戚から「それなら宅建士試験を受けるといいよ!宅建士は本当に魅力があるから」と勧められて、宅建士試験の受験を決意しました。
Q.合格には、どれくらい勉強されましたか?
人生ではじめてと言って良いくらい勉強しましたね。
ただその結果、3〜4ヶ月くらいの勉強で、見事に大願成就することができました。
Q.宅建士試験に合格して、何か変わったことはありましたか?
一番大きかったのは、宅建士試験に合格して自信が出たことです。とても自己肯定感が上がりました。
宅建士試験の合格率は「15%」くらいですから、「100人中15人」に入れたことから来る自信だと思います。
Q.宅建士として、実際に就職活動をしてみてどうでしたか?
試験に合格したことを、改めて実感する場面が非常に多かったです。
転職活動を始めると、書いてあるんですよね、「宅建士資格取得者(優遇)」って。
「あー!自分のことだ」と1人で喜びを感じていました(笑)。
実際、資格の効果もあったのか、見事に一発目で電話した不動産会社に採用されました。
Q.どういった職種で採用されたのですか?
次は行政書士試験に向けて、働きながら勉強をしたかったので、体力を使う営業はしたくないと思っていました。それを伝えたところ、事務系の職種で採用してもらうことができました。
実務でも、宅建士試験で習った知識を存分に活かせる場面が多く、自己肯定感がどんどん上がっていきましたね(笑)
Q.資格手当は付与されましたか?
1ヶ月あたり「5万円」の資格手当が支給されていました。
給与明細を見たときは震えましたね(笑)資格のありがたみを噛み締めた瞬間でした。
井内講師の話からも分かる通り、宅建士は決して「役に立たない資格」ではありません。むしろ、多くの可能性を秘めた魅力的な資格です。
それでは、なぜ「宅建士」に対して、「役に立たない」「やめとけ」といった否定的な意見も聞こえてくるのでしょうか。その理由については、次章以降で解説します。
※井内講師が語る!「宅建士の資格ってどんなもの?【基本をおさらい part.1】

2.宅建士はやめとけと言われるのはなぜ?
宅建士について「やめとけ」といった否定的な意見を耳にすることがあります。
そのような意見が聞こえてくる理由は何なのでしょうか。ここでは、その原因となりやすい、4つのネガティブイメージについて解説します。
2-1.【イメージ①】人数が多く、希少性が低いから
宅建士の数は年々増加傾向にあり、2024年時点で「約115万人」に上ります。
この数字は、他の国家資格と比較しても非常に多い数字です。実際、「宅建士試験」は例年20万人以上が受験する、国内最大規模のマンモス資格試験としても知られています。
資格保有者が多いということは、それだけ希少性が低くなることを意味します。そのため「宅建士はやめとけ」といった否定的な意見が出てくるのかもしれません。しかし、見方を変えれば、宅建士の数が多いのは、それだけ需要が高いことの裏付けです。
不動産取引の専門家としての役割が、社会から強く求められている証拠だといえるでしょう。資格保有者の数が多いからこそ、宅建士の資格が広く認知され、信頼を得ているとも考えられるのです。希少性の低さを嘆くのではなく、需要の高さに目を向けてみるのも一つの視点です。
2-2.【イメージ②】不動産業以外で使えないから
「宅建士」は不動産取引に関する専門家です。そのため、不動産業界以外では役に立たないと考えられがちです。このイメージが「宅建士はやめとけ」といった意見につながっているのかもしれません。しかし実際には、宅建士の知識は「金融」「建設」「保険」「士業」「公務員」など、幅広い業界で活用できます。
例えば、
・金融業界では不動産担保ローンの審査・管理や不動産投資業務
・保険業界では不動産関連保険商品の販売
などで役立ちます。
さらに、行政書士や司法書士として開業している人が、不動産登記や相続、許認可手続きに必要な専門知識を身につけるために、ダブルライセンスとして取得するケースも珍しくありません。宅建士の資格は、不動産業界以外でも、様々な場面で活用できる可能性を秘めているのです。
※宅建が活かせる場面については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→宅建は就職や転職に有利?未経験もOK?不動産以外で活かせる仕事も紹介
2-3.【イメージ③】資格より実力が重視されるから
不動産業界では、資格の有無よりも、営業成績が重視されるイメージがあります。
確かに歩合制の場合、営業成績が良ければ、それだけ待遇も良くなるでしょう。しかし、多くの会社では「資格手当」が支給されており、宅建士の資格を持っていることも評価されています。また、宅建士の資格を取得することは、営業成績の向上にもつながります。専門家としての地位を手に入れることで、顧客からの信頼を獲得しやすくなるからです。
宅建士試験の勉強を通じて、不動産業務に必要なスキルアップを図ることもできるでしょう。つまり、宅建士の資格を持っていることは、実力向上のための大切なステップになるのです。資格取得と実力向上の両方を目指すことで、不動産業界で活躍できる可能性が高まります。
2-4.【イメージ④】長時間の勉強が必要だから
宅建士試験の合格には、長時間の勉強が必要だと言われています。
「長時間の勉強が必要だから、コスパが悪い」と考えている人もいるようです。確かに、宅建士は合格率の低い難関資格の一つで、独学で何年もかかったという話はよく聞きます。
しかし、正しい勉強方法を選べば、短期間でも十分に合格することができます。例えば、受験指導校を活用し、洗練された講義を受講すれば、効率的に知識を身につけることができるでしょう。また、過去問題を分析して、出題傾向を把握することも大切です。
限られた時間の中でも、正しい勉強方法を選択し、効率的に学習することができれば、合格への道が開かれるでしょう。勉強時間を確保することは大変かもしれませんが、宅建士の資格を取得するメリットを考えれば、努力する価値は十分にあります。
※宅建士試験合格に必要な勉強時間については、こちらの記事で詳しく解説しています
→【500時間必要?】宅建士試験の合格に必要な勉強時間について徹底解説!
3.【本当に役に立たない?】宅建を取る7つのメリット
それでは、本当に宅建士の資格は役に立たないのでしょうか。ここでは、宅建士を取得する7つのメリットについて説明します。
3-1.就職や転職に役立つ
宅建士の資格は、就職や転職において大きなアドバンテージになります。
例えば、不動産業界では、宅建士が求人の「歓迎条件」として記載されているケースが珍しくありません。宅建士の数が不足すると、営業に大きな支障が生じてしまうため、1人でも多くの宅建士を求めているのです。
【宅建士が不足するとマズい理由】
・宅建士の設置義務が設けられてるから(5人に1人以上)
・重要事項の説明は、宅建士でないとできないから
・契約書への記名も、宅建士がする必要があるから
また、不動産業界以外でも、宅建士の知識が活かせる職種は多岐に渡ります。例えば、金融、建設、保険、士業、公務員など、幅広い分野で、宅建士が評価されています。
宅建士の資格は就職や転職において、非常に強力な武器になります。特に不動産業界を目指す方にとっては、必須の資格と言えるでしょう。決して役に立たない資格ではありません。
※宅建が活かせる場面については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 宅建は就職や転職に有利?未経験も?不動産以外で活かせる仕事も紹介
3-2.年収アップにつながる
宅建士の資格は、年収アップにも直結します。例えば、多くの企業では、宅建士資格を保有する従業員に対して、資格手当を支給しています。前述の通り、法律で宅建士の設置義務が定められているため、資格手当を支給することで、必要な宅建士を確保しようとしているのです。
資格手当の相場は「月1万〜3万円」程度ですが、一部の企業では「月5万円」以上が支給されている場合もあります。年収ベースでは、数十万円以上のアップが見込めるでしょう。さらに、宅建士資格があれば、そもそも年収の高い仕事に就きやすくなります。
例えば、多くの宅建士が働く「不動産業」の平均年収は「521万4,800円」、「金融業」では「547万5,800円」となっており、日本人の平均年収と比べて、かなり高い水準です。(参考:厚生労働省 令和6年賃金構造基本統計調査 企業規模計(10人以上))
宅建士資格を活かせる職種は、高年収が期待できる傾向にあるのです。宅建士になると、資格手当による直接的な年収アップが期待できることに加え、高年収の仕事にも就きやすくなります。宅建士の資格取得は、年収アップを目指す上でも、非常に有効な手段だと言えるでしょう。
※宅建士の年収については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→宅建士の年収とメリットは?女性にもおすすめな理由を徹底解説
3-3.昇進しやすくなる
宅建士の資格は、キャリアアップにも役立ちます。特に不動産業界では、宅建士資格が、昇進の必須条件となっている企業も少なくありません。
宅建士試験に合格することで、一定の専門知識を有することが証明されるため、社内でも信頼されやすくなるのです。宅建士資格を取得することで、より責任ある立場へと昇進しやすくなるでしょう。また、不動産業界以外でも、宅建士資格が昇進に影響するケースは珍しくありません。例えば金融機関などでは、昇給や人事考課にプラスになる可能性があります。
3-4.顧客からの信頼の獲得につながる
宅建士資格を取得すると、顧客からも信頼を得やすくなります。「宅建士」は、不動産取引における専門家として、圧倒的な認知度を誇っているからです。
実際、宅建士試験は年間20万人もの受験生が挑戦する試験であり、その受験者数の多さは認知度の高さの裏返しだと言えます。不動産関連の資格は他にもたくさんありますが、宅建士ほどの知名度を持つ資格は他にありません。そのため、宅建士資格を保有していると、不動産の専門家として、顧客に認識されやすくなります。一定の知識と能力があることが伝わるため、信頼の獲得につながるのです。
3-5.副業の選択肢が広がる
宅建士の資格を取得すると、副業の選択肢も広がります。
例えば、
・宅建士として、独占業務を代行する
・ライターとして、不動産メディアの記事執筆を請け負う
・宅建士試験の講師を行う
など、様々な副業が考えられます。これらの仕事は、在宅でできる場合も多いため、自分のペースで働けるのもメリットです。
副業で得た収入は、旅行をしたり、趣味に充てたり、将来の資金として貯蓄したりと、自由に使うことができます。このように、宅建士の知識を活かした副業をすれば、本業とは別に大幅な収入アップを目指すことができるのです。宅建士は、本業のキャリアアップだけでなく、副業の選択肢を広げるためにも役立ちます。
※宅建士の副業については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 宅建士資格を活かしたオススメ副業4選!在宅・土日のみ・未経験もOK
3-6.独立開業を目指せる
宅建士のキャリアは、サラリーマンとして昇進するだけではありません。必要なスキルと経験を積んでいけば、独立開業を目指すこともできるのです。もちろん、独立開業には入念な準備が必要です。人脈の構築、事業計画の作成、資金の調達、事務所の確保など、クリアすべき課題は少なくありません。
しかし、その分リターンも大きいと言えるでしょう。独立開業すれば、年収1000万円以上を目指すことも夢ではありません。自分の努力次第で、収入を大きく伸ばすことができるのです。さらに、ワークライフバランスを重視して自分のペースで働くこともできます。会社の方針に縛られることなく、自分の裁量で仕事を進められるのは大きな魅力です。
サラリーマンとして安定的に働くか、独立開業して自由を手にするかは、個人の価値観によって異なります。しかし、選択肢の1つとして、「独立開業」できる可能性があることは、宅建士の大きなメリットです。
※宅建士の独立開業については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→【宅建士の独立開業】成功のコツと失敗しやすい4つの要因を解説
3-7.他の難関資格にもつながる
宅建士試験の学習は、他の難関資格の取得にもつながります。
宅建士試験では、条文の読み方や、法律的な思考法など、法律に関する幅広い知識が問われるからです。これらの知識は、行政書士や司法書士などの法律試験でも重要な要素となっています。例えば、宅建士試験で学んだ民法の知識は、行政書士や司法書士の試験対策にも役立ちます。また、宅建士試験の準備を通して身につけた集中力やモチベーション管理力も、他の試験勉強で大いに発揮されるでしょう。
宅建士は、不動産に関する専門資格ですが、同時に法律系国家資格の入口的な位置づけともなっています。宅建士取得後、自分のキャリアに応じたダブルライセンスを目指すことで、大きな相乗効果を生み出すことができるのです。
※宅建士からのキャリアアップについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
→司法書士・行政書士・宅建士のトリプルライセンスが最強!難易度も解説
4.注意点もある?事前に知っておきたいポイント
ここまで、宅建士の魅力について説明してきました。しかし宅建士には、いくつか注意すべきポイントもあります。ここでは、宅建士を目指す方が事前に知っておきたい2つの注意点を解説します。
4-1.合格するだけでは宅建士になれない
実は、宅建士試験に合格するだけでは、宅建士になることはできません。宅建士試験に合格した後は、資格登録を行い、宅建士証を交付してもらう必要があるからです。資格登録には、試験合格に加えて
・2年以上の実務経験
・登録実務講習の受講
のいずれかが必要です。
※宅建士の資格登録については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 宅建士登録の流れとは?必要書類や費用など宅建士証交付までの手順を全解説!
4-2.独学で合格するのは難しい
宅建士試験は、独学で挑戦する人も多い試験ですが、幅広い出題範囲が特徴の法律系資格であり、合格は決して簡単ではありません。例えば、令和5年度の宅建士試験の合格率は「17.2%」となっており、受験者全体のうち「6人に5人」は不合格となっています。
この数字は、受験指導校を利用している人も含めた全体の合格率であるため、独学者のみに絞ると、さらに低くなるでしょう。
独学で合格するためには、強い意志と計画的な勉強が不可欠です。独学でチャレンジする場合、ハードルの高さを理解した上で、十分な覚悟を持って臨む必要があるでしょう。
※宅建士試験合格のための勉強法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 宅建士試験に独学で合格するための効率の良い勉強法とは?後悔しないための注意点も解説」
※こちらも併せてお読みください。
→ 宅建の通信講座はなぜ伊藤塾がおすすめなのか?宅建士合格講座の魅力を徹底解説
5.まとめ
最後に、今回の記事の要点をまとめます。
◉宅建士は、決して役に立たない資格ではない
◉宅建士を取得すると数多くのメリットがある
◉就職や転職、昇進などのキャリアアップに役立つ
◉年収アップにも直結する
◉会社員以外の働き方もある(独立開業・副業など)
ネガティブな情報を耳にすることもあるかもしれませんが、宅建士は決して「やめとけ」という状況にはありません。むしろ、宅建士に対する需要は年々増加しています。
宅建士試験は、正しい勉強方法で計画的に進めていくことができれば、合格することは決して難しくはありません。
宅建士になりたいという強い想いがある方は、ぜひ法律資格専門指導校である伊藤塾をご活用ください。
「今年はさらにバージョンアップしたコースをご用意!!「2025年合格目標 宅建士合格講座」 のご紹介です!」