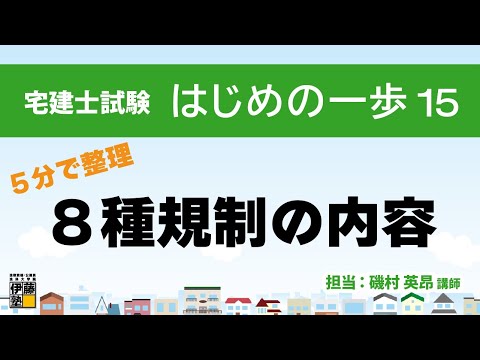宅建の「自ら売主制限(8種制限)」とは?覚え方と試験対策を解説
試験詳細
2025年09月04日


宅建士試験の中でも、「自ら売主制限(8種制限)」は毎年のように出題される重要テーマです。宅建業者が自ら売主となる取引では、買主が一般消費者であることが多く、知識や経験の差から不利益を受けやすいため、業者に一定の制限を課す仕組みが整えられています。
本試験では、この8つの制限の内容や細かい数字を正確に理解しているかどうかが問われます。覚えることが多く難しく感じやすい分野ですが、制度の目的を意識しながら、語呂合わせや表を使って整理すれば効率よく暗記できます。
この記事では、「自ら売主制限(8種制限)」がどのような場面で適用されるのかを確認したうえで、8つの制限内容を一覧にして整理します。この分野を得点源にするためにも、ぜひ覚え方のコツやポイントを確認してみてください。
【目次】
1.自ら売主制限(8種制限)とは?
「自ら売主制限(8種制限)」とは、宅建業者が自ら売主として宅地や建物を販売する際に課される特別なルールのことです。
宅建業者は不動産取引の専門家であるため、知識や経験の少ない一般消費者と比べると立場が強くなりやすい傾向があります。そのままでは消費者が不利益を受ける可能性があるため、宅建業法で8つの制限を定めて、取引の公平性を確保しています。
宅建士試験では、この8種制限の内容や数字が頻繁に出題されるため、内容を正確に理解しておく必要があります。制度の背景を押さえておけば、単なる「暗記」ではなく「理解」して身につき、応用問題にも対応しやすくなります。
1-1. 「自ら売主制限(8種制限)」が適用される場面
「自ら売主制限(8種制限)」が適用されるのは、売主が宅建業者で、買主が一般消費者である場合です。専門知識を持つ業者と経験の少ない消費者の間で力の差が生じるため、消費者を守る仕組みとして各種規制が適用されます。
逆に、売主・買主が双方とも宅建業者である取引や、一般消費者同士の取引では、この制限は適用されません。宅建業者同士なら知識や交渉力に差がなく、また消費者同士の取引では業者による優位性が存在しないからです。
試験ではこの前提条件を問う問題が多いため、しっかり確認しておくことが大切です。
2.自ら売主制限(8種制限)一覧
「自ら売主制限」には、全部で8つのルールがあります。
①自己の所有に属しない宅地・建物の売買契約締結に関する制限
②事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等(クーリングオフ制度)
③損害賠償額の予定等の制限
④手付の額の制限等
⑤担保責任についての特約の制限
⑥手付金等の保全
⑦宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限
⑧所有権留保等の禁止
ここでは、それぞれの制限について順に整理していきます。
①自己の所有に属しない宅地・建物の売買契約締結に関する制限
宅建業者は、自分の所有に属さない宅地や建物について、自ら売主となって売買契約を結ぶことはできません(宅建業法第33条の2)。 これは、業者がまだ権利を持っていない不動産を売ろうとすると、買主が大きなリスクを負うことになるからです。
例えば、宅建業者が他人の土地を「将来購入する予定だから」といって勝手に売却契約を結んでしまえば、買主は代金を支払ったのに物件を引き渡してもらえない事態が起こり得ます。こうしたトラブルを防止するために、この制限が設けられています。
②事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等(クーリングオフ制度)
宅建業者の事務所やモデルルーム以外の場所で契約を申し込んだ場合、買主はクーリングオフ制度を利用して契約を取り消すことができます(宅建業法第37条の2)。クーリングオフとは、一定期間内であれば消費者が自由に契約を解除できる制度のことです。
これは、消費者が冷静な判断をする余裕のない状況で、高額な契約を結ばされるのを防ぐための仕組みです。例えば、喫茶店や自宅に営業担当者が来て強引に勧誘した場合でも、買主は後から契約を撤回できます。
宅建業法では、この制度を「業者が自ら売主となる場合」に認めており、買主はクーリングオフについて書面で告げられた日から8日以内であれば無条件で契約を解除できます。
試験では「クーリングオフができる場所・できない場所」や「期間」が問われることが多いので、数字とセットで覚えておくことが重要です。
③損害賠償額の予定等の制限
宅建業者が自ら売主となる契約では、あらかじめ損害賠償額や違約金の金額を定めることができます。しかし、その上限は「代金の20%まで」と法律で制限されています(宅建業法第38条)。
もし制限がなければ、業者が「違約したら代金の50%を請求する」といった過大な条件を設定し、買主に不当に大きな負担を与える危険があります。こうした不公平を避けるために、20%という上限が設けられていることを理解しておきましょう。
④手付の額の制限等
宅建業者が自ら売主となる場合、手付金の額は「代金の20%以内」と定められています(宅建業法第39条)。手付とは、契約を結ぶ際に買主が売主へ支払う金銭で、契約の証拠や解約の権利に関連する重要なお金です。
もしこの制限がなければ、業者が過度に高額な手付金を要求し、買主が解約したくても事実上できなくなるなど、不利な状況に追い込まれる可能性があります。そこで、消費者保護の観点から上限が20%と決められています。
⑤担保責任についての特約の制限
宅建業者が自ら売主となる場合、種類や品質の不適合に関する担保責任を免除する特約を設けることはできません(宅建業法第40条)。担保責任とは、売買契約で引き渡した宅地や建物に欠陥があった場合に、売主が負う責任のことです。
例えば、引き渡された建物に重大な欠陥(雨漏りや基礎部分のひび割れなど)があった場合、買主は修補や損害賠償を請求できます。ところが、もし売主が「一切責任を負わない」とする特約を結んでしまえば、買主は保護を受けられなくなってしまいます。
この不公平を防ぐため、宅建業法では担保責任の特約に制限を設けています。具体的には、契約不適合に関する通知期間を2年以上にする特約は有効ですが、それ以外で買主に不利になる特約は無効としています。
⑥手付金等の保全
宅建業者が自ら売主となる場合、買主から受け取る手付金や中間金については、保全措置を講じなければなりません(宅建業法第41条、第41条の2)。保全措置とは、もし業者が倒産した場合でも、買主が支払った金銭を返還してもらえるようにする仕組みです。これにより、買主は安心して高額な取引ができるようになります。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は保全が不要です。
・買主に所有権移転登記を行ったとき
・未完成物件で、代金の5%以下かつ1,000万円以下のとき
・完成物件で、代金の10%以下かつ1,000万円以下のとき
保全措置の方法は、以下の4種類です。
①銀行との保証委託契約
②保険会社との保証保険契約
③指定保管機関との手付金等寄託契約
④買主との質権設定契約
ただし、③及び④は完成物件でのみ利用可能で、未完成物件には使えません。
試験との関係では、手付金等の”受領前に”保全措置を講じなければならないことも覚えておきましょう。
⑦宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限
宅建業者が自ら売主となって割賦販売を行う場合、買主に不利益が及ばないよう、特別な制限が設けられています。買主が分割金を滞納したからといって、業者はいきなり「契約解除」や「残代金の一括請求」をすることはできません(宅建業法第42条)。
割賦販売とは、宅地や建物を分割払いで購入する契約のことです。住宅のように高額な不動産を取得するときによく利用される取引形態です。
割賦販売での契約の場合、業者が契約を解除したり残代金の一括請求をしたりするためには、まず30日以上の期間を定めて、書面で支払いを催告しなければなりません。その期間内に買主が履行しなかったとき、初めて解除や一括請求が可能になります。
⑧所有権留保等の禁止
宅建業者が割賦販売(分割払い)を行うときは、原則として物件の引き渡しまでに所有権を買主へ移転登記しなければなりません。これは、買主が代金を払っているのに所有権を得られないと、不動産を自由に利用できず不利益が大きいためです。
ただし、業者側にとって負担が大きすぎる場合もあります。例えば、3,000万円の物件で手付金100万円しか受け取っていない段階で、すぐに所有権を移せと言われれば、売主にとってリスクが大きすぎます。
そこで、次のような場合には所有権を留保できる例外が認められています。
・受け取った代金が総額の10分の3以下の場合
・10分の3を超えて受け取っていても、残代金について買主が担保措置をとる見込みがない場合
例えば、3,000万円の物件に関する売買契約であれば、900万円が所有権留保の可否に関するラインとなります。まだ500万円しか代金を受け取っていない場合、業者は買主に所有権移転登記等を行う必要はありません。
3.自ら売主制限(8種制限)の覚え方
「自ら売主制限(8種制限)」は、宅建士試験でも頻出のテーマですが、内容が細かく数字も多いため「覚えるのが大変」と感じる受験生が多い分野です。ただし、制度の目的や背景を理解し、効率的に記憶する方法を組み合わせることで、得点源にすることができます。
ここでは、学習をスムーズに進めるための代表的な覚え方を紹介します。
3-1. 制度の趣旨・目的を理解する
「自ら売主制限(8種制限)」は、宅建業者と一般消費者の間にある知識や立場の差を埋めるための仕組みです。宅建業者は取引のプロである一方、買主の多くは不動産取引に不慣れな一般消費者です。そのままでは業者が有利になりすぎ、消費者が不利益を受ける可能性があります。
例えば、業者が高額な手付金を要求したり、契約不適合責任を免除する特約を結んだりすれば、消費者は大きな損失を被る恐れがあります。こうした不公平を防ぐために、宅建業法で8つの制限を定め、消費者保護を図っているのです。
このように、制度の目的を理解すると「なぜこの制限があるのか」が見えてきます。単に数字や条文を暗記するよりも、背景を押さえて学習した方が記憶に残りやすく、試験本番でも応用力を発揮できます。
3-2. 語呂合わせで覚える
「自ら売主制限(8種制限)」は、全部で8つのルールを覚える必要があるため、多くの受験生にとって負担の大きい分野です。特に、細かい数字や条件が絡むため、ただ丸暗記しようとすると混乱してしまいがちです。
そこで有効なのが語呂合わせを使った記憶法です。8つの制限の内容を自分なりに語呂合わせで覚えてみたり、リズムに置き換えたりすることで、複雑な内容をひとまとまりのフレーズとして整理できます。声に出して繰り返したり、ノートに書き出したりすることで、短時間でも全体像をスムーズに思い出せるようになります。
また、語呂合わせは学習のリズムをつくるツールとしても役立ちます。語呂をきっかけに思い出した内容を、解説や表とリンクさせて確認すれば、理解と記憶を同時に強化できるでしょう。
3-3. 細かい数字は表で一覧にして覚える
「自ら売主制限(8種制限)」は、複数の制限に細かい数字が設定されているため、文章だけで覚えようとすると混乱しやすい分野です。こうした数字を正しく整理するには、表にまとめて一覧化する方法が効果的です。
表にすれば、制限の内容と数字の対応関係が一目で確認でき、知識の抜けや混同を防ぐことができます。また、作成した表は直前期の復習にも適しており、効率的に記憶を定着させられるのが大きな利点です。
市販のテキストや受験指導校の教材に載っている表を活用するのも効果的ですが、自分なりに表を作ることも有効です。自分の言葉やレイアウトで整理すると記憶が定着しやすくなりますし、弱点が浮き彫りになります。状況に応じて使い分け、復習しやすい形を作ることが合格への近道になります。
3-4. 過去問演習で頻出知識を定着させる
「自ら売主制限(8種制限)」は、宅建士試験で毎年のように出題される重要分野です。条文や数字を覚えるだけで安心してしまうと、本番で「どんな形で問われるのか」がイメージできず、正しく解答できないことがあります。
そこで必ず取り入れたいのが過去問演習です。過去の問題を解くことで、出題のされ方や数字の使われ方を実感でき、記憶した知識を「使える知識」へと変えることができます。間違えた問題は解説を確認し、頭を整理し直すことで理解不足の部分を補えます。
学習効果を高めるためには、「覚える → 解く → 確認する → 再度解く」という流れを繰り返すことが大切です。このサイクルを続ければ、知識が定着し、本番でも迷わず解答できる力が身につきます。
4.宅建士試験を短期間で突破したいなら伊藤塾の「宅建士合格講座」がお勧め
宅建士試験に効率よく合格するためには、基礎から応用まで体系的に学べるカリキュラムと、無理なく継続できる学習環境が欠かせません。もし独学での学習に限界を感じたら、法律系国家資格において圧倒的な合格実績を持つ伊藤塾が提供する「宅建士合格講座」での学習がお勧めです。
講義は1コマ約30分とコンパクトで、倍速視聴も可能なため、忙しい社会人や学生でもスキマ時間を活用して学習を進められます。また、学習目的や経験に応じて選べる複数のコースが用意されており、オリジナル教材と演習問題、模擬試験に加えて、一問一答式の演習アプリ「It’s D」を利用できるなど実践力を鍛える仕組みも充実しています。
さらに、オンライン質問会やスクーリング、無料カウンセリングといったフォロー体制も整っているため、不安を解消しながら安心して学習を継続できます。短期間で効率よく合格を目指したい方は、ぜひ伊藤塾の講座を活用してみてください。
※こちらも読まれています。
5.「自ら売主制限(8種制限)」に関するQ&A
Q1.「 自ら売主制限(8種制限)」の出題頻度はどれくらい?
A. 宅建士試験では、ほぼ毎年のように出題される重要分野です。形式としては「正誤判定」や「数字の適否」を問う問題が多く、知識が曖昧だと失点につながりやすい分野です。したがって、優先的に学習する価値があります。
Q2. 試験本番で細かい数字を忘れてしまったときの対処法はありますか?
A. 万が一、数字を正確に思い出せない場合は、制度の趣旨・目的から考えて「消費者保護に反するような内容は誤り」と判断するのが有効です。例えば「手付金の割合が高すぎる」「催告なしに解除できる」など、消費者に極端に不利な選択肢は誤答である可能性が高いです。
Q3. 8種制限の中で特に試験で出題されやすいものはどれですか?
A. 最も出題されやすいのはクーリングオフ制度です。どのような場所で申し込みをした場合に適用されるのか、また除外されるケースは何かといった点が出題されやすいため、必ず押さえておく必要があります。その他の7つの制限についても全て出題の可能性があるため、偏りなく学習することが重要です。
6.「自ら売主制限(8種制限)」の内容と試験対策まとめ
本記事では、宅建士試験の重要テーマである「自ら売主制限(8種制限)」について、具体的な制限内容と試験対策について解説しました。
以下にポイントをまとめます。
◉「自ら売主制限(8種制限)」 は、宅建業者が自ら売主として宅地や建物を販売する際に適用される、買主である一般消費者を保護するための特別なルールです。
◉この制限は、専門知識を持つ宅建業者と経験の少ない一般消費者の間にある知識や立場の差から、消費者が不利益を被ることを防ぐ目的で設けられています。
◉宅建士試験では毎年出題される頻出分野であり、「正誤判定」や「数字の適否」を問う問題が多いです。
◉8つの制限内容
- 自己の所有に属しない宅地・建物の売買契約締結に関する制限
- 事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等(クーリングオフ制度)
※宅建業者の事務所やモデルルーム以外の場所で契約を申し込んだ場合、買主は書面で告げられた日から8日以内であれば無条件で契約を解除できます。この制度は最も出題されやすいため、場所や期間を正確に覚えることが重要です。 - 損害賠償額の予定等の制限
※損害賠償額や違約金の上限は、代金の20%までと制限されています。 - 手付の額の制限等
※手付金の額は、代金の20%以内と定められています。 - 担保責任についての特約の制限
※宅建業者は、種類や品質の不適合に関する担保責任を免除する特約を設けることはできません。ただし、通知期間を2年以上とする特約は有効です。 - 手付金等の保全
※買主から受け取る手付金や中間金には保全措置を講じる必要がありますが、特定の条件(所有権移転登記完了時、物件の完成度と金額など)に該当する場合は不要です。保全措置は手付金等の受領前に講じなければなりません。 - 宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限
※割賦販売において買主が分割金を滞納しても、業者は30日以上の期間を定めて書面で催告しなければ、契約解除や残代金の一括請求はできません。 - 所有権留保等の禁止
※割賦販売では原則として物件の引き渡しまでに所有権を買主へ移転登記しなければなりません。ただし、受け取った代金が総額の10分の3以下の場合など、特定の例外が認められています。
◉試験対策のポイント
・なぜこの制限があるのか制度の趣旨・目的を理解することで、単なる暗記ではなく「理解」として知識が定着し、応用問題にも対応できます。
・8つの制限や細かい数字を効率的に覚えるために、語呂合わせや自分なりの表を作成して整理することが有効です。
・知識を「使える知識」に変えるため、過去問を解き、間違えた問題は解説を確認して復習するサイクルを繰り返しましょう。
以上です。
宅建士試験の「自ら売主制限(8種制限)」は、その複雑さから多くの受験生が苦手とする分野ですが、ポイントを押さえて学習すれば得点源にすることができます。
短期間で効率よく合格を目指すなら、法律系国家資格で豊富な実績を持つ伊藤塾の「宅建士合格講座」 をぜひご活用ください。伊藤塾はあなたのチャレンジを全力でサポートさせていただきます。