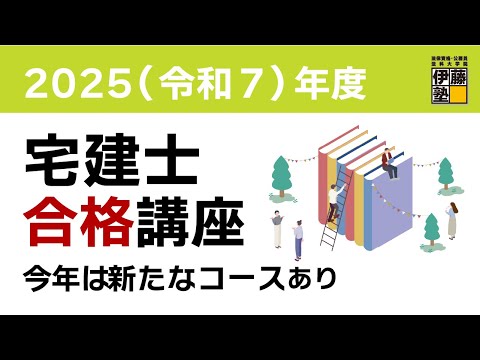宅建の相続で得点するコツとは?基礎から計算方法まで徹底解説
試験詳細
2025年10月06日


宅建士試験の中でも、相続に関する問題は毎年出題される重要な分野です。しかし、日常生活であまり関わることのない相続については、実感が沸かずにイメージしづらかったり、計算方法が複雑で難しいと感じている人も多いのではないでしょうか?
相続に関する知識は不動産業界での実務にも直結することから、宅建士試験においても重要な位置を占めています。確実に得点する力を身につけられれば、宅建士試験合格に一歩近づくでしょう。
この記事では、宅建士試験で相続分野を得点源にするために必要な基礎知識から計算方法まで、わかりやすく解説します。また、実際に出題された過去問の解説も行っていますので、具体的にどのような思考で計算問題等を解けばいいかもわかるようになります。
相続分野が得意分野となるよう、ぜひ一緒に学んでいきましょう。
【目次】
1. 宅建士試験における「相続」の位置付け
宅建士試験における「相続」は、試験の中でも重要なテーマであり、「権利関係」分野における「家族法」の一部として出題されます。
相続に関連する問題では、土地や建物の権利が誰に帰属するかが問われるため、相続に関する基本的な知識は宅建士として業務を行う上で必要不可欠です。
特に出題されやすいテーマには、「法定相続人と法定相続分」「代襲相続」「遺留分」などがあります。これらはすべて、遺産を誰がどのように受け継ぐのかという重要な問題であり、宅建士試験においては毎年1問程度が出題される頻出テーマです。場合によっては、相続分野から2問出題されることもあるので、過去問を解きながら理解を深めていくことが重要です。
相続問題は、単に理論的な知識だけでなく、実務的な視点でも重要です。例えば、相続登記の手続きや空き家問題など、相続と不動産が関わる問題は近年注目されています。相続登記の義務化や相続に関する様々な法改正などの関係もあり、相続に関する出題は今後も継続すると予想されます。相続に関する基本的な知識をしっかり身につけ、試験での得点源として活用できるようにしておきましょう。
2. 宅建士試験における相続の基礎知識
相続は、民法において定められた仕組みであり、被相続人(亡くなった人)が所有していた財産や権利・義務を、一定の親族が引き継ぐ制度です。宅建士試験では、「誰が相続人になるのか」「どのくらいの割合で相続するのか」といった基礎的な内容が出題されます。試験対策としては、全体の流れを押さえつつ、相続分の計算など頻出パターンに慣れておくことが重要です。
2-1. 相続の概要
相続とは、被相続人の財産や権利・義務を、相続人が受け継ぐことを意味します。相続の対象には、現金・預貯金・不動産・有価証券といったプラスの財産だけでなく、借金やローンなどマイナスの財産も含まれます。
例えば、住宅ローンの残る家を相続した場合、そのローン債務も一緒に引き継ぐことになります。こうしたリスクを避けたい場合には、相続放棄や限定承認といった方法も用意されています。
誰が相続できるか、またどの程度の割合で相続するかについては、民法で細かく定められています。ただし、遺言が存在する場合には、原則としてその内容が優先されます。さらに、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって、柔軟に分け方を決めることも可能です。
このように、相続には法律上のルールがある一方で、現実の事情に応じて調整できる側面もあります。宅建士試験では、これらの基礎を正確に理解しておくことが重要になります。
2-2. 法定相続と指定相続
相続には、大きく分けて「法定相続」と「指定相続」の2つの方法があります。それぞれの仕組みと違いを理解しておくことが、宅建士試験の対策としても重要です。
法定相続とは、民法の規定に従って相続を行う方法です。被相続人の配偶者や子ども、親などとの関係に応じて、誰が相続人になるか、そしてそれぞれがどの程度の割合で財産を引き継ぐのかがあらかじめ決められています。例えば、配偶者と子が相続人であれば、それぞれ2分の1ずつ相続するのが基本です。
一方で、指定相続は、被相続人が生前に作成した遺言の内容に基づいて行う相続です。遺言によって、財産の分け方を自由に決めることができ、通常は法定相続よりも優先されます。つまり、法定相続のルールがあっても、遺言がある場合はその指示に従って遺産を配分することになります。
宅建士試験では、どちらの相続方法がどのような場面で適用されるのか、また法定相続と指定相続の優先関係などが問われることがあります。基本的な違いを正確に理解しておきましょう。
2-3. 法定相続人の範囲・順位・割合
相続では、誰が財産を引き継ぐことができるか、またどの程度の割合で受け取れるかが法律によって細かく定められています。
【 法定相続人の範囲および順位】
法定相続人とは、法律上、相続の権利を持つ人のことを指します。その範囲や優先順位は、被相続人との関係性に応じて以下のように決められています。
| 順位 | 相続人の種類 | 補足 |
| 常に相続人 | 配偶者 | 配偶者は順位に関係な く常に相続人となる |
| 第1順位 | 直系卑属 (子・孫など) | 被相続人より下の世代 (血縁関係)が対象 |
| 第2順位 | 直系尊属 (父母・祖父母) | 第1順位がいない場合 に相続権が発生 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 第1・第2順位の相続人 がいない場合に限り相 続権が生じる |
例えば、子どもが相続放棄をし、両親がすでに他界していた場合には、配偶者および兄弟・姉妹が相続権を持ちます。
また、相続が開始した時点ですでに子が亡くなっていた場合は、その子(孫)が相続する「代襲相続」が認められます。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は1代限りで、甥・姪までとなります。甥や姪の子どもには相続権は及びません。
【 法定相続分(相続割合)】
誰がどれだけの割合で遺産を相続できるのかも、法律によって決まっています。以下は代表的なケースです。
| 相続人の 組み合わせ | 配偶者 の取り分 | その他の相続人 の取り分 |
| 配偶者と子ども がいる場合 | 2分の1 | 子ども全体で 2分の1 (人数で等分) |
| 配偶者と親(直 系尊属)の場合 | 3分の2 | 親全体で 3分の1 (人数で等分) |
| 配偶者と兄弟姉 妹がいる場合 | 4分の3 | 兄弟姉妹全体で 4分の1 (人数で等分) |
このように、同じ配偶者でも、誰と一緒に相続するかによって取り分が異なります。
【相続人にならないケース】
民法上、相続人として認められるのは法律に明記された親族に限られます。被相続人とどれだけ親しくしていても、次のような関係にある人は相続人にはなりません。
・内縁関係(事実婚)にある配偶者とその子 ※ 認知した場合には第1順位の相続人となる
・離婚した元配偶者
・養子縁組をしていない配偶者の連れ子
・血縁のない義理の家族(義父母・義理の兄弟姉妹など)
例えば、長年連れ添った内縁の妻であっても、婚姻届を提出していなければ法律上の配偶者ではないため、相続権は発生しません。相続人の範囲を曖昧ではなく正確に理解しておくことが、相続問題を解く上での基本となります。
なお、法定相続人に該当しない親族であっても、療養看護などを通じて被相続人の財産の維持や増加に特別な寄与をした場合には、「特別寄与分」を請求できる制度があります。これは相続人ではない親族が、無償で被相続人に尽くした労務や貢献に対して、金銭での補償を受けられるようにするための仕組みです。
請求には相続人との協議が必要であり、合意できない場合には家庭裁判所に申立てを行うことになります。
試験対策としては、「法定相続人でなくても一定の条件下で金銭的な主張ができる制度」として覚えておくと良いでしょう。
2-4. 遺留分・遺留分侵害額請求
相続では、被相続人が遺言によって財産の分配先を自由に決めることができますが、すべてを自由に分けられるわけではありません。相続人の中には「最低限の取り分」が法律で保障されている人がおり、これを「遺留分」と呼びます。
遺留分は、被相続人が特定の相続人だけに有利な遺言を残した場合でも、その他の相続人が全く相続できないような状況にならないように設けられている制度です。例えば、「長男に全財産を譲る」という遺言があっても、他の法定相続人には一定の割合で財産を受け取る権利が残されます。
この遺留分が侵害された場合、相続人は遺留分侵害額請求という手続きによって、自分の取り分に相当する金銭を他の相続人などに対して請求できます。
遺留分が認められるのは、配偶者、直系卑属(子や孫)、直系尊属(父母や祖父母)に限られます。兄弟姉妹には遺留分がないため、たとえ相続人であってもこの権利を主張することはできません。
遺留分の割合は、法律で以下のように規定されています。
| 相続人 | 遺留分全体の割合 (相対的遺留分) | 遺留分の割合 (個別的遺留分) |
| 配偶者のみ | 遺産全体の2分の1 | 遺産全体の2分の1 |
| 子(直系卑属) のみ | 遺産全体の2分の1 | 遺産全体の2分の1 |
| 父母(直系尊属) のみ | 遺産全体の3分の1 | 遺産全体の3分の1 |
| 配偶者と子 (直系卑属) | 遺産全体の2分の1 | それぞれ遺産全体の 4分の1 |
| 配偶者と父 母(直系尊属) | 遺産全体の2分の1 | 配偶者が遺産全体の 6分の2 父母が遺産全体の 6分の1 |
| 配偶者と 兄弟姉妹 | 遺産全体の2分の1 | 配偶者が遺産全体の 2分の1 |
※ 相続人となる直系卑属および直系尊属が複数いる場合は、その人数で等分します。
遺留分について覚える際は、以下のポイントを意識するのがお勧めです。
・遺留分全体の割合が3分の1になるのは、直系尊属のみが相続人となる場合のみ
・個別の遺留分は、遺留分全体に法定相続分をかけて計算する
この表をもとに、遺留分の「全体に対する割合」と「各相続人が実際に請求できる遺留分の算出方法」を理解しておくと、本試験における計算問題にも対応しやすくなります。
3. 【過去問解説】宅建士試験における相続分野の出題例
ここでは、宅建士試験で実際に出題された相続分野に関する問題を解説していきます。法定相続分などの計算問題が苦手な方は、どのように正解を導くかの思考過程を学びましょう。
3-1. 相続に関連する基礎知識を問う問題
【問 7】 甲建物を所有するAが死亡し、Aの配偶者Bが甲建物の配偶者居住権を、Aの子Cが甲建物の所有権をそれぞれ取得する旨の遺産分割協議が成立した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 遺産分割協議において、Bの配偶者居住権の存続期間が定められなかった場合、配偶者居住権の存続期間は20年となる。
2 Bが高齢となり、バリアフリーのマンションに転居するための資金が必要になった場合、Bは、Cの承諾を得ずに甲建物を第三者Dに賃貸することができる。
3 Cには、Bに対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務がある。
4 Cは、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。
出典:令和5年度問題 第7問|一般財団法人 不動産適正取引推進機構
【解説】
近年、法改正の行われた配偶者居住権に関する知識を問われる問題です。重要な法改正については本試験でも問われることが多いので、重点的に学習しておく必要があります。
1.配偶者居住権の存続期限は、原則として終身です(民法1030条)。被相続人の配偶者における生活の安定を図り、老後の生活資金を確保しやすくすることが制度趣旨であることを考えると、20年という期間を設定する必要がないからです。
2. 配偶者居住権は、あくまでも残された配偶者の居住地を確保するために設けられた制度であり、所有権を有している訳ではありません。所有者に黙って勝手に賃貸すると所有者に迷惑がかかることもあるため、賃貸するのであれば所有者の承諾が必要になります(民法1032条3項)。
3. 配偶者居住権は、所有権とは別に認められる制度です。被相続人もしくは相続人名義にもかかわらず別の人物が住んでいるとなると、第三者とのトラブルに発展する可能性があります。そこで、民法ではその不動産について責任のある所有者に、配偶者居住権の登記義務を課しています(民法1031条)。
4. 固定資産税や建物の修繕費などの通常の必要費について支払い義務を負うのは、所有者ではなく配偶者居住権を持つ人です。実際に住んでいる人が生活に必要な費用を支払うのは当然と言えるでしょう。
3-2. 法定相続分について計算をさせる問題①
【問 9】Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが死亡した場合における法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。1 Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1
2 Aが2分の1、Cが6分の1、Fが6分の1、Gが6分の1
3 Aが2分の1、Gが2分の1
4 Aが2分の1、Cが4分の1、Gが4分の1
出典:令和3年度問題(10月試験) 第9問|一般財団法人 不動産適正取引推進機構
【解説】
法定相続分に関する計算問題です。文章のままだと相続関係が見えにくいので、まずは自分なりにわかりやすく相続図を作成しましょう。その上で、前述した法定相続割合に基づいてそれぞれの相続分を計算していきます。事実関係がわかりにくいので、誰が相続人であるかをまず確定させるとわかりやすいです。
A:配偶者は常に相続人となる
B:死亡しているうえ、そもそも相続人ではない
C:連れ子はDと血縁関係にないので、養子縁組をしない限り法定相続人にならない
D:被相続人
E:離婚した配偶者は相続人にはならない
F:離婚していても、前妻との間に生まれた子は相続人となる
G:離婚していても、前妻との間に生まれた子は相続人となる
以上から、本問における法定相続人は、A・F・Gとなります。本文には親権について書かれていますが、法定相続人を決定する際に親権の有無は関係ありません。ここまで分かれば、具体的な法定相続割合がわからなくても、正解の選択肢である1を選択できます。
なお、配偶者と子が相続人になる場合の相続分は、以下の通りです。
配偶者:2分の1
子:2分の1の財産をFとGと等分する。つまり、それぞれ4分の1ずつが法定相続分となる。
3-3. 法定相続分について計算をさせる問題②
【問 8】1億2,000万円の財産を有するAが死亡した場合の法定相続分についての次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものの組み合わせはどれか。
ア Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。
イ Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、B及びCがそれぞれ3,000万円、Dが6,000万円である。
ウ Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。
エ Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、E及びFがそれぞれ3,000万円、Gが6,000万円である。
1. ア、ウ
2. ア、エ
3. イ、ウ
4. イ、エ
出典:令和2年度問題(12月試験) 第8問|一般財団法人 不動産適正取引推進機構
【解説】
具体的な法定相続分を計算させる問題です。この問題においても、わかりやすいように相続関係がわかる図を自分で作成すると計算しやすくなります。本問では、ア・イおよびウ・エがそれぞれ同じ事例になっているため、それぞれに分けて解説します。
まず、ア・イの事例について、相続人であるB・C・Dがそれぞれ代襲相続をしているため、関係性がわかりにくくなっています。一見すると、全ての相続人が平等に相続するようにも見えますが、B・CおよびDはそれぞれ代襲相続元が異なります。B・Cは長男が相続する分(2分の1)を、Dは次男が相続する分(2分の1)をそれぞれ代襲するため、具体的な相続分は以下の通りとなります。
B・C:1億2000万円の2分の1である6000万円を等分するため、それぞれ3000万円
D:1億2000万円×2分の1=6000万円
次に、ウ・エの事例について、祖父母が相続人となる場合、代襲相続という概念はありません。つまり、相続人であるE・F・Gがそれぞれ均等に遺産を相続することになります(全て第2順位の相続人)。よって、1億2000万円を3等分して4000万円がそれぞれの法定相続人分となります。
4. 宅建士試験で相続問題を落とさないためのポイント
相続分野で確実に得点するためには、細かな知識を丸暗記するのではなく、まずは相続の全体像を掴むことが大切です。学習の初期段階では、相続の流れを大まかに理解し、自分なりに家系図や相続関係図を手書きして整理してみましょう。例えば、被相続人と相続人の関係性を図で確認すると、誰がどのような順位や割合で相続するのかが視覚的に理解しやすくなります。
次に、本試験に向けた対策として意識したいのが「出題傾向を重視した学習」です。相続の出題は毎年1〜2問程度と限られているため、全範囲を深掘りしようとすると時間対効果が悪くなります。過去問を繰り返し解くことで、出題されやすいパターンを体得し、必要なポイントに絞って学習を進めることが効率的です。
また、相続問題には頻出の「法定相続分の計算」や「代襲相続」など、繰り返し出題されるテーマがあります。頻出テーマについては、具体例を交えながら演習を重ねることで、本試験でのひかっけにも対応できるようになります。法改正についても意識しつつ、確実に1点を取りにいく意識で取り組むことが合格への近道となります。
※宅建士試験の勉強法に関してはこちらの記事にて詳しく解説しています。
→ 宅建士試験初心者の勉強方法を6つのステップで解説!科目別の攻略法も
→ 宅建士試験に独学で合格するための効率の良い勉強法とは?後悔しないための注意点も解説
5. 宅建士試験の相続問題に関するQ&A
Q. 宅建士試験の相続問題は難しい?捨てるべき?
A. 相続問題は確実に得点できるよう対策することをおすすめします。
宅建士試験で出題される相続問題の難易度は、決して高くありません。全体の7割以上を得点しなければ合格できない試験において、捨て問を作るのはもったいないです。出題される内容は基礎的な用語や法定相続人・相続分の理解が中心で、極端に難解な応用問題はほとんど見られません。学習範囲もそれほど広くないため、正しく対策すれば得点源にできます。
Q. 宅建士試験の相続問題について配偶者がいない場合はどうなる?
A. 相続順位に従い、子どもや親、兄弟姉妹が相続人となります。
民法では、法定相続人の順位が定められています。配偶者がいない場合、まずは直系卑属(子・孫)が相続人となります。子どもがいなければ直系尊属(父母・祖父母)、それもいなければ兄弟姉妹が相続人になります。また、子どもが亡くなっている場合は、孫が代襲相続人として権利を持ちます。なお、相続放棄をした場合、代襲相続は発生しないため注意が必要です。
6. 宅建士試験の相続分野を得意分野にするなら受験指導校の活用がおすすめ
宅建士試験で出題される相続分野の問題について、民法に基づいた専門用語や制度の理解が求められるため、独学での学習に不安を感じる人も多いでしょう。もし独学での対策に不安を感じたら、伊藤塾の「宅建士合格講座」を活用することをお勧めします。
この講座は、法律初学者でも無理なく学べるように設計されており、1コマ約30分の講義と、理解を深めやすい洗練されたテキストで構成されています。本試験に合格するために必要な知識を詰め込んだ内容となっているため、学習効率が非常に高いのが特長です。倍速再生にも対応しており、通勤時間やスキマ時間を活用しながら、着実に力をつけることができます。
全科目を網羅した「スタンダードコース」、得点が難しい権利関係(民法等)が充実した「スタンダードコース プラス」、民法の学習経験者のための「法律既修者コース」が用意されているので、学習状況に合わせて最適なコースを選択できます。
また、近年の出題傾向を徹底的に分析した問題演習や、過去問の反復学習がしやすい一問一答式の「It’s D」アプリも活用可能です。
さらに、オンライン質問会やカウンセリング、スクーリングといった手厚いサポートも整っているため、独学でつまずきがちな部分も講師と一緒に解決しながら学習を進められます。法律の基礎力から実戦的な解法スキルまでバランスよく身につけたい人にとって、非常に心強い講座と言えるでしょう。
※こちらも読まれています。
→ 宅建の通信講座はなぜ伊藤塾がおすすめなのか?宅建士合格講座の魅力を徹底解説
7.宅建士試験の相続問題を得点源にする方法まとめ
本記事では、宅建士試験の相続分野を確実に得点源にするための考え方や具体的な学習方法について解説しました。
最後に、ポイントをまとめます。
◉宅建士試験において相続は「権利関係」分野の重要なテーマであり、毎年1〜2問出題されるため、確実に得点できるよう対策すべき分野です。
◉相続の理解には、被相続人の財産や権利・義務を相続人が受け継ぐ仕組みの把握が重要であり、「法定相続」「指定相続」といった相続方法や、その優先関係を正確に理解する必要があります。
◉特に出題されやすいテーマとして、「法定相続人の範囲・順位・割合」「代襲相続」「遺留分・遺留分侵害額請求」 が挙げられます。
◉複雑な相続関係や計算問題を視覚的に理解するためには、家系図や相続関係図を作成し、図表を活用した学習が推奨されます。
◉過去問を繰り返し解き、「法定相続分の計算」や「代襲相続」など頻出の計算問題に慣れること が、本試験でのひっかけ問題にも対応するための効率的な学習法です。
以上です。
もしあなたが、「法定相続分の計算が苦手」「法律用語が難しくて理解できない」など独学での対策に不安を感じているのなら、法律初学者でも無理なく学べるよう設計された伊藤塾の「宅建士合格講座」がおすすめです。無駄のない効率的な学習、豊富な演習、スキマ時間を活用できる一問一答式のアプリ学習、オンライン質問会などの手厚いサポートで、あなたの宅建士試験合格を力強く支援します。
伊藤塾はあなたのチャレンジを全力で応援しています。