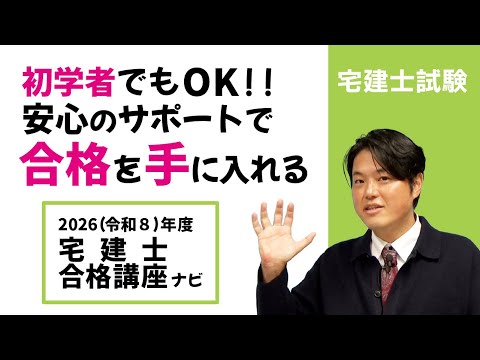宅建士試験に暗記は必要?覚えるコツやポイントを解説
勉強法
2025年11月04日


宅建士試験では、法律・税・権利関係など幅広い知識が問われるため、「どこまで暗記すればいいの?」と悩む人は少なくありません。
たしかに、法律という学問の性質上、暗記が避けられない部分もありますが、すべてを丸暗記する必要はありません。重要なのは、「暗記が必要なポイント」と「理解で乗り切れる部分」を見極めることです。
この記事では、宅建士試験で暗記が必要な範囲や効果的に覚えるためのコツを具体的に紹介し、暗記が苦手な人でも合格を目指せるよう、実践的なアドバイスをまとめました。
宅建士試験の学習を効率よく進め、スムーズに合格を成し遂げたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
【目次】
1.宅建士試験合格に暗記は必要?
宅建士試験は、不動産取引に関する法律や制度を中心に出題されるため、暗記が必要な場面が多いのは事実です。ただし、すべての範囲を丸暗記するのは非効率で、「暗記が必要な部分」と「理解で対応できる部分」を明確に分けて学習することが合格への近道です。
例えば、「法令上の制限(都市計画法・建築基準法など)」や「税・その他」に関する問題は、暗記の比重が高い傾向にあります。
一方、権利関係(民法)などは、考え方を理解すれば自然に答えが導ける問題が多いのが特徴です。
※「権利関係(民法)」の攻略法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
※「法令上の制限」「税・その他」の攻略法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
1-1. 重要な問題は暗記が必要な場面もある
宅建士試験では、「数字」「用語」「条文の言い回し」など、細かい記憶が得点に直結する箇所があります。例えば、建築基準法における建蔽率の制限や、宅地建物取引業法における重要事項説明の対象、宅建士の報酬額の上限などは、細かい内容まで記憶しておかなければ確実に正解を導くことは難しいです。
また、出題されやすい条文の語句を覚えておくことで、選択肢を見た瞬間に「これは正しい」「これは誤り」と正誤の”アタリ”をつけやすくなります。特に近年の試験では、ひっかけ問題が増えているため、条文の正確な表現を記憶しておくことが得点力アップの鍵です。
さらに、試験では過去問と同じ趣旨の問題が繰り返し出題されるため、過去問学習の中で自然に暗記を進めていくのが効果的です。
※建築基準法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
1-2. 試験に出題されない細かい知識の暗記は不要
一方で、テキストに書かれているすべてを丸暗記しようとするのは非効率です。細かい知識まで覚えておくに越したことはないですが、試験で出題される可能性の低い暗記に時間をかけると、本来重点的に学習すべきことが疎かになってしまう恐れがあります。
本試験で出題されるのは「実務に関係のある部分」「法令上の重要な数字」「出題実績のあるテーマ」などが中心で、細かい枝葉の知識が合格に直結するケースはそう多くはありません。聞き馴染みのないマイナーな法令に関する制限や民法のレアな判例などは出題可能性が低いため、時間をかける必要はありません。
宅建士試験においては、「出題される可能性の高い知識を重点的に覚える」ことが合格戦略の基本です。つまり、丸暗記ではなく、出題範囲を見極めて効率よく暗記することが求められます。
2.宅建士試験の重要ポイントを暗記するコツ
宅建士試験は範囲が広いため、どこから手をつけるべきか迷う人も多いでしょう。暗記を効率化するためには、「闇雲に数字をとにかく覚える」ではなく、「理解して整理しながら覚える」ことが重要です。
ここでは、得点につながる知識を確実に定着させるための4つのコツを紹介します。
2-1. 制限・規定の趣旨から考える
宅建士試験で出題される法律・法令の多くは「なぜこの制限があるのか」という目的(趣旨)を理解しておくと、暗記がぐっと楽になります。
例えば、都市計画法の開発許可制度は、無秩序な開発を防ぎ、住環境を守るための制度です。この趣旨を理解していれば、「どの地域で開発が許可されるか」「誰が許可を出すのか」といった条文も自然と整理できます。また、宅地建物取引業法の規定も同様です。重要事項説明や広告規制は、「消費者を保護するため」に設けられたものであると意識すると、細かな規定も理解しやすくなります。
単なる丸暗記ではなく、「なぜこの決まりがあるのか」という背景のストーリーを思い出しながら覚えることが、長期記憶への近道であると同時に、初見の問題にも対応できる力を培います。
2-2. 出題可能性の高い分野を重点的に暗記する
宅建士試験では、過去に出題されたテーマが形式を変えて繰り返し登場します。そのため、効率よく得点を伸ばすには、出題頻度の高い分野を中心に暗記を固めることが最も重要です。
例えば「権利関係」に関する分野では、不動産取引と深く関わる借地借家法・区分所有法・不動産登記法などが頻出です。一方、「法令上の制限」や「宅建業法」では、毎年似た範囲から満遍なく出題されます。そのため、都市計画法・建築基準法・宅建業法などでよく出題される数字・条件・手続きの違いなどを体系的に整理しておくことが大切です。
特に宅建業法は全50問中20問を占める最重要科目であり、ここでの暗記精度が合否を左右します。
限られた時間で合格点を取るためには、全範囲を無理に覚えるのではなく、過去問で毎年出題されている「定番テーマ」を優先し、出題されやすい部分を確実に記憶する戦略的学習を心がけましょう。
2-3. 実際に問題を解きながら暗記する
テキストを何度読んでも頭に入らないという人は、アウトプット中心の学習法に切り替えましょう。人間の記憶は、読むだけよりも「使う」ことで定着します。過去問や予想問題を解くことで、知識を思い出す練習ができ、結果的に暗記が強化されます。
特に効果的なのは、間違えた問題をその日のうちに復習することです。間違えた直後に復習することで、記憶の修正が早く行われ、忘れにくくなります。インプットとアウトプットを繰り返す「反復学習」を取り入れることで、単なる暗記ではなく「思い出せる知識」として定着させられます。
2-4. 表・暗記カード・語呂合わせ活用する
宅建士試験では、似たような数字や用語が多数登場します。用途規制に関する地域名や防火地域内における建築制限、免許の基準や有効期間等、制限内容や数字が混ざると混乱しがちです。
こうした分野は、一覧表や暗記カードを自作して整理するのがお勧めです。市販の参考書を利用するのも良いですが、わかりにくい箇所は自分なりにアレンジする方が整理しやすくなります。
また、覚えにくい数字は「語呂合わせ」を活用すると、記憶が定着しやすくなるでしょう。語呂合わせは人に見せるものではないので、自分が覚えやすいものであれば何でも問題ありません。
さらに、暗記カードを活用したり、スマートフォンの暗記アプリなどを使って繰り返し確認する方法も効果的です。スキマ時間に反復できるため、通勤や休憩中にも効率よく暗記が進むのでおすすめです。
当コラムを運営している伊藤塾の「宅建士 合格講座」では、「問題演習アプリ It’s D」をご提供しています。「問題演習アプリ It’s D」は、科目やカテゴリー、重要度といった項目で絞り込んでの問題演習が可能な独自開発の問題演習アプリで、「一問一答」形式と「四肢択一」形式の問題に取り組むことが出来ます。
講義を受けた直後は「一問一答」形式で内容を復習し、一通り学習した後は「四肢択一」形式で複数分野に跨る知識を確認しながら演習を行うなど、学習開始から試験直前まで、皆さまの学習を強力にサポートします。
3.宅建士試験で暗記すべき内容の一覧は?
宅建士試験で暗記すべき項目は幅広く、すべてを自力で整理するのは容易ではありません。
そのため、どの分野を重点的に覚えるべきかを一覧で把握したい場合は、受験指導校の講座や教材を活用するのが効率的です。
宅建士試験で安定して得点を取るには、毎年のように出題される定番テーマを確実に暗記することが重要です。例えば、35条書面と37条書面の違い、宅建物取引業者が受け取れる報酬額の上限などは、ほぼ毎年出題される鉄板の論点です。これらはいずれも宅建業法の中核をなす内容であり、数字や文言のわずかな違いを正確に記憶しておくことが合否を分けるポイントとなります。
また、権利関係の分野では、不動産登記法や借地借家法の出題頻度が特に高いです。例えば、借家契約の存続期間や更新条件などは、「最短期間」「最長期間」「期間の定めの有無」といった観点で整理しながら暗記すると、理解しやすく記憶にも残りやすくなります。
とはいえ、出題範囲をすべて自分で取捨選択するのは時間がかかります。効率的に学習を進めたい場合は、市販の宅建士試験対策書や伊藤塾などの受験指導校の教材を活用すると良いでしょう。
出題頻度に基づいた「重要問題リスト」を確認し、自分の理解度に合わせて優先順位をつけて暗記を進めることで、効率的に合格点を目指せます。
4.暗記すべき問題は伊藤塾の「宅建士合格講座」で確認がお勧め
「どの範囲を暗記すればいいのか分からない」「過去問を解いても覚えるべきポイントが整理できない」と感じる方には、伊藤塾の「宅建士 合格講座」の活用をお勧めします。
伊藤塾の「宅建士 合格講座」を一言で表すと、【楽しく学んで、合格してしまう講座】です。
具体的には…
●何のための制度・手続きなのかを徹底解説
→ 制度趣旨を理解することで、未知の問題にも強くなる!
●実務家の講師による「実務談義」が豊富
→ リアルな実務談義によって、難解な条文もイメージしやすく覚えやすい!
●語呂合わせによる暗記術を活用
→ 覚えるのが苦手な方でも無理なく楽しく覚えられる!
●伴走型の参加イベント(スクーリング、オンライン質問会、オンライン座談会など)を多数用意
→ 充実したサポートで、最後までやり遂げられる!
●写真・表・データが豊富でわかりやすいテキスト・問題集・補助レジュメ・学習アプリ・模試まで揃ってインプットもアウトプットも万全
→合格するために必要十分かつ適切な教材が全部セット!
●他の受験生と「一番差がつく」権利関係を手厚くカバー
→ 多くの受験生が苦手としている権利関係を得点源に!
これら合格に必要なものが全て揃って、受講料は追加料金なしの
39,800円
5. 宅建士試験の暗記に関するQ&A
Q. 宅建士試験は暗記だけで合格できますか?
A. 宅建士試験は「暗記の試験だ」と言われることもありますが、暗記だけで合格するのは難しいです。
特に「権利関係」では、法律の趣旨や条文の背景を理解していなければ、ひっかけ問題に対応できません。
一方、「宅建業法」「法令上の制限」「税・その他」は暗記の比重が高いため、知識を正確に覚えることで得点を伸ばせます。つまり、「理解すべき分野」と「暗記で対応できる分野」を見極め、学習バランスを取ることが合格への近道です。
Q. 暗記が苦手ですが、どのように克服できますか?
A. 暗記が苦手な方は、問題演習とセットで覚える方法が効果的です。単にテキストを読むだけでは記憶が定着しにくいため、問題を解きながら「この選択肢はなぜ正しい(または誤り)なのか」を確認することで、知識が整理されます。
また、語呂合わせ・一覧表・カードアプリなどを使い、短時間で繰り返し触れることも記憶の定着につながります。伊藤塾の講義なら、講師が暗記のコツや整理法を具体的に教えてくれるため、独学よりも効率的に覚えられるでしょう。
Q. 暗記はいつから開始すべきですか?
A. 暗記は、学習初期から少しずつ始めるのが理想的です。一気に詰め込もうとすると、試験直前に混乱したり、記憶が定着しないまま終わったりするケースが多いです。
特に宅建業法や法令上の制限に関するものは早めに覚え始めることで、過去問を解く際に理解が深まり、復習の効率も上がります。
6.宅建士試験の暗記について・まとめ
本記事では、宅建士試験の合格を目指す上で重要な暗記について解説しました。
以下にポイントをまとめます。
- 宅建士試験では、すべてを丸暗記するのではなく、法律の趣旨を理解した上で暗記が必要な部分と、理解で対応できる部分を見極めることが合格への近道となります。
- 「法令上の制限(都市計画法・建築基準法など)」や「税・その他」に関する問題は暗記の比重が高い傾向にありますが、「権利関係(民法)」は考え方を理解することで答えが導ける問題が多いという特徴があります。
- 宅建士試験では、「数字」「用語」「条文の言い回し」など、細かい知識が直接得点に結びつく箇所があります。特に宅建業法は全50問中20問を占める最重要科目であるため、正確な記憶が合否を左右します。
- テキスト全てを丸暗記しようとするのは非効率であり、出題される可能性の高い知識(過去問で繰り返し出題される「定番テーマ」)を優先して重点的に覚えることが合格戦略の基本です。
- 単なる丸暗記ではなく、制限や規定の「趣旨(目的)」を理解しながら覚えることで、長期記憶につながります。また、問題を解きながら知識を使うアウトプット中心の「反復学習」や、表・暗記カード・語呂合わせ、スマートフォンの暗記アプリ活用が効果的です。
- どの分野を重点的に暗記すべきかを自力で整理するのが難しい方は、受験指導校の講座や教材を活用することで、効率的に学習を進めることができます。
もしあなたが、「どの範囲を暗記すればいいのか分からない」「覚えるのが苦手」と感じていらっしゃるなら、ぜひ伊藤塾の「宅建士 合格講座」をご活用ください。
合格に必要な教材とサポートが全て揃った【楽しく学んで、合格してしまう講座】で、効率よく、確実に合格を手に入れましょう。
伊藤塾は、合格も合格後の活躍も、あなたのチャレンジを力強く応援し続けます。