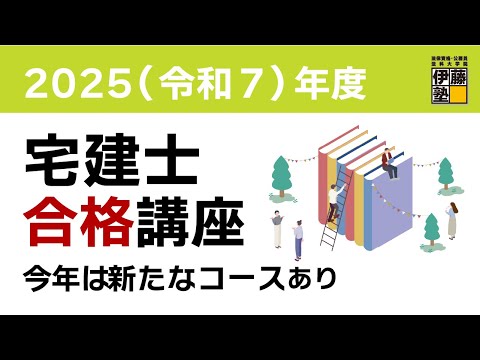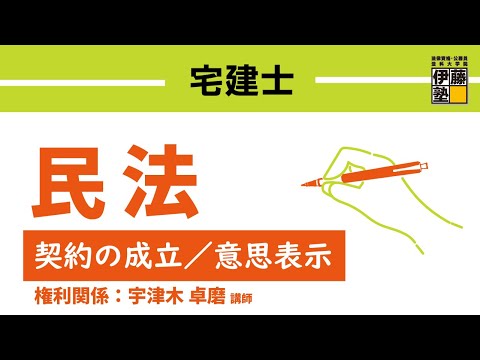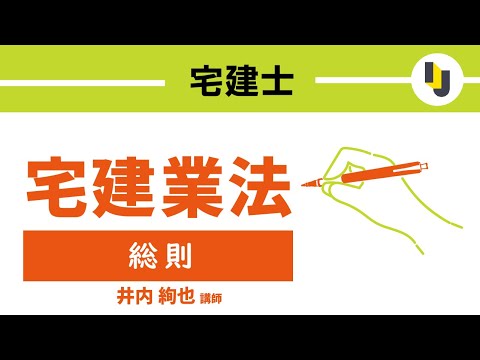宅建の勉強方法でノート作りは有効?作り方と活用方法を詳しく解説
勉強法
2025年10月06日


宅建試験の合格を目指す多くの方にとって、効果的な勉強方法を見つけることは非常に重要です。その中で「ノート作り」が役立つのか気になる方も多いでしょう。
結論として、適切な形でまとめノートを作れば、理解度が深まり合格に近づく手助けになります。ただし、作り方や活用方法を間違えると逆効果になることもあります。
この記事では宅建の勉強におけるノート作りの必要性や作成するメリット、具体的な活用法や注意点まで詳しく解説します。ノートを作成すべきかどうかで迷っている方は、ぜひ最後までご覧ください。
【目次】
1. 宅建の勉強でノート作りは必要?
宅建の勉強でノートが必要かどうかは、人によるため一概には言えません。学習スタイルや知識の習得状況によって、ノート作りの効果は大きく変わります。
宅建士試験では、宅建業法・民法・都市計画法・建築基準法など、幅広い法律知識や細かな規則の理解が求められます。そのため、情報を整理し、記憶に定着させる工夫が欠かせません。この点で、ノート作りは自分なりに知識をまとめる作業となるため、理解度を高め、苦手分野の把握や効率的な復習に役立ちます。
一方で、法律に馴染みがある方や短期間で合格を目指す方にとっては、ノート作成に多くの時間を割くよりも、過去問演習やテキストの繰り返しに重点を置く方が効果的な場合もあります。例えば、法律系の資格試験経験者で民法の基礎が身についている方であれば、民法のノートを一から作るより、その時間を他分野の強化に充てた方が合理的です。
ノートを作成すべきかどうかは、「自分が合格するためにノート作成が必要か」という観点から考えると良いでしょう。その際は、ノート作りそのものを目的とするのではなく、あくまでも学習を補助するためのツールとして考えることが重要です。
2. 宅建の勉強でノートを作るメリット
宅建の勉強でノートを作ることには、さまざまなメリットがあります。ここでは主なメリットを6つ紹介します。
・情報を自分なりに整理できる
・書くことで記憶に定着しやすくなる
・自分専用の復習用教材が作れる
・試験直前の見直しが効率よくできる
・学習の進捗や理解度が「見える化」される
・モチベーション維持につながる
それぞれ解説していきます。
2-1. 情報を自分なりに整理できる
情報を自分なりに整理できることは、ノート作りの大きなメリットの一つです。
宅建士試験の出題範囲は非常に広く、複雑な法律用語や条文が多いため、テキストを読むだけでは内容が整理されず、混乱しやすい傾向があります。
ノート作りは、こうした膨大な知識を自分の言葉や図解に落とし込み、理解しやすい形にまとめる作業です。例えば、宅建業法における契約の流れを図式化したり、民法の条文を具体例と関連づけて整理することで、難解な内容も身近に感じられ、記憶にも残りやすくなります。
このような「自分仕様」の情報整理は、単なる暗記に留まらず、内容の理解を深める上でも非常に効果的です。整理されたノートは、復習時にもスムーズに知識を確認でき、学習全体の効率化に繋がります。
2-2. 書くことで記憶に定着しやすくなる
ノートに「書く」という行為そのものが、記憶の定着を助ける効果を持ちます。
単に目でテキストを読むだけよりも、実際に手を動かして書き出すことで脳がより能動的に情報を処理し、記憶に残りやすくなるからです。
ノートを作成する際は、分かりにくい用語を自分なりに言い換えたり、補足のコメントを添えたりすると、その内容が自然と頭に入りやすくなります。特に法律の学習は抽象的な概念が多いため、書くことでより具体的なイメージとして理解できるようになります。
2-3. 自分専用の復習用教材が作れる
ノート作りの大きなメリットの一つは、「自分専用の復習用教材」を作れることです。
市販のテキストや問題集は情報が網羅されている反面、自分がどこを苦手としているのか、どの部分が特に重要なのかが分かりにくいことがあります。画一的な内容では、自分に本当に必要な情報だけを効率よく復習するのは難しい場合もあります。
その点、自分でノートを作成すれば、苦手な分野、過去問で間違えたポイント、講義で強調された重要事項など、自分にとって必要な情報だけを整理・集約することができます。つまり、自分の学習状況にぴったり合った「オーダーメイドの復習教材」が手に入るのです。
これは市販の教材では得られない、ノート作成ならではの大きな利点と言えるでしょう。
2-4. 試験直前の見直しが効率よくできる
あらかじめ要点や苦手分野をまとめたノートを作成しておけば、試験直前の見直しが格段に効率的になります。
分厚い市販のテキストを最初から読み返す必要はなくなり、限られた時間の中でも重要なポイントだけを優先的に復習できます。特に、自分がつまずきやすい箇所をピンポイントで確認できるため、無駄を省いた集中的な対策が可能になります。
こうした見直しの効率化は、理解の定着や得点力アップにも直結する大きなメリットです。
2-5. 学習の進捗や理解度が「見える化」される
ノートを作ることで、自分の学習の進み具合や理解度を視覚的に把握できます。どの分野が理解できていて、どこがまだ不十分かが一目でわかるため、効率的な学習計画を立てやすくなるでしょう。
例えば、苦手な論点を色分けしたり、苦手な分野には書き込みを多めにしたりすることで、復習すべきポイントが明確になります。ノートによる「見える化」によって、学習の漏れや偏りを防ぎやすくなる効果も期待できます。
このように、ノート作りは学習全体の状況を明確にし、計画的かつ効果的な勉強を支える重要な役割を果たします。
2-6. モチベーション維持につながる
ノート作りは、自分の努力が目に見える形で残るため、学習意欲の維持に役立ちます。宅建士試験の勉強は長期にわたることが多く、途中で挫折しないためには、達成感や前進感が非常に重要です。
ノートのページ数が増えたり、分かりやすくまとまった内容を目にしたりすると、「自分が確実に成長している」という実感が湧き、やる気を保ちやすくなります。
このように、目標に向かって少しずつ前進していることを視覚的に確認できることは、継続的な学習の大きな支えとなるでしょう。
3. 宅建で合格するためのノート作りのコツ
ノートを効果的に作るには、いくつかのポイントがあります。ここでは合格に役立つ具体的なコツを4つ紹介します。
・最初から完璧を目指さず書き足していく
・参考書や講義内容を「写すだけ」にしない
・重要ポイントや苦手分野を重点的にまとめる
・試験直前期に活用しやすい形に整えていく
それぞれ解説していきます。
3-1. 最初から完璧を目指さず書き足していく
ノート作りを始めるときは、最初からすべてを完璧にまとめようとしないことが大切です。宅建の学習範囲は広く、一度に全てを理解・整理するのは現実的ではありません。
まずは、大まかなポイントや重要なキーワードだけを押さえる程度に留めておきましょう。その後、問題演習や講義を通じて理解が深まった部分、新たに気づいたことなどを、少しずつ追記していく形がお勧めです。
このように段階的にノートを育てていけば、無理なく自分の理解にフィットした、実用的な学習ツールへと仕上げていくことができます。
3-2. 参考書や講義内容を「写すだけ」にしない
ノート作りでは、テキストや講義の内容をただそのまま書き写すだけにしないことが重要です。単純な写し書きでは、自分の理解が深まらず、記憶にも定着しにくいためです。
ノートを作成する過程で、重要なポイントを自分の言葉に言い換えたり、図や表を加えたりすることで、内容を自分の頭でしっかり咀嚼しながらまとめることができます。こうした工夫によって理解が深まり、知識がより確実に身につくでしょう。
さらに、疑問点や具体例、関連事項などを書き加えることで、自分だけのオリジナルの学習ツールとして活用しやすいノートが完成します。
3-3. 重要ポイントや苦手分野を重点的にまとめる
ノート作成の際は、内容をすべて網羅しようとしないことが重要です。全てを書き写してしまうと、教科書を読み直すのと大差なくなり、ノート作りの意味が薄れてしまいます。それならば、教科書に自分で加筆して活用した方が効果的でしょう。
そこで意識したいのが情報の取捨選択です。ノートには、「出題頻度の高い重要ポイント」や「自分が苦手としている分野」を中心にまとめていきましょう。そうすることで、限られた学習時間を効率よく活用でき、試験対策としても高い効果が期待できます。
すべてをカバーしようとせず、「自分にとって本当に必要な情報」に絞ってノートを作ることが、効率的な学習への近道です。
3-4. 試験直前期に活用しやすい形に整えていく
ノートは「試験直前の復習用に使いやすい形」に整えていく意識が重要です。
初めから全てを網羅的にまとめてしまうと、ノートの分量が膨大になり、限られた直前期にはとても見返せない状態になってしまいます。これでは本来の目的である「効率的な復習」にノートを活かせません。
そのため、作成段階から重要ポイントや苦手分野に絞ってまとめたり、学習が進む過程でノートの内容を整理をしていくとよいでしょう。
ノートは単に「作ること」が目的ではなく、試験直前まで活用することが大切です。そのためにも、直前期を見据えて使いやすい形に仕上げておきましょう。
4. 作成したノートの効果的な活用法
ノートを作成しても、作成後にうまく活用できなければ時間の無駄になってしまいます。ここでは、ノートを使った効率的な復習方法や学習のポイントを紹介します。
・過去問とノートの併用学習を行う
・苦手分野や頻出テーマを重点的に見返す
・デジタル化していつでも見られるようにする
・模試の復習や間違えた論点をノートに加筆していく
・本試験直前に「自分専用の要点集」として集中的に確認する
それぞれ解説していきます。
4-1. 過去問とノートの併用学習を行う
作成したノートは、過去問演習と組み合わせて活用することで、より大きな効果を発揮します。過去問を解く際に間違えた問題や迷った問題の内容をノートで確認すれば、知識の定着と弱点の補強がしやすくなります。
また、過去問演習後に「なぜ間違えたのか」「どの部分が曖昧だったのか」をノートに書き加えておくことで、自分の理解が不十分な箇所や勘違いしやすいポイントが明確になります。その結果、同じミスを繰り返しにくくなります。
さらに、過去問の解説から得た新しい知識や視点をノートに追記すれば、内容がより深まり、自分だけの理解ツールとしてノートを進化させることができます。
このように、過去問とノートを併用することで、実践的な得点力を着実に養えるでしょう。
4-2. 苦手分野や頻出テーマを重点的に見返す
ノートを復習に活用する際は、苦手分野や頻出テーマを重点的に見返すことが効果的です。
宅建士試験では、毎年出題傾向がある程度決まっており、頻出論点を押さえておくことが合格に直結します。また、自分が苦手とする分野を把握して集中的に復習することで、得点力の底上げが期待できるでしょう。
ノートの作成方法は人それぞれですが、理解が曖昧なテーマや、過去問や模試などで間違いが多かった分野に付箋を貼ったり、ノートの該当箇所を色分けしたりしておくと、見返す際に効率よく復習できます。
ノート全体を均等に見返すのではなく「今の自分に必要な箇所」に重点を置いて確認することが、限られた学習時間を有効に使うコツです。
4-3. デジタル化していつでも見られるようにする
作成したノートをデジタル化しておくと、外出先やスキマ時間でも手軽に見返せるため、学習効率が高まります。紙のノートは場所によって開きにくい場合もありますが、スマートフォンやタブレットで閲覧できる形にしておけば、通勤時間や休憩時間など短い時間でも学習に活用しやすくなります。
具体的には、ノートを写真に撮ってスマートフォンに保存したり、PDF化して専用アプリで整理したりする方法が便利です。自分にとって使いやすい形式で管理すれば、いつでも簡単にアクセスでき、復習のハードルがぐっと下がります。
4-4. 模試の復習や間違えた論点をノートに加筆していく
模試は自分の理解度や実力を客観的に把握できる重要な機会です。模試で間違えた問題や曖昧だった論点は、ノートに加筆してしっかり復習しましょう。
間違えた原因や正解のポイントをノートに書き加えることで、自分の弱点を明確にできます。これにより同じミスを繰り返すリスクが減り、苦手分野の克服に役立ちます。
また、模試の解説で新たに理解した知識や注意点もノートに追加していくと、内容がより充実し、実践的な学習ツールとしての価値が高まります。ノートを更新し続けることで、合格に必要な知識が確実に身についていくでしょう。
4-5. 本試験直前に「自分専用の要点集」として集中的に確認する
本試験が近づく直前期は、作成したノートを「自分専用の要点集」として活用することが効果的です。試験範囲全体を細かく復習する時間が限られているため、ノートにまとめた重要ポイントや苦手分野を中心に集中的に確認しましょう。
これまでの学習で特に注意が必要だと感じた箇所や、何度も間違えた論点に絞って復習することで、効率的に得点力を高められます。
また、自分で作成したノートを見返すことで「これだけやったんだから必ず合格できる」と、自信を持って本試験に臨むことができます。
5. ノート作りをする際の注意点
ノート作りは学習効果を高めるために効果的な手段ですが、注意点を守らないと逆に非効率になりかねません。
ここでは、ノート作りでありがちな失敗を避け、効果的に活用するためのポイントを詳しく解説します。
| ・ノート作成が目的にならないようにする ・時間をかけすぎない ・テキストをそのまま写すだけにならない ・情報を詰め込みすぎない ・追記できるよう余白を残しておく ・マーカーを使いすぎない |
それぞれ見ていきましょう。
5-1. ノート作成が目的にならないようにする
ノート作成はあくまでも学習を支えるツールであり、ノート自体を作ることが最終目標ではありません。ノート作りにこだわりすぎると、テキストの復習や過去問演習といった本来の学習が疎かになる可能性があります。
大切なのは、ノートを作ることで学習の質を高めることです。ノートを作る行為そのものに満足せず、実際に理解を深め、得点力を伸ばすために活用しましょう。目的を見失わず、学習全体のバランスを意識することが重要です。
5-2. 時間をかけすぎない
ノート作成にかける時間は必要最低限に抑えることが重要です。時間をかけすぎると、復習や過去問演習に使える時間が減り、効率的な学習が難しくなります。
効率よくノートをまとめるためには、要点を絞って簡潔に書き、後から加筆できるよう余白を残しておくことが大切です。
また、完璧を目指すよりもスピーディーに必要な情報を整理し、何度も見返して記憶を深めることを優先しましょう。時間の使い方にメリハリをつけることが、宅建合格への近道です。
5-3. テキストをそのまま写すだけにならない
ノート作りで注意したいのは、テキストの内容をただ丸写しするだけにならないことです。単に書き写すだけでは、自分の理解が深まらず、記憶にも残りにくくなってしまいます。
ノートを作る際は、重要なポイントを自分の言葉で言い換えたり、図や表を使ってわかりやすく整理したりする工夫が必要です。そうすることで、内容をしっかり理解しながらまとめられ、記憶にも定着しやすくなります。
また、疑問点や具体例を付け加えることで、オリジナルの学習ツールとして活用しやすいノートが完成します。これらの工夫がノート作りの効果を高めるポイントです。
5-4. 情報を詰め込みすぎない
一冊のノートに情報を詰め込みすぎると、逆に見返しにくくなり、復習の効率が落ちてしまいます。重要なポイントが埋もれてしまい、何を重点的に確認すればよいのか分かりづらくなるためです。
もし網羅的に情報をまとめたいのであれば、市販のテキストに直接書き込みをする方法で十分です。テキストはすでに全体像が整理されているため、必要に応じて注釈やマーカーを使って補足すれば効率的に学習できます。
ノートはあくまで、自分にとって特に重要なポイントや苦手分野を絞ってまとめる場所として使い、情報量を適度に制限することが復習の効率化に繋がります。
5-5. 追記できるよう余白を残しておく
ノート作成は一度で完成させるものではなく、学習の進行に合わせて内容を更新していくことが重要です。そのため、あらかじめページの余白や行間を広めに取り、後から追記できるスペースを確保しておきましょう。これにより、新たに気づいたポイントや模試で間違えた論点をすぐに加筆でき、ノートの質を継続的に高められます。
逆に、余白がないと後から修正や追加が面倒になり、ノートの更新が滞る原因になります。
5-6. マーカーを使いすぎない
マーカーや色ペンは重要な箇所を目立たせるのに便利ですが、使いすぎると逆効果になることがあります。色の種類が多すぎたり、全体的に色が散らばっていると、情報の優先順位がわかりにくくなり、かえって見づらくなるためです。
効果的に使うには、色を3~4色程度に絞り、それぞれに「重要」「頻出」「苦手」などの意味を持たせて使う方法がお勧めです。こうすることで、見返すときにどこを重点的に確認すればよいか一目で分かり、効率的な復習が可能になります。
6.ノートを作るなら受験指導校のテキストをベースにすべき理由
ノート作成の際は、市販の参考書よりも受験指導校のテキストをベースにするのがお勧めです。宅建士試験合格に特化したテキストなら試験傾向を踏まえて必要な情報が整理されており、効率よく学習できるからです。
市販の書籍は内容が詳しい一方で、宅建士試験に不要な情報や細かすぎる解説が含まれている場合があります。こうした情報までノートに盛り込んでしまうと、余計な時間がかかることで試験対策として非効率になりかねません。
一方、受験指導校のテキストなら、頻出ポイントや押さえるべき箇所が明確にまとまっているため、そこを土台にノートを作れば内容の取捨選択がしやすくなります。さらに、講義で扱った内容に沿ってノートを補完していけば、自分専用の効率的な復習ツールが完成します。
無駄なく要点を整理するためにも、受験指導校のテキストを軸にノート作成を進めると良いでしょう。
※受講生が書き込みやすい大きめの余白、法律初学者にもわかりやすい豊富なイラストや図解での説明など、効率良く学習するための工夫が満載の【伊藤塾のテキスト】

※こちらも読まれています。
→ 宅建の通信講座はなぜ伊藤塾がおすすめなのか?宅建士合格講座の魅力を徹底解説
7. 宅建士試験の勉強でのノート作成に関するよくある質問
Q1. 宅建士試験はノートなしでも合格できる?
A. 宅建士試験では、ノートを作らなくても合格は可能です。
市販のテキストや問題集を繰り返し読み解き、過去問演習を重ねることができれば、ノートがなくても合格に必要な知識は十分身につきます。
とはいえ、ノート作りは自分の理解を深め、苦手分野を整理するために有効な手段です。特に法律知識に不慣れな初心者や、独学で学習を進める人にとっては、ノート作成が効率的な復習と記憶の定着に役立ちます。
自分の学習スタイルに合わせて使い分けるのが賢明です。
Q2. ノート作成する際の形式は?紙とデジタルどちらがよい?
A. ノートの形式は、個人の好みやライフスタイルに合わせて選びましょう。
紙のノートは手で書くことで記憶に残りやすく、視覚的な工夫も自由に行えます。勉強中にすぐに書き込める手軽さも魅力です。
一方、デジタルであれば、スマホやタブレットでどこでも閲覧可能になります。通勤中やお昼休みなど、場所を選ばず学習できるメリットがあります。
可能であれば紙とデジタルの両方を併用し、状況に応じて使い分けるのが効果的です。自分に合った形式を見つけることで、学習の効率と継続性が高まるでしょう。
Q3. ノート作りに時間をかけても良い?
A. ノート作りに適度な時間をかけることは理解を深める上ではプラスですが、時間の使い方には注意が必要です。時間をかけすぎて過去問演習などが疎かになると、「勉強時間の割に得点が伸びない」という事態に陥ってしまいます。
学習の進度や自分の理解度に応じて、柔軟にノート作成にかける時間を調整しましょう。重要なのは、バランスよく学習を進めることです。
Q4. どんな内容をノートにまとめればいい?
A. ノートにまとめるべき内容は「自分が苦手な箇所」や「本試験での頻出分野」が中心です。テキストに書かれている内容を網羅的に書き写すようなノート作成は、くれぐれもしないようにしましょう。
直前期における復習用教材として活用するためにも、記載する内容は絞っておくことをお勧めします。
Q5. ノート作りと問題演習はどちらが優先?
A. 問題演習を優先し、ノート作りはそれを補完する形で活用するのが効果的です。
宅建士試験では、法律知識を実際に問題で使いこなす能力が求められるため、問題を解く経験が不可欠です。効率良く得点力を上げたいのであれば、「演習を通じて自分の弱点や理解不足を見つける→その内容をノートにまとめる」というサイクルを回す勉強法がお勧めです。
この方法なら、ノートが単なるメモや写しではなく、実践的な知識の整理ツールとして機能します。
8.宅建士試験の学習においてノートは必須ではないが有効なツールとなる
最後に本記事の内容をまとめます。
◉宅建試験においてノート作りは必須ではないものの、苦手分野や頻出分野をまとめることで効率的な学習と得点アップに繋がります。
◉ノート作成のメリット
・情報を整理し、記憶に定着させやすい
・自分専用の復習教材となり、試験直前の見直しに役立つ
・学習の進捗や理解度が可視化され、モチベーション維持にも繋がる
◉ノート作成のコツ
・最初から完璧を目指さず、追記していく
・参考書や講義内容をただ書き写すだけでなく、自分の言葉でまとめる
・重要ポイントや苦手分野に絞って作成する
・試験直前に活用しやすい形に整える
◉ノートの効果的な活用法
・過去問演習と併用し、間違えた箇所をノートで確認・加筆する
・苦手分野や頻出テーマを重点的に見返す
・デジタル化してスキマ時間に活用する
・模試の復習内容や間違えた論点を追記する
・試験直前には「自分専用の要点集」として集中的に確認する
◉ノート作りの注意点
・ノート作成自体が目的にならないようにする
・時間をかけすぎず、効率を意識する
・テキストをそのまま写すだけにしない
・情報を詰め込みすぎず、余白を残しておく
・マーカーを使いすぎない
以上です。
本記事の内容を参考にして、適宜ノートを活用し、知識の定着に役立てていただければ幸いです。
もし、「ノートをうまく活用できない」「どこが重要な論点なのか見極められない」などの不安がある方は、ぜひ受験指導校の活用をご検討ください。
伊藤塾では現在、2025年合格目標 宅建士合格講座を開講中です。
伊藤塾の「宅建士合格講座」は、2025年からバージョンアップし、よりカリキュラムが充実しました。
「宅建士合格講座」の内容・特長について井内絢也講師がお伝えしていますので、初めての法律資格試験として、宅建士試験を目指そうとしている方、行政書士試験、他資格からWライセンス取得を目指している方などは、是非ともご視聴ください。
「今年はさらにバージョンアップしたコースをご用意!「2025年合格目標 宅建士合格講座」 のご紹介です!」
法律知識ゼロの方でもわかりやすい講義で、短い学習時間で効率よく合格できる「宅建士合格講座」から、「権利関係」の民法「契約の成立・意思表示」の体験講義をご視聴いただけます。
是非、テキストとあわせてご覧ください。担当:宇津木 卓磨 講師
宅建業法「総則」の体験講義です。ぜひご覧ください。担当:井内 絢也 講師
伊藤塾は、宅建士試験に本気で挑む受験生を全力で応援しています。