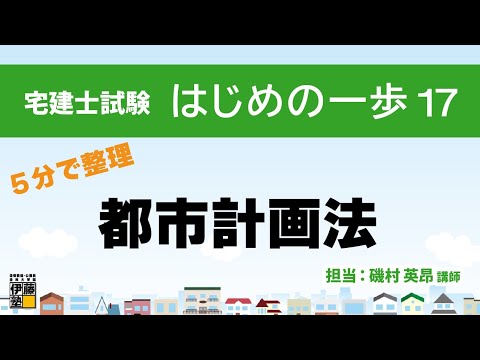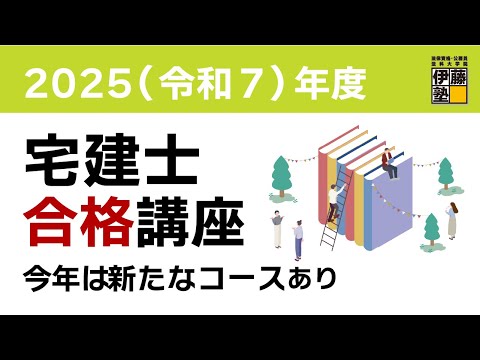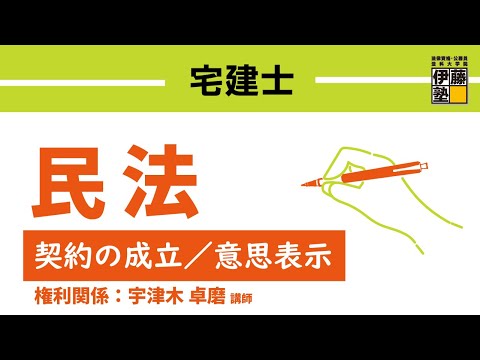宅建士試験の都市計画法は難しい?覚え方のコツや頻出ポイントを解説
勉強法
2025年10月06日


宅建士試験で出題される「法令上の制限」という分野では、毎年「都市計画法」に関する問題が出題されます。区域区分や開発許可の要否など専門用語が多く、細かな規制や数字が出てくるため、宅建士試験の勉強開始当初は「難しい」と感じる方も多いのではないでしょうか。
一見すると難解に感じてしまう都市計画法ですが、出題パターンがある程度決まっているため、効率よく学習すれば着実に得点を積み上げることが可能です。
本記事では、都市計画法の基礎知識から宅建士試験での出題傾向、効率的な勉強法までをわかりやすく解説します。これから宅建士試験の勉強を始める方や、都市計画法を苦手に感じている方はぜひ参考にして、得点アップを目指してください。
【宅建士試験】はじめの一歩シリーズ第17回 都市計画法を5分で整理『都市計画法』
【目次】
1. 宅建士試験における都市計画法
宅建士試験では、「法令上の制限」に関する分野の一つとして「都市計画法」が出題されます。都市計画法に対する苦手意識を無くすためにも、まずは都市計画法がどんな法律なのかを確認していきましょう。
1-1. 都市計画法とは
都市計画法は、都市が無秩序に拡大することを防ぎ、計画的で持続可能なまちづくりを目指すための法律です。主に土地利用のルールを定め、市街化の範囲や建築物に関する制限などを規定しています。
具体的には、「都市計画区域」「市街化区域」「市街化調整区域」などの区域区分を設け、それぞれの区域に応じて開発や建築に対する許可・制限を設ける仕組みとなっています。
例えば、市街化区域は積極的な都市化を進めるエリアで、新たな住宅や商業施設の建設が促進されます。
反対に、市街化調整区域では都市の無秩序な広がりを防ぐため、原則として開発行為が制限されています。
このように、都市計画法は都市の将来的な姿を描きつつ、地域ごとの特性や社会のニーズに応じた土地利用を適切にコントロールする役割を果たしているのです。
1-2. 宅建士試験での出題数・配点
宅建士試験において、都市計画法からの出題数は例年2問です。全50問中の2問という位置づけで、科目としては「法令上の制限」に含まれます。近年の宅建士試験では「法令上の制限」に関する問題が8問出題されており、そのうち2問が都市計画法にあたります。
試験科目全体のバランスで見ると、権利関係(民法等)や宅地建物取引業法などの高配点分野に比べて出題数は少なめですが、毎年必ず出題されている科目でもあります。
また、出題テーマはある程度固定されているため、短時間でも効率よく対策できる点が特徴です。
2. 宅建士試験で都市計画法の問題は捨てるべき?
都市計画法は出題数が少ないため、「他の分野に集中した方が良いのでは?」と考える方もいます。ですが、都市計画法の問題をあえて捨て問にするのはお勧めできません。
理由は大きく2つあります。
まず、都市計画法は他の科目に比べて出題範囲が限定されており、比較的短時間の学習で得点が見込める分野だからです。しっかりと対策をすれば、効率良く確実な得点源にできます。
次に、宅建士試験の合格点は例年36点前後とされており、全50問中で7割以上の正解が求められます。合格点は年によって多少の変動がありますが、このラインをクリアするには1問の得点が非常に重く、1問足りずに不合格になってしまうことも珍しくありません。
そのため、出題パターンがある程度決まっている都市計画法の問題は、確実に取れるようにしておくことが合格への大きな助けとなります。
もちろん、学習時間が極端に不足している場合は、権利関係や宅地建物取引業法などの配点の高い分野を優先する戦略も有効です。しかし、可能な限り都市計画法の基本は押さえ、確実に得点できる状態を作ることが、合格をぐっと近づけるポイントと言えるでしょう。
3. 都市計画法の出題傾向・頻出分野
都市計画法の問題は、毎年似たテーマやパターンで出題される傾向が強く、比較的対策しやすいのが特徴です。過去問を分析すると、問われやすい内容がかなり絞り込めるため、効率的に学習を進められます。
具体的に、頻出しているテーマは次の通りです。
【区域区分の理解】
都市計画区域・市街化区域・市街化調整区域などにおける区分の違いや、それぞれの特徴・趣旨・規制内容を問う問題。用途地域や地区計画などによる建築物に対する制限内容についても出題されています。
【開発許可の要否】
開発行為の定義や、許可が必要なケース・不要なケースの判断。
こうしたテーマは 過去問で繰り返し出題されており、基本的な理解をしっかり固めるだけでも十分に安定した得点が期待できます。
一方で、年度によってはやや難易度が高い問題や、細かな数値・条文の暗記を求められる内容が出題されることもあります。ただし、そうした難問は全受験生にとって正答率が下がるため、合格を目指す上では「全体像をつかむ」ことと「頻出事項を確実に理解する」ことが最も重要です。
基本事項を押さえておけば都市計画法で大きな失点をする心配は少なくなります。短時間でも着実に成果が出やすいため、力を入れて取り組むべき分野と言えるでしょう。
4. 都市計画法で得点するためのポイント
都市計画法で得点するための主なポイントは、以下の4つです。
・規制の理由を常に考える
・頻出分野を押さえる
・図解・図表を活用して覚える
・よく問われる引っかけパターンを知っておく
苦手分野を得意分野に変えるためにも、これから解説するポイントをしっかり意識して学習を進めましょう。
4-1. 規制の理由を常に考える
都市計画法の学習に限らず、法律を学ぶ上では「なぜこのルールが存在するのか」という視点を常に意識することが重要です。規制の目的や背景が理解できていれば、たとえ見慣れない問題が出題されても、規制の趣旨・目的から正しい選択肢を導き出す力が養われます。
都市計画法の条文は、一見すると単なる規則の羅列に思えるかもしれません。しかし、その背後には都市づくりや環境保護、住民の生活の質を守るといった社会的な意義が存在します。
たとえば、市街化調整区域の目的は「無秩序な都市の拡大を防ぎ、インフラ整備のコストを抑える」ことです。このような背景を理解して学習を進めることで、数字や手続きも単なる暗記項目ではなく、意味のある知識として記憶に残りやすくなります。
単に表面的に覚えるのではなく、「なぜこの規制が必要なのか?」「どんな目的のために設けられているのか?」という視点を持ちながら学ぶ姿勢が、得点力アップの大きなポイントになります。
4-2. 頻出分野を押さえる
都市計画法は出題パターンがある程度決まっているため、すべてを完璧に覚える必要はありません。
まずは出題頻度の高い分野を優先的に学習し、効率よく得点力を高めることが重要です。
具体的な進め方としては、まず過去問を分析し「よく出題されているテーマ」を確認することから始めましょう。出題実績の高いテーマに優先順位をつけて学習を進めれば、短期間でも得点できる力が養えます。
学習時には「このテーマは毎年のように出ている」「ここは頻度が低いから後回しでもよい」など、メリハリを意識して取り組むことがポイントです。
都市計画法に関する知識を網羅的に覚えようとすると時間がかかってしまいますが、頻出テーマに的を絞ることで限られた学習時間を最大限活用できます。
さらに、過去問とテキストの出題傾向を比較し、出題が集中している項目は 「なぜこの分野がよく問われるのか」まで理解を深めておくと、応用問題にも対応できるようになります。
4-3. 図解・図表を活用して覚える
都市計画法を勉強する際は、図解や表を活用して情報をまとめる方法が非常に効果的です。
都市計画法は、文章だけで学習を進めようとすると混乱しやすい分野です。特に、区域区分や開発許可に関する問題などでは細かな違いが重要になるため、視覚的に整理することが理解の助けになります。
例えば、都市計画法における「特別用途地区」と「特定用途制限地域」の違いについて理解したいのであれば、以下のような表を自分なりに作成してみると良いでしょう。
| 特別用途地区 | 特定用途 制限地域 | |
| 定める場所 | 用途地域内 | 用途地域が未 指定の区域 ※ ただし、市 街化調整区域 内は✕ |
| 目的 | 用途地域内に おける用途制 限を加重・緩 和するため | 用途地域では ない区域にお ける建築制限 |
こうした表を自分で作成することで、曖昧な知識が整理されて記憶にも残りやすくなります。また、試験本番でもこの整理したイメージが役立ち、迷ったときに正確な判断を下せるようになります。
市販の参考書や受験指導校のテキストには良質な図解が多く掲載されています。そうしたものも積極的に活用し自分なりにまとめ直す作業を加えると、より深い理解に繋がります。
4-4. よく問われる引っかけパターンを知っておく
都市計画法では、典型的な「ひっかけパターン」の出題が非常に多いことが特徴です。単純な知識問題だけでなく、「例外事項」や「適用除外」を正しく判断できるかどうかが問われます。暗記に頼った知識やうろ覚えの知識だと、こうした設問に引っかかってしまいがちです。
「通常はどうなのか」「例外となる条件は何か」を明確に整理しておくことが重要です。
たとえば、次のような過去問例が挙げられます。
【例題】
「市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。」
【正解】誤り
市街化区域で一定規模以上の開発行為を行う場合、都道府県知事の許可を受ける必要があります。しかし、市街地再開発事業の施工として行う開発行為については、他の法律に基づき、すでにその事業計画につき都道府県知事の許可・認可を受けているため、規模に関係なく改めて開発許可を受ける必要はありません。
出典:令和4年宅建士試験 第16問|一般財団法人 不動産適正取引推進機構
効果的な対策方法としては、過去問を繰り返し解きながら、出題パターンを体で覚えていくことです。過去問で出題パターンを学んでおけば、本番の試験で「これは例外のパターンだ」「ここでは●●の条件が問われている」と冷静に判断できるようになります。
こうした引っかけパターンを事前に把握しておけば、不用意なミスを減らし、大きな得点源にすることが可能です。
5. 都市計画法の効率的な勉強法
都市計画法の出題は限られた範囲のため、短期間でも十分に対策が可能です。ここでは、都市計画法に関する学習を効率よく進め、得点力を高めるための具体的な勉強法を紹介します。
5-1. 過去問を使って頻出分野を抑える
都市計画法の問題を確実に得点できるようにするためには、過去問演習が不可欠です。
宅建士試験で出題される都市計画法の問題は、出題傾向に大きなブレがなく、毎年似たテーマが繰り返し出題されています。過去5年分の問題を解き出題傾向を把握することで、どの分野を重点的に学ぶべきかが明確になります。
特に区域区分や開発許可に関する問題などは何度も出題されているため、繰り返し演習して確実に得点できるレベルまで仕上げましょう。
また、過去問を繰り返すことで「出題時の文章のクセ」や「ひっかけ問題」に対する対応策も身につきます。出題者の作問意図を意識しながら解く習慣をつけていきましょう。
※こちらの記事も読まれています。
→ 宅建士試験初心者の勉強方法を6つのステップで解説!科目別の攻略法も
5-2. 作成した図解・図表をスキマ時間で覚える
都市計画法の細かい知識を定着させるには、作成した図解や図表を繰り返し確認することが重要です。作るだけで満足してしまい、見直す機会が少ないと学習効果は上がりません。大切なのは、スキマ時間を活用して図解・図表を何度も見返し、記憶に定着させることです。
スマートフォンで撮影して画像として保存したり、小さなカードにまとめて持ち歩けば、通勤・通学中や昼休み、就寝前などに手軽に復習できます。短時間でも繰り返し目にすることで、自然に知識が身につきます。
また、スキマ時間の活用は、机に向かう学習とは異なる角度から記憶を補強できる点でも有効です。
5-3. 受験指導校を使って効率良く学習する
独学ではどうしても難しい、都市計画法に関する苦手意識が抜けないという場合は、受験指導校を活用するのも有効な選択肢です。通学する時間が取れない社会人受験生でも、オンライン講座を活用すれば自分の好きな時間に重要ポイントを効率よく学べます。
プロの講師による講義では「なぜその制度が必要なのか」「なぜここが出題されやすいのか」といった背景まで学べるため、細かい知識を問われることも多い都市計画法の理解が進みやすくなります。
また、最新の出題傾向をふまえ「本試験で問われやすいポイント」を的確に示してくれるのも大きな特長です。学習の方向性に迷うことなく、限られた時間を最大限に活かせるようサポートしてくれるでしょう。講義を受けているだけで、知らない間に都市計画法に関する問題を得点源にできます。
法律系資格専門の伊藤塾では、毎年多くの合格者を送り出してきた実績と信頼をもとに、学習の不安を「自信」に変えるサポートを行っています。都市計画法に苦手意識をお持ちの方こそ、ぜひ伊藤塾の講座で本試験合格を目指してください。
※こちらも読まれています。
→ 宅建の通信講座はなぜ伊藤塾がおすすめなのか?宅建士合格講座の魅力を徹底解説
6. 宅建士試験の都市計画法に関するよくある質問(Q&A)
Q1. 都市計画法は毎年何問くらい出題される?
A. 都市計画法からの出題数は、宅建士試験では例年2問です。他の分野での失点をカバーするためにも、都市計画法の問題で確実に点を取っておくことが、合格への第一歩となります。
Q2. 都市計画法の問題は年度によって難易度が変わる?
A. 年度ごとに細かな出題内容や設問の切り口に多少の違いはありますが、都市計画法で問われる基本的なテーマや出題傾向は、例年大きく変わることはありません。
そのため、受験指導校のテキストや過去問を活用して基礎からしっかり学習しておけば、どの年度の出題にも十分対応できる力を養うことが可能です。
Q3. 都市計画法の勉強にどれくらいの時間をかけるべき?
A.「法令上の制限」の中でも、都市計画法にかけるべき学習時間は個人差があります。
もともと法律系科目に慣れている方や、図解・表を使って整理するのが得意な方であれば、比較的短時間でも得点源に仕上げることが可能です。特に、社会人の方で実務の中で都市計画法に触れている場合には、感覚的に理解できる部分も多く、スムーズに学習が進むケースもあります。
一方で、法律用語や制度に馴染みがない方、行政の仕組みに不慣れな方は、やや時間をかけて丁寧に理解する必要があります。そのため、余裕を持って学習計画に組み込むことをお勧めします。
あくまで大切なのは自分の理解度や苦手意識に合わせて柔軟に時間を調整することです。
※こちらの記事も読まれています。
→【500時間必要?】宅建士試験の合格に必要な勉強時間について徹底解説!
Q4. 細かい数字や手続きも全部覚える必要ある?
A. 都市計画法では細かな数字や手続きが数多く登場しますが、それらをすべて網羅的に覚える必要はありません。
過去問を繰り返し解いていくと、出題頻度が高い数字や手続きは限られていることが分かります。そのため、学習の際は「出題頻度が高い数字」や「正誤判断のカギとなる数字」に絞って重点的に覚える方が効率的です。
Q5. 都市計画法の問題は独学でも得点できるようになる?
A. 都市計画法に関して独学で学ぶことも不可能ではありません。市販の参考書や過去問集を活用し、図解や表を作って整理しながら学習すれば、独学でも安定して得点できる実力を養えるでしょう。
しかし、学生などで行政に関わりのない場合、都市計画法に関する内容に馴染みのない人も多いです。似たような名前や細かな数字を問われることもあるので、学習当初は理解しづらいと感じることもあるでしょう。
その場合は、受験指導校の講義などで「なぜこの規制があるのか」「どこが狙われやすいのか」といったポイント解説を聞くことで、理解がスムーズになります。
大切なのは、苦手意識をそのままにせず、必要に応じて受験指導校のサポートを受けて、自分に合った方法で理解を深めることです。独学にこだわり過ぎず、効率よく学べる環境を整えて学習を進めることが、得点力アップにつながります。
※こちらの記事も読まれています。
→ 宅建士試験に独学で合格するための効率の良い勉強法とは?後悔しないための注意点も解説
7. 正しい勉強法で都市計画法を得点源に!
宅建士試験における都市計画法は、専門用語や細かい規制が多く「難しい」と感じやすい分野ですが、短期間でも対策が可能であり、確実に得点できる分野となるため、合格を目指す上で重要な科目です。
◉宅建士試験での出題
・例年2問出題され、配点は4点
・「法令上の制限」分野(全8問)の一部として出題
・出題テーマは比較的固定されており、対策しやすいのが特徴
・効率よく確実に得点できるため、捨て問にせず、対策することがおすすめ
◉得点するためのポイント
・規制の理由を常に考える
・頻出分野を抑える
・図解・図表を活用して覚える
・引っかけパターンを知っておく
◉効率的な勉強法
・過去問演習: 過去5年分の問題を解き、出題傾向と自身の苦手分野を把握
・図解・図表の活用: 作成した図解や図表をスキマ時間に繰り返し確認し、知識の定着を図る
・受験指導校の活用: 独学で難しい場合は、専門講師の講義で効率的に学習し、得点アップを目指すのも有効
以上です。
伊藤塾では現在、2025年合格目標 宅建士合格講座を開講中です。
伊藤塾の「宅建士合格講座」は、2025年からバージョンアップし、よりカリキュラムが充実しました。
「宅建士合格講座」の内容・特長について井内絢也講師がお伝えしていますので、初めての法律資格試験として、宅建士試験を目指そうとしている方、行政書士試験、他資格からWライセンス取得を目指している方などは、是非ともご視聴ください。
「今年はさらにバージョンアップしたコースをご用意!「2025年合格目標 宅建士合格講座」 のご紹介です!」
法律知識ゼロの方でもわかりやすい講義で、短い学習時間で効率よく合格できる「宅建士合格講座」から、「権利関係」の民法「契約の成立・意思表示」の体験講義をご視聴いただけます。
是非、テキストとあわせてご覧ください。担当:宇津木 卓磨 講師
伊藤塾は、宅建士試験に本気で挑む受験生を全力で応援しています。