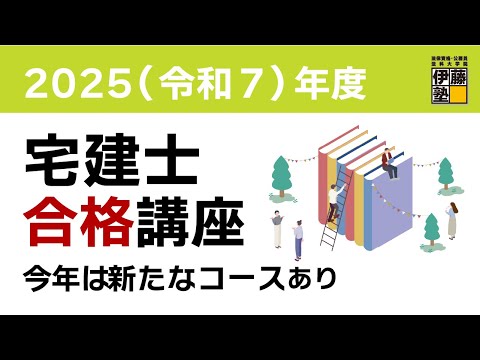【2025年】宅建士試験の申込方法は?必要な書類やよくある失敗も解説
基本情報
2025年08月29日


2025年の宅建士試験は、令和7年10月19日(日)に行われます。
申込方法は、インターネットでの申込みと郵送での申込みがあり、期日は以下の通りです。
| 申込方法 | 申込期間 |
| インターネット 申込み | 令和7年7月1日(火) 9:30〜 令和7年7月31日(木) 23:59 |
| 郵送申込み | 令和7年7月1日(火)〜 令和7年7月15日(火)まで ※簡易書留郵便として郵便窓口にて 受付され、消印が上記期間中のもの |
必要書類などをしっかりと確認して、早めに受験申込みすることが大切です。必要書類が不足していたり、申込み期間に遅れたりすると、試験を受験できなくなってしまうかもしれません。
積み上げた努力を無駄にしないためにも、事前に確認しておきましょう。
本記事では
・宅建士試験の申込方法と必要な書類
・申込みでよくある失敗例
等について取り上げました。出願ミスを防止するために、是非ご一読ください。
※宅建試験の日程や登録までの流れについては、こちらの記事で詳しく解説しています
→【2025年最新】宅建の試験日は?申込み・持ち物・合格発表など試験の詳細を解説
※宅建士の資格の詳細については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
→【完全版】宅建とは?試験の詳細や宅建士の仕事内容など資格のすべてを徹底解説!
【目次】
1.宅建士試験の申込みに必要な書類
宅建士試験の申込みに必要な書類は、申込方法によって異なります。
・インターネットでの申込み
・郵送での申込み
それぞれで必要な書類を説明します。
1-1.インターネットで申込む場合
インターネットで申込む場合、願書などの書類は必要ありません。ただし、次の準備が必要です。
・インターネットに接続できる環境
・メールアドレス
・顔写真(顔部分が画像全体の高さの80~90%を占めているもの)
顔写真は、スマートフォンでも撮影することができます。なお、免許証などの本人確認書類は必要ありません。
インターネットによる申込みは、次の手順で行うことができます。
令和6年度のインターネット申込みページ
→ 不動産適正取引推進機構|宅建試験インターネット申込システム
※「令和 7年7月1日9時30分」から操作可能となる予定です。
① メールアドレスを登録する
② 「メールアドレス登録完了のお知らせ」が届くので、メールに記載されているURLから、氏名、生年月日、パスワード等を登録する ③ 「マイページ登録完了のお知らせ」のメールが届く
④ 登録した情報を用いて、マイページにログインする
⑤ マイページの「受験の申込み」から、試験申込を行う
1-2.郵送で申込む場合
郵送で申込む場合は、次の書類が必要です。・受験申込書(願書)
・顔写真(縁なしで縦4.5㎝、横3.5㎝のもの)
・A4判の用紙が折らずに入る大きさの返信用封筒
免許証などの本人確認書類は必要ありません。受験申込書は、全国の協力機関や書店などで配布されています。また、協力機関宛に郵送で請求することもできます。
受験申込書(願書)を入手したら、受験手数料(8,200円)の支払いを行いましょう。支払い方法は、次のいずれかの方法が、試験案内で指定されています。
・ペイジー
・コンビニエンスストア
・郵便振替
各都道府県ごとに、指定されている支払い方法が異なるため注意しましょう。
2.【注意】宅建士試験の申込みでよくある失敗3選
宅建士試験の申込みでよくある失敗を3つ紹介します。
・申込期間を間違える
・郵送の方法を間違える
・顔写真の規格を間違える
出願ミスをしてしまうと、受験できなくなる可能性もあるので、十分注意しましょう。それぞれ説明します。
2-1.申込期間を間違える
よくある失敗の1つ目は、「申込期間を間違える」ことです。宅建士試験の申込方法は、インターネットで申込む場合と、郵送で申込む場合で異なっています。
| 申込方法 | 申込期間 |
| インターネット 申込み | 令和7年7月1日(火) 9:30〜 令和7年7月31日(木) 23:59 |
| 郵送申込み | 令和7年7月1日(火)〜 令和7年7月15日(火)まで ※簡易書留郵便として郵便窓口にて 受付され、消印が上記期間中のもの |
上記の通り、「郵送申込み」は「インターネット申込み」より受付締切日がかなり早くなっています。申込期間を過ぎてしまうと、受験できなくなってしまうため、早めの申込みを心がけましょう。
2-2.郵送の方法を間違える
よくある失敗の2つ目は、「郵送の方法を間違える」ことです。
郵送による申込みについて、不動産適正取引推進機構のHPでは、「簡易書留郵便として郵便局の窓口で受付されたもので、消印が上記期間中のもののみ受付けます。 それ以外のものは受付けません。」と指定されています。
間違えて、普通郵便でポストに投函しないように注意しましょう。
2-3.顔写真の規格を間違える
よくある失敗の3つ目は、「顔写真の規格を間違える」ことです。申込みで必要な顔写真には、次のような規格が決められています。
・縦4.5cm×横3.5cm(パスポート申請用サイズ)
(※インターネットの場合、縦900ピクセル以上、横720ピクセル以上)
・受験する年の1月1日以降に撮影されたもの
・背景がないもの
・帽子やヘアバンド、マスクをしていない
・アプリで加工していない
・シール式の写真は不可
※参考:(一財)不動産適正取引推進機構「宅建試験のFAQ」
顔写真は、試験当日の本人確認でも使用されるので、できる限り鮮明に撮影しましょう。
3.身体に障がい等がある方への注意事項
身体に障がい等がある場合、一定の配慮をしてもらうことができます。
例えば、
・車いすを使用しており、低層階での試験室を希望する場合
・視聴覚等に障害があって、通常の試験方法に支障がある場合
などです。
ただし、事前に申し出ることが必要です。受験申込みの際に、協力機関に相談してみましょう。
4.受験票は必ず手元に保管を!
試験の申込みが完了したら、10月1日(水)に受験票が発送される予定です。
受験票には、自分が受験する試験会場が記載されています。
インターネット申込みが受理された方は、マイページで8月下旬から確認できます。 郵送申込みの方は、8月下旬に開設予定の専用の問合せダイヤル(郵送申込みの試験案内に記載)又は、試験を申し込んだ都道府県の協力機関へお問合せください。
受験票は、試験当日に持参する必要があるため、紛失しないように大切に保管しましょう。
10月8日(水)までに届かない場合は、各県の協力機関又は不動産適正取引推進機構への問い合わせが必要です。また、万が一紛失してしまった場合は、試験当日に「顔写真付きの身分証明書」を持参して、再発行の手続きを行いましょう。
5.【Q&A】宅建士試験の必要書類に関するよくある質問
5-1.Q.申込みに必要な書類(願書)はどこでもらえる?
願書(受験申込書)は、全国の協力機関や書店などで配布されています。例えば、東京都では、次のような場所で入手できます。
・東京都庁や市役所
・東京都宅地建物取引業協会
・全日本不動産協会東京都本部
・各書店(紀伊國屋書店、くまざわ書店、ジュンク堂書店など)
なお、配布期間は「7月1日(火)〜15日(火)」までです。
5-2.Q.免許証や身分証のコピーはいる?
宅建士試験の申込みに、免許証や身分証のコピーは必要ありません。ただし、受験票を紛失した場合は、当日、顔写真付きの身分証明書の持参が必要です。
5-3.Q.宅建士試験の申込みが無事に完了したかはいつ分かる?
インターネット申込みの場合、受験手数料の払込日から3営業日目にメールが届く他、マイページにも表示されます。不備がある場合も、補正の連絡がマイページで告知されるため、確認しておきましょう。
郵送申込の場合も、不備があれば連絡が来るケースが多いようですが、心配な場合は、協力機関等に確認してみましょう。
5-4.Q.申込みが遅れたらどうなる?
申込みが遅れると、宅建士試験を受験できなくなります。申込期間は、インターネットと郵送で異なるため、必ず事前に確認して、早めの申込みを行いましょう。
6.まとめ
今回は、宅建士試験の申込方法と必要な書類や、注意点について取り上げました。
申込みに必要な書類や、受験生が失敗しがちな注意点を確認して、万が一の出願ミスを防止しましょう。
もしも「宅建士試験に申込もうと思っているけど、このままでは合格が難しいかも…」と感じている方は、法律資格専門の指導校である伊藤塾にぜひご相談ください。
伊藤塾の「宅建士合格講座」は、2025年からバージョンアップし、よりカリキュラムが充実しました。
「宅建士合格講座」の内容・特長について井内絢也講師がお伝えしていますので、初めての法律資格試験として、宅建士試験を目指そうとしている方、行政書士試験、他資格などのWライセンス取得を目指している方は、是非ともご視聴ください。
※こちらも併せてお読みください。
→ 宅建の通信講座はなぜ伊藤塾がおすすめなのか?宅建士合格講座の魅力を徹底解説
「今年はさらにバージョンアップしたコースをご用意!!「2025年合格目標 宅建士合格講座」 のご紹介です!」