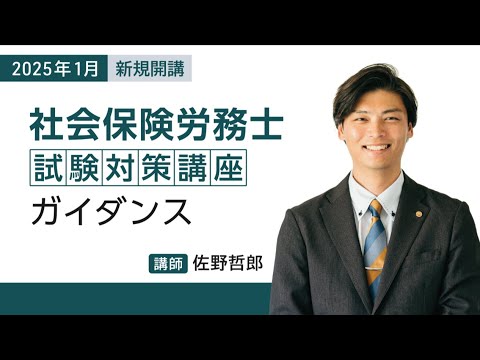社労士試験は独学で合格できる?効果的な勉強方法や独学ならではの課題を解説
勉強法
2025年09月10日


労務コンプライアンスや従業員のメンタルヘルスケアに注目が集まる現代において、社会保険労務士(以下、社労士)という資格は、キャリアアップを目指す多くの人から注目されています。
しかし、いざ資格取得を目指すとなった場合、多くの人が「独学でも合格できるのだろうか」「どのような学習方法をすれば合格できるのか」と考えるのではないでしょうか。
社労士試験は難易度が高い資格試験ではありますが、独学での試験合格も決して不可能ではありません。
ただし、独学で合格を達成するためには、押さえるべきポイントや、乗り越えなければならない壁が存在します。
本記事では、社労士試験を独学で合格するために重要となる要素や、独学ならではの課題を解説していきます。さらに、より効率的に合格を目指すための選択肢として、受験指導校活用のメリットについてもご紹介していきます。
社労士試験に挑戦をしてキャリアアップを目指している方は、試験合格への一歩として、ぜひ参考にしてください。
【目次】
1. 独学による社労士試験合格は無理?社労士試験の難易度は?
社労士試験は難易度の高い国家試験ですが、独学で合格を達成する受験生がいることも確かです。まずは試験の概要を踏まえた難易度と、独学で試験に挑戦するメリットをお伝えします。
1-1.社労士試験の概要と難易度
社労士試験は、以下の通り開催されます。
| 項目 | 内容 |
| 実施日 | 毎年8月の第4日曜日 2025年8月24日(日) |
| 試験時間 | 約5時間 午前:10:30〜11:50 午後:13:20〜16:50 |
| 試験科目 | 全10科目 |
| 試験形式 | 選択式試験(午前) 択一式試験(午後) |
| 合格基準 | 選択式試験・択一式試験の総得点と それぞれにおける各科目の得点が すべて基準点を満たすこと ※基準点は合格発表日に公表 |
社労士試験は、合格率が例年10%を下回る難易度の高い国家資格です。
試験範囲が全部で10科目と幅広く、いずれかの科目や総得点が基準点数に満たないと不合格となる厳格な合格基準が設けられています。
※社労士試験の合格基準点などについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
1-2.独学のメリット
非常に難易度の高い試験ですが、独学で試験に挑戦することには次のようなメリットがあります。
1-2-1.費用を抑えられる
独学による最大のメリットは、費用が大幅に抑えられる点です。講座を受講する場合は、相応の受講費用を支払う必要があります。しかし、独学であれば、最低限のテキストや問題集の費用のみで学習を進めることが可能です。
受験のためのコストをできるだけ抑えたい人にとっては、非常に大きなメリットとなります。
1-2-2.自分のペースで学習を進められる
自分の生活リズムや理解度に合わせて学習を進められる点も、独学のメリットです。通学の手間やオンライン環境の準備などが不要で、好きな時間に好きな場所で学習をすることができます。
周りから学習方法や進捗を指定されずに、自分のペースで学習を進めていきたい人にとって、自由度が高く魅力的な学習方法です。
2. 独学で合格するために必要な3つのポイント
独学で試験に挑戦することはメリットもありますが、決して簡単な道のりではありません。そこで、独学での合格を実現するために不可欠なポイントを3つご紹介していきます。
・学習スケジュールを組み立てる
・勉強方法を確立する
・自己管理能力を身につける
2-1.学習スケジュールを組み立てる
1つ目のポイントは、自分自身で学習の進捗を管理するために、適切な学習スケジュールを組み立てることです。
社労士試験合格には、一般的に1,000時間程度の学習時間が必要と言われています。1年間で合格を目指すのであれば、1週間で20時間程度の学習時間を確保する必要がある計算です。
かなりの時間を費やす必要があるため、仕事や生活と両立するにはしっかりとスケジュールを考え、生活の中に学習を組み込んでいくことが不可欠です。
ゴールである試験日から逆算して、「いつまでにどこまで進めるか」「週にどのくらい勉強をするか」などを具体的に予定を決めることで、試験日までの道筋が明確になり、モチベーションを保ちながら学習を進めやすくなります。
ただし、社労士試験のように長期間の学習が必要な資格勉強では、生活リズムを無視して無理に勉強時間を作ろうとすると、学習を続けることに疲れ、挫折してしまう可能性があります。試験日まで学習を継続するためには、無理なく仕事や生活と両立できるスケジュールを立てることが非常に大切です。
2-2.勉強方法を確立する
2つ目のポイントは、自分に適した勉強方法を確立することです。相性の良い勉強方法を見つけて取り入れることは、学習を継続させるために重要な要素です。
2-2-1.テキストの選択
学習方法を確立するためには、まずは使いやすいテキストを見つける必要があります。
テキストは複数の出版社から出ているため、実際に中身を確認し、読みやすさやわかりやすさを考えながら、自分に適したものを選ぶことが重要です。
また、古いテキストを使用すると、新たな法改正の内容が反映されていないなど、誤った知識を身につけてしまう可能性もあるので、注意が必要です。
テキストは学習の基盤であり、特に独学においてはテキストから得た知識を元に資格試験に臨むことになります。そのため、価格などで安易に決定せず、自分が無理なく学習を継続できると思えるものを選びましょう。
2-2-2.疑問点の解消方法
テキストを正しく理解するには、学習時の疑問点を適切に解消することが必要です。
社労士試験は専門的な知識が多いため、テキストを読むだけでは理解が難しい箇所に必ず直面します。わからない箇所を読み飛ばしていると、知識を体系的に理解することができません。
疑問点を解消する際、インターネットでの検索を利用するのが一般的ではありますが、インターネット上には古い法令に基づいた情報や根拠が明らかではない情報など不確かなものも多くあるため、注意が必要です。
そのため、疑問点を検索する際は、厚生労働省や年金機構など行政機関から発信された情報や、根拠が明らかである情報を参考にして、正しい知識を確認する必要があります。
2-2-3.法改正情報の収集方法
社労士試験に関係する法令は頻繁に改正が行われるため、受験する年の試験に合わせた最新の情報を収集することが不可欠です。
学習期間中に法改正がある場合、テキストの内容とは異なった情報を改めて覚えなければいけない可能性もあります。使用しているテキストの内容から、法令等の変更が行われていないか、試験に必要なのはどの情報なのかを定期的に確認しながら学習を進めていくことが必要です。
2-2-4.インプットとアウトプットを繰り返す
幅広い範囲の知識を効率的に学習するためには、インプットとアウトプットをバランスよく組み合わせた学習を取り入れることが大切です。
「テキストを読む」「ノートをまとめる」といったインプット学習だけをしていると、知識の定着率が上がらず、自分の理解度を把握することも困難です。
「過去問題を解く」「学習した知識を人に話す」などのアウトプット学習も並行することで、学習したことを頭の中で整理することができます。さらに、理解が不足している部分が明確になり、それを新たに調べていくことで、知識の定着率を上げることに繋がります。
社労士試験では幅広い範囲の知識を理解していかなければいけないため、インプットとアウトプットを繰り返し、着実に知識を身につけていきましょう。
2-3.自己管理能力を身につける
3つ目のポイントは、学習における自己管理能力を身につけることです。自分が学習を続けやすい環境を管理していくことが、試験日まで学習を継続させる鍵となります。
2-3-1.モチベーションの維持
長い学習期間の中では、勉強に対するモチベーションが下がってしまう時が必ず訪れます。特に独学の場合は、試験に関して誰かと話したり情報共有したりする機会が少なく、一人きりで勉強を進めることが多いため、学習に対する意欲を見失いがちです。
モチベーションが下がると、学習を続けることが苦痛になり、集中力や理解度も低下してしまいます。
そのため、勉強の合間に息抜きの時間を設けてメリハリをつけたり、目標達成時に自分へのご褒美を用意したりするなど、学習のモチベーションを保つ工夫をすることが重要です。
2-3-2.スケジュール設計と進捗管理
独学で試験に合格するためには、決めた学習スケジュールを守るための時間管理も必要です。スケジュールを決めることの大切さは先ほどお伝えしましたが、ただ決めるだけではなく、その通りに学習を進められるような時間管理をしなければいけません。
予定通りに時間が取れなかった部分は別日に振り替えたり、理解が進まない箇所は学習時間を増やしたり、学習の進捗と過不足などを考えながら学習を進めていくことが重要です。
2-3-3.学習環境の整備
日々の学習を前向きに取り組むためには、自分が勉強を続けやすい環境を整えることも重要です。自宅に学習スペースを作ったり、図書館を利用したりするなど、勉強を日常的に取り入れられるような環境を作り出すことで、集中して継続的に学習を進めることができます。
また、スマートフォンやテレビなどを物理的に遠ざけたり、集中しやすい音楽を聴いたりするなどの環境作りも有効です。
自分にとって最適な学習環境を整えることで、長期的な学習を乗り切ることができます。
3. 独学での学習管理の難しさ
ここまで、独学で合格を目指すための重要なポイントをお伝えしてきました。しかし、社労士試験を独学で合格するためには、乗り越えなければならない壁も存在します。
次に、独学で試験に挑戦する上で直面する4つの課題についてご説明していきます。
・孤独な学習により不安感が生じる
・専門知識を収集することに限界がある
・全科目を網羅的に学習する必要がある
・利用できる学習ツールが限定的である
3-1.孤独な学習により不安感が生じる
学習を進めていると、自分の理解度や学習方法に不安が生じてしまうことがあります。
正しい情報の区別がつかなくなったり、適切な学習方法に迷ってしまったりすると、モヤモヤとした気持ちのまま進めることになります。
独学の場合は、不安な気持ちを誰かに共有したり、疑問を解消する方法を見つけることが特に困難です。勉強に対して孤独感や不安感を持ったまま続けると、モチベーションが低下し、途中で挫折してしまう原因にもなり得ます。
3-2.専門知識を収集することに限界がある
社労士試験の試験範囲は非常に幅広く、専門的な知識を細かく理解することが必要です。しかし、テキストの内容だけでは理解ができない時にインターネットなどで検索をしても、納得できる回答が得られないこともあります。
正確な情報を把握することができないと、学習に対する不安感を持ったまま学習を進めていかなければなりません。特に独学では、専門的な情報を集めることに限界があるため、理解が進まないことで学習の意欲や効率が低下してしまう可能性もあります。
3-3.全科目を網羅的に学習する必要がある
試験合格のためには、全10科目の幅広く細かい知識を学習する必要があります。
合格の基準として全科目で一定以上の点数の取得が求められるため、苦手科目であっても最低限の理解をしておくことが不可欠です。試験範囲の全体を網羅的に学習することは、独学において非常に難しい点です。
試験範囲が広く、学習期間も長期にわたるため、各科目への時間配分や苦手科目の克服方法を見出すことが課題となります。
さらに、独学の場合、知識をどこまで深く理解しなければいけないのかを把握することが難しく、不必要に深堀りしてしまい、時間を費やしてしまう可能性もあります。
このように、全科目を効率的に学習することが独学では困難であり、この点が学習効率を低下させる大きな要因にもなります。
3-4.利用できる学習ツールが限定的である
独学では、利用できる学習教材や問題集が限られています。
試験傾向を分析した教材や演習問題を使うことが難しいため、効率的な学習の妨げとなります。また、使用できる学習アプリなども限定的であり、学習方法の幅が狭まってしまいます。
このため、最新の試験傾向や頻出問題などの情報を適切に把握できず、十分な試験対策を行いながら学習を進めることが難しくなります。
4. 学習の自己管理が難しいと感じたら
先述の通り、独学で社労士試験に合格することは不可能ではありません。
しかし、10科目と広範な学習が必要なうえに頻繁な法改正もある社労士試験に対し、独学で臨むことは決して簡単なことではないという点も事実です。
実際に、社労士試験の合格者の多くは受験指導校を活用し、無駄のない効率的な学習によって合格を手にしてきました。もし独学では難しいと感じた際には、受験指導校の活用を検討してみるとよいでしょう。
ここでは、受験指導校で学ぶことにはどのようなメリットがあるのかを具体的にご紹介していきたいと思います。
4-1.効率的かつ体系的な学習カリキュラムがある
受験指導校では、試験合格に向けた体系的なカリキュラムが用意されており、効率的な学習が可能です。
考え抜かれたカリキュラムに沿って学習を進めていくだけで、社労士試験の広範な試験範囲をヌケモレなく効率よく学習することができます。
また、講座の開始時には、効果的な受講方法や復習の仕方なども教えてくれるため、安心して学習をスタートすることができ、学習方法に迷うことなく試験日を迎えることができるでしょう。
教材は一般的に販売されているものよりも「読みやすさ」「使いやすさ」が意識されたものとなっており、学習に対する抵抗を減らして学習を進めることできます。
4-2.専門家に質問して疑問を解消できる
受験指導校では、学習内容に関する疑問が生じた際に、講師に質問ができるシステムが用意されています。そのため、複雑な制度の内容や判例の解釈など、独学では理解が難しい部分に対して、試験に精通した専門家から的確な回答を得ることができます。
これにより、疑問点が生じるたびに解決しながら学習を進められるため、知識を確実に定着させることが可能となります。
4-3.最新の法改正情報を得られる
受験指導校で学ぶことで、その年度の最新の法改正に合わせた学習範囲の変更点を、適切に把握することができます。社労士試験に関連する法令は頻繁に改正が行われるため、最新の法改正への対応は合格のための重要なポイントです。
独学の場合は自力で行う必要があり、正確性に不安が残りますが、受験指導校では適切なタイミングで必要な法改正情報を通知してくれます。
自分で情報を探して曖昧な知識を取り込んでしまうリスクを避け、試験に必要な知識を効率的に習得することができるのです。
5. まとめ
当記事では、社労士試験に独学で挑戦をするメリットや合格のためのポイント、重要な壁について解説をしました。
独学には費用を抑えたり、自分のペースで学習を進められるなどのメリットがある一方、モチベーション維持や情報収集の難しさなどの課題も存在します。
もし、自分自身で学習スケジュールを作成、自己管理し、法改正のこまめな情報チェック、難しい問題を自己解決していくことなどに対して不安を感じるのであれば、受験指導校の利用もぜひ検討してみてください。
伊藤塾では、2025年の合格を目指して、2025年合格目標 社労士試験合格講座を開講中です。
社労士試験に合格して人生を変える挑戦に臨みたい方は、ぜひ一歩を踏み出してみてください。伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。
【社労士】伊藤真塾長×持田裕講師~伊藤塾で「社労士」を目指す意味とは~