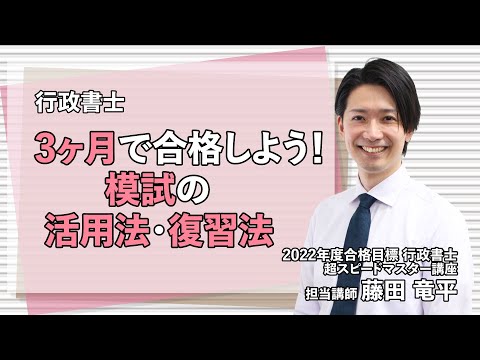行政書士試験の模試はいつから受ける?模試の活用法を徹底解説
試験詳細
2025年09月12日


行政書士試験が近づくと、本格的な模試シーズンに突入します。
「模試はいつから受ければいい?」
「本試験より難しいって本当?」
「120点〜130点しか取れてなくても、合格した人はいる?」
このように模試との向き合い方に悩んでいる方も多いでしょう。
実は、多くの受験生が模試の位置づけを間違えています。
点数ばかり気にしたり、模試の問題を徹底的に復習したりと、間違った使い方をしている人が珍しくないのです。
模試を正しく活用できるかどうかが、合格のカギを握っているといってもよいでしょう。
うまく使えば、勉強の方向性を修正してくれる強力なツールになりますが、使い方を間違えると、逆に合格を遠ざけてしまう可能性もあるのです。
そこで今回は、模試について受験生が知っておくべき内容を取り上げました。
◉この記事を読んで分かること
・模試を受け始めるタイミングと回数
・本試験との難易度の違い
・模試の正しい活用法
・当日に気をつけるポイント など
ぜひこの記事を読んで、模試への向き合い方や正しい活用法を身につけてください。
模試をうまく使うことができれば、一気に合格へと近づくはずです。
【目次】
1.行政書士試験の模試はいつから受けるべき?
行政書士試験の模試を受け始めるタイミングは、人によって異なります。
・初めての行政書士試験を受験するのか
・それとも、2回目や3回目以降の再受験なのか
・いつから勉強を始めたのか
・どの程度の勉強期間を確保できるのか
・学習の達成度はどれくらいか
このような要素によって変わってくるからです。
例えば、インプット・アウトプットが全く終わっていないのであれば、毎日の勉強を犠牲にしてまで模試を受ける必要性はないでしょう。逆に、一通り勉強が終わっていれば、模試を受けることで勉強の方向性を修正していくことができます。
あなたが置かれている状況によって、最適なタイミングは変わってくるのです。
一般的には、1年以上かけて勉強する場合は5月頃、短期間での合格を目指す場合は9月頃を目安にすると良いと言われています。自分の学習状況に合わせて、柔軟に判断しましょう。
1-1.1年以上かけて勉強するなら半年前
1年以上かけて勉強する場合は、5月あたりを1つの目安にしましょう。
半年前から模試を受け始めて、学習の達成度をチェックします。
この時点での目的は、どこまで学習が進んでいるのか、基本事項や重要論点が理解できているのかをチェックすることです。細かいテーマや知識を気にする必要はありませんし、本試験と同じボリューム(60問)にこだわる必要もありません。自分の実力を客観的に確認して、その後の学習計画に役立てるという意識で受験しましょう。
1-2.短期間での合格を目指すなら3ヶ月前
短期間での合格を目指す場合は、9月あたりを目安に、試験の3ヶ月前から受け始めると良いでしょう。本試験までに、2回〜3回程度受けることを目標にして、自分の弱点をチェックしましょう。
・受験生の50%が正解しているのに自分だけ落としている問題はないか
・明らかに弱点となっている科目はないか
・記述式で何も書けないという状況になっていないか
このような点を確認し、学習の方向性を見定めることが大切です。
なお、模試の結果が悪かったとしても、時間をかけて復習する必要はありません。あくまでも「弱点を把握できれば良い」という意識で受験しましょう。
※あわせてこちらの記事も読まれています。
2.行政書士の模試は点数取れない?本番より難しい?
行政書士の模試は、本試験よりも難しいと言われることがあります。
しかし、はっきりとした難易度の差があるわけではなく、年によって異なるのが実情です。模試の方が難しい年もあれば、本試験の方が難しい年もあるでしょう。
では、なぜ多くの受験生が「模試は本試験よりも難しい」と感じるのでしょうか?
その理由として、次のようなことが考えられます。
・模試と本試験で、問題の傾向が若干異なっていた
・模試で、自分の苦手分野が集中的に出題された(弱点をチェックできた)
・模試が終わった後の、超直前期に実力が急激にアップした
つまり、模試で思うような点数が取れなかったことが、「模試は難しい」という印象につながっているのです。
しかし結局のところ、模試の難易度がどうであれ、大切なのはそれをどのように活用するかです。実際、以下のようなケースはよく聞く話です。
・模試で一度も合格点が取れなかったのに、本試験で合格した
・模試の点数が200点を超えていたのに、本試験で不合格となった
模試は、あくまでも「模擬」試験に過ぎません。結果に一喜一憂するのではなく、自分の実力を測る貴重な機会と考えましょう。
3.行政書士試験の模試の活用例
行政書士試験の模試は、自分の実力を測る貴重な機会です。
しかし、模試の活用法を間違えると、逆に合格から遠ざかってしまう場合もあるため注意が必要です。模試を上手に活用するための方法を見ていきましょう。
3-1.◯良い例|自分の弱点をチェックするために使う
模試の効果的な活用法は、自分の弱点を把握するために使うことです。
模試では、それぞれの問題で受験生が正答している割合(正答率)が公表されます。点数に一喜一憂するのではなく、この正答率に目を向けることが大切です。
◉正答率が70%を超えている問題
→絶対に落としてはいけない基本的な問題
◉正答率が50%を超えている問題
→合否を分ける重要な問題
◉正答率が30%しかない問題
→間違っても気にする必要がない問題
このように、問題の正答率によって、復習の方向性も変わっていきます。
他の受験生の正答率が高いのに、自分が間違っている問題は、自分の弱点である可能性が高いでしょう。本番までに優先的に復習することが必要です。
3-2.◯良い例|時間配分の練習をする
模試を利用して、時間配分の練習をすることも効果的です。
行政書士試験では、3時間で60問の問題を解くことになります。3時間と聞けば長く感じるかもしれませんが、実際に解くと非常に短いです。おそらく、多くの人が「時間が足りない」と感じるでしょう。
本番でパニックにならないためにも、時間配分を確認しておくことが大切です。
・今の解き方で時間が足りるのか
・基礎知識科目と法令等科目で、どの程度の時間をかけるべきか
・記述式問題には、どれくらいの時間を確保すべきか など
もしも時間が足りないと感じたら、問題の解き方を工夫するだけで改善できる場合もあります。例えば、次のような方法を試してみましょう。
・問題に取り掛かる順番を変えてみる
・ポイントがすぐに分かるように、重要キーワードをマーカーで塗ってみる
・問題文をスラッシュ(/)を区切りながら読んでみる など
最低でも2〜3回は模試を受けて、時間配分の練習をしておきましょう。
何度か練習するうちに、自然と自分に合った解き方が分かってくるはずです。
3-3.✕悪い例|模試の問題を徹底的に復習する
一方、最も避けるべきなのは、模試の問題を徹底的に復習することです。そもそも、合格に必要な知識は、毎日の勉強で学習しているはずです。そのため、模試で間違えても「実は分かっていなかった」ということさえ分かれば、模試の問題を復習する必要はありません。
もちろん、中には模試の予想が的中するケースもありますが、それが合否に影響する可能性は低いでしょう。本当に大事な問題(基本的な問題)であれば、模試で解いていなくても正答できるはずだからです。実際、合格者に話を聞いてみても、模試のおかげで合格できたという声は少ないです。
むしろ、模試で新しい知識を吸収しようとして、本当に重要な知識が抜けてしまうリスクの方を恐れるべきです。
曖昧な知識をどれだけ増やしても、合格に近づくことはありません。基本的な知識を正確に理解してこそ、初めて合格に近づけるのです。
模試の復習は当日の2〜3時間程度にとどめて、翌日に持ち越さないことをオススメします。
4.模試は何回受ける?120点〜130点しか取れない場合は回数を増やす?
行政書士試験の模試は、何回受けるべきでしょうか?
結論から言えば、模試の点数によって、受けるべき回数も変わってきます。
4-1.点数が合格ラインに達している場合|4回前後が目安
模試の点数が合格ライン(180点)に届いているなら、4回前後を目安にすると良いでしょう。ある程度の実力が付いているので、何度か本番のシミュレーションをしてみることで、本番の得点が上がりやすくなります。
ただし、回数の増やしすぎには十分に注意しましょう。模試を受ける回数は、多ければ多いほど良いわけではありません。
4-2.点数が伸び悩んでいる(120点〜130点など)場合|2回前後が目安
一方、模試の点数が伸び悩んでいるのなら、2回前後を目安にするのがよいでしょう。点数が取れないからといって、模試を受ける回数を増やすべきではありません。
例えば、模試で120点〜130点程度しか取れていなかったりする場合は、そもそも基本的な知識が漏れている可能性が高いです。
そのため、何度もシミュレーションを重ねても大きな効果は得られません。模試に時間を費やすのではなく、日々の学習に力を入れましょう。
SNSなどを見ると、「模試を〇〇回受けて、全て180点を超えた」などという投稿がたくさん出てきます。しかし、これを気にする必要は全くありません。
大切なのは、模試で見つかった弱点を、本番までに克服することです。模試はあくまでも単なる通過点に過ぎません。最終的な目標は、本試験での合格であることを忘れないようにしましょう。
5.行政書士試験の模試当日に気をつけること
行政書士試験の模試は、本番さながらの環境で受験することが大切です。
当日は、「朝からの行動をすべて決めておく」「本番と同じ環境で解いてみる」などのポイントに気を配って、本試験当日のコンディションを再現しましょう。
5-1.朝からの行動をすべて決めておく
模試の当日は、朝からの行動をすべて決めておくことをオススメします。試験の3時間だけではなく、その前の行動も決めておき、本試験当日のシミュレーションをしてみましょう。
・朝は何時に起きるのか
・朝ご飯は何を食べるのか(ご飯?パン?)
・午前中は勉強をするのか
・お昼ごはんはどうするのか
・会場には何時に行くのか
・着いてからどうするのか など
起床時間、食事の内容、午前中の過ごし方によって、脳のコンディションは変わってきます。せっかく受けるなら、本試験当日のコンディションを再現した上で受験しましょう。
5-2.本番と同じ環境で解いてみる
本番と同じ環境で解いてみることも、模試当日に気をつけたいポイントの一つです。
1人で試験を受けるのと、周りに人がいる環境で受けるのでは、集中力が全く変わってくるからです。毎年、多くの人から「模試の会場の雑音が気になって集中できなかった」という相談をいただきます。
・隣に座っていた人の筆記音が気になった
・前の人が貧乏ゆすりをしていて気が散った
・会場で、咳や鼻水の音がうるさかった
・外から騒ぎ声が聞こえてきた など
しかし、これらは模試に限った話ではありません。
本試験当日も、こういった問題は必ず発生します。「当日、会場が静かで集中できました」と話す合格者はほとんどいません。
そのため、模試を利用して、集中しづらい状況で解くトレーニングをしておきましょう。
・近くに模試の会場があるなら、できる限り会場で受験してみる
・会場受験が難しいなら、周りに人がいる環境で解いてみる(コワーキングスペースなど)
・耳栓をして受験することはしない など
本番さながらの環境で受験し、周りの環境に左右されずに、試験に集中する練習をすることが大切です。模試を有効活用して、本番に向けた練習を積んでおきましょう。
6.模試が難しい・点数取れないと感じる方へ!藤田講師が語る模試の活用法
最後に、伊藤塾の藤田講師が、模試の正しい活用法と復習方法について、わかりやすく解説します。
8分程度の動画なので、ぜひ内容をご覧いただき、直前期の大きな悩みである「模試の活用法・復習法」について確認してください。
7.まとめ
最後に、今回のポイントをまとめます。
◉ 模試を受け始めるタイミングは、学習状況に応じて判断する
・1年以上かけて勉強する場合→半年前(5月頃)からが目安
・短期間での合格を目指す場合→3ヶ月前(9月頃)からが目安
◉ 点数に一喜一憂するのではなく、目的を明確にして模試を活用すること
・(◯)自分の弱点をチェックする
・(◯)時間配分の練習をする
・(✕)全ての問題を復習する
◉ 模試を受ける回数は実力によって変える
・点数が合格ラインに達している場合→4回前後が目安
・点数が伸び悩んでいる場合→2回前後に留め、日々の学習を優先する
◉ 模試の当日に気をつけるポイント
・朝からの行動を決めて、本試験当日のコンディションを再現する
・会場の環境や雑音に慣れるため、周りに人がいる環境で受験する
以上です。
模試を上手く活用すれば、行政書士試験の合格に大きく近づきます。
是非、この記事を参考にして、模試の活用法を再確認してみてください。
伊藤塾では、行政書士試験で必要な内容を、初歩からしっかり学習していくことができる「行政書士合格講座」も開講しています。
夢の実現に向けて、ぜひ一歩を踏み出してみてください。
伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。