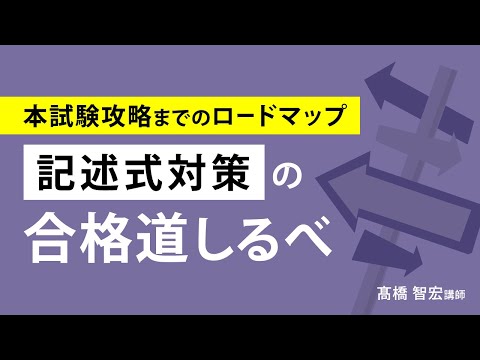【2025年度】司法書士試験の合格点を講師が分析!上乗せ点は今後どうなる?
試験詳細
2025年10月02日


令和7年10月2日(木)、司法書士試験の筆記試験合格点が発表されました。
合格点は「満点350点中255.0点」、上乗せ点は「35.0点」という結果でした。
※「上乗せ点」については、2章で詳しく解説しています。
ちなみに、記述式の基準点は昨年よりも大幅に下がりました(83点→70点)が、上乗せ点の大幅な増減はありませんでした。
合格点に届かなかった方は、とても悔しい思いをされているでしょう。しかし、ここで諦める必要はありません。
本記事では、令和7年度(2025年度)司法書士試験の合格点について、昨年と比較しながら、伊藤塾・髙橋講師による詳細な分析をお届けします。さらに、令和8年度(2026年度)試験に向けて、上乗せ点を確保するための具体的な戦略もお伝えします。
合格点分析から見えてくる傾向と対策を知って、合格を勝ち取りましょう。
【目次】
1.令和7年度(2025年度)司法書士試験における合格点は255点
2025年10月2日(木)、令和7年度(2025年度)司法書士試験の合格点が発表されました。
筆記試験の合格点は「満点350点中255点」、合格点と基準点の差は「35点」でした。
| 令和7年度(2025年度)の司法書士試験における合格点・基準点 | ||
| 試験内容 | 合格点及び基準点 | 得点率 |
| ①午前の部(多肢択一式問題) の基準点 |
満点105点中78点 | 74.3% |
| ②午後の部(多肢択一式問題) の基準点 |
満点105点中72点 | 68.6% |
| ③記述式問題の基準点 | 満点140点中70点 | 50.0% |
| 筆記試験合格点 | 満点350点中255.0点 | 72.9% |
| 筆記試験合格点と基準点の差 (上乗せ点) |
35.0点 | ー |
参照:令和7年度司法書士試験筆記試験の合格点等について|法務省
「①午前の部(択一式)」で78点以上、「②午後の部(択一式)」で72点以上、「③午後の部(記述式)」で70点以上を得点し、かつ「筆記試験全体の合計点」が255点を超えていた方が、筆記試験合格ということになります。
なお、令和6年度(2024年度)の配点変更によって、記述式が「2問で70点満点」から「2問で140点満点」に変わりました。これに伴って、筆記試験で必要な合格点・上乗せ点も大幅に上がっています。
試験全体で記述式問題の重要性が高まっていると考えてよいでしょう。
(参照:【重要】司法書士試験筆記試験記述式問題の配点の変更について|法務省)
2.そもそも司法書士試験の基準点・合格点・上乗せ点とは
ここで、司法書士試験の「基準点」「合格点」「上乗せ点」の仕組みについて確認しておきしょう。
司法書士試験は、午前の部(多肢択一式)、午後の部(多肢択一式)、午後の部(記述式)の3つで構成されていますが、それぞれで「基準点」が設定されています。
「基準点」とは、午前の部(多肢択一式)、午後の部(多肢択一式)それぞれにおいて、合格に必要な最低限の点数のことで 仮に筆記試験の総合点が「合格点」を超えていた場合でも、「基準点」を一つでも下回っていれば、司法書士試験は不合格となります。
【司法書士試験における3つの基準点・合格点】
| 必要な得点率の目安 | |
| 基準点① 午前の部(多肢択一式) |
概ね71〜77%前後 |
| 基準点② 午後の部(多肢択一式) |
概ね62〜71%前後 |
| 基準点③ 午後の部(記述式) |
概ね43〜50%前後 |
| (筆記試験合格点) | (概ね73〜77%前後) |
他方、3つの基準点をすべてクリアしたからといって、合格できるわけではありません。
最終的な合格点は、3つの基準点の合計より35点ほど高くなるのが通常です(この35点分を、いわゆる「上乗せ点」と呼びます)。
たとえば、令和7年度(2025年度)の場合、筆記試験の合格点は255点でした。
仮にそれぞれの基準点をギリギリでクリアしたとすると、午前の部(多肢択一式問題)が78点、午後の部(多肢択一式問題)が72点、記述式問題が83点で、合計得点は220点です。筆記試験全体の合格点には35点足りません。
つまり、3つの「基準点」をクリアした上で、かつ必要な「上乗せ点」を確保して、はじめて筆記試験全体の「合格点」を突破できる、というイメージです。
※令和7年司法書士試験の基準点は、以下の記事で詳しく解説しています。
3.【髙橋講師が解説】令和7年度(2025年度)司法書士試験の合格点
続いて、令和7年度(2025年度)司法書士試験の合格点について詳しく分析していきましょう。
3章は、伊藤塾司法書士試験科の髙橋智宏講師による解説からお届けします。さらに詳しい内容を以下の動画でお伝えしていますので、あわせてご覧ください。
3−1.令和7年度本試験の結果について

まずは、令和7年度(2025年度)本試験(筆記試験)の結果です。
総合合格点は255点。基準点は択一式(午前)が78点(26問分)、択一式(午後)が72点(24問分)、記述式が70点でした。
ちなみに記述式については、平均点が69.3点とされており、「基準点と平均点がほぼ同じ」という構図です。これは昨年も同様で、令和6年度本試験では記述式の基準点が83.0点、平均点は81.7点という結果でした。
昨年と比べて、記述式の平均点が「−12.4点」、基準点が「−13.0点」と大幅に下がっているのは、今年の問題が昨年よりも難しかったからです。問題の難化に伴って平均点が下がり、そして基準点も下がっているという構図になっています。
択一式(午前・午後)、記述式でそれぞれ基準点に到達した人の数は1,402名、そのうち合格者は751名です。基準点と合格点の合計の差、いわゆる上乗せ点として必要な点数は35点でした。
3−2.上乗せ点は今後も35点前後が目安となる可能性が高い

次に、基準点合計から求められる上乗せ点の推移をみていきます。
令和6年度(2024年度)から、記述式の配点変更が行われました。そこで、記述式が350点満点になってからの推移をみていくと、昨年の上乗せ点が34.0点、今年の上乗せ点が35.0点となっています。
ここから分かるのは、(令和7年のように)記述式の難易度が上がり、そしてそれにより基準点が大きく異なっても、求められる上乗せ点自体はあまり変わらない、ということです。
そのため、今後も合格に必要な上乗せ点は「34〜35点程度を目安」に考えていけばよいでしょう。
3−3.どうやって上乗せ点を確保すればよいのか

それでは、その上乗せ点をどうやって確保すればよいのか。
先程もお伝えしたとおり、上乗せ点の目安は35点前後、択一式でいうと12問分です。これをすべて択一式で獲得するのは現実的に難しいでしょう。
そのため、記述式からも一定の上乗せ点は獲得する必要があります。
とはいえ、記述式のみから上乗せ点を確保しようとするのも危険です。記述式は採点方法が公表されていない上、問題との相性によって得点の高低が生じやすいからです。
そのため、以下のスタンスで取り組むことをおすすめします。
◉得点が安定しやすい択一式で、上乗せ点を一定数獲得する
◉その上で、記述式での上乗せ点も積極的に狙っていく
目標点数としては、以下を目安として考えるのがよいでしょう。
午前の部(択一式):90点/105点(30問/35問・得点率85.7%)
午後の部(択一式):84点/105点(28問/35問・得点率80%)
午後の部(記述式):基準点+10〜20点
上記を本試験の目標点数として、そこから逆算して「今何をすべきなのか」「 これから何をすべきなのか」を考えていくことが大切です。
4.過去5年間における基準点・合格点の推移
司法書士試験の過去5年間における基準点や合格点の推移を確認してみましょう。
4-1.午前の部(多肢択一式問題)
午前の部(多肢択一式問題) の基準点の推移は次の通りです。
| 午前の部(多肢択一式問題) の基準点の推移 | ||
| 年度 | 基準点 | 得点率 |
| 令和7年度(2025年度) | 満点105点中78点 | 74.3% |
| 令和6年度(2024年度) | 満点105点中78点 | 74.3% |
| 令和5年度(2023年度) | 満点105点中78点 | 74.3% |
| 令和4年度(2022年度) | 満点105点中81点 | 77.1% |
| 令和3年度(2021年度) | 満点105点中81点 | 77.1% |
参照:司法書士試験|法務省
午前の部(多肢択一式問題) の基準点は、78〜81点で推移しており、得点率は概ね74〜77%前後となっています。
午前の部の試験科目は「憲法、民法、刑法、商法(会社法)」の4科目となっていますが、特に民法と商法(会社法)については問題数が多いため、ここでどれくらい得点を伸ばせるかが、基準点を超えられるかどうかのポイントになるでしょう。
4-2.午後の部(多肢択一式問題)
午後の部(多肢択一式問題)の基準点の推移は次の通りです。
| 午後の部(多肢択一式問題) の基準点の推移 | ||
| 年度 | 基準点 | 得点率 |
| 令和7年度(2025年度) | 満点105点中72点 | 68.6% |
| 令和6年度(2024年度) | 満点105点中72点 | 68.6% |
| 令和5年度(2023年度) | 満点105点中75点 | 71.4% |
| 令和4年度(2022年度) | 満点105点中75点 | 71.4% |
| 令和3年度(2021年度) | 満点105点中66点 | 62.9% |
参照:司法書士試験|法務省
午後の部(多肢択一式問題) の基準点は、66〜75点で推移しており、得点率は概ね62〜71%前後となっています。
午後の部の試験科目は「民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、司法書士法、供託法、不動産登記法、商業登記法」の7科目となっています。が、午後の部は、3時間という試験時間の中で記述式問題も解かなくてはいけないため、試験戦略や解答スピードも必要となり、全体の得点率は午前の部よりも低くなっています。
4-3.記述式問題
午後の部(記述式問題)の基準点の推移は次の通りです。
| 午後の部(記述式問題) の基準点の推移 | ||
| 年度 | 基準点 | 得点率 |
| 令和7年度(2025年度) | 満点140点中70.0点 | 50.0% |
| 令和6年度(2024年度) | 満点140点中83.0点 | 59.3% |
| 令和5年度(2023年度) | 満点70点中30.5点 | 43.6% |
| 令和4年度(2022年度) | 満点70点中35.0点 | 50.0% |
| 令和3年度(2021年度) | 満点70点中34.0点 | 48.6% |
参照:司法書士試験|法務省
午後の部(記述式問題)の基準点は、30〜35点(配点変更後は70〜83点)で推移しており、得点率は概ね43〜60%前後となっています。
ただし、令和6年度(2024年度)に行なわれた司法書士試験から、記述式問題の得点が「2問で70点満点」から「2問で140点満点」に変更された関係で、基準点が大きく変わっています。記述式試験全体の配点が2倍になった関係で、部分点をつけやすくなるなど採点の幅が広がり、得点差がつけやすくなったと言えるでしょう。
従来通りの学習プランを大きく変える必要はありませんが、記述式の対策を今まで以上にしっかり行い、記述式問題でライバルと差をつけることが、司法書士試験に合格する一つのポイントであると言えるでしょう。
4-4.筆記試験全体
筆記試験全体の合格点の推移は次の通りです。
| 筆記試験全体の合格点の推移 | ||
| 年度 | 合格点 | 得点率 |
| 令和7年度(2025年度) | 満点350点中255.0点以上 | 72.9% |
| 令和6年度(2024年度) | 満点350点中267.0点以上 | 76.3% |
| 令和5年度(2023年度) | 満点280点中211.0点以上 | 75.4% |
| 令和4年度(2022年度) | 満点280点中216.5点以上 | 77.3% |
| 令和3年度(2021年度) | 満点280点中208.5点以上 | 74.5% |
参照:司法書士試験|法務省
筆記試験全体の合格点は、208.5〜216.5点(配点変更後は267.0〜255.0点)で推移しており、得点率は概ね73〜77%前後となっています。
司法書士試験全体で7割程度の得点を獲得するためには、出題数が多く配点も高い主要4科目(民法、商法(会社法)、不動産登記法、商業登記法)でいかに得点できるかが重要になります。
特に民法は出題数がもっとも多く、かつ出題範囲も広いため、他の科目よりも時間をかけて徹底して基礎力を身につける必要があります。
さらに、令和6年度(2024年度)に行なわれた試験から記述式問題の配点が2倍になったことを考えると、記述式問題でどれだけ上乗せ点を稼げるかも、合格するためのポイントになると言えるでしょう。
5.【最後に】令和7年度(2025年度)司法書士試験で合格点に届かなかった方へ
基準点には達したが惜しくも合格点に達しなかった方、あるいは基準点にすら届かなかった方、様々な状況の方がいらっしゃると思います。
そんな方に伊藤塾からお伝えしたいのは、「司法書士試験は諦めなければ必ず合格できる試験」だということです。
伊藤塾で学ばれた方の中にも、2回、3回、4回と挑戦して、合格を掴みとった方がたくさんいます。なかには、9回連続の不合格から伊藤塾で再チャレンジして合格した方や、働きながら勉強して上位1%の成績で合格した方もいらっしゃいます。
合格者に共通しているのは、どれだけ苦しくても最後まで諦めなかったこと、そして誤ったやり方に気づいて正しい勉強法に切り替えたこと、これに尽きるといってよいでしょう。
少しでも、「司法書士になって人生を変えたい」という気持ちが残っているのなら、来年試験に向けて、もう一度一歩を踏み出してみてください。
伊藤塾では、司法書士試験を知り尽くした業界トップクラスの講師陣が、合格に必要なレベルまで徹底指導しています。
2024年度は、「合格者の59%」が伊藤塾の有料講座を利用して合格しており、確かな実績に基づいた講義・教材と手厚いフォローであなたの合格を力強くサポートしていきます。
司法書士になりたいという強い想いがある方は、ぜひ伊藤塾で一緒に頑張りましょう。
※こちらの記事も多くの方に読まれています。
6.司法書士試験でよくある質問
Q. 司法書士試験の「基準点」と「合格点」の違いは何ですか?
基準点は各科目(択一式(午前・午後)・記述式)ごとに設定される合格ラインで、1つでも下回ると不合格になります。一方、合格点は筆記試験全体の合格ラインです。
司法書士試験では、基準点をすべてクリアした上で、合格点を超える必要があります。
Q. 「上乗せ点」とは何ですか?
上乗せ点とは、合格点と基準点の合計の差のことです。
令和7年試験でいえば、合格点が255.0点、基準点の合計が220点だったので、上乗せ点は35点となります。
Q. 令和7年度の上乗せ点35点は例年と比べて高いですか?
配点変更後(令和6年度以降)の上乗せ点は34〜35点で推移しており、令和7年度の35点は標準的です。今後も35点前後が目安になると考えられます。
Q. 上乗せ点35点を確保するための目標点数は?
午前の部90点(30問/35問)、午後の部84点(28問/35問)、記述式は基準点 +10〜20点を目標にするとよいでしょう。択一式で上乗せ点を確保しつつ、記述式でも積極的に得点を狙っていきましょう。
Q. 記述式の配点が2倍になったことで、勉強法を変える必要がありますか?
基本的な学習方針を変える必要はありません。
ただし、記述式の重要性が高まったため、これまで以上にしっかりと記述対策を行い、記述式でも確実に得点できるようにしましょう。
※こちらの記事も読まれています。
Q. 基準点に届かなかった場合、どの科目から対策すべきですか?
午前の部なら民法と会社法、午後の部なら不動産登記法と商業登記法を重点的に対策するのがセオリーです。ただ、ご自身の状況によっても異なるので、本試験の結果をもとにパーソナルカウンセリングなどで相談してみましょう。
Q. 基準点に達して合格点に届かなかった場合、どのように進めるべきですか?
まず、なぜ合格点に届かなかったのかを振り返ることが重要です。
択一式が基準点ギリギリだったのか、記述式の得点が低かったのか、あるいはその両方か。それによって方向性が変わってくるので、パーソナルカウンセリングなどで相談してみるのがおすすめです。
Q. 択一式と記述式の学習バランスはどうすればよいですか?
当面は「択一式7:記述式3」または「択一式8:記述式2」程度がおすすめです。
実力がついてきたら「択一式6:記述式4」に近づけていきましょう。
Q. 何度も不合格になっています。もう合格は無理でしょうか?
諦める必要は全くありません。大切なのは、不合格という結果だけを見て落ち込むのではなく「なぜ不合格だったのか」その原因を冷静に分析し、次の試験に向けて勉強法を修正することです。
司法書士試験は「やるべきことを確実にやっていけば合格できる」試験です。
※こちらの記事も読まれています。
7.令和7年度(2025年度)司法書士試験の合格点まとめ
本記事では、令和7年度 司法書士試験の合格点について解説しました。
筆記試験合格を確実にするために必要なポイントを以下にまとめます。
- 司法書士試験に合格するためには、午前の部(択一式)、午後の部(択一式)、午後の部(記述式)の3つの基準点を全てクリアすることが大前提となります。
- その上で、筆記試験全体の合格点を突破する必要があります。この合格点と3つの基準点の合計との差を「上乗せ点」といいます。
- 令和7年度(2025年度)の試験では、合格点が255.0点、基準点の合計が220点であったため、上乗せ点は35.0点でした。
- 記述式の難易度が変動し基準点が大きく下がった場合でも、合格に必要な上乗せ点自体はあまり変わらない傾向にあり、今後も34〜35点程度が上乗せ点の目安となります。
- 合格戦略としては、得点が安定しやすい択一式で一定の上乗せ点を確保しつつ、記述式でも積極的に得点を狙っていくことが推奨されます。
- 上乗せ点を確保するための目標点数として、午前の部(択一式)で90点(30問/35問)、午後の部(択一式)で84点(28問/35問)、記述式で基準点+10〜20点を目安に学習計画を立てることが有効です。
- 令和6年度(2024年度)以降、記述式の配点が70点満点から140点満点に変更されたことにより、試験全体における記述式問題の重要性が高まっています。記述式対策を今まで以上にしっかり行い、記述式でライバルと差をつけることが合格の重要なポイントです。
- 司法書士試験は諦めなければ必ず合格できる試験です。不合格の原因を冷静に分析し、正しい勉強法に切り替えることが、合格への道を切り開きます。
司法書士になって人生を変えたいという強い想いがある方は、法律系難関資格において圧倒的な合格実績を誇る受験指導校「伊藤塾」の「司法書士試験 入門講座」をぜひご活用ください。
司法書士試験を知り尽くした業界トップクラスの講師陣が、永年の実績に基づいた確かな講義と手厚いフォローで、あなたの合格を力強くサポートさせていただきます。
司法書士という新しいキャリアを、ぜひ一緒に築いていきましょう。