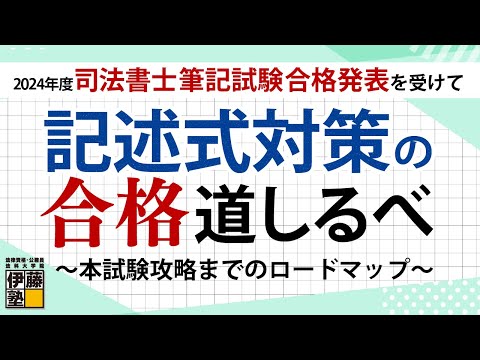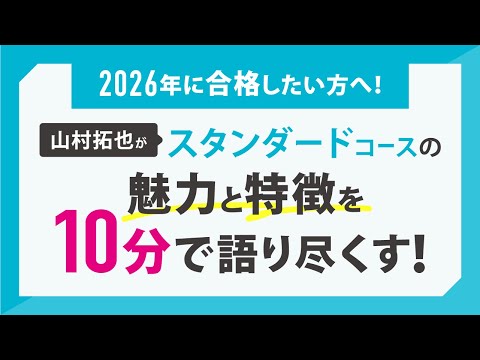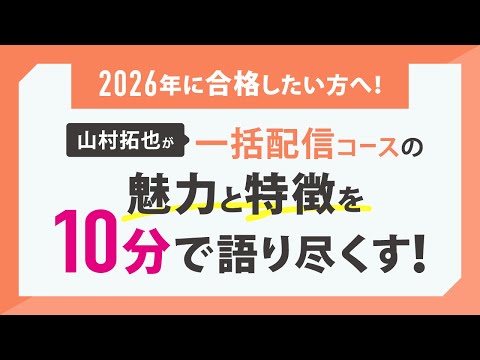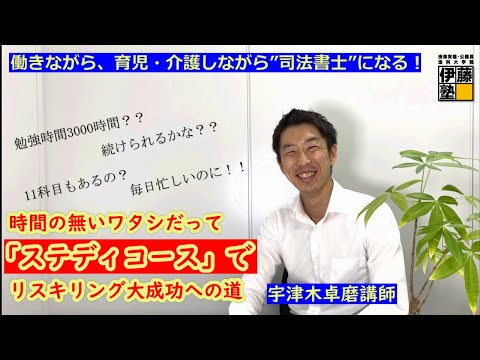司法書士試験の記述式を得点源に!本試験を5ステップで攻略する勉強法
勉強法
2025年10月17日


司法書士試験の合否を左右するのが「記述式試験」です。
筆記試験の40%を占めていますが、「何から手をつけていいのか分からない…」「いつまでも得点が伸びなくて不安…」といった悩みを抱えている方も少なくないはずです。
そこで本記事では、そんな司法書士試験の記述式について、試験の内容から目標点の考え方、そして具体的な対策方法、さらに何を意識すれば実力が伸びるのかまで、分かりやすく解説していきます。
この記事を読めば、記述式対策の全体像と具体的な勉強法が見えてくるはずです。ぜひ最後までお読みいただき、記述式を得点源にしましょう。
【目次】
1.司法書士試験の記述式とは
司法書士試験の記述式は、登記申請の実務を想定した試験です。
出題科目や問題の形式、配点について説明します。
1-1.出題科目・問題の形式
司法書士試験では、「不動産登記法・商業登記法」の2科目から各1問、記述式の問題が出題されます。試験問題は、いずれも具体的な事例に基づき、申請すべき登記の内容を判断し、実際に登記申請書を作成するというものです。
法学部の論文試験や、行政書士試験のような形式ではなく、実務に即した登記申請を行うイメージで作られているのが大きな特徴です。
1-2.記述式の配点
司法書士試験の記述式の配点は次のとおりです。
| 配点 | 全体に 占める 割合 | 出題科目 | 試験 時間 | |
| 択一式 (午前の部) | 105点 | 30% | 合計35問 ・憲法(3問) ・民法(20問) ・刑法(3問) ・商法(9問) | 2時間 |
| 択一式 (午後の部) | 105点 | 30% | 合計35問 ・民事訴訟法(5問) ・民事執行法(1問) ・民事保全法(1問) ・司法書士法(1問) ・供託法(3問) ・不動産登記法(6問) ・商業登記法(8問) | 3時間 |
| 記述式 | 140点 | 40% | 合計2問 ・不動産登記法(1問) ・商業登記法(1問) | |
| 合計 | 350点 | 100% | 合計72問 | 5時間 |
司法書士試験の配点350点のうち、記述式問題だけで140点(40%)を占めています。
合否に直結する科目であり、記述式の攻略なくして司法書士試験に合格することはありえません。
2.記述式の目標得点は「基準点+10点〜20点」が目安
司法書士試験の記述式は、「基準点+10点〜20点」を目標点数にして勉強を進めていきましょう。この章では、基準点の仕組みや、記述式試験を突破するための得点戦略を説明します。
2-1.そもそも基準点とは?
司法書士試験では、「基準点」という制度が設けられています。
基準点は、いわゆる「足切り」のようなイメージで考えるとよいでしょう。記述式が基準点に満たなければ、その時点で不合格が決定します。
基準点は、その年の受験者全体のレベルによって変動しますが、例年、平均点に近い点数で設定されています。令和6年度の場合、記述式の平均点は81.7点、基準点は83.0点でした。つまり、基準点で83点未満だった人は、択一式でいくら高得点をとっても不合格になります。
一方で、基準点を超えたからといって、必ず合格できるわけでもありません。
司法書士試験に合格するためには、基準点をクリアした上で、試験全体で最終合格点を超えることが必要だからです。択一式・記述式をあわせて、25〜35点の上乗せ点が求められます。
2-2.「基準点+10点〜20点」を記述式の目標にしよう
上記を踏まえて、記述式の目標点は、「基準点+10点〜20点」を目安にすると良いでしょう。
令和6年度を例に挙げると、最終合格には「基準点+34点(上乗せ点)」が必要でした。つまり、記述式で「10点〜20点」、択一式で「14点〜24点(5問〜8問分)」の上乗せ点を確保するというのが、最終合格点をとるイメージです。
【司法書士試験の得点目標】
(※令和6年度試験のイメージ)
| 目標点数 | 基準点 | 上乗せ点 | |
| 択一式 (午前) | 87~90点 | 78点 (26問/35問) | 9〜12点 (3問~4問) |
| 択一式 (午後) | 81~84点 | 72点 (24問/25問) | 9〜12点 (3問~4問) |
| 記述式 | 93~103点 | 83点 | 10~20点 |
| 合計 | 267点以上 (合格点) | 233点 | 34点以上 |
なお、配点は大きいですが、記述式だけで大幅な上乗せを狙うのはリスクが伴います。
記述式は問題との相性や採点基準などで得点が変動しやすいからです。例えば、記述式だけで「基準点+34点」を狙うのは現実的ではありません。
得点が安定しやすい択一式で着実に得点を重ねつつ、記述式と合わせて合格点を確保するというバランス感覚が重要です。
3.【最新データあり】令和6年記述式の配点変更による影響
令和6年の司法書士試験では、下記の通り、大幅な配点変更が行われました。
・記述式の配点が「70点→140点」に倍増
・配点割合が「択一75%、記述25%」から「択一60%、記述40%」に変更
そこでここからは、記述式の配点が2倍になったことで、司法書士試験の成績にどのように影響しているのかを見ていきます。
まずは、以下のデータをご覧ください。この表は、令和5年(配点変更前)と令和6年の試験結果を比較したものです。「記述式の成績」と「最終合格するために、択一式で何問正解する必要があったか」の関係を示しています。
(※あくまでも目安です。試験年度によって、問題の難易度・基準点が異なるため、参考値としてご活用ください。)
| 記述式試験 の成績 | 最終合格に必要な択一の正答数 | |
| (令和6年度) | (令和5年度) | |
| 上位0.1% | ― | 51問/70問 (※基準点) |
| 上位3%〜4% | 50問/70問 (※基準点) | 55問/70問 |
| 上位7〜8% | 52問/70問 | 56問/70問 |
| 上位12〜13% | 54問/70問 | 57問/70問 |
| 上位20%程度 | 56問/70問 | 58問/70問 |
| 上位30%程度 | 58問/70問 | 59問/70問 |
| 上位40%程度 | 60問/70問 | 60問/70問 |
(出典:「令和6年度司法書士試験筆記試験の結果等について」・「令和5年度司法書士試験筆記試験の結果等について」を加工して作成|法務省)
令和5年度(配点変更前)の場合、記述式の成績が上位20%でも、択一式で「58問/70問」の正解が必要でした。しかし、令和6年度の場合、「56問/70問」の正解で最終合格できることが分かります。
同様に、択一式の成績がちょうど基準点と同じだった場合、令和5年以前はほぼ逆転不可能でしたが、令和6年度では上位3〜4%の成績が取れれば、最終合格できるようになりました。配点変更によって、記述式対策の重要性が一層高まったといえるでしょう。
ただし、結局、択一式とのバランスが大切という点は全く変わりません。
そもそも択一式の得点力がない人が、記述式で高得点をとることはできないからです。さらに、択一式の点数が合否に大きく影響するという点も以前と同様です。今後も、択一式で高得点を得ることが、合格の必須条件となるでしょう。
これまで以上に記述式対策に力を入れつつ、択一式でも確実に得点するというスタンスで進めていきましょう。
※こちらの記事も読まれています。
4.司法書士試験の記述式対策の流れ
司法書士試験の記述式では、基礎から応用へと、段階を踏んで実力を伸ばしていくことが重要です。そこで、初学者から本試験直前まで、5つのステップに分けて効率的な記述式対策の流れを解説します。
ここでは、「不動産登記法」をモデルとしていますが、「商業登記法」にも応用できる考え方ですので、ぜひ学習ロードマップを作成する際の参考にしてください。
【記述式対策のロードマップ】

(出典:【司法書士試験】記述式対策の合格道しるべ ~本試験攻略までのロードマップ~|伊藤塾YouTubeチャンネル)
4-1.【STEP①】基本的な雛形を覚える
記述式対策の最初のステップは、基本的な登記申請の「雛形」を正確かつスムーズに書けるようになることです。
まずは、所有権移転登記・抵当権設定登記といった、頻繁に出題される雛形をマスターしましょう。これらは、あらゆる記述式問題の基本であり、本試験レベルの問題に取り掛かるときの土台となる部分です。
ここで気をつけてほしいのは、「雛形の丸暗記で終わらせない」ことです。
「なぜその記載が必要なのか」、「添付情報はどのようなルールで判断するのか」といった理由・制度趣旨を理解することが、記述式を得意にするためのコツです。
基本的な雛形が頭に思い浮かび、すぐに書き出せるレベルを目指しましょう。このステップにしっかり取り組めるかどうかで、その後の理解度が大きく変わってきます。
4-2.【STEP②】基本問題(2〜3件の連件申請)を解けるようになる
基本的な雛形を覚えたら、基本問題に取り組みましょう。
本試験レベルの問題に取り組む前に、まずは2〜3件の連件申請の問題を繰り返して、基本的な「型」を身に付けてください。これが本試験レベルの問題に取り組む前段階となります。
複数の事実関係を正確に読み取り、簡単な答案構成を行う練習を繰り返して、記述式の思考プロセスに慣れていきましょう。
特に、記述式に苦手意識がある方ほど、このステップを大切にして、じっくり取り組むことをおすすめします。焦らず、日々取り組むことを習慣づけましょう。
基本的な問題パターンや流れを体に染み込ませることがこの段階の目標です。
4-3.【STEP③】本試験レベルの問題の枠を押さえる
基本問題で実力を養ったら、いよいよ本試験レベルの問題(4〜6件程度の連携申請)に取り組みます。
ただし、ここでも段階を踏むことが大切です。まずは、申請すべき登記の種類と順番、いわゆる「答案の枠」を正確に把握し、安定して解答できるようになることを目指しましょう。細かい部分の正確さを追求するのではなく、「答案全体の骨組み」を固めることを意識してください。
この段階からは、択一式の問題を解くときも、記述式の出題を想定しながら取り組みましょう。これまで択一式で出題されていた論点が、本試験では記述式として出題されることも十分に考えられます。択一式で学んだ知識を、改めて記述式の視点から見直し、全体の知識を再確認していきましょう。
4-4.【STEP④】本試験レベルの問題の詳細を詰めていく
答案の枠を作れるようになったら、次のステップとして、答案の詳細を詰めていきます。
記載の変形パターンや添付情報、登録免許税の記載など、細かな点まで正確に押さえていきましょう。ただし、満点を目指すような過度な対策は必要ありません。あまりに細かすぎる論点(例えば、全ての戸籍のパターンを網羅するなど)に深入りすると、膨大な時間を費やしてしまいます。「満点」ではなく、「合格」が目標であることを忘れないようにしてください。
並行して、過去の演習で自分が間違えたパターンも分析し、具体的な対策を立てていくことも必要です。「また同じミスをした」で終わらせず、「なぜ間違えたのか」を考え、それを「間違いノート」や「間違い付箋」に記録し、集中的に克服していくのです。
この段階まできて、はじめて本試験レベルの問題で高得点を獲得することができます。地道な作業ですが、弱点を一つずつ潰していきましょう。
4-5.【STEP⑤】仕上げ(スピード、細かい書きぶり等)
最後のステップは、試験本番を見据えた最終調整、すなわち「仕上げ」です。
ここでは、答案作成のスピードを向上させることと、知識の漏れがないか最終確認を行うことが主な目的です。具体的には、時間を計りながら雛形をスピーディに書く練習をしたり、細かい書きぶりを正確に覚え直したりします。さらに、対策が手薄になりがちなマイナーな雛形についても、今まで学習した範囲内で最終チェックしておきましょう。
この仕上げ作業を通じて、本試験で実力を最大限に発揮するための準備を整えていきます。時間配分の練習も行い、制限時間内に全問解き終わるためのペース配分を身につけましょう。
5.司法書士試験の記述式対策で意識するべきポイント
司法書士試験の記述式対策では、単に問題を解いて答え合わせをするだけでは効果的な学習になりません。ある程度までは実力が伸びるかもしれませんが、すぐに限界がきて、合格までに時間がかかってしまいます。
記述式の学習効果を高めるためには、以下の2つのポイントを意識してください。
・過去問だけではなく、周辺の論点まで押さえる
・解答プロセスに重点を置いて勉強する
これらを意識するだけで、同じ勉強時間でも学習の質が大きく向上するはずです。それぞれ詳しく説明します。
5-1.過去問だけではなく、周辺の論点まで押さえる
まず意識すべきなのは、出題された論点だけでなく「周辺論点」まで広く押さえることです。
本試験の問題は、膨大な法律知識から一部分だけを切り取って作られています。そのため、過去問の論点だけ対策しても、本試験で高得点を取ることはできません。少し角度を変えた問題が出たら対応できなくなってしまいます。
過去問に取り組むときは、「単に解く」のではなく、その都度択一式のテキストに戻り、関連箇所にマーカーや付箋をつけておくなど、「立体的な学習」を心がけましょう。
「1を知って1を知る」学習から「1を知って5を知る」学習へと発展させていくことで、どんな問題にも対応できる応用力が身についていきます。
5-2.解答プロセスに重点を置いて勉強する
「問題をどう解くか」という解答プロセスに重点を置いた学習も重要です。
司法書士試験の記述式は、複雑な事例から必要な情報を読み取り、法律知識を当てはめ、論理的に考え、登記申請書を作成するという一連の流れが評価される試験です。単に知識や雛形を暗記しただけでは高得点は望めません。
過去問を解くときは、単に正誤だけ確認するのではなく「自分はどのような手順でこの結論に至ったか」「正しい判断手順を実践できていたか」を振り返るようにしましょう。解答のプロセスを意識することで、ケアレスミスが減り、限られた時間内でも質の高い答案が作成できるようになります。
知識として覚えるのではなく、「解き方」自体を磨くことが、記述式攻略の鍵となるのです。
6.まとめ
最後に、記事のポイントをまとめます。
1.司法書士試験の記述式は、実登記申請の実務を想定した試験
司法書士試験の記述式は、登記申請の実務を想定した試験です。
不動産登記法と商業登記法から各1問出題されます。配点は140点で試験全体(350点)の40%を占めています。論文形式ではなく、登記実務をイメージした実践的な内容です。
2.記述式の目標得点は「基準点+10点〜20点」が目安
記述式の目標得点は「基準点+10点〜20点」を目安にしましょう。
基準点は「足切り」のようなイメージで、これを下回ると不合格となります。令和6年度の場合、基準点が83.0点、最終合格には「基準点+34点」が必要でした。
記述式で「基準点+10〜20点」を確保し、残りを択一式で補うようなイメージです。
3.記述式対策は5つのステップに分けて進めることが重要
記述式対策では、基礎から応用へと、段階を踏んで実力を伸ばしていくことが重要です。
次のような流れで進めていきましょう。
①基本的な雛形を覚える
↓
②基本問題を解けるようになる
↓
③本試験レベルの問題の枠を押さえる
↓
④本試験レベルの問題の詳細を詰めていく
↓
⑤仕上げ(スピード・細かい書きぶりなど)
4.2つのポイントを意識すると、学習の質が向上する
記述式対策では、「過去問だけではなく周辺の論点まで押さえること」と「解答プロセスに重点を置くこと」が重要です。2つのポイントを意識するだけで、同じ勉強時間でも学習の質が大きく向上します。
以上です。
司法書士試験に合格したい方は、ぜひ法律資格専門の指導校である伊藤塾をご活用ください。伊藤塾の司法書士試験対策講座は、合格者の半数近くが利用しているという確かな実績を持っています。ぜひ新たな一歩を踏み出してみてください。伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートします。
→「伊藤塾 司法書士入門講座」はこちら
→「伊藤塾 司法書士入門講座の無料体験講義」はこちら
2026年の司法書士試験に合格したい方向けに、伊藤塾の講師が「司法書士入門講座」の各コースの魅力と特徴を解説しています。司法書士試験の受験を検討されている方は、ぜひご覧ください。
合格に必要十分な講義を展開する王道カリキュラム「司法書士入門講座 スタンダードコース」
2026年の本試験までフリースケジュールで視聴可能な「司法書士入門講座 一括配信コース」
仕事や育児で忙しくても司法書士になる!少ない時間で最大限の効果を上げる「司法書士入門講座 ステディコース」