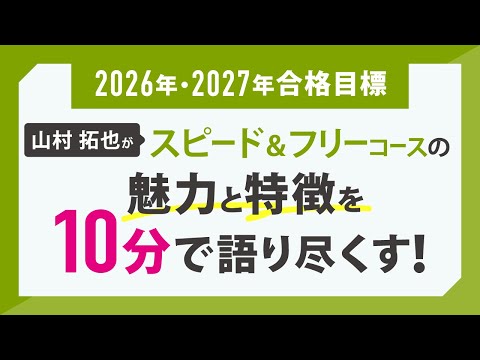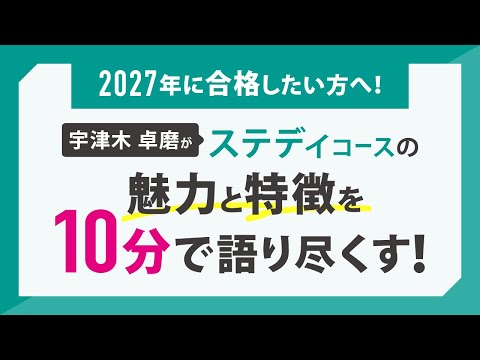宅建から司法書士へステップアップ!難易度や勉強法方法を徹底解説
キャリア
2025年11月21日


近年、宅建士試験に合格した方が不動産業界や法律分野でキャリアアップを目指し、「宅建士試験に合格した次は、司法書士に挑戦したい」と司法書士試験の受験にシフトする人が増えてきています。
司法書士は登記や法律手続きの専門家であり、宅建士試験で培った不動産知識をさらに発展させられる資格です。
とはいえ、「本当にステップアップできるの?」「勉強時間や難易度はどれくらい違うの?」と不安に思う方もいるはずです。実際に宅建士から司法書士を目指す人は増えており、両資格を組み合わせて活躍する専門家も多く見られます。
この記事では、宅建から司法書士へのステップアップが可能かどうかをはじめ、両試験の違いや効率的な勉強法、合格後のキャリアの広がりまで詳しく解説します。
【目次】
1. 宅建から司法書士へのステップアップは可能?
宅建士試験に合格した後、司法書士試験合格を目指すことは十分に可能です。
両資格には共通する法律分野が多く、宅建士試験で培った基礎力をそのまま司法書士の学習に活かせます。法律用語や条文の読み方にも慣れているため、まったくの初心者よりもスムーズに学習を始められるでしょう。
ここでは、宅建士試験と司法書士試験の「試験範囲」「勉強時間」「難易度」の違いを詳しく確認していきます。
1-1. 宅建士試験と司法書士試験の試験範囲
宅建士試験と司法書士試験は、いずれも法律知識を問う国家資格ですが、出題範囲には明確な違いがあります。
宅建士試験は、不動産取引に関する法律や実務知識を問う試験です。
試験は全50問の四肢択一式マークシート方式で出題されます。
主な出題科目は以下の通りです。
【宅建士試験の主な出題科目】
● 権利関係(民法、不動産登記法、借地借家法等)
● 宅建業法
● 法令上の制限(建築基準法、都市計画法、国土利用計画法等)
● 税・その他(固定資産税・登録免許税、地価公示法、不動産に関する直近の統計等)
一方で、司法書士試験は、登記・供託・裁判手続きなどより専門的で実務寄りの法律を広く深く問う試験です。
試験は多肢択一式と記述式で構成されています。
主な試験科目は以下の通りです。
【司法書士試験の主な出題科目】
● 民法
● 不動産登記法
● 商法・会社法
● 商業登記法
● 民事訴訟法
● 民事執行法
● 民事保全法
● 供託法
● 司法書士法
● 憲法
● 刑法
両者の共通点として、「民法」や「不動産登記法」「借地借家法」などが挙げられます。そのため、宅建士試験の学習で得た基礎知識は司法書士の勉強にも活かせます。
特に登記や民法等の基礎的な理解は宅建士試験経験者の大きな強みとなり、司法書士試験の学習初期段階で大きなアドバンテージを得られます。
※司法書士試験の科目については、こちらの記事で詳しく解説しています。
1-2. 宅建士と司法書士における合格までの勉強時間
宅建士試験の合格に必要な勉強時間は、一般的に「300〜500時間」と言われています。一方、司法書士試験はその10倍近い「3,000時間程度」が目安とされており、国家資格の中でも最難関クラスに位置づけられています。この差は、司法書士が登記や訴訟手続きなど、実務レベルの法的判断を求められる専門職であることが理由です。
ただし、宅建士試験に合格している人は、すでに民法や不動産関連法の基礎が身についています。ゼロから学ぶ場合に比べ、数百時間単位で学習負担を軽減できる可能性があります。
また、宅建士試験で身についた「学習計画を立てて継続する力」も大きな武器になります。司法書士試験は長期戦になるため、宅建受験で培った習慣や集中力が合格への支えとなります。
※司法書士試験の合格に必要な勉強時間については、こちらの記事で詳しく解説しています。
1-3. 宅建士試験と司法書士試験における難易度の違い
宅建士試験の合格率は毎年約15〜17%で、国家資格の中では中程度の難易度です。一方、司法書士試験の合格率はおおよそ4〜5%と非常に低く、法律系資格の中でも屈指の難関試験だと言われています。
試験の形式も大きく異なり、宅建士試験は4択のマークシート方式のみですが、司法書士では配点の高い記述式も含まれるため、理解力と実践力の両方が求められます。
しかし、難易度が高い分、司法書士の社会的評価や収入面での魅力も大きくなります。宅建で得た知識を活かしつつ、長期的な目標として司法書士を目指すことは、キャリアアップの面でも非常に合理的な選択です。
焦らず計画的に学習を進めれば、宅建から司法書士へのステップアップは十分に実現可能です。
※司法書士試験の難易度については、こちらの記事で詳しく解説しています。
2. 宅建合格後に司法書士試験にチャレンジするメリット
宅建士試験を乗り越えた人にとって、司法書士試験は決して「未知の世界」ではありません。すでに法律の基礎を理解しており、学習の進め方も体得しているため、次のステップへ進みやすいのが大きな利点です。
宅建士試験合格者が司法書士試験に挑戦する際の主なメリットは以下のとおりです。
● 法律学習への抵抗が少なくスムーズにステップアップできる
● 共通科目があり基礎知識を活かせる
● 宅建合格で得た勉強習慣を維持できる
● 「合格経験」が自信になりモチベーションを保ちやすい
具体的に見ていきましょう。
2-1. 法律学習への抵抗が少なくスムーズにステップアップできる
宅建士試験で民法や不動産登記法等を学んだ経験がある人は、司法書士試験の勉強に自然と入りやすくなります。法律の条文構成や判例の読み方に慣れているため、「法律を学ぶこと」への抵抗感が少なく、初学者よりも理解のスピードが速い傾向にあります。
司法書士試験では、宅建よりも一段階深いレベルで法的思考力が問われますが、基礎的な概念は共通しています。そのため、宅建士試験を通して得た法律の基礎知識が、司法書士の学習を支える土台として大きな力を発揮します。
2-2. 共通科目があり基礎知識を活かせる
宅建士試験と司法書士試験では、いくつかの科目が重なっています。例えば「民法」「不動産登記法」「借地借家法」などは両方の試験で出題されるため、宅建で学んだ内容を復習する形で司法書士の学習を進められます。
宅建では登記や権利関係の“概要”を理解しますが、司法書士ではそれをより実務的・体系的に掘り下げます。
つまり、まったく新しい分野を一から学ぶわけではなく、「知っている内容を深める」学習に変わるのです。
この“学びの継続性”が、宅建合格者にとって司法書士を目指す際の大きなアドバンテージといえます。
2-3. 宅建合格で得た勉強習慣を維持できる
宅建士試験に合格した経験がある人は、すでに「計画的に学習を進める力」や「毎日机に向かう習慣」が身についています。
司法書士試験は長期戦になりやすいですが、学習ペースを維持できる人ほど合格に近づきます。宅建合格直後に司法書士の勉強を始めれば、宅建勉強中に確立した学習リズムをそのまま継続でき、効率よく知識を積み上げられます。
勉強のモチベーションを保つためにも、宅建合格後の“熱量が冷めないうち”に司法書士の学習へ移行するのがお勧めです。
2-4. 「合格経験」が自信になりモチベーションを保ちやすい
宅建士試験に合格したという成功体験は、司法書士の学習を続けるうえで大きな支えになります。
司法書士試験は範囲が広く、合格までに数年かかることも珍しくありません。その中で「自分は国家試験を突破した経験がある」という自信は、長期間の学習を乗り越える原動力になります。
また、宅建士試験の成功をきっかけに「次はもっと専門的な法律を学びたい」という向上心が生まれる人も多く、学習のモチベーションを高く維持できることも宅建士試験合格者の大きなメリットでもあります。継続が鍵となる司法書士試験では、この“前向きな勢い”が非常に重要です。
3. 宅建と司法書士のダブルライセンスを取得するメリット
宅建士と司法書士の両方を持つことで、仕事の幅が大きく広がります。お互いの資格の持つ専門性を兼ね備えることで、顧客へのサービスの質が高まり、将来的なキャリアの選択肢も増えます。
ここでは、ダブルライセンス取得による具体的なメリットは以下の通りです。
● 独立開業の際に強力な武器になる
● 年収アップ・安定した収入が期待できる
● 専門職としての市場価値・希少性が高い
具体的に見ていきましょう。
3-1. 独立開業の際に強力な武器になる
司法書士は、資格を取得すれば自分の事務所を開業できる「独立性の高い資格」として知られています。ここに宅建士資格が加わることで、開業時の強みはさらに広がります。
不動産の売買や相続に関する相談を受けた際、宅建の知識があることで、顧客の悩みをより実務的な視点から理解しやすくなります。また、司法書士が不動産会社や宅建業者と連携して業務を行うことで、登記や契約手続きに関する案件を安定的に確保できます。
相続・売買・登記といった関連業務を一体的に扱えるため、「ワンストップで頼れる専門家」として顧客からの信頼も高まります。
宅建と司法書士を両方持つことは、独立後の安定経営と差別化を実現するうえで、非常に強力な武器となります。
※司法書士については、こちらの記事で詳しく解説しています。
3-2. 年収アップ・安定した収入が期待できる
宅建士と司法書士の両方を持つことで、収入の柱を複数確保でき、景気に左右されにくい安定した収入が見込めます。不動産に強い司法書士として独立すれば、年収が1,000万円を超えることも珍しくありません。
両資格を活かして業務範囲を広げれば、不動産取引・登記・相続・企業法務など、報酬単価の高い仕事を幅広く受任できます。例えば、登記業務に加えて不動産売買の契約相談や相続不動産の売却支援まで手掛けることで、1件あたりの売上を増やせます。
また、司法書士が行う業務は、企業登記や相続登記、認定司法書士であれば債務整理など、社会的に常に需要があります。不動産市場が低迷しても登記や法務の仕事は継続的に発生するため、宅建士だけの収入構造よりも安定性が高いといえます。
ダブルライセンスを取得することは、単に年収を上げるだけでなく、長期的に安定した専門職として生きていくための大きな強みになります。
※司法書士の年収については、こちらの記事で詳しく解説しています。
3-3. 専門職としての市場価値・希少性が高い
宅建士と司法書士の両資格を持つ人は、全国的にも決して多くありません。それぞれ独立した難関資格であり、両方を取得するには時間と努力が必要なため、自然と市場での希少性が高まります。
例えば、不動産会社では「契約内容を法的にチェックできる人材」として重宝され、司法書士事務所では「取引の現場に強い法務担当」として信頼を得やすくなります。
士業が増え続ける中で、差別化できる資格の組み合わせは大きな武器です。宅建士としての実務経験と、司法書士としての法的知識を兼ね備えることで、他にはない独自の価値を発揮できるでしょう。
※宅建とのダブルライセンスについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
4. 宅建・行政書士・司法書士のトリプルライセンスで広がる選択肢
宅建士と司法書士のダブルライセンス取得により、不動産に強い司法書士として市場価値や年収のアップが見込めることをご説明しました。
さらに付加価値を付け、圧倒的な差別化を実現したい方には、「行政書士」の取得もおすすめです。
行政書士資格を取得することで、不動産関連の手続き、行政手続き、登記手続きといった関連分野を幅広く扱えるようになります。扱う領域が近いため知識の繋がりが強く、実務でも連携しやすい点が大きな特徴です。
例えば、飲食店を開業するケースでいえば、テナント契約の仲介から店舗の登記手続き、その後の営業許可の申請までをワンストップで提供できます。物件契約 → 登記 → 許可申請という一連のプロセスを一人で支援できることで、顧客にとって「最初から最後まで任せられる存在」になれます。
顧客の多様な課題を一括で解決できる専門家として信頼を得やすく、独立・転職のどちらでも強みを生かせます。
※ 宅建・行政書士・司法書士のトリプルライセンスについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
5. 宅建合格後に司法書士試験の勉強を開始するタイミング
宅建に合格した後、「いつから司法書士の勉強を始めるのが良いのか」と迷う人は多いはずです。
結論としては、合格直後のモチベーションが高い時期に学習を始めるのが最も効率的です。宅建の学習習慣が残っているため、長期戦となる司法書士の対策にもスムーズに移行できます。
宅建士試験の知識は、民法や不動産登記法など司法書士試験に直結する部分が多く、記憶が新しいうちに取り組めば理解の負担を減らせます。
特に民法は司法書士試験でも中心科目となるため、宅建で学んだ内容を忘れないうちに取り組むことで、スタートダッシュを切りやすくなります。
とはいえ、合格後すぐに勉強を再開する余裕がない人もいるでしょう。その場合は、遅くとも翌年の1〜3月頃までには学習を再開するのがお勧めです。
6. 宅建から司法書士へステップアップするなら伊藤塾がおすすめ
これまで述べてきたように、近年、多くの方がチャレンジし始めている「宅建士から司法書士へステップアップ」については、学習面におけるアドバンテージもあり、非常におすすめしたいキャリアプランです。
しかしながら、司法書士試験の合格に必要な勉強時間は「約3,000時間」ともいわれ、宅建士試験と比べ難易度はかなり高くなります。そのため、勉強時間の捻出が難しい社会人が「独学」で受験した場合、数年にわたる長期間の学習が必要となる可能性が高いでしょう。
そんな忙しい社会人の方におすすめなのが、司法書士試験合格者の約6割が利用している 伊藤塾の「司法書士 入門講座」です。
中でも、「スピード&フリーコース」「ステディコース」では、あなたのタイミングでいつでも学習をスタートすることができ、2026年度・2027年度司法書士試験の合格を目指すことが可能です。
以下に、担当講師の解説動画を掲載しますので、ぜひご視聴のうえご検討ください。
【自分のペースで学習を進めたい方に最適なスピード&フリーコース】
【仕事や家事・育児等の忙しい中で受験を目指される方に最適なステディコース】
宅建合格直後の勢いを保ちつつ、自分の生活環境に合ったタイミングで学習を始めることが、司法書士試験の長期戦を乗り越える大切なポイントです。
もし、司法書士へのステップアップを目指されるのなら、司法書士試験合格者の約6割が利用している 伊藤塾の「司法書士 入門講座」をぜひご検討ください。
※こちらの記事も多くの方に読まれています。
7. 宅建から司法書士を目指す場合によくあるQ&A
Q. 社会人や子育て中でも宅建から司法書士を目指せる?
A. 司法書士の学習量は多いものの、通信講座やオンライン教材を使えば、限られた時間でも効率よく学習を進められます。宅建で法律の基礎を理解しているため、初学者より学習をスタートしやすい点も強みです。毎日1〜2時間の積み重ねでも十分成果につながるので、生活リズムに合わせて無理なく続ける工夫が大切です。
Q. 宅建合格からどのくらいで司法書士試験に受かる?
A. 人によって合格までにかかる期間は異なりますが、学習の進み方によっては宅建士試験翌年の司法書士試験に合格することも不可能ではありません。宅建で学んだ民法や不動産登記法の基礎知識が残っていれば、学習初期の負担が軽くなり、効率よく計画的に学習を進められます。
Q. 宅建合格後なら独学でも司法書士に合格できる?
A. 独学での合格も不可能ではありませんが、合格率や学習範囲を踏まえると、司法書士試験の難易度は宅建士試験と比べかなり高いといえます。特に商業登記法などの専門性の高い科目を独学で理解するには時間がかかります。宅建で学んだ基礎があるとはいえ、効率よく学習するためには、プロの講師による指導で理解を深められる受験指導校の利用を検討するのがお勧めです。
8. 宅建から司法書士へのステップアップについて・まとめ
本記事では、宅建士資格経験者が司法書士へステップアップする際の難易度、学習期間、および共通科目について解説しました。
以下にポイントをまとめます。
- 宅建士試験に合格した後、司法書士試験合格を目指すことは十分に可能です。
- 司法書士試験の合格率はおおよそ4〜5%と非常に低く、宅建士試験(合格率約15〜17%)に比べて難易度は格段に高い難関試験です。また、司法書士試験は四肢択一式のみの宅建士試験とは異なり、配点の高い記述式も含まれるため、より深い理解力と実践力が求められます。
- 司法書士試験の合格には一般的に「3,000時間程度」が必要とされています。しかし、宅建士試験経験者はすでに民法や不動産関連法の基礎が身についているため、ゼロからの学習者に比べ数百時間単位で学習負担を軽減できる可能性があります。
- 「民法」「不動産登記法」「借地借家法」などの共通科目があり、宅建で培った基礎知識や法律学習への抵抗のなさ、計画的に学習を進める力、そして合格経験によるモチベーションの維持が、司法書士の学習を支える大きな土台となります。
- 宅建合格で得た知識が新しいうち、合格直後のモチベーションが高い時期に司法書士の学習を始めるのが最も効率的です。
- 宅建士と司法書士のダブルライセンスを取得することで、相続・売買・登記といった関連業務をワンストップで扱えるようになり、独立開業時の強力な武器となります。これにより、年収アップや安定した収入、専門職としての市場での高い希少性が期待できます。また、さらに「行政書士」の資格も加えることで、行政手続きを含めたトリプルライセンスによる圧倒的な差別化も可能です。
司法書士試験は「3,000時間」が目安とされる長期戦であり、特に忙しい社会人の方が独学で挑戦する場合、数年にわたる学習が必要となる可能性が高いです。
宅建合格直後の勢いを保ちつつ、難関試験を効率よく乗り越えるためには、プロの指導による体系的な学習が不可欠といってよいでしょう。
もし、あなたが司法書士へのステップアップを目指されるのなら、司法書士試験合格者の約6割が利用している 伊藤塾の「司法書士 入門講座」をぜひご検討ください。
伊藤塾では、ご自身のペースで学習を進めたい方に最適な「スピード&フリーコース」や、仕事や家事・育児等の忙しい中で受験を目指される方に最適な「ステディコース」などをご用意しており、2026年度・2027年度の合格を目指すことが可能です。
今こそ、宅建合格で得た自信と習慣を活かし、さらなる高みを目指しましょう!
伊藤塾があなたの新たなチャレンジを力強くサポートさせていただきます。