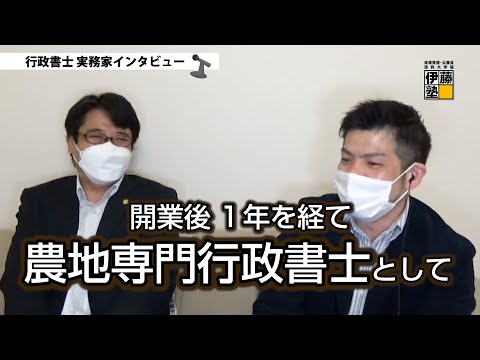行政書士の廃業率は4%?廃業しないための開業成功の秘訣も解説
キャリア
2025年09月10日


「行政書士は廃業しやすい…」という噂を聞いて、不安になっていませんか?
実際のデータを見ると、行政書士の廃業率はわずか4.4%。10年後も約7割の人が事業を継続している計算となります。
本記事では、総務省のデータから行政書士の廃業率を明らかにし、なぜ「廃業しやすい」という誤解が生まれるのかを解説します。さらに、廃業しないために必要な5つの心構えや、開業1年目の実務家インタビューも掲載。
「本当に行政書士としてやっていけるのか?」という不安を抱えている方は、ぜひ最後までお読みください。データに基づいた正しい情報を知れば、自信を持って行政書士への道を歩めるはずです。
【目次】
1.行政書士で廃業する人は多い?
行政書士として独立開業したい方の中には、「廃業する人が多いのでは?」という不安を抱えている方もいるでしょう。
しかし、行政書士の廃業率は年間4.4%程度であり、他の業種と比べても高くはありません。
1-1.行政書士の廃業率は4.4%
令和5年度のデータによると、行政書士の廃業率は4.4%です。
これは総務省のホームページで公表されている「行政書士の登録状況」から算出できます。
| 令和5年度 | 人数 |
| 当初の行政書士(A) | 51,041名 |
| 年度中に新しく開業した人(B) | 2,946名 |
| 年度中に廃業した人(C) | 2,368名 |
| 廃業率 ※C/(A+B) | 4.4% |
(出典:総務省|行政書士の登録状況(令和5年度))
つまり、100人の行政書士がいれば、1年間で廃業するのは4~5人程度だと考えられます。
他方、「2024年版 中小企業白書」によれば、一般企業の廃業率は3〜4%で推移しています。一般企業と比較しても、特別高い数値とはいえません。
1-2.廃業した人の理由内訳
行政書士の廃業理由の内訳も確認してみましょう。
令和5年に廃業した人のうち、廃業届を提出した人は2,064名。これがいわゆる「廃業」としてイメージされる人数です。
「経営がうまくいかずに廃業を選んだ」など、自分の意思で廃業した人は、すべてここに含まれます。
この廃業届を提出した2,064名の廃業率を計算すると「3.8%」となります。
しかも、この2,064名の中には、準備不足のまま見切り発車的な開業をしてしまった人も少なからずいるはずです。しっかりと準備を行ったうえで開業をした人に絞れば、さらに廃業率は低くなることは間違いありません。
| 廃業理由 | 人数 |
| 欠格事由に該当 | 7名 |
| 廃業届の提出 | 2,064名 |
| 死亡 | 292名 |
| 行政書士会による登録の抹消 ・2年以上業務を行わない ・心身の故障 | 5名 |
| 小計 | 2,368名 |
(出典:総務省|行政書士の登録状況(令和5年度))
ちなみに、廃業届を提出せずに廃業となった304名は、死亡(292名)、欠格事由該当(7名)、行政書士会による登録の抹消(5名)です。行政書士会による登録の抹消は、2年以上業務を行わない場合や心身の故障が原因です。
1-3.開業10年後の廃業率は?
日本では「企業は10年以内に9割が廃業する」と言われることがあります。では、行政書士の場合はどうでしょうか?
上記のデータを元に、行政書士が開業した後10年の廃業率を計算したところ、10年後の廃業率は約36.5%でした。廃業届を提出した人の廃業率(約4%)で計算すると、10年で廃業する人の割合は約33.5%となります。
■開業10年間の廃業率のイメージ
| 廃業する人の割合 | |
| 開業1年後 | 4% |
| 開業2年後 | 7.8% |
| 開業3年後 | 11.5% |
| 開業4年後 | 15.1% |
| 開業5年後 | 18.5% |
| 開業6年後 | 21.7% |
| 開業7年後 | 24.9% |
| 開業8年後 | 27.9% |
| 開業9年後 | 30.7% |
| 開業10年後 | 33.5% |
廃業届を提出した人の中にも、家庭の事情や健康上の問題など、さまざまな事情の人が含まれています。純粋に「行政書士としてやっていけるのか」という面から考えれば、廃業率はさらに低くなるでしょう。
行政書士は、きちんと経営努力を続ければ、20年・30年と稼ぎ続けられる仕事です。長年にわたって安定的に経営している人も数多く存在します。
※こちらの記事も読まれています。
2.なぜ行政書士は廃業しやすいと言われるの?
実際の廃業率は高くないのに、なぜ行政書士は廃業しやすいと言われるのでしょうか?
その理由として、以下の3つが考えられます。
・仕事のイメージが湧きにくいから
・士業の中では人数が多いから
・開業までのハードルが低いから
それぞれ説明します。
2-1.仕事のイメージが湧きにくいから
まず、仕事内容がイメージしにくいことが考えられます。
たとえば、弁護士なら「法律相談・裁判」、司法書士なら「不動産登記・商業登記」というように、代名詞となる業務があります。しかし行政書士には分かりやすい看板業務がありません。独占業務の範囲が「書類作成」と広すぎるため、具体的に何をする人なのか、そもそもなぜ行政書士に依頼するのかが分かりにくいのです。
さらに、行政書士は基本的にBtoB(対企業)の仕事が中心です。一般の方と接点を持つ機会は、それ程多くありません。そのため、誰から仕事が来るのか、どこにニーズがあるのかも分かりづらく、「仕事がない」というイメージが先行してしまうのです。
※こちらの記事も読まれています。
2-2.士業の中では人数が多いから
次に、行政書士は士業の中でも人数が多いことが挙げられます。
2025年6月時点で全国の行政書士は約5.3万人にのぼり、士業の中でもトップクラスの人数を誇ります。人数が多ければ、当然ながら「廃業する人の絶対数」も多くなります。同じ廃業率4%でも、登録者数が1万人なら年間400人、5万人なら年間2,000人が廃業するからです。
実際の廃業率は低いですが、廃業者の数は多くなるため、「行政書士は廃業しやすい」というイメージが広まりやすいのです。
※こちらの記事も読まれています。
2-3.開業までのハードルが低いから
最後に、開業までのハードルが低いことも理由の一つです。
行政書士は、試験に合格すれば実務経験がなくてもすぐ開業できます。これは行政書士のメリットでもありますが、同時にリスクでもあります。ハードルが低いがゆえに、見切り発車で開業する人もいるからです。
行政書士に限った話ではありませんが、資格があるだけで稼げるわけではありません。開業するためには、資金を準備したり、営業努力を行ったりなど、経営を続けていく努力が必要です。いくら開業しやすいからといって、準備不足のまま開業すれば、廃業リスクは高くなります。
ただし、経営努力さえ怠らなければ、行政書士は廃業しやすい仕事ではありません。
※こちらの記事も読まれています。
3.廃業しない行政書士になるために必要な5つのこと
では、廃業しない行政書士になるためにはどうすればいいのでしょうか?
行政書士が成功するために必要な5つのことを説明します。
・入念な開業準備をする
・「専門分野」を絞って実績を積む
・SNS等を利用して集客する
・「価格」ではなく「信用」を武器にする
・他の行政書士にはない「強み」をもつ
それぞれ見ていきましょう。
3-1.入念な開業準備をする
廃業を防ぐために最も大切なのは、入念な開業準備です。
行政書士の資格を取っても、すぐに仕事が来るわけではありません。開業してやっていくには、集客の検討、ホームページの作成、事務所の準備、事業計画の作成など、さまざまな準備が必要です。
特に大切なのは、余裕をもった資金の確保です。
開業初期は収入が不安定になりがちなので、(開業資金とは別に)最低でも6ヶ月〜1年分の生活費は用意しておきましょう。準備不足のまま開業すると、上手くいかなかったときに気持ちばかり焦って、悪循環に陥ります。
しっかりとした準備を行えば、開業後の成功確率は大幅に高められます。
※こちらの記事も読まれています。
3-2.「専門分野」を決めて実績を積む
専門分野を絞って実績を積むことも、長く続けるためのポイントです。
開業直後に限れば、仕事を選ばず、何でも引き受けるべきかもしれません。しかし、最終的には専門性を身につけた方が良いでしょう。特定の強みがなければ、結局、価格競争に巻き込まれてしまうからです。
国際業務、相続、農地法許可、建設業許可など、何か1つの分野で他の行政書士に負けない実績を築きましょう。専門分野を確立できれば、「この分野ならあの先生」という評判が生まれ、ライバルが増えても選ばれる行政書士になれます。
※こちらの記事も読まれています。
3-3.SNS等を利用して集客する
現代の行政書士にとって、SNSを活用した集客は欠かせません。
特に開業直後は、ウェブやSNSが最も効果的な集客方法となります。紹介や口コミも大切ですが、ゼロイチで顧客も実績もない段階では効果が上がりづらいです。
SNSやブログ、YouTubeなどを活用して情報発信すれば、開業直後から顧客との接点を作れます。相続を専門にするなら相続に関する情報を、建設業許可を専門にするなら許可取得のポイントなどを発信すると良いでしょう。
SNSなどで継続的に情報発信をすれば、「この人は専門家だ」という信頼を獲得でき、問い合わせにもつながります。
SNS等は無料で始められるため、開業資金が限られている場合にも適した方法です。
3-4.「価格」ではなく「信用」を武器にする
長く続く行政書士事務所を作るには、「価格」ではなく「信用」で勝負することが大切です。
開業したばかりの頃は、あえて報酬を低く設定するべきタイミングもあるでしょう。しかし、いつまでも「価格」だけを武器にしていると、長期的には続きません。休みなく働いているのに稼げないという悪循環に陥り、廃業につながります。
大切なのは、適正な報酬を設定し、価格に見合った価値を提供することです。
親身な対応、専門知識、迅速で確実な仕事など、価格以外の価値を提供できれば、信用が積み重なり、「値段」以外で選んでくれる顧客が増えてきます。良いお客は、必ず良いお客を連れてきてくれるため、安定した集客と収益アップにつながります。
※こちらの記事も読まれています。
3-5.他の行政書士にはない「強み」をもつ
最後に重要なのは、他の行政書士にはない独自の「強み」をもつことです。
行政書士としての開業は、結局のところ事業主として生きていくことに他なりません。試験合格後も、自分の市場価値を高め続けることは不可欠です。
営業力を磨く、特定分野で圧倒的な実績を積む、人脈を広げるなど、さまざまなアプローチがあるでしょう。
その一例として、伊藤塾でオススメしているのがダブルライセンスの取得です。
司法書士や社会保険労務士など、関連する資格を取得すれば、提供できるサービスの幅が広がるからです。たとえば、会社設立なら行政書士と司法書士の資格があれば、許認可から登記まで1人で対応できるようになります。
複数の資格を組み合わせることで、他の行政書士にはない強みが生まれるのです。
※こちらの記事も読まれています。
4.「開業後1年目のリアルは?」ー行政書士実務家インタビュー
行政書士として活躍している先輩たちは、開業1年目にどのような印象を抱いたのでしょうか。
井内講師の教え子であり、農地専門行政書士として開業した野口真守先生(野口真守行政書士事務所)に、開業1年目のリアルな感想を伺いました。
5.【Q&A】行政書士の廃業についてよくある質問
最後に、行政書士の廃業についてよくある質問をまとめました。
Q.行政書士は9割が廃業すると聞きましたが本当ですか?
A. いいえ、それは誤解です。
本記事で紹介したとおり、行政書士の廃業率は年間4.4%しかありません。世間のイメージより大幅に低いのが現実です。
Q.行政書士会の退会と廃業は同じですか?
A. 厳密には異なりますが、実質的にはほぼ同義です。
行政書士会を退会すると行政書士として活動できなくなるため、事実上の廃業となります。再び行政書士として活動するには、改めて行政書士会に登録する必要があります。
6.行政書士の廃業率は年4.4%で「廃業しやすい」という噂は誤解!
行政書士の廃業率は年間4.4%で、10年後も約7割以上が事業を継続しており、「廃業しやすい」という噂は誤解です。廃業の主な理由は自己都合による廃業届の提出(2,064名)ですが、死亡や心身の故障なども含まれます。
◉行政書士が廃業しやすいと言われる理由
・仕事内容のイメージが湧きにくいこと
・士業の中で人数が多いこと
・開業までのハードルが低いこと
◉廃業しないための開業成功の秘訣
・入念な開業準備をする(特に6ヶ月〜1年分の生活費の確保)
・専門分野を決めて実績を積む
・SNSなどを利用して集客する
・「価格」ではなく「信用」を武器にする
・他の行政書士にはない「強み」を持つ(ダブルライセンスなども有効)
以上です。
独立開業に強い資格として有名な行政書士ですが、開業してうまくやっていけるのか不安だったり、開業後のイメージがわかなかったり、一歩踏み出す勇気が持てない方も多いでしょう。
そんな方におすすめしたいのが伊藤塾です。
伊藤塾では、行政書士試験の合格がゴールではなく、合格後の活躍まで視野に入れた指導を行っています。
「合格後を考える」という理念のもと、卒業生がつながる伊藤塾同窓会や実務家による講演会の開催など、合格後の活躍を支援する取り組みが充実していることも伊藤塾の特徴です。
社会の原動力になろうとするあなたを、様々な教育サービスを通じてサポートしていくことが伊藤塾の使命です。あなたの志に、進むための確かな実力が必要なら、ぜひ私たちにお手伝いさせてください。
その志に、実力を。
伊藤塾は、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。