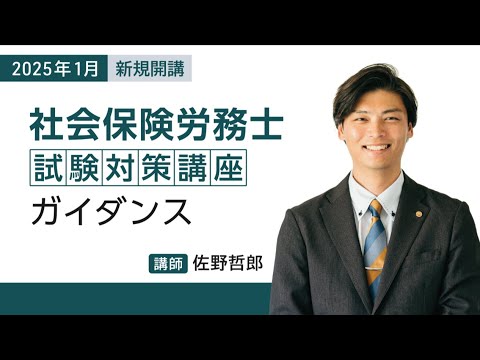【2025年度】社労士試験日はいつ?合格までのスケジュールと対策を徹底解説
基本情報
2025年10月30日


社会保険労務士(以下、社労士)は、労働・社会保険に関する専門家として高い需要があり、その資格はキャリアアップや独立開業を目指す多くの人からも注目されています。
社労士試験の受験を検討している方は、まず試験日を確認しましょう。試験日を知ることで、それに向けて適切な学習スケジュールを立てることができます。
例年の合格率が8%を切る社労士試験に合格するためには、試験の概要や効果的な学習計画の立て方など、事前の情報収集が重要です。
本記事では、2025年度の社労士試験について、試験日程や合格発表までのスケジュール、試験当日の注意点や効果的な学習方法について詳しく解説します。社労士試験合格を目指す方は、この記事を参考に試験日までの準備を進めていきましょう。
【目次】
1. 2025年度社労士試験スケジュール
まずはじめに、2025年度の社労士試験スケジュールを解説します。
1-1. 試験日
2025年度の社会保険労務士試験の実施日は2025年8月24日(日)です。
社労士試験は例年8月の第4日曜日に行われます。2025年は8月が5週間あるので「最終週」と間違えないように注意しましょう。
1-2. 申込みから合格発表・成績通知までの流れ
次に、試験申込みから合格までの一連の流れをご説明します。計画的に準備を進めるためにも、各ステップの順番や時期を把握しておきましょう。
①受験の申込み
2025年度の試験申込期間は、4月14日(月)から5月31日(土)です。申込み方法と期限は、以下の通りです。
■インターネット:5月31日23:59までにオフィシャルサイトから手続きを完了させる
■郵送:5月31日までの消印が押された簡易書留で必要書類を郵送する
※申込みの手順の詳細はこちらの記事でさらに詳しく解説しています。
→社労士試験の申込みはいつからいつまで?インターネットと郵送の手順・必要書類についても解説
②受験料の払込み
受験料の払込みは、申込みの際に行う必要があります。
支払いが完了していないと申込みが完了とはならないため、手順をよく読んで支払いを済ませましょう。
選択できる払込方法は、申込みの仕方により異なります。
③受験票の発送
試験の受験票は、8月上旬に試験センターから、申込みの際に登録した住所宛に発送されます。8月7日までに到着しなければ、試験センターへ問い合わせてみましょう。 手元に受験票が到着した際は、氏名や住所など、内容に誤りがないかを必ず確認してください。
④試験当日
2025年度の試験日は8月24日(日)です。試験は午前と午後の2部構成で実施されます。当日の詳細なスケジュールは後ほど説明します。
⑤合格発表
2025年度試験の合格発表日は10月1日(水)です。厚生労働省ホームページ及び社労士試験オフィシャルサイトにて、合格者の番号が発表されます。
⑥合格証書・成績通知書の送付
合格者には2025年10月14日(火)に合格証書が簡易書留で発送されます。また、受験者全員には、合否に関わらず、同日付で成績通知書が普通郵便で発送されます。
⑦官報への公告
合格者の受験番号が、2025年10月下旬に官報に公告されます。
参考:厚生労働省「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 受験案内」
2. 試験日の概要
次に、試験日に関する概要を説明していきます。
2-1. 当日のタイムスケジュール
まずは、当日の試験スケジュールです。社労士試験は午前と午後の2部に分けて1日をかけて実施されます。
| 【午前の部:選択式試験】 ・開場時間:9:30 ・集合時間:10:00 ・試験時間:10:30〜11:50 ・退出可能時間:11:10〜11:40 |
| 【午後の部:択一式試験】 ・集合時間:12:50 ・試験時間:13:20〜16:50 ・退出可能時間:14:10〜16:40 |
試験時間内に退出をした場合、再入室はできないので注意しましょう。
2-2. 試験会場
社労士試験の会場は、以下の19都道府県にある、学校や催事会場に設置されます。
北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、
兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県及び沖縄県
試験会場は申込み時に登録した「希望試験地」をもとに決定され、具体的な会場は受験票に記載されます。受験票が手元に届いたら必ず確認をしておきましょう。
試験当日の会場付近は混雑が予想されるため、事前にルートを確認し、当日は時間に余裕を持って会場に向かうのがおすすめです。試験会場へのアクセスは車での来場が認められていないため、公共交通機関を利用する必要があります。
2-3. 持ち物と心構え
ここからは、試験に臨むにあたり、必要な持ち物と心構えについて解説をします。試験勉強に没頭してその他の準備がおろそかにならないよう、しっかり確認をしておきましょう。
2-3-1.持ち物・服装
試験当日の持参品(持ち物)は以下の通りです。
【試験時間中に机上に置けるもの】
・受験票
・筆記用具(HBの黒鉛筆、シャープペンシル、プラスチック消しゴム)
・腕時計(通信・計算機能がなく、音を発しないもの)※置き時計は使用不可
・眼鏡(必要な方のみ)※眼鏡ケースはカバン等に収納
・目薬(必要な方のみ)※外箱はカバン等に収納
・ハンカチ、ポケットティッシュ(必要な方のみ)
【その他の持参品】
・飲料水(ペットボトルのみ可、ボトルカバー使用不可、ボトル缶不可、水筒不可)
・昼食
・写真付きの身分証明書(運転免許所、パスポート、社員証、学生証など)
・座布団、膝掛け(必要な方のみ)
【携帯電話・スマートウォッチなど電子機器類について】
・不正行為防止のため、時計としても携帯電話、スマートウォッチなどは試験室内で使用できません。
・試験中に音が鳴る、あるいはバイブレーションが作動し、所有者を特定したときや電源を付けたまま所持していることが確認された場合は失格となります。
【服装】
・体感温度の調節が可能な服装(冷房設備の温度調整ができない場合があるため)
・帽子類(フード等を含む)の着用は不可(本人確認が困難になるため)
2-3-2.当日の心構え
試験当日は、落ち着いて試験に臨むために次のことを心がけましょう。
・当日は開場時刻である9:30頃に到着できるよう、時間に余裕を持った計画を立てる
・試験前は食事や睡眠など体調管理を心がけ、万全な状態で試験に臨む
・前日の過度な勉強は避け、心身をリラックスさせる
・緊張を落ち着かせようとし過ぎず、1問1問を解くことに集中する
3. 社労士試験の合格基準と合格率
社労士試験に挑戦をするにあたって、試験の合格基準や例年の合格率を知っておくことも大切です。ここからは、社労士試験の合否基準と合格率について説明していきます。
3-1.合格基準
社労士試験の合格には、選択式試験と択一式試験それぞれの総得点が基準点に達していること、及び各科目でも基準点数以上を獲得していることが必要です。原則的な合格基準点は、以下の通りです。
| 試験種類 | 科目 | 満点 | 合格基準点 |
| 選択式試験 | 総得点 | 40点中 | 28点以上 ※満点の7割以上 |
| 各科目 | 5点中 | 3点以上 | |
| 択一式試験 | 総得点 | 70点中 | 49点以上 ※満点の7割以上 |
| 各科目 | 10点中 | 4点以上 |
参考:厚生労働省「社会保険労務士試験の合格基準の考え方について」
具体的な点数は、毎年の試験の難易度や受験者全体の得点分布にに応じて調整され、合格発表の日に公表されます。参考までに、2024年度試験の合格基準は以下の通りでした。
【2024年度試験 合格基準】
次の2つの条件を満たした者
①選択式試験は、総得点25点以上かつ各科目3点以上(ただし、労務管理その他の労働に関する一般常識は2点以上)である
②択一式試験は、総得点44点以上かつ各科目4点以上である者
3-2.合格率
2024年度の社労士試験の合格実績は「受験者数43,174人」「合格者2,974人」「合格率6.9%」です。過去5年間の社労士試験合格率はいずれも8%を切っており、社労士試験が難関試験であることを表しています。
【過去試験の合格率データ】
| 実施年度 | 受験人数 | 合格者数 | 合格率 |
| 2024年(令和6年) | 43,174人 | 2,974人 | 6.9% |
| 2023年(令和5年) | 42,741人 | 2,720人 | 6.4% |
| 2022年(令和4年) | 40,633人 | 2,134人 | 5.3% |
| 2021年(令和3年) | 37,306人 | 2,937人 | 7.9% |
| 2020年(令和2年) | 34,845人 | 2237人 | 6.4% |
4. 合格のために必要なこと
試験範囲が広く専門的で難易度が高い社労士試験ですが、合格を勝ち取るために重要なポイントがあります。ここからは、社労士試験に合格するために特に大切なことをご紹介します。
4-1. 学習スケジュールを立てる
社労士試験合格への第一歩は、学習を生活の中に取り入れ、試験日までの具体的な学習計画を立てることです。
合格に必要な学習時間は、一般的に800時間から1000時間程度と言われています。これは、1日3時間で1年間、1日8時間で4ヶ月間という計算になります。ただし、これはあくまでも目安であり、個人の知識や経験によって必要な時間は変わってきます。
この時間を参考に、学習開始から試験日までの期間で、まずは大まかなスケジュールを組み立てましょう。
1日あたりの学習時間を増やしすぎると、仕事や生活との両立が困難になったり、途中で学習意欲が低下したりするリスクがあります。
さらに、作成したスケジュールは、定期的に進捗状況や習熟度を確認し、必要に応じて見直しを行うことが重要です。このように、現実的で柔軟な学習スケジュールを立てることが、試験合格の鍵となります。
なお、特に短期間で合格を目指すなど限られた時間の中で効率的に学習を進めていきたい方や、学習スケジュールを自己管理することが苦手な方は、受験指導校の活用を検討してみることをおすすめします。
4-2. 学習方法を確立する
社労士試験に合格するために、自分に合った学習方法を確立しましょう。
4-2-1.日々の学習方法を決める
まずは、日常的な学習方法を決定することです。
学習方法を決める際は、「インプット」と「アウトプット」を意識することで、効率的に記憶を定着させて学習を進めることができます。
| 【インプット勉強法の例】 ・テキストや判例を読む ・ノートに書き写す ・講座を受講する |
| 【アウトプット勉強法の例】 ・過去問題や模擬試験を解く ・学習内容を人に話す ・ノートにまとめて知識を整理する |
効果的な学習方法は、個人によって大きく異なります。自分に合った、継続しやすく効率の良い学習スタイルを見つけ出すことが、試験合格の鍵にもなります。
4-2-2.最新の法改正情報を収集する
社労士試験では、法改正が頻繁に行われる科目が多くあるため、最新の情報を正確に把握することが重要なポイントになります。
受験指導校などで学ぶ場合には、試験に必要な法改正情報が提供されますが、独学では自分で情報収集を行う必要があります。その際は、厚生労働省の公式サイトや信頼できる法律情報サイトなど、確実な情報源から収集することが大切です。
4-3. 過去問や模擬試験を活用する
社労士試験の学習において、模擬試験や過去問の活用は知識を効率的に定着させるための重要な方法の1つです。
4-3-1.過去問の活用例
過去問は、全科目の学習が終わってからではなく、各科目の学習と並行して取り組むことをおすすめします。テキストなどでインプット学習をしながら過去問に取り組んでアウトプット学習をすることで、頭の中の知識が整理され、記憶の定着力が高まります。
問題に取り組む際は、得点よりも「なぜこの選択肢が正解なのか」「自分はどうして間違えたのか」など、自分の理解度を分析することが大切です。
社労士試験では、類似の論点や選択肢が出題されることも多くあるため、選択肢の表現などが変わったとしても適切な答えを見つける力が必要になります。
4-3-2.模擬試験の活用例
全体的な学習が進み、試験日が近づいた段階で、実際の試験と同じ時間設定・形式で模擬試験に挑戦しましょう。これにより本番の緊張感に慣れるとともに、解答スピードや時間配分の感覚を養うことができます。
4-4.受験指導校を利用するメリット
効率的に学習を進める1つの方法として、受験指導校を活用するという手段も有効です。受験指導校では、体系的なカリキュラムと資格試験に精通した専門家によるサポートが用意されています。
例えば、伊藤塾の場合、学習の進め方などに不安を感じた場合や学習時に理解が難しいと感じた際には、いつでも自由に相談や質問をすることができ、講師や社労士試験合格者が丁寧かつスピーディーな回答で学習をサポートしています。
また、最新の法改正情報をタイムリーに取得できるため、試験に必要な知識を着実に身につけ、自信を持って合格を目指すことができます。
5. まとめ
本記事では、2025年度の社労士試験について、試験日程から合格に向けた具体的な対策まで詳しく解説しました。
社労士試験は合格率8%を下回る難関試験ですが、試験日を確認することにより、合格までの道筋を具体的に描くことができるようになります。
合格のためには1000時間の学習が必要と言われていますが、効率的な学習を行うことにより、最短距離での合格を目指すことができます。そのため、試験日に向けて計画的な学習スケジュールを作成し、自分に合う適切な学習方法を取り入れていきましょう。
伊藤塾では、2025年の合格を目指して、2025年合格目標 社労士試験合格講座を開講中です。
社労士試験に合格して人生を変える挑戦に臨みたい方は、ぜひ一歩を踏み出してみてください。伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。
【社労士】伊藤真塾長×持田裕講師~伊藤塾で「社労士」を目指す意味とは~