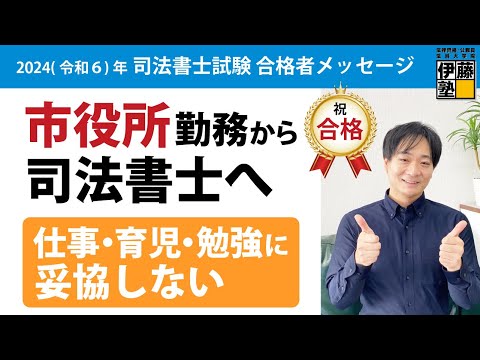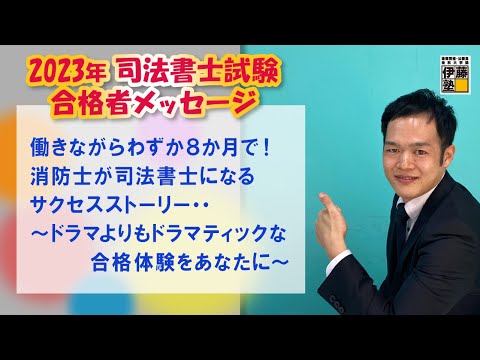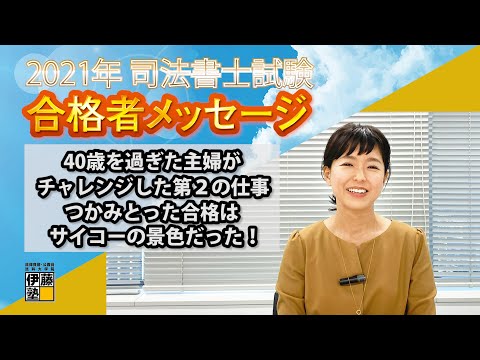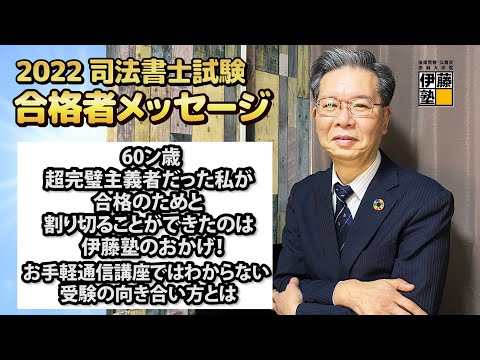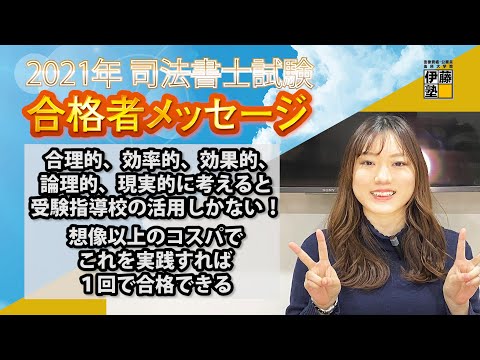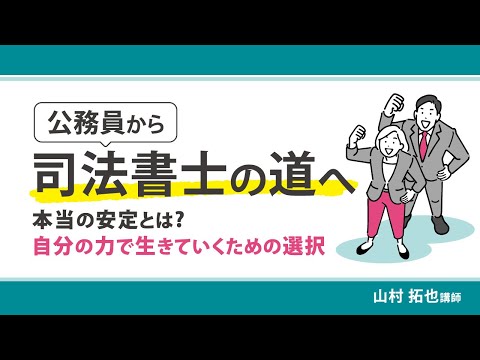公務員を辞めたい方へ!元・公務員が語る後悔しないための考え方
キャリア
2025年11月07日


「今すぐ公務員を辞めたい…」
「安定はしているけど、何かが違う…」
公務員になって数年、あるいは数十年が経ち、このように感じていませんか。
家族や友人に相談しても、「せっかく公務員になったのにもったいない」「民間はもっと大変だよ」と言われ、「辞めない方が良いのか」と悩んでいる方は意外と多いものです。
独身ならまだしも、家族を養っているような状況においては、自分の本当の気持ちに蓋をして、家族のため安定した生活を優先してしまっている人がほとんどかもしれません。
しかし、人生において自分の気持ちを大切にすることは決して悪いことではありません。むしろ、自分の気持に正直になり、リスクを承知で新しいことに挑戦することは、有意義な人生を送るためには非常に大切なことでもあります。
したがって、「公務員を辞めたい」という気持ちに従うのは、人生で必要な決断といってもよいでしょう。
残りの人生をずっと、「もっと違う仕事がしたい」と思いながら通勤するのは辛いですし、挑戦した方が後悔のない人生を送れるからです。
しかし当然ながら、「安定した収入を失う」「福利厚生がなくなる」といったリスクもあります。そのため、退職の判断は慎重に行う必要があります。
そこで本記事では、実際に公務員を辞めた方へのインタビューも行いつつ、
- すぐに公務員を辞めてもよい3つのケース
- 辞める前に知っておくべき退職金などの知識
- 後悔しないための必要な3つのステップ
- 退職後、どのような選択肢があるのか
などについて解説していきます。
ぜひ最後まで読み進めて、公務員を辞めるべきか否か、あなたのキャリアについて真剣に考えてみてください。
【目次】
1.「公務員を辞めたい…」という気持ちは無視してはダメ
冒頭でもお伝えしたとおり、「公務員を辞めたい」という気持ちは無視してはいけません。主な理由として以下2つが挙げられます。
・仕事には誰にでも向き、不向きがあるから
・公務員を辞める人は珍しくないから
それぞれの理由について、詳しく見ていきます。
1−1.仕事には向き・不向きがある
どれだけ素晴らしい仕事でも、必ず「向き・不向き」があります。
安定が約束された公務員でも、なかには「自分には向いていない」「職場に違和感がある」と感じる人がいるのは、ごく自然なことです。
「この職場は嫌だ」「本当はもっと違う仕事がしたい」と感じながら働くのは辛いですし、ストレスも溜まっていく一方です。
いくら安定しているからといって、公務員だけに囚われる必要はありません。
1−2.公務員を辞める選択をする人は珍しくない
今の時代、公務員を辞める選択をする人も決して珍しくありません。
人事院の「令和5年度一般職の国家公務員の任用状況調査」によると、公務員を辞めた人のうち、辞職した人(定年退職ではなく自分の意思で辞めた人)の割合は、約43%にのぼります。

(出典:人事院「令和5年度一般職の国家公務員の任用状況調査‐1(1)給与法職員、任期付職員、任期付研究員、行政執行法人職員:俸給表別・項目別総集計表)」
さらに、同じ調査では、辞職者の49%が40代以下となっており、若手〜中堅層も自分の意思で公務員を辞めています。公務員を退職するのは、あなたが考えているほど特別なことではありません。
2.【退職者インタビュー】実際に公務員を辞めて感じたこと
では、実際に公務員を辞めると、どのような変化があるのでしょうか。
公務員を辞めた後、伊藤塾で行政書士の資格を取り、現在はフリーランスのライターとして活躍されている石井さんにお話を伺いました。
Q.安定した公務員を、なぜ辞めようと決意したのですか?
「もっと自由に生きてみたい」という気持ちが日に日に大きくなっていったのが一番の理由です。もちろん、周囲からは「もったいない」と言われましたし、自分でも本当に悩みました。
ただ、最終的には自分の人生だから後悔しない生き方をしようと思いました。
Q.実際に公務員を辞めてみて、いかがでしたか?
公務員を辞めた直後は、解放感でいっぱいでした。でも、すぐにものすごい不安に襲われました(笑)。
分かってはいたつもりですが、手厚い福利厚生や有給休暇、退職金などがすべてなくなる。そして何より、「毎月決まった日に給料が振り込まれる」という安心感がなくなったのは、想像以上に大きな変化でした。
「ああ、自分は守られていたんだな」と痛感し、自分で生きていくための「武器」が必要だと強く思いました。
それがきっかけで、色々なご縁もあって伊藤塾で行政書士の資格を取ることにしました。もともと法律の勉強が面白くて公務員になった経緯もあったので。
※行政書士については、以下の記事で詳しく解説しています。
Q.公務員を辞めた後、「良かった」と感じるのはどんな時ですか?
一番は、働く時間と場所、そして一緒に働く人を「自分で選べる」ことです。
もちろん責任は大きいですが、その分、自由度は比較になりません。公務員時代が「コンクリートで舗装された安全な道を歩いている」感覚だとすれば、今は「大自然の中を裸足で進んでいる」ような感覚です(笑)。リスクは大きいですが、見える景色は全く違います。
あと、地味ですが、平日の昼間に役所や病院に行けたり、ふらっと遊びに行けたりするのも、本当にありがたいと感じます。
Q.行政書士の資格もお持ちですが、なぜ今「司法書士」を目指しているのですか?
伊藤塾で行政書士の資格を取ったのが、大きなきっかけです。
もともと法律の勉強が好きだったんですが、伊藤塾で本格的に法律を学んでみたら、改めてその面白さに気づいて。「もっと専門性を高めてステップアップしたい」という気持ちが強くなったんです。
司法書士は将来性も専門性も非常に高い資格ですし、法律の勉強が好きな自分にはぴったりだと思いました。
あと、少し本音を言うと、公務員時代のような社会的信用や安定性を、今度は自分の力で手に入れたい、という思いが心のどこかにあるのかもしれません(笑)。
Q.最後に、同じように公務員を辞めたいと悩んでいる方へ、メッセージをお願いします。
もし今、公務員を辞めるか悩んでいるなら、まず「勢いだけで辞めるのは絶対にやめた方がいい」と伝えたいです。公務員には、辞めてみて初めて分かる良いところが本当にたくさんあります。
その上で、ご自身のキャリアと本気で向き合い、しっかりと準備をしてから辞めるのであれば、きっと今とは違う素晴らしい景色が見えるはずです。大変ですが、挑戦する価値は十分にあると思います。
3.今すぐ公務員を辞めてもよいと言える3つのケース
先ほどのインタビューにもあったように、勢いで公務員を辞めてしまうと、想像以上の不安や困難に直面します。では、どのような場合なら今すぐ公務員を辞めてもよいと言えるのか、3つのケースを紹介します。
◉今すぐ公務員を辞めてもよいと言える3つのケース
・やりたいことが決まっており、その準備もしている
・退職後、しばらく生活できるだけの貯蓄がある
・専門的な国家資格、スキルがある
なお、上記のいずれにも当てはまらないが、「どうしても早く辞めたい」という方は、5章で紹介する「今すぐとるべき3つの行動」を参考に、次の一歩を考えてみてください。それでは、1つずつ見ていきます。
3−1.やりたいことが決まっており、その準備もしている
まずは、すでに公務員を退職した後にやりたいことが決まっているケースです。
たとえば、
- 働きたい民間企業からすでに内定をもらっている
- ずっと挑戦したかった飲食店を開くために、有名店で修行をする予定
- 地方へ移住すると決めており、住む場所や仕事のあてもついている
といった場合です。
このような方は、現状維持を選ぶよりも、思い切って新しい道へ挑戦した方が、後悔のない人生を送れるかもしれません。
3−2.退職後、しばらく生活できるだけの貯蓄がある
次に、退職してしばらくは生活に困らないだけの貯蓄があるケースです。この場合、思い切って先に退職するのも一つの手段です。
自由な時間が増えるので、転職活動に集中したり、資格を目指したりと、新しい人生に向けた準備をじっくりと進められます。
ただ、次の仕事が決まるまでは、貯金が減っていくだけなので、精神的なプレッシャーも相当のものです。「独身で、いざとなれば実家に戻れる」、あるいは「夫(妻)が働いており、子供もいない」といった方でなければ、あまりおすすめはできません。
3−3.すぐに働ける国家資格を持っている
公務員の中には、「資格免許職、専門職」といわれる仕事があります。具体的には、医師、看護師、薬剤師、裁判官、検察官といった、国家資格がなければ就けない仕事です。
こういった資格があれば、公務員か民間企業かに関わらず、就職先で困るケースは少ないです。 もし今の職場が合わないと感じているのなら、思い切ってすぐに辞めてみるのも良いでしょう。
なお、資格の中には公務員として働きながら目指せるものもあるので、6章で後述します。
※こちらの記事も多くの方に読まれています。
4.公務員を辞める前に知っておくべき知識(退職金・失業手当・休暇制度など)
公務員を辞めると決意したとき、一番の不安はやはり「お金」の問題でしょう。
4章では、失業手当や退職金、休暇制度など、公務員を辞める前に知っておくべき知識について解説します。
4−1.公務員は失業手当が支給されない
民間企業を自己都合で退職した場合、ハローワークで手続きをすれば、一定期間後に「失業手当(基本手当)」が支給されます。
ただ、公務員は雇用保険の対象外なので、失業手当は受け取れません。つまり、退職してから次の仕事が見つかるまでの生活費は、基本的にご自身の貯蓄でまかなう必要があります。
この失業手当の代わりとなるのが、次に説明する「退職手当」です。
4−2.退職手当の平均支給額は約300万円
内閣官房によれば、公務員を自己都合で辞めた人に支給される退職手当は、平均で約300万円です。
(出典:内閣官房内閣人事局「退職手当の支給状況(令和6年12月)」)
300万円を「高い」と感じるか「低い」と感じるかは人それぞれですが、これはあくまでも全体の平均値です。実際の支給額は、勤続年数によって大きく変わります。
参考として、勤続年数ごとの計算式(国家公務員の場合)を紹介します。ご自身の給料(俸給月額)を当てはめて、おおよその支給額を計算してみてください。
| 勤続年数 | 退職手当の支給額 |
| 3年 | 俸給月額×1.5066 |
| 5年 | 俸給月額×2.511 |
| 10年 | 俸給月額×5.022 |
| 15年 | 俸給月額×10.3788 |
| 20年 | 俸給月額×19.6695 |
| 25年 | 俸給月額×28.0395 |
| 30年 | 俸給月額×34.7355 |
(出典:人事院「退職手当制度の概要」)
たとえば、勤続年数が20年で、退職時の俸給月額が40万円の方なら、「40万円×19.6695=786万7800円」が退職手当の支給額となるイメージです。勤続年数によっては、退職手当で当面の生活費を賄える人もいるでしょう。
4−3.体調不良が原因なら有給の病気休暇・休職も検討しよう
もし、公務員を辞めたい原因が、身体や心の不調にあるのなら、退職の前に「病気休暇」や「病気休職」の利用も検討してみてください。
病気休暇を取得すれば、最大90日間は給与が全額支給されます。
90日で復職できない場合は、病気休職に切り替わり、そこから1年間は給与の80%が支給されます。2年目からは給与は支給されませんが、共済組合から傷病手当金として給与の約3分の2にあたる金額が、1年6ヶ月にわたって支給されます。
その期間が経過した後も、6ヶ月は傷病手当の付加金が支給されるため、3年間は無収入になりません。
| 期間 | 内容 |
| 〜90日 | 給与が全額支給される |
| 休職後1年 | 給与の80%が支給される |
| 2年目〜3年目 (前半) |
傷病手当(給与の約3分の2相当)が 支給される |
| 3年目 (後半) |
傷病手当金附加金が支給される |
これらの制度を利用すれば、お金の心配をせずに、ゆっくりと心と体を休ませることができます。体調不良が原因なら、辞める前に一度休職してみることを強くおすすめします。
5.公務員を辞めて後悔しないために必要な3つのステップ
ここまでの内容を読んだ上で、それでも「公務員を辞めたい」という気持ちが変わらないなら、具体的な準備を始めましょう。
以下で紹介する3つの行動を順番に試してみてください。
・なぜ公務員を辞めたいのかを徹底的に考え抜く
・辞める「前」に転職活動をしてみる
・「民間企業への転職」以外の選択肢を探ってみる
それぞれ詳しく説明します。
5−1.なぜ公務員を辞めたいのかを徹底的に考える
まず初めにやるべきなのは、「なぜ自分は公務員を辞めたいのか?」を徹底的に考え抜くことです。
「やりがいを感じられない」
「給与がなかなか上がらない」
「部署によっては残業が多くて大変」
「職場の独特の雰囲気が苦手」
など、人によって理由があると思います。
しかし、その悩みは本当に公務員を辞めれば解決するのでしょうか。
たとえば、民間企業でも同じような悩みにぶつかる可能性はありますし、今より給与が下がることもあるでしょう。公務員を辞めなくても、異動するだけで悩みが解消されるケースもあります。
勢いで辞めて後悔しないためにも、もう一度「なぜ公務員を辞めたいのか」、自分と真剣に向き合ってみてください。
5−2.辞める「前」に民間企業への転職活動をしてみる
自分と真剣に向き合った結果、どうしても公務員は続けたくないと思ったのなら、公務員を「辞める前」に、民間企業への転職活動をしてみましょう。
◉在職中にやるべきこと
・自分の年齢や経歴で応募できる求人を探してみる
・これまでの経験をまとめた「職務経歴書」を書いてみる
・実際にいくつか応募して、書類選考でどのくらい通過するか試してみる
・有給休暇を使って、面接に行ってみる など
辞める前に転職活動をするのは基本的に問題ありません。利害関係企業等でなければ、(決まる前は)職場に報告する必要もないでしょう。
ただ、公務員としての職歴は、必ずしも民間企業で高く評価されるとは限りません。「すぐに見つからないかも…」という覚悟はしておきましょう。
5−3.「転職」以外の選択肢を探ってみる
転職活動をした結果、もし「応募したい企業が見つからない」「なかなか選考に通らない」となったら、一度立ち止まって転職以外の選択肢も考えてみてください。
妥協して転職すると、結局「公務員のままでいればよかった」となるリスクがあります。
◉辞めた後、民間企業への転職以外でとれる選択肢
・フリーランスや自営業者として働く
・経験者採用枠などを利用して、他の公務員試験を受け直す
・国家資格を取得して、専門職として就職・開業する など
中でも、公務員の方におすすめなのは「国家資格を取得して、専門職として就職・開業する」ことです。特に法律系の士業資格は、公務員の経験との相性が良く、働きながらでも合格を目指せます。
※こちらの記事も多くの方に読まれています。
6.公務員を辞めるために資格をとるなら司法書士がおすすめ
法律系の士業資格の中でも、公務員からのキャリアチェンジに特におすすめなのが「司法書士」の資格です。
6章では、なぜ司法書士が公務員からの転職におすすめなのかを、3つのポイントから説明していきます。
・年齢・経験に関わらず、圧倒的に就職しやすい
・公務員としての経験と相性が抜群に良い
・働きながらでも、最短1年〜2年で合格を目指せる
それぞれ詳しくみていきます。
6−1.年齢・経験に関わらず、圧倒的に就職しやすい
司法書士の魅力は、年齢やこれまでの職務経験に関わらず、就職しやすいことです。
つまり、公務員ほどではないにせよ、「食いっぱぐれる」というリスクが少ないため、「安定」が期待できるのです。
伊藤塾では、毎年多くの司法書士試験合格者を送り出していますが、就職先で困ったという声はほとんど聞きません。中には50代で合格された方もいますが、そういった比較的年齢が高めの方でもスムーズに事務所に採用されています。
さらに、1〜2年ほど経験を積めば、独立開業して年収1000万円以上も目指せます。働き方の自由度や収入の高さを追求しつつ、国家資格としての安定性も期待できる、まさに公務員からの転職にうってつけの資格です。
※司法書士の仕事は、以下の記事で詳しく解説しています。
6−2.公務員としての経験と相性が抜群に良い
司法書士は、不動産や会社の登記、成年後見といった法律的な手続きを扱う仕事です。
同じ法律家でも、弁護士が「紛争の解決」を得意としているのに対し、司法書士は「手続きの専門家」であるという特徴があります。
一方、公務員の仕事も法律や条例にもとづいて、適正な行政手続きを進めていくものです。 法律の知識を扱い、手続きの適正さが求められるという点で、両者の仕事はとても相性が良いのです。
実際に伊藤塾では多くの方が、公務員から司法書士にキャリアチェンジして活躍しています。
伊藤塾で公務員から司法書士になった方の体験談動画をご紹介します。
・雪竹晴輝さん(市役所職員):市役所勤務から司法書士を目指し、家事・育児・仕事と両立して2回目の試験で合格
・安井さん(消防士):働きながらわずか8か月で!消防士が司法書士になるサクセスストーリー
・井上安恵さん(県庁職員):40歳を越えた県庁職員から司法書士にチャレンジして、1回の受験で合格
・原晃一さん(地方公務員):定年間近から司法書士を目指し、60歳を超えて合格
・深谷典子さん(法律系の公務員):法律系の公務員から司法書士を目指し、1回の受験で合格
他にも多数の体験談動画があります。ご興味のある方はコチラもご覧ください。
法務局や裁判所で働く国家公務員はもちろん、それ以外の省庁や地方公務員として働いてきた経験も、仕事の考え方や進め方という面で大いに発揮されるでしょう。
6−3.働きながらでも、最短1年〜2年で合格を目指せる
司法書士試験は、国家資格の中でも最難関の一つとして知られています。
しかし、実は正しい方法で勉強すれば、働きながらでも十分に合格を目指せる試験です。
実際、上記の動画で紹介している雪竹さんは、市役所職員として働きながら合格しています。他にも、法律を全く学んだことがない状態から司法書士試験の勉強をスタートし、仕事や家事・育児と両立させながら合格している方はたくさんいます。
伊藤塾の合格者の中には、消防士から8ヶ月で合格した人もいるほどです。もちろん簡単な試験ではありませんが、世間で言われるほど難しくもありません。
※こちらの記事も読まれています。
7.公務員から司法書士の道へ〜本当の安定とは?自分の力で生きていくための選択〜
最後に、伊藤塾の入門講座・中上級講座を受講して令和5年度の試験に合格し、令和6年に独立開業をした中村翔太郎さん(東京都庁出身)に、受験時代の勉強法から実務のリアル、そして独立後の変化までをお話しいただきます。
今回は、入門講座担当の山村拓也講師が、対談形式で具体的なお話をお聴きします。これから合格を目指す受験生へ、一歩先の未来をイメージできる時間になれば幸いです。
8.公務員をやめたい方からのよくある質問(Q&A)
Q. 公務員をやめたいと思うのは甘えでしょうか?
A. いいえ、決して甘えではありません。公務員といえども職場の人間関係や業務量、やりがいの問題などで悩む人は多くいます。「安定しているから続けるべき」と思い込みすぎると、心身をすり減らすこともあります。まずは「なぜ辞めたいのか」を整理することから始めましょう。
Q. 辞めるタイミングはいつがいいですか?
A. 多くの公務員は年度末(3月)で退職するケースが多いですが、必ずしもそれにこだわる必要はありません。転職先が決まっている場合は、その入社時期に合わせて調整して問題ありません。ボーナス支給日なども考慮して判断する人も多いです。
Q. 退職を伝えるときは、どのように上司に話せばいいですか?
A. まずは直属の上司に、退職の1か月以上前に「一身上の都合で退職を考えている」と丁寧に伝えるのが基本です。公務員の場合、正式な辞職願の提出や決裁に時間がかかるため、早めの相談が安心です。
9.公務員を辞めたい方へのアドバイスとご提案のまとめ
本記事では、「公務員を辞めたい」と悩む方へ向けて、元公務員へのインタビューや退職前に知っておくべき知識、後悔しないための準備について解説しました。
以下にポイントをまとめます。
- 公務員を辞めることは珍しくなく、辞職者(定年退職ではない)の割合は約43%であり、そのうち40代以下が49%を占めています。
- すぐに公務員を辞めてもよい3つのケース
1.やりたいことが決まっており、その準備もしている
2.退職後、しばらく生活できるだけの貯蓄がある
3.専門的な国家資格、スキルがある - 公務員は雇用保険の対象外のため、民間企業のような失業手当は支給されません。その代わりとなるのが退職手当(自己都合退職の場合、平均支給額は約300万円)です。また、体調不良が原因であれば、給与が全額支給される病気休暇や、その後も傷病手当などが支給される病気休職の利用を検討すべきです。
- 後悔しないための3つのステップ
1.なぜ辞めたいのかを徹底的に考え抜く
2.辞める『前』に転職活動をしてみる
3.民間企業への転職以外の選択肢を探る(特に法律系の士業資格など) - 公務員からのキャリアチェンジにおすすめな資格は司法書士です。 司法書士は、年齢や経験に関わらず就職しやすく「安定」が期待できます。また、公務員の経験は、法律手続きの専門家である司法書士の仕事と非常に相性が良いです。
- 働きながらでも合格を目指せる 司法書士試験は最難関の一つですが、正しい方法で勉強すれば働きながらでも合格可能です。伊藤塾の合格者の中には、市役所職員や消防士といった公務員から短期間で合格を果たした実例もあります。
公務員からの転職という大きな決断には、確固たる「武器」と正しい準備が必要です。
年齢にかかわらず就職が可能で、高い専門性と安定性を兼ね備え、かつ公務員の経験が活かせる司法書士資格は、公務員からのキャリアチェンジの選択肢としては非常に有効だといえるでしょう。
伊藤塾では、公務員から司法書士を目指す方々を全力でサポートしています。
まずは一歩踏み出し、専門性の高い法律の知識を身につけ、「本当の安定」を掴みませんか。
あなたの未来を変えるために、伊藤塾が力強くお手伝いをさせていただきます。