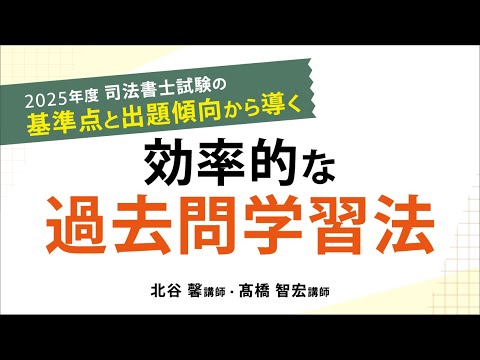令和7年度(2025年度)司法書士試験の基準点を講師が分析!届かなかった方への対策も伝授
勉強法
2025年10月17日


令和7年8月12日、司法書士試験の択一式基準点が発表されました。
午前の部は3年連続で78点(26問)、午後の部は昨年と同じ72点(24問)という結果でした。ただ、没収問題(以下「没問」と表記)で全員に3点が加点されたため、基準点が押し上げられています。午後の部については、昨年より難化したといってよいでしょう。
基準点に届かなかった方は、さぞ悔しい思いをされていると思います。しかし、ここで諦める必要はありません。
本記事では、令和7年度(2025年度)司法書士試験の基準点について、過去の試験と比較しながら、伊藤塾・髙橋講師による詳細な分析をお伝えします。さらに、令和8年度(2026年度)試験に向けてどのように学習を進めるべきか、具体的な対策も解説します。
基準点分析から見えてくる傾向と対策を、ぜひ今後の学習に活かしてください。
【目次】
1.令和7年度(2025年度)司法書士試験における基準点は?
令和7年(2025年)8月12日(火)16時、司法書士試験の択一式基準点が発表されました。
今年の基準点は、午前の部が「満点105点中78点」、午後の部が「満点105点中72点」という結果になりました。
■令和7年度(2025年度)司法書士試験の基準点
| 基準点 | 得点率 | |
| 午前の部 (多肢択一式問題) | 満点105点中78点 (全35問中26問) | 74.30% |
| 午後の部 (多肢択一式問題) | 満点105点中72点 (全35問中24問) | 68.60% |
| 記述式問題 | 10月2日発表 | ー |
| 筆記試験の合格点 | 10月2日発表 | ー |
(出典:法務省|令和7年度司法書士試験筆記試験(多肢択一式問題)の基準点等)
午後の部について、難易度の体感より基準点が高めに感じた方もいるかもしれません。これは没問があった影響です。
法務省の公式発表によると、第33問は「正答となる肢がなかった」として全員が正答になっています。受験者全員に3点が加点されたため、基準点が押し上げられた形になりました。
なお、「午後の部・第30問」も同じように疑義が生じていましたが、こちらは没問とはなっていません。
1-1.過去5年間における基準点・合格点の推移
ここで、令和7年度(2025年度)の基準点がこれまでと比較してどうなのかも見ておきましょう。過去5年間における司法書士試験の基準点・合格点の推移を以下にまとめました。
| 午前の部 (多肢択一式問題) | 午後の部 (多肢択一式問題) | 記述式 | |
| 2025年度 (令和7年度) | 105点中78点 (全35問中26問) | 105点中72点 (全35問中24問) | 不明 (10月2日発表) |
| 2024年度 (令和6年度) | 105点中78点 (全35問中26問) | 105点中72点 (全35問中24問) | ※140点中83.0点 |
| 2023年度 (令和5年度) | 105点中78点 (全35問中26問) | 105点中75点 (全35問中25問) | 70点中30.5点 |
| 2022年度 (令和4年度) | 105点中81点 (全35問中27問) | 105点中75点 (全35問中25問) | 70点中35.0点 |
| 2021年度 (令和3年度) | 105点中81点 (全35問中27問) | 105点中72点 (全35問中24問) | 70点中34.0点 |
(出典:法務省|司法書士試験)
※令和6年度(2024年度)以降、記述式問題の得点が「2問で70点満点」から「2問で140点満点」に変更されました。
午前の部については「3年連続78点」、午後の部については「2年連続72点」となっています。
ただし、先ほど説明したとおり、令和7年試験では没問によって受験生全員に3点が加算されています。そのため、午後の部は「難化」と考えてよいでしょう。
記述式の基準点は、筆記試験の合格発表日に公表されるので、現時点では不明です。
2.基準点から求められる上乗せ点・合格点の予想【令和7年度版】

今回発表されたのは択一式の基準点、いわば「最低限クリアすべきライン」です。
司法書士試験に合格するためには、基準点を超えるだけでなく、さらに上乗せ点が必要になります。この上乗せ点がどの程度になるのかは、10月2日の合格発表まで分かりません。
参考として、令和6年度(2024年度)までの上乗せ点・合格点の推移を紹介します。
■司法書士試験の上乗せ点・合格点の推移
| 上乗せ点 | (基準点の合計) | 合格点 | |
| 2024年度 (令和6年度) | 34.0点 | (233.0点) | 267.0点 |
| 2023年度 (令和5年度) | 27.5点 | (183.5点) | 211.0点 |
| 2022年度 (令和4年度) | 25.5点 | (191.0点) | 216.5点 |
| 2021年度 (令和3年度) | 27.5点 | (181.0点) | 208.5点 |
| 2020年度 (令和2年度) | 26.5点 | (179.0点) | 205.5点 |
(出典:法務省|司法書士試験)
2024年から急激に上乗せ点が高くなっているのは、配点変更があったからです。記述式の配点変更によって、満点が1.25倍に増加したため、それに応じて上乗せ点も同程度(1.24倍)増加しました。
令和7年試験でも、同じような結果となるのかは分かりません。あくまでも一つの指標としつつ、自分の得点と照らし合わせて合格可能性を検討してみてください。
3.【髙橋講師が解説】令和7年度(2025年度)司法書士試験の基準点
続いて、令和7年度(2025年度)司法書士試験の基準点について、詳細な内容を分析していきます。今回は、伊藤塾司法書士試験科の、髙橋智宏講師による解説をお届けします。
さらに詳しい内容を、以下の動画にてお伝えしていますので、あわせてご覧ください。
3-1.【午前の部】司法書士試験の基準点の推移

(出典:伊藤塾YouTube|【司法書士試験】2025年度 司法書士試験の基準点と出題傾向から導く効率的な過去問学習法)
まずは、午前の部の基準点についてです。
今年の基準点は35問中26問(105点中78点)でした。これまでの推移をみると、3年連続、基準点が26問(78点)ということになります。
では、これを踏まえて来年どうなるのか。あくまで可能性の話ですが、基準点25問レベルの難化をしていく、あるいは基準点27問レベルの易化をしていく、という両方が考えられます。
その中で、特に注意していただきたいのが、会社法が難化する可能性があるということです。
3年連続で解きやすい問題でしたが、令和8年以降難化をしていくという可能性は十分にあります。
とはいえ、難化に備えるからと言って細かい発展知識ばかりを押さえて欲しいというわけではありません。基礎をしっかり固めた上で周辺の細かめの知識まで押さえていく、基本的なところだけで終わらない、という意識をもって取り組みましょう。
3-2.【午前の部】令和7年試験で基準点に到達した人の割合

(出典:伊藤塾YouTube|【司法書士試験】2025年度 司法書士試験の基準点と出題傾向から導く効率的な過去問学習法)
次に、午前の部の基準点到達者の推移を見ていきます。
上記のグラフは、基準点の発表と同時に法務省から発表されている「順位別員数累計表」というものを使って作成しました。令和7年司法書士試験の午前の部において、どれぐらいの方が基準点に到達したのか、その比率を示しています。(出典:法務省「令和7年度司法書士試験得点順位別員数累計表」)
午前の部においては32.02%の方が、基準点に到達していることが分かります。
昨年(令和6年)の30.9%からやや上がっており、「基準点に到達する難易度」については易化したと言えるでしょう。
3-3.【午前の部】基準点到達のカギは民法
とはいえ、昨年の本試験や模試では点数が取れていたのに、本試験で点数が落ちてしまったという方もいらっしゃると思います。
では、午前の部の得点を安定させるためにはどうすればいいのか。その安定化のカギを握るのが民法です。民法で18問近く取れていけば、午前の部の得点は安定しやすく、基準点割れのリスクも回避しやすくなっていきます。
裏を返せば、民法で14問程度の点数になると、そこから基準点割れのリスクが生じていく、加えて上乗せ点の確保もしづらい状況になっていくわけです。
したがって、民法をいかに安定させるのかが、午前の部の基準点を安定して超えるための鍵になっていきます。
では、その民法を強化するためのポイントを2つお伝えしていきます。
※こちらの記事も読まれています。
3-3-1.制度趣旨から理解する
1つ目のポイントは、制度趣旨から理解することです。
なぜそういった制度になっているのか、その背景を趣旨からしっかり理解をしていきましょう。
一般的に、民法がなかなか点数が取れないという方は暗記の詰め込みに走りがちという傾向があります。そのため、今の時期しっかり制度趣旨から理解をしていくんだ、丸暗記に走らないように理解をしていくということを心がけていただければと思います。
3-3-2.知識の網羅性を確保する
2つ目のポイントは、知識の網羅性を確保することです。
民法は範囲が広い分、知識の抜けが生じやすくなっていきます。
そのため、しっかり網羅性を確保していく、徐々にテキストで細部の知識をこぼさず拾っていく、このようなスタンスで勉強を進めていきましょう。
3-4.【午後の部】司法書士試験の基準点の推移

(出典:伊藤塾YouTube|【司法書士試験】2025年度 司法書士試験の基準点と出題傾向から導く効率的な過去問学習法)
次に、午後の部の基準点についてです。
令和7年度(2025年度)試験の基準点は35問中24問(105点中72点)でした。これは、一見すると標準的だったようにも思えます。しかし、先ほどお伝えしたように、没問となった第33問を全員正解にしたことが影響しています。そのため、午後の部の難易度自体はかなり難しかったと思ってよいでしょう。
では、令和8年試験の難易度はどうなるのか。一般的には、疑義があった年・難しかった年の翌年というのは難易度が下がりやすいと言われています。そのため、どちらかと言えば、問題の難しさ自体は易しくなっていく可能性が高いです(もちろん難化する可能性もあります)。
そして、今回特にお伝えしたいのが、商業登記法についてです。
今回、商業登記法が難しく感じたという方もいますが、これは疑義があった問題によるところが大きいと思います。したがって、商業登記法の「過度な」対策はしないようにしてください。
3-5.【午後の部】令和7年試験で基準点に到達した人の割合

(出典:伊藤塾YouTube|【司法書士試験】2025年度 司法書士試験の基準点と出題傾向から導く効率的な過去問学習法)
次に、午後の部の基準点到達者の推移を見ていきましょう。
法務省の「順位別員数累計表」を用いて算出したデータによれば、今回の基準点到達者の割合は21.6%という数字が出ています。昨年度の基準点到達者の割合は19.9%、つまり昨年と比べて1.7%上がっています。
午前の部と同様に、「基準点に到達する難易度」自体は少し易化したといえるでしょう。
3-6.【午後の部】基準点に届かない方は全肢検討もアリ
とはいえ、それでも午後の部の点数が安定せずに悩んでいる方も多いと思います。
では、午後の部の得点を安定させるためにはどうすればいいのか。その手段の1つとして考えられるのが「全肢検討」を取り入れることです。
※チェックポイント
全肢検討とは、「アからオ」まで全ての肢をザッと見てから、組み合わせを使って解く方法です。対して、現在の司法書士受験生の間でメジャーとなっているのは「軸足検討」です。軸足検討とは、まず解答の軸となる肢を見つけて、そこから最低限の肢だけを見て正誤判断をする方法です。
なお、当然ですが「全肢検討でないとダメ」という話ではありません。人によって相性がありますので、あくまで1つの選択肢として考えてください。
以下で、全肢検討をおすすめする理由を説明します。

(出典:伊藤塾YouTube|【司法書士試験】2025年度 司法書士試験の基準点と出題傾向から導く効率的な過去問学習法)
3-6-1.軸足検討でも、全肢検討になっているケースが多い
現在、司法書士受験生の間でメジャーなのは軸肢検討(正解を出すのに最低限必要な肢だけを検討すること)です。
しかし、軸肢検討で問題を解いても、結局不安になって全肢を検討しているという方が多いです。
たとえば、肢の「ア」を軸として判断をして、そこから「イ」と「ウ」だけを見て答えを出すとします。ところが、結局不安になって「エ」と「オ」も見てしまい、結果的に全ての選択肢を見ているケースが少なくないのです。
このとき、それぞれの肢の行き来が存在するため、時間のロスが生じています。
そのため、最初から全肢を見て、最後に組み合わせを検討する全肢検討の方が、それぞれの肢の行き来がない分、かえって早く解ける可能性があるのです。
3-6-2.全肢検討の方が、点数が安定しやすい
さらに、全肢検討の方が点数が安定しやすいという側面もあります。
たとえば、本試験の後、振り返りとして時間無制限で問題を解くと、本番よりも点数が取れたという方は多いと思います。これは触れる肢の幅が広がっているからという可能性が高いのです。
つまり、本試験時では肢のア・イだけに限定して解いていたが、振り返りのときは時間無制限で解いたため、肢のエ・オにも触れていた。そして、肢のエ・オにも触れた結果、解ける問題が増えて、点数が上がっていったということです。
一般的に、検討する肢の数が多くなるほど、他の肢における判断ミスに気づきやすく、そしてそれを修正しやすくなっていきます。結果として、得点が安定していくと考えられるのです。
経験上、「軸足検討」から「全肢検討」に転向をしたとき、およそ2問程度点数が上昇したというケースが多いです。全科目で全肢検討をするのが難しい場合は、商業登記法など一部の科目だけ部分的に実施するのも有効でしょう。
ただ、先ほどお伝えしたように人によって相性があります。そのため、まずは答練・模試などで試してみて、もし自分に合うようであれば積極的に取り入れていただければと思います。
4.令和7年度(2025年度)年基準点発表から令和8年度(2026年度)司法書士試験までの学習のポイント
次に、基準点の発表後、令和8年度(2026年度)司法書士試験に向けた学習のポイントを紹介します。
◉基準点発表から令和8年度(2026年度)試験までの学習ポイント
・択一対策もしっかり行う
・記述式対策を早期にスタートする
・記述式対策は基本から段階的に進める
それぞれ詳しく説明します。
4-1.択一対策もしっかり行う
まず1つ目のポイントは、択一対策もしっかり行っていくことです。
基準点発表後、当面は「択一式7:記述式3」あるいは「択一式8:記述式2」程度を目安にして進めていきましょう。
択一式の比率が高めなのは、基準点をクリアした上で、上乗せ点でも一定点数の確保が必要になるからです。記述式の配点が高くなったとはいえ、記述式だけで上乗せ点を確保するのは難しいです。筆記試験に合格するためには、択一式からも記述式からも、両方から上乗せ点を取っていく必要があります。
そして、徐々に実力がついてきたら「択一式6:記述式4」程度に近づけていきましょう。
マイナー科目についても、早めに触れておくことが必要です。たとえば、スキマ時間の学習をマイナー科目に当てるなどして、早期に対策をスタートさせましょう。
※こちらの記事も読まれています。
4-2.記述式対策は早期にスタートする
2つ目のポイントは、早期に記述式対策を開始することです。
目安として、9月頃には記述式の学習を再開させましょう。そして、単発で行うではなく、日々のルーティンとして取り入れてください。つまり、日々の学習において、先ほどの学習割合(択一7:記述3)に落とし込んで記述式の学習を行っていくというイメージです。
1日単位でもよいですし、1週間の中で7対3という割合でも構いません。日々の勉強の中に、記述式対策をルーティンとして取り入れてください。
4-3.記述式対策は基本から段階的に進める
3つ目のポイントは、記述式対策を基本から段階的に進めることです。
いきなり本試験レベルの問題を解くのではなく、10月頃までは雛形の訓練や、基本的な問題に重点的に取り組んでください。そして基本を固めつつ、徐々に問題のレベルを上げていきましょう。
なお、記述式においても過去問への取り組みは必須です。本試験でも、「過去問の焼き直し+α」の問題となる傾向が顕著になっているため、年内に一通りは取り組んでおきましょう。
※こちらの記事も読まれています。
5.【最後に】令和7年度(2025年度)司法書士試験で基準点に届かなかった方へ伝えたいこと
令和7年度(2025年度)の司法書士試験で基準点に届かなかった方へ、最後に伝えたいことがあります。
それは、「司法書士試験は諦めなければ必ず合格できる」ということです。
伊藤塾で学ばれた方の中には、一発合格した方もいます。しかし、2回、3回、4回と挑戦して、合格を掴みとった方も、それ以上にたくさんいます。そして、皆さん現在は司法書士として実務の最前線でご活躍されています。
合格者に共通しているのは、どれだけ苦しくても最後まで諦めなかったこと、これに尽きます。大丈夫です。諦めさえしなければ、司法書士試験は必ず合格できる試験です。
少しでも、「司法書士になって人生を変えたい」という気持ちが残っているのなら、来年試験に向けて、もう一度一歩を踏み出してみてください。伊藤塾は、あなたの挑戦を全力で応援しています。
6.令和7年度(2025年度)司法書士試験の択一式基準点のまとめ
本記事では、令和7年度(2025年度)司法書士試験の択一式基準点の発表に伴い、その詳細な分析と令和8年度(2026年度)に向けた学習対策について伊藤塾の髙橋講師による解説を掲載しました。
以下にポイントをまとめます。
◉令和7年度(2025年度)司法書士試験の択一式基準点は、8月12日に発表されました。
・午前の部は3年連続で78点(全35問中26問)でした。
・午後の部は昨年と同じ72点(全35問中24問)でした。しかし、第33問が没問となり、受験者全員に3点が加点されたため、基準点が押し上げられており、実質的には昨年より難化したと言えます。
・記述式問題および筆記試験の合格点は、10月2日に発表される予定です。
◉午前の部に関する分析と対策
・基準点到達者の割合は32.02%で、基準点到達難易度は「易化」しました。
・来年については、基準点が25問レベルへの難化、または27問レベルへの易化の両方の可能性があります。特に会社法が難化する可能性があり、基礎を固めた上で周辺の細かな知識まで押さえる必要があります。
・午前の部の得点安定のカギは民法にあり、18問近く取れるようになると基準点割れのリスクを回避しやすくなります。
・民法を強化するためには、制度趣旨からの理解と知識の網羅性の確保が重要です。
◉午後の部に関する分析と対策
・基準点到達者の割合は21.6%で、基準点到達難易度は「易化」しました。
・午後の部の難易度自体は「かなり難しかった」と評価されていますが、疑義があった年の翌年は難易度が下がりやすい傾向があるため、来年は易化する可能性が高いでしょう。
・商業登記法は難しく感じられたかもしれませんが、「過度な」対策はしないように注意が必要です。
・ 得点安定化の手段として、「全肢検討」を取り入れることも有効です。ただし、人による相性があるため、答練や模試で試してみるとよいでしょう。
◉令和8年度(2026年度)試験に向けた学習のポイント
・択一対策もしっかりと行うことが重要で、当面は「択一式7:記述式3」または「択一式8:記述式2」程度の割合で学習を進め、択一と記述の両方から上乗せ点を確保する必要があります。マイナー科目も早期に対策を開始しましょう。
・記述式対策は早期に開始し、9月頃を目安に日々のルーティンとして取り入れましょう。10月頃までは雛形の訓練や基本的な問題に重点的に取り組み、年内に過去問を一通りこなしておくことが推奨されます。
◉司法書士試験は、諦めなければ必ず合格できる試験です。多くの合格者が、苦しい状況でも最後まで諦めずに挑戦を続けた結果、合格を掴み取っています。
以上です。
司法書士試験の合格のためには、適切な戦略と着実な学習が必要不可欠です。
伊藤塾では、長年の実績と徹底した試験分析に基づいたカリキュラムで、多くの受講生を合格へと導いてきました。本記事で解説された詳細な基準点分析や学習対策は、伊藤塾の講座でさらに深く掘り下げられ、皆さんの疑問を解消し、効率的な学習をサポートします。
「司法書士になって人生を変えたい」という強い思いがあるのなら、ぜひ伊藤塾で次のステップを踏み出してください。司法書士試験を知り尽くした専門講師陣が、あなたの挑戦を全力で応援し、合格への道を共に歩みます。 ぜひ一度、伊藤塾の講座をご検討ください。