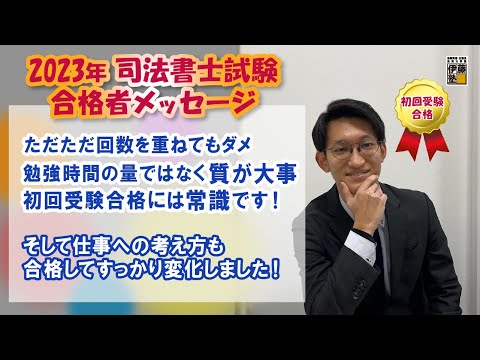司法書士試験は難しすぎる?一発合格者が語る合格の秘訣と勉強法
勉強法
2026年02月17日


「司法書士試験は難しすぎる」
「こんなに勉強したのに、なぜ合格できないの?」
「興味はあるけど、自分には無理だと思う」
こんな悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?
確かに、司法書士試験は簡単ではありません。
5%という合格率を聞けば、挑戦をためらったり、途中で挫折しそうになる人もいるでしょう。
しかし一方で、真剣に勉強して受験している人は、半数に満たないとも言われています。本気で勉強するだけで、上位50%には入ることができるのです。
さらに、合格者の多くは社会人です。
難しいと言われている司法書士試験ですが、仕事や家事・育児と両立しながら、見事に合格を勝ち取っています。
司法書士試験は、正しい勉強さえできれば、誰でも合格を目指せる試験です。
本記事では、次の点を取り上げました。
【この記事を読んで分かること】
・司法書士試験が「難しすぎる」は本当なのか
・難しすぎる、合格できないと感じる理由
・合格するための科目別の勉強法
・一発合格者が語る「初回合格の秘訣」
司法書士試験を目指している人は、是非ご一読ください。
【目次】
1. 司法書士試験は難しすぎる?実質的な合格率は?
司法書士試験の合格率は、ここ数年「5%程度」で推移しています。
合格率だけを見ると、なかなか厳しい試験だと感じる人も多いでしょう。
しかし、実際の合格率はそこまで低くありません。なぜなら、受験者全員が本気で勉強しているわけではないからです。
中には、次のような人も数多く含まれています。
・市販の参考書で少しだけ勉強した人
・試験範囲の勉強が全て終わっていない人
・お試し受験の人や記念受験の人 など
真剣に勉強している人は、出願者のおおよそ半分程度しかいないとも言われています。
つまり、実質的な合格率は10%を超えてくる可能性もあるのです。
少なくとも、きちんと勉強しているだけで、全体の上位50%には入ると考えて良いでしょう。
1-1. 司法書士試験の合格率は上昇している
さらに言うと、司法書士試験の合格率は、ここ数年上昇しています。
次のデータをご覧ください。
| 受験者数 | 最終合格者数 | 合格率 | |
| 令和7年 | 14,418人 | 751人 | 5.21% |
| 令和6年 | 13,960人 | 737人 | 5.28% |
| 令和5年 | 13,372人 | 695人 | 5.20% |
| 令和4年 | 12,727人 | 660人 | 5.19% |
| 平成28年 | 16,725人 | 660人 | 3.95% |
| 平成27年 | 16,725人 | 707人 | 4.23% |
| 平成26年 | 20,130人 | 759人 | 3.77% |
参照:司法書士試験丨法務省
平成の時代、司法書士試験の合格率は、3%〜4%程度で推移していました。
しかし、最近では5%程度にまで上がっています。
これは、平成の時代に比べ受験者数が減少している一方で、最終合格者の数が大きく変わっていないからです。
おそらく司法書士の数が足りていないことが大きな理由でしょう。
社会の変化に伴い、司法書士への需要が増加しているため、司法書士の数を増やそうとしている可能性が高いのです。
いずれにせよ、以前に比べて合格しやすくなっていることは間違いありません。
司法書士を目指す人にとって、今は絶好のチャンスと言えるでしょう。
※司法書士試験の合格率は、次の記事で詳しく解説しています。
2. 司法書士試験の難しさはどの程度?
司法書士試験の難しさは、様々な角度から考えることが必要です。
「合格点や基準点」「必要な勉強時間」「合格者のデータ」などを見ていくと、司法書士試験の本当の難しさが見えてくるからです。
それぞれの観点から、司法書士試験の難しさを見ていきましょう。
2-1. 合格点・基準点
2024年度(令和6年度)以降に行なわれる司法書士試験では、記述式問題の得点が「2問で70点満点」から「2問で140点満点」に変更され、2025年度は、総合点で350点満点中255.0点以上が合格点でした。
得点率に換算すると、およそ73%が合格ラインです。
ただし、単に合格点をクリアすればよいというわけではありません。
司法書士試験では、択一式(午前)・択一式(午後)・記述式の各科目について、基準点が設けられています。
たとえ合計点が合格点を上回っていても、1つの科目でも基準点を下回ると、不合格となってしまうのです。
【2025年度司法書士試験の合格点・基準点】
| 試験区分 | 満点 | 合格点 基準点 | 合格点率 基準点率 |
| 総合点 | 350点 | 255点 | 72.9% |
| 午前の部(多肢択一) | 105点 | 78点 | 74.3% |
| 午後の部(多肢択一) | 105点 | 72点 | 68.6% |
| 記述式問題 | 140点 | 70点 | 50.0% |
司法書士試験の合格のためには、各科目のバランスを考慮した戦略的な学習計画が必要です。
※司法書士試験の合格点や基準点については、こちらの記事で詳しく解説しています。
2-2. 必要な勉強時間
司法書士試験の合格に要する勉強時間は、一般的に3,000時間程度が目安だと言われています。
ただし、これはあくまで平均値に過ぎません。
実際には、個人差が大きく、人によって大きな開きがあります。
例えば、正しい学習方法を最初から実践できれば、法律の知識がゼロからスタートしても、平均よりはるかに短期間で合格する人もいます。
逆に、勉強の方向性を見誤ってしまうと、何年勉強を続けても合格できないケースもあります。
結局のところ、司法書士試験の合格に必要なのは、勉強の「量」ではなく「質」です。
勉強時間はあくまで参考程度に捉え、質の高い学習を心がける必要があるでしょう。
※司法書士試験の勉強時間については、こちらの記事で詳しく解説しています。
2-3. 合格者のデータ(年齢や性別)
司法書士試験の合格者には、どのような人が多いのでしょうか?
合格者の年齢や性別を確認していくと、いくつかの特徴が見えてきます。
【2025年度 司法書士試験の合格者】
| 平均年齢 | 42.05歳 |
| 最低年齢 | 17歳 |
| 最高年齢 | 74歳 |
| 男性の割合 | 70.3% |
| 女性の割合 | 29.7% |
まず年齢についてですが、合格者の平均年齢は42.05歳となっています。
平均年齢が40代であることから、多くの人が社会人になってから司法書士を目指していると考えられます。
ただし、平均はあくまで平均です。
最年少は「17歳」、最高齢は「74歳」と、幅広い年齢層の人が合格を勝ち取っています。
次に、男女比を見てみましょう。
合格者のうち、男性は70.3%、女性は29.7%という内訳になっています。
現時点では男性の合格者の方が多いようですが、女性の合格者も着実に増えてきています。
職業に関するデータは公表されていませんが、年齢のデータから推測するに、多くの人が仕事をしながら勉強に励んでいると思われます。
仕事や家事・育児と勉強を両立することは、とても難しいと感じる人も多いでしょう。
しかし、合格者のデータからも分かるとおり、様々なバックグラウンドを持つ人が実際に合格しています。
年齢も性別も、合格への障壁ではありません。
司法書士になりたいという強い想いをもって学習に取り組めば、誰にでも合格するチャンスがあると言えるでしょう。
※女性司法書士については、こちらの記事で詳しく解説しています。
3. なぜ合格できない?司法書士試験が難しすぎると感じる理由
司法書士試験に合格できない理由は、人それぞれ異なります。
しかし、多くの人が「司法書士試験は難しすぎる」と感じる理由には、いくつか共通点があります。
ここでは、主な理由を5つ挙げて、それぞれ詳しく解説します。
・試験科目が多く、計画的な勉強が必要だから
・馴染みのない法律科目が多く、とっつきにくいから
・勉強の時間を確保できないから
・モチベーションを保つことが難しいから
・記述式の勉強が大変だから
順番に見ていきましょう。
3-1. 試験科目が多く、計画的な勉強が必要だから
1つ目の理由は、試験科目が非常に多いことです。
司法書士試験では、択一式と記述式を合わせて全11科目が出題されます。
これは法律系の国家資格の中でも、群を抜いて多い科目数です。
参考までに、行政書士試験の科目数は7科目、最難関と呼ばれる司法試験ですら8科目しかありません。
このように多岐にわたる科目全てを網羅的に学習しようとすると、膨大な時間が必要です。
そのため、限られた時間の中で効率的に合格するには、重要なポイントを絞り込んだ計画的な勉強が不可欠です。
逆に言えば、勉強の進め方を間違えると、いつまでたっても学習が終わらず、難しすぎて合格できないと感じる要因になってしまいます。
3-2. 馴染みのない法律科目が多く、とっつきにくいから
2つ目の理由は、馴染みのない法律科目が多いことです。
司法書士試験では、「不動産登記法」や「商業登記法」など、他の試験ではあまり目にしない法律が出題されます。
民法などと異なり、日常生活で耳にする機会が少ないため、とっつきにくいと感じる人も多いでしょう。
しかし一方で、これらの科目の配点は大きく、合格後も頻繁に活用します。
つまり、試験で大切なのはもちろんのこと、司法書士としての実務を見据えても、これらの科目を得意にしておくことが望ましいのです。
試験のためだけではなく、就職後に向けたトレーニングだと考えて取り組みましょう。
具体的な学習ポイントについては、後ほど詳しく解説します。
3-3. 勉強の時間を確保できないから
3つ目の理由は、勉強時間を確保できないからです。
勉強時間の確保に悩み、司法書士試験が難しすぎると感じている人は多いでしょう。
しかし、実はこれは本質的な問題ではありません。
なぜなら、前述したように、司法書士試験の合格に必要なのは、勉強の「量」ではなく「質」だからです。
実際、多くの合格者は仕事や家事・育児をこなしながら、限られた時間を有効活用して、見事に合格を勝ち取っています。
「十分な勉強時間が確保できていた」と語る人はほとんどいません。
「勉強時間が取れない」と諦めるのではなく、限られた時間を最大限に活用する方法を考えましょう。
司法書士試験は、正しい勉強さえできれば、「働きながら」でも「家事・育児をこなしながら」でも十分に合格できる試験です。
3-4. モチベーションを保つことが難しいから
4つ目の理由は、モチベーションを保つことが難しいからです。
モチベーション管理は、「勉強時間の確保」と並び、受験生の多くが苦しむ要因です。
1年以上の長期間にわたって、モチベーションを保ち続けることは簡単ではありません。途中で、諦めたくなったり、挫折しそうになったりする瞬間もあるでしょう。
そんな時におすすめなのが、合格後の自分の姿をイメージすることです。
原点に立ち返り、「なぜ自分が司法書士を目指そうと思ったのか」を振り返って、合格した自分をイメージしてみましょう。
既に司法書士として活躍している先輩の話を聞くのも効果的です。
例えば、伊藤塾でも「合格後を考える」という理念のもと、様々な取り組みを行っています。
また、受験指導校のスクーリングやカウンセリングに参加するのもオススメの対策です。
人と会ったり、講師や仲間に悩みを打ち明けることで、モチベーションが上がる人も多いです。
3-5. 記述式の勉強が大変だから
5つ目の理由は、記述式の勉強が大変だからです。
記述式試験への苦手意識から、司法書士試験の難易度を高く感じている人は多いでしょう。
しかし、記述式が解けなければ、司法書士試験の合格は厳しいです。
特に2024年度からは記述式の配点が大幅に引き上げられ、140点満点(以前の2倍)となりました。これまで以上に、記述式の得点が合否を左右することとなったのです。
記述式対策のポイントは、可能な限り「早期」から「正しい」学習を始めることです。
基本的な内容を一通り学習したら、すぐに記述式対策をスタートしましょう。
・後回しにするのではなく、各学習ステージでできることを着実に積み重ねていく
・やみくもに問題を解くのではなく、思考のプロセスを重視して勉強する など
上記のようなポイントに注意して勉強を進めていけば、確実に力をつけて、苦手意識を克服できるはずです。
4. 難しい司法書士試験に合格する方法は?|科目別の学習法
司法書士試験に合格するためには、ポイントを絞った学習が欠かせません。
試験科目は全部で11科目ありますが、特に重要なのは「民法」「不動産登記法」「商法」「商業登記法」の4科目です。
これらの科目は、いずれも配点が高く、4科目だけで「全体の82%」を占めています。
そこで、メインとなる4科目の特徴とそれぞれの学習方法を解説します。
4-1. 民法
民法は択一式試験の中で最も出題数が多く、20問が出題されます。
特に午前の部では、満点の半分以上の得点を占めており、民法の得点力が合否を左右するといっても過言ではありません。
民法の特徴は、解きやすい問題が多いことです。
一見すると難しそうに感じるかもしれませんが、実のところ、中心となるのは基本的な問題です。過去問の焼き直しが出題されるケースも珍しくありません。
したがって、民法では基礎知識を確実に身につけることが大切です。
過去問を繰り返し解き、記憶に定着させましょう。
その際、単に○×で終わらせるのではなく、解答の根拠となる条文や判例もしっかりと理解・記憶することが必要です。
さらに、周辺の条文にも目を通すことで、知識の幅を広げることができます。
他の受験生に差をつけられないためにも、基本的な問題を、確実に得点源にすることが求められます。
4-2. 不動産登記法
不動産登記法は、基本的な問題だけでなく、難易度の高い問題も出題される科目です。
これらの問題は、合否を分ける問題にもなり得ます。
正答するには、基本知識だけではなく、発展的な知識も身につけることが必要です。
最近の先例・判例など、過去問だけでは対応しきれない問題も出題されるため、過去問演習だけで得点を伸ばすことは難しいでしょう。
そこでおすすめなのが、受験指導校の答練を活用することです。
答練では、まだ出題されたことのない細かな知識や、最新の先例・判例もカバーすることができます。これらに取り組むことで、不動産登記法の得点力を飛躍的に向上させることができるでしょう。
不動産登記法は、合格後も実務で頻繁に使う法律です。
試験対策だけでなく、就職後に向けたトレーニングだと考えて、徹底的に演習を重ねましょう。
4-3. 商法・商業登記法
商法と商業登記法は、一体的に学習することが求められる科目です。
なぜなら、両者は「実体法」と「手続法」の関係にあるからです。
「商法」がビジネスの基本ルールを定めているのに対し、商業登記法はそのルールをどのように実現するかを規定しています。
つまり、両者は表裏一体の関係にあるのです。商法と商業登記法のリンクを常に意識することで、効率的に学習を進めていくことができます。
①. 商法
商法の特徴は、問題の難易度が年によって大きく変動することです。
解きやすい問題ばかり出題される年もあれば、正答率の低い難問が半数以上を占める年もあります。
したがって、基本的には「他の受験生に差をつけられない」ことを意識すべきでしょう。
必要以上に時間をかけるのではなく、解きやすい問題を確実に得点するというスタンスで取り組みましょう。
②. 商業登記法
商業登記法は、全般的に難易度が高い科目です。
不動産登記法と似ており、応用レベルの知識も身につけなければ得点力を上げることはできません。
そのため、商業登記法の対策でも、受験指導校の答練を活用することが効果的です。
答練を通じて、細かな知識や最新の判例・先例もしっかりと押さえておきましょう。
5. 勉強の量ではなく質!合格者が語る初回合格の秘訣
司法書士試験の勉強において、多くの人が悩むのが「勉強量」の問題です。
働きながら、家事や育児をこなしながら、十分な勉強量を確保することは簡単ではないでしょう。しかし、合格者の多くは口をそろえて「勉強の量より質が大事」と言います。
つまり、司法書士試験の合格のカギを握るのは、勉強時間の長さではなく、勉強内容の濃さなのです。
繰り返しになりますが、司法書士試験で求められているのは、がむしゃらに勉強時間を積み重ねることではありません。「回数をこなすこと」や「時間をかけること」よりも、学習の質を高め、継続して学習することが何より大切です。
ここでは「勉強の質」にこだわって勉強した結果、見事に初回合格を果たした先輩の体験談をご紹介します。
ぜひ動画をご覧いただき、効果的な勉強法について考えてみてください。
「2023年司法書士試験合格 ただただ回数を重ねてもダメダメ、勉強時間の量ではなく質が大事、初回受験合格には常識です!そして仕事への考え方も合格してすっかり変化しました!」
6.【Q&A】司法書士試験についてよくある質問
6-1. 合格率を見ると不安になりますが、誰でも合格できますか?
司法書士試験の合格率は、確かに低く感じるかもしれません。
しかし、実際のところ、受験者の中で本気で勉強している人は半分程度だと言われています。
しっかりと勉強に取り組むだけで、上位50%に入ることができるのです。
司法書士試験は、諦めずに勉強を続ければ、誰でも合格を目指せる試験です。
6-2. 仕事や家事、育児と両立して合格できますか?
はい。十分に両立可能です。
実際、2025年度司法書士試験の合格者の平均年齢は「42.05歳」となっており、大半は社会人です。仕事や家事・育児と両立している人も珍しくありません。
6-3. どの程度の期間を勉強すれば、合格できますか?
受験指導校を利用する場合、一般的には、1年〜2年程度が目安です。
ただし、個人の学習環境によっても異なります。
6-4. 独学でも司法書士試験に合格できますか?
独学でも合格できる可能性はあります。
しかし、司法書士試験に合格するには、「勉強の質」を高めることが最も大切です。
限られた時間で司法書士試験に合格するのであれば、やはり受験指導校を活用することがおすすめです。
7. 司法書士試験は難しい?合格の秘訣と勉強法まとめQ&A
-
司法書士試験は本当に難しいですか?
-
司法書士試験は簡単ではありませんが、本気で勉強すれば合格は十分可能です。合格率は5%程度で推移していますが、真剣に勉強している人は受験者の半分程度と言われており、きちんと勉強すれば上位50%には入れます。
-
司法書士試験の実質的な合格率はどのくらいですか?
-
受験者全員が本気で勉強しているわけではないため、市販の参考書で少しだけ勉強した人やお試し受験の人も多く含まれます。このため、実質的な合格率は10%を超える可能性もあります。
-
司法書士試験の合格率は上昇傾向にありますか?
-
はい、ここ数年司法書士試験の合格率は上昇しています。平成時代は3〜4%程度でしたが、最近では5%程度に上がっており、受験者数が減少している一方で最終合格者数が大きく変わっていないため、以前より合格しやすくなっています。
-
司法書士試験の合格点や基準点はどのように設定されていますか?
-
2025年度の司法書士試験では、総合点が350点満点中255点以上が合格点でした。総合点だけでなく、択一式(午前・午後)と記述式の各科目で設けられた基準点を全てクリアする必要があります。
-
司法書士試験の合格に必要な勉強時間はどれくらいですか?
-
一般的に3,000時間程度が目安とされますが、これは平均値であり個人差が大きいです。重要なのは勉強の「量」ではなく「質」であり、正しい学習方法を実践できれば、短期間での合格も可能です。
-
社会人や家事・育児をしながらでも司法書士試験に合格できますか?
-
はい、十分に両立可能です。多くの合格者は社会人であり、仕事や家事・育児と両立しながら合格を勝ち取っています。2025年度の合格者の平均年齢は42.05歳です。
-
司法書士試験の主要な科目と、特に重要な科目は何ですか?
-
司法書士試験は択一式と記述式を合わせて全11科目が出題されます。特に重要なのは「民法」「不動産登記法」「商法」「商業登記法」の4科目で、これらで試験全体の82%を占めています。
-
司法書士試験の勉強において、勉強時間と勉強の質、どちらが重要ですか?
-
司法書士試験の合格のカギを握るのは、勉強時間の長さではなく、勉強内容の濃さ(質)です。限られた時間の中で効率的に合格するには、重要なポイントを絞り込んだ計画的で質の高い勉強が不可欠です。
-
司法書士試験の記述式対策で注意すべきことは何ですか?
-
記述式は2024年度から配点が大幅に引き上げられ、合否を大きく左右します。対策のポイントは、可能な限り「早期」から「正しい」学習を始めることです。やみくもに問題を解くのではなく、思考のプロセスを重視して勉強しましょう。
-
司法書士試験は独学でも合格を目指せますか?
-
独学でも合格できる可能性はあります。しかし、司法書士試験に合格するには「勉強の質」を高めることが最も重要であり、限られた時間で効率的に合格を目指すのであれば、受験指導校の活用が推奨されます。
合格者の話からも分かるとおり、合格に必要なのは、勉強の「量」ではなく「質」です。
質の高い勉強を継続できれば、司法書士試験は決して難しすぎる試験ではありません。
働きながらでも、家事や育児をこなしながらでも、誰でも合格を目指せる試験だと言えるでしょう。
司法書士試験に合格したい方は、ぜひ法律資格専門の指導校である伊藤塾をご活用ください。
伊藤塾の司法書士試験対策講座は、合格者の半数近くが利用しているという確かな実績を持っています。
ぜひ新たな一歩を踏み出してみてください。
伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートします。