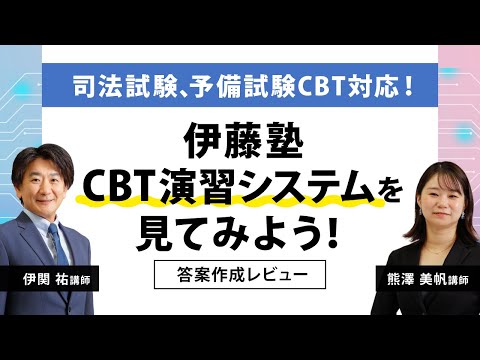2026年最新!司法試験・予備試験CBT方式とは?概要・対策を徹底解説
司法試験
2026年02月06日


【2026年1月23日更新】令和8年(2026年)実施の司法試験・予備試験より、パソコン受験(CBT方式)が導入されます。法務省より試験用法文の紙媒体配布が正式決定、入力可能文字数は1頁23行×30文字と発表されました。2026年2月10日・11日には全国でプレテストも実施されます。
司法試験には、マークシート(短答式試験)と記述式(論文式試験)があり、従来より手書き方式で試験が行われてきました。
しかし、2023年(令和5年)6月9日、法務省は「デジタル社会の実現に向けた重点計画」の中で、司法試験のデジタル化を進めるために、パソコン受験(CBT方式)を実施することを公表しました。
近年、様々な資格試験において、CBT(Computer Based Testing)やIBT(Internet Based Testing)と呼ばれるパソコンを使用した受験を導入する例が増えてきていますが、司法試験でも、ようやくCBT方式での受験が実現することとなりました。
この記事では、司法試験におけるパソコン受験(CBT方式)はいつから行なわれるのか、具体的にはどのような点が変更になるのか概略について説明した上で、注意点や対策方法について詳しく解説していきます。
新たに公示された内容なども順次追記してまいりますので、ぜひ、この記事を参考にしていただき、パソコン受験(CBT方式)についての不安を払拭していただければ幸いです。
2026年以降司法試験・予備試験ではパソコン受験が必須
そこで伊藤塾ではCBTシステムをリリースいたしました。
>>> いますぐCBTシステムをご確認下さい <<<
【目次】
1. 司法試験におけるパソコン受験(CBT方式)とは?
司法試験におけるパソコン受験(CBT方式)とは、法務省が2023年(令和5年)6月9日に公表した「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に明記されている具体的なデジタル化の施策の一つで、司法試験及び予備試験において、パソコンを利用して答案を作成する方式のことを指します。
参照:デジタル社会の実現に向けた重点計画|デジタル庁
CBT方式とは、Computer Based Testingのことで、コンピュータを利用して実施する試験方式のことです。
パソコン受験と言っても、IBTのように自宅にいながらオンラインで受験できるようになるわけではなく、不正防止のため、受験会場に用意されたインターネットに接続していないパソコンを用いて答案を作成することが想定されています。
法務省によると、司法試験においてパソコン受験(CBT方式)を導入する目的は次の通りです。
【司法試験におけるパソコン受験(CBT方式)導入の目的】
・ 受験者の利便性を向上させる
→手書きによる負担を軽減する
・ 試験関係者の負担を軽減する
→判別できない文字を無くし、採点者の負担を軽減させる
司法試験では、従来より手書き方式で試験が行われてきましたが、実務の現場において、手書きの書面を作成して提出する場面はほとんどありません。裁判においても、相手方とやり取りする際も、基本的にはパソコンで作成した書面を利用して手続きを進めていくことになります。
パソコン受験(CBT方式)の導入は、こうした実務の世界でのデジタル化の流れを汲んだ形での試験方式に変更されることを意味します。つまり、司法試験では、実務家として必要となるパソコンでの文書作成能力が求められることにもなります。
また、CBT方式による司法試験は、すでにニューヨーク州などで導入されており、諸外国の事例を参考にしながら、日本での導入へ検討が進められています。以下、令和7年4月までに法務省より公示された「司法試験及び司法試験予備試験のデジタル化について」を踏まえてご案内いたします。
2. 司法試験におけるパソコン受験(CBT方式)はいつから?
| 試験 | CBT試験導入年度 |
| 司法試験(短答式試験) | 2026年(令和8年) |
| 司法試験(論文式試験) | 2026年 (令和8年) |
| 予備試験(短答式試験) | 未定 |
| 予備試験(論文式試験) | 2026年(令和8年) |
司法試験については、令和8年試験から短答式試験及び論文式試験のいずれにもCBT試験を導入することを目指しています。
司法試験予備試験については、令和8年試験においては、論文式試験のみを対象としてCBT試験を導入することを目指しています。
なお、司法試験のデジタル化に向けて併せて実施される「出願手続、受験票・成績通知書の交付等のオンライン化」については2025年(令和7年度)から段階的※に、「受験手数料の納付をキャッシュレス化」については2026年(令和8年度)から開始される予定です。
※2025年(令和7年度)は従来通り紙形式での出願手続きが行われています。
出典:司法試験及び司法試験予備試験のデジタル化について|法務省
出典:司法試験等のCBT(Computer Based Testing)方式の導入に関するQ&A
3. CBT試験の実施方法について
CBT試験では、司法試験委員会(法務省)が用意した「CBTテストセンター」のパソコンを使用して、集合形式での試験実施が予定されています。
なお、短答式試験においては、解答の修正も、問題をスキップして後から戻ることも可能とされる予定です。
CBT システムに搭載する司法試験用法文の表示形式については、 電子政府の総合窓口(e-Gov)の法令検索のような、横書きでの表示を予定してい ます。
なお、CBT試験を導入する司法試験(短答式試験、論文式試験)、司法試験予備試験(論文式試験)のそれぞれにおいて、答案構成用紙(メモ用紙)は配布する(持ち帰り可)予定としています。
出典:司法試験等のCBT(Computer Based Testing)方式の導入に関するQ&A
※試験用法文・問題文の配布について
問題文については紙媒体での配布は行われず、パソコン画面上で閲覧する形式となります。
試験用法文については、当初は画面上での閲覧のみが検討されていましたが、令和8年1月23日の発表で紙媒体での配布が正式決定しました。令和8年の司法試験および予備試験では、画面上で閲覧できる機能に加えて、紙媒体の法文が配布されます。
なお、令和9年以降の試験における法文配布については引き続き検討中とされています。
| 配布物 | 令和8年試験での対応 |
| 問題文 | 紙配布なし (画面上で閲覧) |
| 試験用法文 | 紙媒体で配布 +画面閲覧可 |
| 答案構成用紙 (メモ用紙) | 紙配布あり (持ち帰り可能) |
4. 使用するパソコンと文字入力について
CBTテストセンターに用意されているデスクトップ型パソコン等を使用する予定です。
用意されるパソコンは、以下の基準を満たす予定となっています。
・OS:Windows 11 Pro
・CPU:1.5 GHz 以上のマルチコアプロセッサ
・メモリ:8GB 以上
・画面解像度:1920×1080 ピクセル以上
・モニターサイズ:23 インチ(モニターの対角線の長さが約 58.4cm)以上
・ネットワークインターフェース:IEEE802.11ac 対応
・キーボード:USB接続、JIS配列(日本語配列)、テンキーあり、静音加工あり
・マウス:USB接続、光学式、スクロールホイールあり
CBT試験で使用する文字入力ソフト、また、使用できる機能については以下が予定されています。
・日本語 Microsoft-IME を使用
・Microsoft-IMEの学習機能は使用可能、予測文字変換・手書き入力等の機能は使用不可予定
・コピー、貼り付け、検索等のドキュメント編集に係る一部機能は使用できる
・インデントの設定や、禁則処理の機能は使用できない予定
・一部入力できる文字に制限があり、具体的に半角文字は入力できず、半角文字を入力した場合、自動的に全角に変換されて入力されます。また、一部(⑴、①、ⅰ等)を除き、記号等の入力もできない
※使用可能なキーボードショートカット一覧
当初はショートカットキーは使用不可の予定でしたが、段階的に使用可能なショートカットが追加されています。
Ctrl + A 全選択
Ctrl + Z 元に戻す
Ctrl + C コピー
Ctrl + Shift + Z やり直す
Ctrl + V 貼付け
Ctrl + Home 文頭に移動
Ctrl + X 切取り
Ctrl + End 文末に移動
Ctrl + Y やり直す
→上記以外のWindowsショートカットキー(Ctrl+Sなど)は使用できません。
出典:司法試験等のCBT(Computer Based Testing)方式の導入に関するQ&A
5. CBTシステム体験版の利用方法
2025年度(令和7年度)4月25日よりCBT体験システムの体験版が利用可能になりました。
下記よりダウンロードして実際に練習をすることをおすすめします。
→ 司法試験及び司法試験予備試験のデジタル化について(法務省Webページ)
<推奨環境>
OS:Windows11
画面解像度:1920×1080
ディスプレイのレイアウトサイズ:100%
<使用方法・注意事項>
インストールなどのマニュアルの詳細ダウンロードはこちら
5-1. 短答式試験の体験版の操作マニュアル
※画面の詳細はこちらを参照して下さい。
→ 操作マニュアル(短答式)
5-2. 論文式試験の体験版の操作マニュアル
※画面の詳細はこちらをを参照して下さい。
→ 操作マニュアル(論文式)
5-3. 体験版の変更点
令和8年1月に公開された最新の体験版では、以下の変更が行われています。
① 令和7年司法試験予備試験論文式試験の問題を追加
最新の予備試験問題が体験版に格納され、より実践的な練習が可能になりました。
② ペンツールの仕様変更
問題文に連続して書き込みをした場合に、一連の書き込みをグループ化しない仕様に変更されました。これにより、書き込みの削除や修正がより柔軟に行えるようになっています。
③ 全画面表示の解除機能(体験版のみ)
体験版では「F11」キー(または「Fn + F11」キー)を押すことで全画面表示を解除し、他のアプリケーションと並べて表示することが可能です。
6. 入力可能文字数と答案作成の注意点
令和7年11月26日の司法試験(予備試験)考査委員会議において、CBT試験における答案の入力可能文字数が正式に決定されました。従来の手書き試験と同様に、答案には頁数(文字数)の制限があります。
6-1. 入力可能文字数(ページ数・行数・文字数)
| 試験 | 科目 | 頁数 | 1頁あたり | 最大文字数 |
| 司法試験 | 必須科目 (1問につき) | 8頁 | 23行×30文字 | 5,520文字 |
| 司法試験 | 選択科目 (1問につき) | 4頁 | 23行×30文字 | 2,760文字 |
| 予備試験 | 法律基本科目・ 選択科目(各科目) | 4頁 | 23行×30文字 | 2,760文字 |
| 予備試験 | 法律実務基礎科目 (民事・刑事それぞれ) | 4頁 | 23行×30文字 | 2,760文字 |
※1頁は23行、1行あたり最大30文字の入力が可能です。
6-2. 答案入力箇所の取り違えは零点になる
司法試験の選択科目や予備試験論文式試験において、答案入力箇所を取り違えた場合は零点となることが決定しています。
例えば、選択科目第1問の答案入力箇所に第2問の答案を入力してしまった場合、その答案は零点として扱われます。
| 状況 | 対処法 |
| 試験時間中に 気付いた場合 | コピー・貼付け機能等を使用して、受験者自身で 正しい答案入力箇所に転記する |
| 文字数制限で直接 転記できない場合 | 「メモ画面」への転記を介して、各答案入力箇所 の内容を入れ替える |
| 試験時間終了後 | 取り違えの申請は一切受け付けられません |
試験開始時に、必ず自分が入力している箇所が正しい問題番号に対応しているか確認する習慣をつけましょう。
7. プレテスト(事前体験)について
法務省は、CBTテストセンターでの試験環境を事前に体験できる「プレテスト」を実施します。本番前に実際の試験会場・設備で操作感を確認できる貴重な機会です。
7-1. プレテストの実施概要
| 項目 | 内容 |
| 実施日 | 令和8年2月10日(火)・11日(水/祝) |
| 試験時間 | 70分(論文式試験50分+休憩5分+短答式試験15分) |
| 出題内容 | 論文式試験(公法系科目)+短答式試験(憲法) |
| 出題範囲 | 過去に実施した司法試験等の問題から出題 |
| 受験手数料 | 無料 |
| 会場 | 全国のCBTテストセンター |
※プレテストはCBTテストセンターでの受験環境を体験することが目的のため、実際の司法試験・予備試験での基準による受験特別措置の決定等は行われません。
7-2. プレテストの予約方法
プレテストは事前予約制です。会場・時間枠ごとの先着順となりますので、早めの予約をおすすめします。
| 項目 | 2月10日分 | 2月11日分 |
| 予約開始 | 令和7年12月15日(月)午前10時 | 令和7年12月17日(水)午前10時 |
| 予約締切 | 令和8年1月15日(木)正午 | 令和8年1月15日(木)正午 |
予約方法
司法試験等CBTプレテストから申込
7-3. プレテストの持込可能物品一覧
プレテストでは、試験時間外を含め、以下の物品のみ試験室内に持ち込むことができます。電子機器類、時計、ストップウォッチ、筆記用具等は持ち込み不可です。
| 物品 | 備考 |
| 飲用水 | 容量1,000ml以下の透明な ペットボトル入り1本に限る。 ラベルは事前に外すこと |
| ハンカチ、ハンドタオル | — |
| ポケットティッシュ | ケース等の持ち込みは不可 (元のビニールのみ可) |
| マスク | 着用の上入室すること |
| ヘアゴム、ヘアピン | — |
| 眼鏡 | 眼鏡型の拡大鏡を含む。 サングラスは不可 |
| 耳栓 | — |
| 目薬、点鼻薬 | — |
| 薬 | 受付で申請の上、服用の際は 監督員に申し出ること |
| 法文 | 一般的な法文集であれば 出版社等は問わない |
8. 試験中のトラブル対応
CBT試験では、地震・停電・機器トラブルなど予期せぬ事態への対応が気になる方も多いでしょう。法務省から発表されているトラブル対応について解説します。
地震・停電が発生した場合
発生した事象の規模・内容等を考慮し、具体的な状況に応じて試験時間を変更するなど適切な対応が行われます。
ネットワーク障害が発生した場合
CBTシステムは、万が一ネットワークに障害が生じた場合でも試験を継続できる仕様となっています。ネットワーク障害によって試験が中断される心配は基本的にありません。
パソコンに不具合が生じた場合
自動バックアップ機能により、作成中の答案・問題文へのメモ画面への書き込みは入力の都度自動で保存されています。万が一パソコンに不具合があっても、直前の状態から再開できる仕様です。
その上で、生じた不具合の内容等を考慮し、具体的な状況に応じて試験時間を変更するなど適切な対応が行われます。
誤って答案を消してしまった場合
「元に戻す」ボタン(または「Ctrl + Z」キー)を押すことにより、直前の状態に戻すことが可能です。
答案の保存について
答案を手動で保存する機能はありませんが、上記のとおり入力の都度自動でバックアップ保存が行われているため、意識的に保存操作を行う必要はありません。
答案の提出方法
試験終了時に、答案入力箇所に入力された内容だけが答案として自動で回収されます。
※注意
試験時間終了前に答案を提出して受験を終了することはできません。
試験開始前の操作確認
試験当日、試験開始前にタイピング等のCBT試験の操作性を確認できる画面が用意されることが検討されています。
9. パソコン受験(CBT方式)における注意点
2026年度(令和8年度)以降に実施される試験を受験する予定のある方は、次の点に注意しておく必要があります。
| パソコン受験(CBT方式)における5つの注意点 |
| ◉タイピング次第で書ける分量が変わる ◉不慣れなパソコンだと答案作成に影響が出る可能性がある ◉試験問題や採点方法が変更になる可能性がある ◉問題処理速度次第で点差が開く可能性がある ◉パソコンの不具合で焦ってしまう可能性も |
ここからは、それぞれの注意点について詳しく解説していきます。
9-1. タイピングスピードによって文章量が変わる
今まで手書きで行なわれていた司法試験の論文式試験において、パソコンで答案を作成することになるため、タイピング次第で時間内に書ける答案の分量が変わることになります。
タイピングに慣れている人ほど答案構成に時間をかけることができ、また時間内に書ける分量も多くなります。つまり、タイピング次第で、答案の質に差が出てくる可能性があるのです。
従来のように手書きの試験であれば、受験生によって書くスピードが大幅に異なることはありませんでしたが、パソコンで答案を作成するとなると、タイピングが得意な人とそうでない人との間で、書ける分量に大きな差が出てしまう可能性が高いです。
もちろん、ただたくさん書けば合格できる試験ではないので、タイピングが得意であるだけで試験自体に有利になるわけではありません。
しかし、今後、司法試験の学習をする中で、タイピングを使った答案作成の訓練をしておくことは非常に重要になってくると言えるでしょう。
9-2. 不慣れなパソコンだと答案作成に影響が出る可能性がある
受験時は、法務省側が用意した会場のパソコンを利用して回答することになるため、16インチ以上のノートパソコンという点は、普段使いなれているものよりも大きな場合が多く、使用感が異なることが考えられます。
また、漢字変換についても、単語登録機能や予測変換も使えず、予測変換を行う通常のPCとは変換候補が異なります。
特に、法律用語は日常的に使われる用語とは異なる使い方をされることがよくあるため、変換候補に当該漢字がない可能性がありますので注意が必要です。
試験現場で戸惑わないためにも、キータッチの感覚や細かなキーボードの配置が違うこと、思ったように変換されない可能性なども頭に入れておく必要があるでしょう。
9-3. 試験問題や採点方法が変更になる可能性は?
従来型の手書き方式からパソコン方式(CBT方式)に変更されることで、問題の傾向や採点方法が変更される可能性は否定はできません。
まず前提として、従来の司法試験で配布される答案用紙の枚数が決まっていたように、パソコン受験(CBT方式)では、行数や文字数の制限が予定されています。
答案に書き表すことができる上限が設定されているため、タイピングにより答案を書くスピードが上がったとしても、従来通り核心についてのみ論述するという方向性は今後も変更はないでしょう。
ただし、受験生がどれだけCBT方式に適応できるかにより、受験生に求められるものや、今後の司法試験の出題方式や採点方法が変更される可能性は否めません。
司法試験に関しての採点実感を通して、CBTでの答案の問題点等について、採点委員や司法試験委員会が公表する内容の情報収集は欠かすことができないものとなります。
9-4. 問題処理速度次第で点差が開く可能性がある
パソコン受験(CBT方式)の場合、問題処理速度が早い人と遅い人で点差が開いてしまう可能性があります。
慣れない形式だと、問題文へのメモ書きや答案構成に手こずって、時間がかかりすぎてしまう危険があります。論文式試験の問題分析における処理速度が遅いと、その分答案構成や解答作成にかけられる時間も変わってきます。
特に、タイピングを駆使して答案を作成する場合、手書きで答案を作成するよりも多くの情報を瞬時に処理しながら答案を作成していくため、従来型の手書きの試験とは違った頭の使い方が必要になります。
自分のタイピングのスピードを知った上で、自分に合う答案構成の仕方や答案作成の時間を決めるという自分オリジナルの戦略が必要となるでしょう。
10. パソコン受験(CBT方式)の対策とは?今のうちからやっておくべきこと
パソコン受験(CBT方式)が導入される前に、受験生としてやっておくべきことには何があるのでしょうか?
ここでは、次の5つの対策について解説していきます。
| パソコン受験(CBT方式)導入前にできる5つの対策 |
| ◉タイピングに慣れておく ◉採点者にわかりやすい答案構成力を身につける ◉CBT対応答練で時間配分を考えておく ◉CBT対応教室を活用して現場感覚を掴む ◉CBT方式に合わせてブラッシュアップされた受験指導校の講義を活用する |
10-1. タイピングに慣れておく
日常生活であまりパソコンを使っていない場合には、パソコン受験(CBT方式)が導入されるまでにタイピングに慣れておく必要があります。
CBT方式では、パソコンで論文を作成することになるため、早く正確にタイピングできる受験生とそうでない受験生との間で、答案の質に差が出てくる可能性があります。
タイピング練習にどこまで時間をかけるべきかは人によって異なりますが、少なくとも日常の使用で不便さを感じない程度には、タイピングに慣れておく必要があります。学校でのレポート作成や仕事での文書作成など、様々な場面でタイピングを意識するようにしてください。
実務の世界に出れば、書面作成のほとんどはパソコンで作成することなるため、法律家にとってタイピングは必須のパソコンスキルだと言えます。
ただし、どれだけタイピングが早くても、そもそも論文の内容が適切な内容でない場合には、司法試験に合格することはできません。
あくまでも優先は法律の勉強であることを常に頭に入れておきましょう。
10-2. 採点者にわかりやすい答案構成力を身につける
パソコン受験(CBT方式)の導入にあたり、今まで以上に、正確な答案構成力を身につけることを意識する必要があります。
パソコンで答案を作成する場合、手書きよりも早く文書を作成できるため、より多くの論点を答案の中に詰め込むことができます。これは、メリットであると同時にデメリットであるとも言えます。文章が長くなればなるほど、全体としてメリハリのない文章になる可能性が高く、何を言いたいのか、答案のポイントはよくわからなくなる可能性があるからです。
そのため、一文を短くしたり、接続詞を効果的に使用するなど、今まで以上に、読み手である採点者が分かりやすいような答案を作成するように意識してください。
10-3. CBT対応答練で時間配分を考えておく
パソコン受験(CBT方式)が導入される前に、CBT方式対応の答練を活用して、本番当日の時間配分をしっかり固めておく必要があります。
手書きよりも早く答案を作成できるCBT方式では、より答案構成に時間をかけられるようになります。そのため、自分の中で答案構成にかける時間と答案作成に書ける時間の配分をしっかり頭に入れておく必要があると言えます。
もちろん、人によってタイピング速度や問題処理速度も異なるため、時間配分を一概に決めることはできません。
また、長時間継続してタイピングを行なうことになるため、指の負担から後半のタイピング速度が落ちることもあるでしょう。
これら全ての要素を加味した上で、実際にパソコンで答練を受けてみることで、自分なりのペース配分を試したり、あらかじめ身体に染み込ませておくことが重要です。
CBT対応の答練であれば、時間配分を身につける訓練になるだけでなく、パソコンを利用した受験の雰囲気や機材トラブルがあった時の対処法についても学ぶことができます。
10-4. CBT対応教室を活用して現場感覚を掴む
各受験指導校が提供するCBT対応教室を活用することで、あらかじめ試験当日の現場感覚を掴んでおく事も、有効な対策と言えるでしょう。
伊藤塾では、誰も体験したことがないCBT方式の現場シミュレーションができる「CBT対応教室」を開室予定です。
パソコンに苦手意識がある人も、定期的に現場シミュレーションを行なっておく事で、試験当日も安心して試験問題に集中することができます。
伊藤塾はCBT完全対応の準備ができています。ぜひ詳細をご確認ください。
10-5. CBT方式に合わせてブラッシュアップされた受験指導校の講義を活用する
手書き方式からCBT方式への変更に伴い、試験問題や採点方式が変わる可能性があります。もし、試験問題や採点方式が変わっても得点を伸ばせるように、情報収集に長けた受験指導校を利用して、CBT方式に合わせてブラッシュアップされた講義を受講しておくと良いでしょう。
伊藤塾では、AIによる本試験分析データを基に、経験豊かな講師陣がブラッシュアップした教材や問題を使用して講義を行なっています。これらの講義を有効活用して勉強することで、CBT導入後の試験でも効果的に得点できるだけの実力を身につける事ができます。
CBT方式に関する情報についても、法務省から発表があり次第すぐに対応しているため、リアルタイムで最新の情報を手に入れる事もできます。
11. 司法試験・予備試験におけるCBT方式のまとめ
Q. 司法試験のCBT方式とは何ですか?
A.司法試験におけるパソコン受験(CBT方式)とは、司法試験及び予備試験において、パソコンを利用して答案を作成する方式を指します。これは、デジタル庁が公表した「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に明記された具体的なデジタル化施策の一つです。
Q. 司法試験でCBT方式はいつから導入されますか?
A.司法試験では、2026年(令和8年度)に実施される試験から、短答式試験及び論文式試験のいずれにもCBT方式が導入されることを目指しています。
Q. 司法試験予備試験でもCBT方式は導入されますか?
A.司法試験予備試験では、2026年(令和8年度)の試験において、論文式試験のみCBT方式が導入されることを目指しています。
Q. CBT方式が導入される目的は何ですか?
A.主な目的は、受験者の利便性を向上させること(手書きによる負担軽減)と、試験関係者の負担を軽減させること(判別できない文字を無くし、採点者の負担軽減)です。また、実務の世界でのデジタル化の流れを汲み、法律家として必要となるパソコンでの文書作成能力が求められるようになります。
Q. CBT方式の試験はどこで実施されますか?
A.CBT方式の試験は、司法試験委員会(法務省)が用意した「CBTテストセンター」のパソコンを使用して、集合形式で実施される予定です。自宅からの受験(IBT)は、不正防止のため想定されていません。
Q. CBT試験で使用するパソコンのOSやスペックは決まっていますか?
A: 使用するデスクトップ型パソコンは、OSにWindows 11 Pro、CPUは1.5 GHz以上のマルチコアプロセッサ、メモリは8GB以上、画面解像度は1920×1080ピクセル以上、モニターサイズは19インチ以上または23インチ以上などが予定されています。
Q. 文字入力ソフトや使用できる機能に制限はありますか?
A.文字入力ソフトは日本語 Microsoft-IMEを使用します。学習機能は使用可能ですが、予測文字変換や手書き入力などの機能は使用できません。ドキュメント編集に係る一部機能(コピー、貼り付け、検索等)は使用できます。キーボードショートカットキーはCtrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+Zのみ使用可能です。
Q. 文字入力や記号の入力に関する制限はありますか?
A: 一部入力できる文字に制限があり、具体的に半角文字は入力できず、入力した場合は自動的に全角に変換されます。また、一部(⑴、①、ⅰ等)を除き、記号等の入力もできません。インデントの設定や禁則処理の機能も使用できません。
Q. CBT方式導入の主な注意点は何ですか?
A.注意点として、タイピングスピードによって文章量が変わる可能性があること、不慣れなパソコンだと答案作成に影響が出る可能性があること、問題処理速度次第で点差が開く可能性があること、パソコンの不具合で焦ってしまう可能性などが挙げられています。
Q. CBT方式への対策として、今のうちから何をすべきですか?
A.CBT方式が導入される前に、タイピングに慣れておくこと、採点者にわかりやすい答案構成力を身につけること、CBT対応答練を活用して時間配分を考えておくこと、CBT対応教室を活用して現場感覚を掴むことなどが推奨されています。ただし、タイピング練習に時間をかけすぎて法律の勉強が疎かにならないよう注意が必要です。
Q. CBT試験で使用できるショートカットキーを教えてください。
A. Ctrl+C(コピー)、Ctrl+V(貼付け)、Ctrl+X(切取り)、Ctrl+Z(元に戻す)、Ctrl+A(全選択)、Ctrl+Y(やり直す)、Ctrl+Shift+Z(やり直す)、Ctrl+Home(文頭に移動)、Ctrl+End(文末に移動)が使用可能です。それ以外のWindowsショートカットキーは使用できません。
Q. 試験用法文は紙で配布されますか?
A. はい。令和8年の司法試験および予備試験では、試験用法文は画面上で閲覧できる機能に加えて、紙媒体でも配布されることが正式決定しています。令和9年以降については引き続き検討中です。
Q. 答案入力箇所を間違えたらどうなりますか?
A. 答案入力箇所を取り違えた場合は零点となります。試験時間中に気付いた場合は、コピー・貼付け機能等を使用して自分で正しい箇所に転記する必要があります。試験時間終了後の取り違え申請は一切受け付けられません。
Q. 試験中にパソコンが故障したらどうなりますか?
A. 作成中の答案は入力の都度自動でバックアップ保存されており、パソコンに不具合があっても直前の状態から再開できる仕様となっています。その上で、状況に応じて試験時間の変更など適切な対応が行われます。
Q. 答案を手動で保存する必要はありますか?
A. 手動で保存する機能はありませんが、入力の都度自動でバックアップ保存が行われるため、保存操作は不要です。
Q. 試験終了前に答案を提出して退出できますか?
A. できません。試験時間終了時に答案が自動で回収される仕組みのため、途中で提出して退出することはできません。
Q. プレテストの予約方法を教えてください。
A. プロメトリックIDを事前に作成した上で、プロメトリック株式会社のホームページから予約します。予約・受験は一人一回限りで、会場・時間枠ごとの先着順です。
Q. プレテストに何を持っていけますか?
A. 飲用水(透明ペットボトル1本)、ハンカチ、ポケットティッシュ、マスク、眼鏡、耳栓、目薬、薬、法文が持込可能です。電子機器、時計、筆記用具は持ち込めません。筆記用具はシャープペンシル1本が配布されます。
Q. タイピング速度はどのくらい必要ですか?
A. 法務省から具体的な基準は示されていませんが、1頁23行×30文字(690文字)を制限時間内に書ける速度が目安となります。日常的にパソコンで文書作成をしている方であれば問題ないレベルですが、不安な方は事前に体験版で練習することをおすすめします。
Q. CBTシステム以外のアプリケーション(Wordなど)は使用できますか?
A. 実際の司法試験・予備試験では、CBTシステム以外のアプリケーションは起動できない仕様となっています。
伊藤塾では、AIによる本試験分析データを基に、経験豊かな講師陣がブラッシュアップした教材や問題を使用して講義を行なっています。これらの講義を有効活用して勉強することで、CBT導入後の試験でも効果的に得点できるだけの実力を身につける事ができます。
CBT方式に関する情報についても、法務省から発表があり次第すぐに対応しているため、リアルタイムで最新の情報を手に入れる事もできます。
また無料の体験受講や説明会も実施していますので、司法試験の受験に興味をお持ちの方は、ぜひ一度伊藤塾までお問い合わせください。
2025年 司法試験合格者1,581人中 1,432名(90.6%)※1
2025年 予備試験合格者 452人中405名(89.6%)※2
が伊藤塾有料講座の受講生でした。
※1(講座内訳:入門講座640名、講座・答練321名、模試471名)
※2(講座内訳:入門講座228名、講座・答練130名、模試47名)
なぜ、伊藤塾の受講生は、これほどまでに司法試験・予備試験に強いのか?
その秘密を知りたい方は、ぜひこちらの動画をご覧ください。