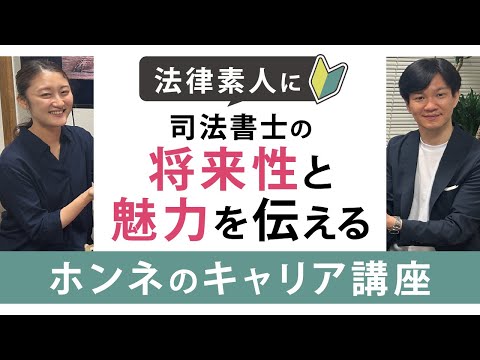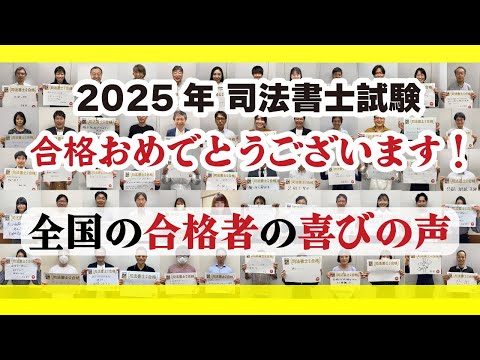【最新】司法書士試験の合格率はなぜ低い?2025年度の合格率や推移・社会人の合格必勝法も解説
難易度・合格率
2025年10月02日


司法書士試験は、近年合格率が5%台で推移している、法律系の難関国家資格のひとつです。
学生や社会人の方の中には、司法書士試験にチャレンジしたいけれど、合格率の低さから、自分では無理かもしれないとマイナス思考に陥ってしまっている方も多いのではないでしょうか。
たしかに、司法書士試験は難易度の高い試験ではありますが、合格率の低さには理由があり、コツコツと勉強を継続すれば、誰でも合格できる試験であることは間違いありません。
このコラムでは、司法書士試験の合格率がなぜ低いのか、本当の合格率や難易度の実態はどれくらいなのかについて詳しく解説していきます。
【目次】
1.令和7年度(2025年度)の最新データと推移
司法書士試験の合格率は、法律系の資格の中でもとくに低い部類に入る難関国家資格です。ここでは、令和7年度(2025年度)におこなわれた司法書士試験の合格率や、過去10年間の合格率の推移について確認していきます。
1-1.令和7年度(2025年度)の合格率は5.21%
令和7年度(2025年度)に行われた司法書士試験の結果は、次の通りです。
【令和7年度(2025年度) 司法書士試験 結果】
| 年度 | 受験者数 | 最終合格者数 | 合格率 |
| 令和7年 (2025年) |
14,418人 | 751人 | 5.21% |
| 男性528人(70.3%) 女性223人(29.7%) |
|||
| 令和6年 (2024年) |
13,960人 | 737人 | 5.28% |
| 男性495人(67.2%) 女性242人(32.8%) |
※受験者数は午前の部及び午後の部の双方を受験した者の数
令和7年度(2025年度)の司法書士試験の合格率は、受験者数14,418人に対し、合格者が751人、最終合格率は5.21%という結果となりました。
1-2.過去10年の合格率は概ね4〜5%台で推移
令和7年度(2025年度)の司法書士試験の合格率は5.21%でしたが、これまでの合格率はどれくらいで推移しているのでしょうか。
過去10年間における司法書士試験の合格率の推移を確認してみましょう。
| 試験年度 | 受験者数 | 最終合格者数 | 合格率 |
| 令和7年(2025年) | 14,418人 | 751人 | 5.21% |
| 令和6年(2024年) | 13,960人 | 737人 | 5.28% |
| 令和5年(2023年) | 13,372人 | 695人 | 5.20% |
| 令和4年(2022年) | 12,727人 | 660人 | 5.19% |
| 令和3年(2021年) | 11,925人 | 613人 | 5.14% |
| 令和2年(2020年) | 11,494人 | 595人 | 5.18% |
| 令和元年(2019年) | 13,683人 | 601人 | 4.39% |
| 平成30年(2018年) | 14,387人 | 621人 | 4.32% |
| 平成29年(2017年) | 15,440人 | 629人 | 4.07% |
| 平成28年(2016年) | 16,725人 | 660人 | 3.95% |
過去10年間の合格率をみると、おおむね4〜5%前後で推移しているのがわかります。
また、合格率は年々上昇傾向にあり、令和2年度に5%を超えてからは、一度も5%を下回っていません。
1-3.司法書士試験の難易度とは?
合格率は近年上昇傾向にあるものの、過去10年では4〜5%程度で推移していることを考えると、司法書士試験の難易度は高いといえるでしょう。
受験者数や合格者数もそれほど大きな変動があるわけではないので、今後も合格率は5%台で推移していくことが考えられます。
※司法書士試験の難易度については、こちらの記事で詳しく解説しています。
2.司法書士試験の合格率は他の資格と比べてなぜこんなに低いのか?
下記は、主要な法律系国家試験の合格率を比較した表です。
司法書士試験の合格率は、他の資格試験と比べて、なぜこんなにも低いのでしょうか。
【主要な法律系国家試験の合格率】
| 試験名 | 合格率 |
| 司法試験 | 20〜45% ※ 受験資格あり |
| 司法書士試験 | 4〜5% |
| 中小企業診断士試験 | 3〜8% |
| 弁理士試験 | 5〜10% |
| 社労士試験 | 6〜7% |
| 土地家屋調査士試験 | 8〜10% |
| 行政書士試験 | 10〜12% |
| 宅建士試験 | 15〜17% |
合格率だけを見て、「こんな難しい試験に挑戦するなんて、自分には到底無理」と最初から諦めてしまう人もいらっしゃるでしょう。
しかし、合格率が低いことには理由があります。
合格率が低い原因を正しく理解することで、試験にチャレンジするモチベーションを保ちやすくなることもあるでしょう。ここでは、司法書士試験の合格率が他の資格試験と比べて低い5つの理由について詳しく解説していきます。
【司法書士試験の合格率が低い5つの理由】
1. 試験科目が多く試験範囲が膨大だから
2. 基準点、合格点とクリアすべきハードルがあるから
3. 司法書士試験が実質的に「相対評価」の試験であるから
4. 記念受験生が多いから
5. 仕事をしながら受験する人が多いから
2-1.試験科目が多く試験範囲が膨大だから
司法書士試験の合格率が低い大きな要因の一つに、試験科目の多さと学習範囲の膨大さが挙げられます。
筆記試験の対象となるのは、憲法、民法、刑法、商法(会社法)、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、司法書士法、供託法、不動産登記法、商業登記法の合計11科目にも及びます 。特に主要4科目(民法・商法・不動産登記法・商業登記法)だけでも学習量は多く、法律初学者にとっては、基礎知識をひと通りインプットするだけでも相当な時間を要します 。
しかし、範囲が広いからといって「すべてを完璧に記憶しなければならない」わけではありません。多くの受験生が挫折してしまう原因は、真面目さゆえに最初から完璧を求めすぎてしまい、学習が前に進まなくなってしまうことにあります 。
膨大な試験範囲を攻略するための重要な勉強法は、「完璧主義を捨てること」です 。
法律の学習では、最初は理解できなくても、学習を進めて全体像が見えてくることで、後から点と点がつながるように理解できることが多々あります 。一度で全てを理解しようと立ち止まるのではなく、「今はわからなくても大丈夫」と割り切り、まずはテキストを最後まで読み進める勇気を持つことが大切です 。
「回転数(繰り返し)」を重視し、何度も触れることで記憶を定着させていく学習スタイルを身につければ、膨大な範囲も決して怖いものではありません。この「前に進む学習」こそが、合格への近道となります。
※司法書士試験の勉強法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
2-2.基準点、合格点とクリアすべきハードルがあるから
司法書士試験の難易度が高いと言われるもう一つの理由は、独特の「基準点」制度と「合格点」の仕組みにあります。
本試験では、単に総合点で競うだけでなく、以下の3つのパートそれぞれで、一定の基準点(ボーダーライン)をクリアしなければなりません。
- 午前の部(多肢択一式)
- 午後の部(多肢択一式)
- 午後の部(記述式)
たとえ総合点で合格ラインを超えていても、このうちの一つでも基準点に届かなければ、その時点で不合格となってしまいます。つまり、「得意科目で点数を稼いで、苦手科目をカバーする」という戦略が通用しにくく、全科目において偏りなく実力をつけることが求められるのです。
一見すると非常に厳しいハードルに見えますが、これを乗り越えるための対策は明確です。それは「誰もが解ける基本問題を、絶対に落とさないこと」です。
基準点を突破するために、難問や奇問を解けるようになる必要はありません。合格者の多くは、テキストに載っている基礎的な知識(Aランク知識)を徹底的に固めることで、この基準点をクリアしています。「苦手科目を作らない」「基本を疎かにしない」という学習の王道を貫けば、基準点は決して越えられない壁ではありません。
また、完璧を目指す必要がないという点も重要です。満点を取る必要はなく、基準点プラスアルファの得点を確実に積み重ねることを目標にすれば、気持ちも楽になります。
この制度は「極端に知識が偏っている人をふるい落とす」ためのものであり、正しい努力をしている受験生を拒むものではありません。基礎を大切にバランスよく学習を進めれば、必ず道は開けます。
【令和7年度(2025年度) 筆記試験合格点・基準点一覧】
| 試験区分 | 満点 | 令和7年(2025年) 合格点・基準点 |
令和6年(2024年) 合格点・基準点 |
| 筆記試験 合格点 |
350点 | 255.0点 | 267.0点 |
| 午前の部 (多肢択一) 基準点 |
105点 | 78点 | 78点 |
| 午後の部 (多肢択一) 基準点 |
105点 | 72点 | 73点 |
| 記述式問題 基準点 |
140点 | 70.0点 | 83.0点 |
※司法書士試験の基準点・合格点についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
2-3.司法書士試験が実質的に「相対評価」の試験であるから
司法書士試験の合格が難しいと言われる背景には、この試験が「絶対評価」ではなく、実質的な「相対評価」で行われる競争試験であるという事情があります。
一定の点数を取れば全員が合格できる検定試験などとは異なり、司法書士試験は「受験者全体の上位数%(およそ4〜5%)」しか合格できない仕組みになっています。つまり、合格点は毎年変動し、ライバルたちよりも1点でも多く取る必要があるのです。
「他人との競争」と聞くと、プレッシャーを感じたり、非常に高いレベルの争いを想像して尻込みしてしまうかもしれません。しかし、この仕組みを正しく理解すれば、恐れる必要はありません。
相対評価の試験で勝つための鉄則は、「誰もが正解する問題を、絶対に落とさないこと」に尽きます。
合格者の多くは、難問奇問を解く力ではなく、基本事項における「圧倒的な正確さ」で勝負しています。多くの受験生が正解できる基本問題(Aランク問題)でのミスをなくし、確実に得点することさえできれば、自然と合格ライン(上位層)に食い込むことができるのです。
周りを気にする必要はありません。昨日の自分よりも正確な知識を身につけること、そして基礎を徹底すること。このシンプルな積み重ねが、相対評価の壁を突破する最も確実な方法です。
2-4.記念受験や準備不足の受験生も含まれるから
合格率「約4〜5%」という数字だけを見ると、100人中4〜5人しか合格できない非常に狭き門のように思えます。しかし、この数字を鵜呑みにして恐れる必要はありません。
司法書士試験の出願者の中には、学習が十分に間に合っていない状態で受験する「記念受験」や「お試し受験」の層が一定数含まれていると言われています。「とりあえず雰囲気を知るために受けてみよう」「今年は無理だけど来年のために」といった層です。
つまり、合格を本気で争う「実質的なライバル」の数は、統計上の受験者数よりもずっと少ないのです。
全範囲の学習を終え、本気で合格を目指してスタートラインに立っている受験生だけで見れば、実質的な倍率はもっと下がります。数字のマジックに惑わされず、「きちんと準備すれば、十分に勝負の土俵に乗れる」と自信を持って学習を継続してください。
2-5.仕事をしながら受験する人が多いから
合格率が低いもう一つの背景には、受験生の属性があります。
司法書士試験は、大学生などの学生よりも、社会人として働きながら受験する人の割合が非常に高い試験です。
仕事をしながらの学習は、どうしても「勉強時間の確保」が難しくなります。十分な対策時間が取れずに涙を呑む受験生が多いため、結果として全体の合格率が低く出やすい傾向にあります。
しかし、これは裏を返せば「時間の使い方さえ制すれば、誰にでもチャンスがある」ということでもあります。
実際、多くの合格者が、通勤時間や昼休みなどの「スキマ時間」を徹底的に活用し、働きながら合格を勝ち取っています。社会人受験生が多いということは、一日中勉強できるライバルばかりではないということです。
「時間がないから無理」と諦めるのではなく、「限られた時間でいかに効率よく学ぶか」に意識を向けましょう。密度の高い学習を積み重ねれば、社会人であっても合格は決して難しいことではありません。
※こちらも読まれています。
3.司法書士試験に強い大学は?
司法書士試験の大学別合格率等は、法務省から公表されていません。司法書士試験は受験資格が不要であり、さまざまな学歴、バックボーンを持つ人が受験できる試験です。
また、法学部以外の学部出身でも司法書士試験に合格している方はたくさんいますし、実務家の中でも、他学部出身で活躍している司法書士は多いです。
学歴が大卒でなくとも、また、法学部でなくても、司法書士試験に合格することは十分可能ですし、これまでの社会人経験を活かし、合格後も、職業の枠を超えてさまざまなフィールドで活躍できるのが、司法書士の大きな魅力だといえるでしょう。
※司法書士の受験資格については、こちらの記事で詳しく解説しています。
4.5%台の合格率に隠された司法書士試験の実態とは?
ここでは、4つの視点から、司法書士試験の合格率の実態について解説していきます。
4-1.記念受験や準備不足の受験生を除けば合格率は上がる
第2章でも触れた通り、司法書士試験の合格率「4〜5%」という数字は、全受験者を分母とした統計上の結果に過ぎません。ここから、「記念受験」や「準備不足」の受験生を除外して考えると、実態は大きく変わります。
合格を目指す上で意識すべきなのは、見かけの倍率ではなく「実質倍率」です。
伊藤塾の分析では、全科目の学習を一通り終え、過去問演習などの試験対策を万全に行った「実質的な受験者」だけで見れば、合格率は大きく跳ね上がると考えています。
つまり、真剣に学習に取り組んだ人同士の戦いにおいては、「20人に1人」という無謀な賭けではなく、「数人に1人」という十分に手の届く競争になるのです。
重要なのは、まずこの「実質的な競争の土俵」に上がることです。 途中で投げ出さずに学習を継続し、全範囲を修了した時点で、あなたはすでに多くのライバルを追い抜き、合格を争う上位層の集団に入っています。
「5%の壁」という数字に圧倒される必要はありません。正しい努力を継続して「本気で合格を目指す層」に入りさえすれば、合格は決して不可能な奇跡ではなく、現実的な目標となります。
4-2.合格者の平均年齢は42歳!受験に年齢は関係ない
「記憶力の良い若い学生じゃないと、合格できないのではないか?」 もし年齢を理由に受験を躊躇しているなら、それは大きな誤解です。
令和7年度(2025年度)司法書士試験の合格者の平均年齢は42.05歳。例年40代で推移しています。これは他の国家資格と比べても非常に高く、合格者のボリュームゾーンが30代・40代、そして50代以上にも広く分布している「大人のための試験」といえます。
例えば、不動産登記や相続といった分野は、学生よりも、実際に家を買ったり、親族間の手続きを見聞きしたりした経験のある社会人の方が、イメージが湧きやすく深く理解できる場面が多々あります。これまで培ってきた人生経験や社会常識が、法律の学習において強力な武器になるのです。
また、司法書士は定年がないため、セカンドキャリアとして目指す人が多いのも特徴です。 年齢に関わらず就職先には困らないといわれている点も大きな魅力です。
「もう歳だから」と諦める必要は全くありません。むしろ、様々な経験を積んだ今だからこそ、目指すべき資格だと言えるでしょう。
下記グラフは、令和7年度(2025年度)司法書士試験の年齢別合格者数を表したものですが、最年少合格者の17歳(平成19年生)から最高齢合格者の74歳(昭和26年生)まで、幅広い世代の人が合格している試験であることがわかります。※年齢は、令和7年(2025年) 11月4日現在

4-3.法学部出身でなくても十分合格可能
司法書士試験において、出身学部や法学の学習経験は、合否を分ける決定的な要因ではありません。実際、理系学部出身者や、高卒の合格者も数多く活躍しています。
法学部出身でなくても合格できる理由は大きく2つあります。
1. 大学の勉強と試験勉強は「別物」だから
大学の法学部で学ぶのは、主に法律の「解釈」や「学説」といった学問的な理論です。一方、司法書士試験で問われるのは、条文や判例、そして実務的な手続の「知識」です。求められる能力が異なるため、法学部出身者が圧倒的に有利というわけではありません。
2. 誰もが「初学者」としてスタートする科目が多いから
司法書士試験の最重要科目である「不動産登記法」や「商業登記法」は、大学の授業ではほとんど扱われない実務的な分野です。つまり、法学部出身者であっても、これらの科目についてはゼロからのスタートとなります。
過去の経歴は関係ありません。「法律を知っているか」ではなく、「これから試験に向けてどれだけ真剣に取り組めるか」。その意欲さえあれば、法学部出身者と対等以上に渡り合うことは十分に可能です。
司法書士試験は、法学部出身ではない法律初学者でも十分合格を目指せる試験です。
もちろん、法学部出身であれば、学生時代に聞いたことがある用語があったりと、初めて学ぶ方より多少理解が早いかもしれません。しかし、法学初学者であっても、法律を一から効率よく学ぶことで、最終的に合格レベルまで到達することは十分可能です。
5.司法書士試験の合格率を上げるなら受験指導校に行くべき?
司法書士試験を独学で突破することは、不可能ではありません。しかし、司法書士試験にいち早く合格したいのであれば、受験指導校を有効活用して、効率よく勉強を進めることをおすすめします。
司法書士試験の試験科目は合計11科目あり、その試験範囲は膨大です。加えて、法律の学習を初めて行う方にとっては、参考書を読んでも具体的なイメージがつきづらく、内容を理解するだけでも莫大な時間がかかってしまうでしょう。
働きながら合格を目指すのであれば、勉強時間を捻出することが困難である場合が多く、遠回りの勉強をしていては、いつまで経っても合格を手にすることはできません。また、独学で勉強する場合、最新の法改正に対応することや、時事情報をキャッチすることが難しい点も挙げられます。
スケジュール管理やモチベーションの維持も含め、受験指導校の講義やカウンセリング制度などを効果的に利用することで、最短での合格を目指すことができます。
※こちらも読まれています。

6.司法書士試験の合格率についてよくある質問(Q&A)
Q. 合格率5.21%と聞くと、法律の勉強が初めての自分には無理だと感じてしまいます…
A. そのように感じる必要は全くありません。合格率5.21%は、受験者全員(何度も受験しているベテラン受験生、記念受験の方、学習が間に合わなかった方など、様々なレベルの人が含まれます)を母数とした数値です。
重要なのは、初学者であっても「正しい学習戦略」で「合格に必要な知識」だけを効率よく学べば、この試験は十分に突破可能であるという点です。
実際に、伊藤塾の講座などを利用し、法律の学習経験ゼロから一発で合格される方も毎年いらっしゃいます。合格率の数字だけを見て、挑戦を諦めてしまうのは非常にもったいないことです。
Q. 働きながらの受験を考えています。合格率5%台の試験に兼業受験生が合格するのは難しいですか?
A. 非常に多くの方が働きながら合格を勝ち取っています。合格率5%台の試験を突破するために必要なのは「学習時間の総量」だけではありません。
むしろ、限られた時間の中でいかに効率よく学習を進めるかという「学習の質」が重要になります。
働きながら合格される方の多くは、独学ではなく受験指導校(伊藤塾など)をうまく活用しています。試験に出るポイントが絞られたテキストや、スキマ時間で視聴できる講義(Web受講)などを利用し、可処分時間を最大限に活用することで、合格率の壁を突破しています。
Q. 今年度(2025年度)は記述式の基準点が大きく下がりましたが、これは合格率や難易度にどう影響しましたか?
A. 2025年度は記述式の基準点が2024年度の83.0点から70.0点へと13.0点も低下しました。これは、記述式問題の難易度が高かったか、もしくは採点が厳格であったことを示しています。
しかし、注目すべきは、最終合格率は5.21%と、例年通りの水準に維持されている点です。
これは、試験実施側が「合格者数(約750人)」を一定に保つため、問題の難易度に合わせて基準点を調整した結果です。
受験生としては、択一式・記述式ともに、どちらかが易化・難化しても対応できる「総合力」を身につけておくことが、合格率の壁を超える鍵となります。
Q. 合格率5%の試験を突破するには、「基準点」と「合格点(総合点)」のどちらを意識すべきですか?
A. 両方とも意識する必要がありますが、意識する順番が重要です。
まず第一のハードルは、「すべての基準点(午前の部・午後の部・記述式)をクリアすること」です。一つでも下回れば、総合点がどれだけ高くても不合格となります。
そして、第一ハードルを越えた人たちの中で、今度は「総合合格点(2025年度は255.0点)」に達しているか」という第二のハードルでふるいにかけられます。
2025年度は、基準点の合計(78+72+70=220点)に対し、合格点は255.0点でした。つまり、基準点ギリギリでは合格できず、さらに「35.0点分の上乗せ点」が必要でした。合格率が5%台と低いのは、この二つの厳しいハードルを両方とも越えなければならないからです。
7.令和7年(2025年)司法書士試験の合格率は?なぜ低い?まとめ
本記事では、司法書士試験の最新の合格率と、司法書士試験の合格率が低く難関といわれることの実態について解説しました。
以下にポイントをまとめます。
- 司法書士試験は、近年合格率が5%台で推移している法律系の難関国家資格です。
- 令和7年度(2025年度)の合格率は5.21%となり、令和2年度(2020年度)以降は一度も5%を下回っていません。
- 合格率が低い5つの理由
- 試験科目が多く試験範囲が膨大だから
- 基準点、合格点とクリアすべきハードルがあるから
- 司法書士試験が実質的に「相対評価」の試験であるから
- 記念受験生が多いから
- 仕事をしながら受験する人が多いから
- 合格者の平均年齢は42.05歳(令和7年度)であり、最年少17歳から最高齢74歳まで幅広い世代が合格していることから、受験に年齢は関係なく、むしろ社会人経験を活かせる「大人のための試験」といえます。
- 合格率5%台という数値に悲観的になる必要はなく、コツコツと勉強を継続できれば、誰でも合格できる試験です。
- 合格を本気で狙うなら、「誰もが解ける基本問題を、絶対に落とさないこと」「苦手科目を作らないこと」「満点を取る必要はなく、基準点プラスアルファの得点を確実に積み重ねること」が大切です。
- 司法書士試験は、法学部出身ではない法律初学者でも十分合格を目指せる試験です。
合格率5%台という難関を突破し、「司法書士」という生涯にわたり活躍できる専門職を目指すには、効率の良い学習戦略が不可欠です。
司法書士試験は合計11科目という膨大な試験範囲を持ち、働きながら受験する方が多いため、独学では最新の法改正への対応や、最短で合格に必要な知識を習得することが困難になりがちです。
限られた時間の中でいかに効率よく学習を進めるかという「学習の質」 が、合格の鍵となります。
伊藤塾では、入門講座から中上級講座、直前対策講座まで多彩なラインナップの講座を開講中です。詳しくはこちらをご覧ください。
法律の学習経験ゼロの方でも「正しい学習戦略」で効率よく合格レベルに到達できるよう、一人ひとりの環境に合わせた学習スケジュール作成、カウンセリング制度、24時間WEB質問制度など強力なサポート体制であなたを支え、合格まで導きます。
実際に、伊藤塾では法律の学習経験ゼロから一発で合格される方も毎年大勢いらっしゃいます。
最短で合格を勝ち取りたい方は、まずは伊藤塾にご相談ください。
※伊藤塾「司法書士 入門講座」の「無料体験講義」「受講相談」はこちらから
※2025年度司法書士試験の合格者の声もぜひお聞きください。
「なんだか、私も合格できちゃうかも!」と勇気をもらえる動画です。