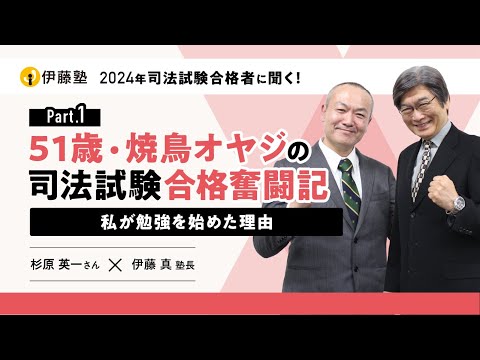50代からの挑戦!理想のセカンドキャリアの築き方とおすすめ資格5選
キャリア
2025年09月30日


「定年まであと10年、このまま何もせずにいて後悔しないだろうか…」
「でも、50代から新しいことに挑戦するなんて、もう遅いのでは…?」
50代になって、こんなモヤモヤを抱えていませんか。
今まで会社のために頑張ってきて、ようやく子育ても一段落。でも、定年まであと10年を切り、老後資金にも不安がある。かといって、このまま惰性で働き続けるのも何か違う気がする…そんな複雑な気持ちを抱えるのは、あなただけではありません。
しかし、人生100年時代の今、50代はまだ折り返し地点です。
むしろ、経験と体力のバランスが取れた50代こそ、セカンドキャリアに向けて動き出す絶好のタイミングなのです。
そこで本記事では、50代からセカンドキャリアを考えるための具体的な3つのステップと、定年なく長く働くことが可能な仕事の選択肢をお伝えします。さらに、実際に50代からセカンドキャリアを築いた方の体験談も交えながら、あなたに合った働き方を見つけるお手伝いをしていきます。
ぜひこの記事を読んで、「50代からでも遅くない」という確信と、理想のセカンドキャリアを築くためのヒントをつかみ取ってください。
【目次】
1.50代はセカンドキャリアを考える絶好のタイミング
50代になると、一気に「定年が近づく…」という実感が出てきます。とはいえ、人生100年時代とも言われる現代。50代はまだまだ折り返し地点といってよいでしょう。
厚生労働省の調査によれば、健康寿命(健康上の問題で日常生活に制限のない期間)の平均は、男性で72.57歳、女性75.45歳です。
かつては60歳で定年退職していたかもしれませんが、今では50代から計算すると、平均で「20年以上のキャリア」が残されていることになります。

(出典:厚生労働省|第4回 健康日本21(第三次)推進専門委員会 資料)
一方で、50代というのは、子育てなどが落ち着き、精神的に余裕が出てきつつ、老後の過ごし方などが気になってくる時期でもあります。
お金(老後資金)が気になる、昔からやりたかったことがある、人生で成し遂げたいことがある、状況は人それぞれかもしれませんが、50代はセカンドキャリアについて考える絶好のタイミングでもあるのです。
2.50代からセカンドキャリアを考えるための3つのステップ
それでは、50代からのセカンドキャリアでは、どのようなことを考えていく必要があるのでしょうか。理想の働き方を描くことから、実際に必要なスキルを身につけるまで、3つのステップに分けて解説していきます。
2−1.これからどんな働き方をしたいかを考える
まず考えるべきは、これからどんな働き方をしたいかです。
家族との時間を大切にしたい、趣味に時間を使いたい、社会に貢献したい。優先順位は人それぞれですが、自分にとって何が一番大切なのか整理すると、理想の働き方が見えてくるはずです。このまま会社員を続ける、パート・時短勤務で働く、開業するなど、さまざまな選択肢があるでしょう。
ちなみに、「仕事をする=会社員・パートで働く」というイメージの人が多いかもしれませんが、実は60代になると、自営業者の割合が急増します。
以下は、内閣府が「60代で働いている人に対して、仕事の種類を調査した結果」です。

(出典:令和6年度 高齢社会対策総合調査(高齢者の経済生活に関する調査)の結果)
60代で働いている人のうち、4人に1人以上は自営業主・個人事業主などです。一般的に、日本の自営業者の割合は10人に1人だと言われているため、60代の自営業率は平均の2倍以上です。
これはおそらく、働く場所や時間が自由、自分で裁量を発揮できる、といった自営業ならではのメリットが影響しているのでしょう。
当コラムを運営する伊藤塾でも、「50代からのセカンドキャリアで、開業できる資格を取りたい」とご相談に来られる方が多くいらっしゃいます。
「お金・時間・やりがい」の3つのバランスを考えつつ、あなたにとって理想の働き方を考えてみてください。
2−2.これまでのキャリアを棚卸ししてみる
次に、これまでの経験(キャリア)を具体的に書き出して、棚卸ししてみましょう。自分に何ができるのかを知らなければ、次の一歩は踏み出せないからです。
会社で担当した業務、関わったプロジェクト、取得した資格、築き上げた人脈。一つひとつ振り返ると、あなたならではの強みが見つかります。専門的なスキル・知識があって、嫌いではないなら、それを活かせるセカンドキャリアを探すのがもっともおすすめです。
もし自分の強みが分からない場合は、同僚や家族に「私の強みは何だと思う?」と聞いてみるのも良いでしょう。自分では当たり前だと思っていたことが、実は貴重な能力だったということもよくあります。
2−3.必要なスキル・資格を身につける
どのような人生を歩みたいのか、そして今何ができるのかが分かったら、足りないものを補う手段として、新たな資格・スキルの取得も検討しましょう。
「50代から新しいことに挑戦するなんて遅すぎるのでは?…」と思う人もいるかもしれませんが、決してそんなことはありません。実際、伊藤塾では、60代、70代で司法試験に合格するような方もいます。何歳になっても遅すぎることはありません。
ただし、このとき大切なのが、必ず先に「なぜ資格・スキルを目指すのか」というゴールを設定することです。「なんとなく不安だから」といった理由で資格・スキルを取得すると、失敗してしまいます。
資格やスキルは、あくまで理想のセカンドキャリアを実現するための「手段」です。
まず目指すべきゴールを明確にし、そこから逆算して必要なものを身につける。この順番を間違えないことが、50代からの挑戦を成功させるポイントです。
3.50代からのセカンドキャリアにおすすめなのが法律系の国家資格
資格やスキルといっても、選択肢はさまざまです。
たとえば、開業したいなら独立に適した資格を取る、専門性を高めたいなら特定分野のスキルを身につける、安定収入を得たいなら需要の高い資格を選ぶなど、目的によって最適な選択は変わってきます。
では、「定年なく長く働きたい」「これまでの経験を活かしたい」「年齢がハンディにならない仕事がしたい」という、50代共通の願いを叶える資格は何でしょうか?
その答えとしておすすめしたいのが、「法律系の国家資格」です。なぜ50代のセカンドキャリアに法律系資格が最適なのか、3つの観点から説明します。
3−1.合格者の平均年齢が高く、50代から挑戦しやすい
まず、法律系の国家資格は、50代から挑戦する人が多いので、年齢がハンディになりづらいです。以下のデータは、主要な法律系国家資格合格者の年齢層をまとめたものです。
| 合格者の 年齢層 |
合格者の 最高年齢 |
|
| 行政書士 | 50代以上が約27% | 81歳 |
| 司法書士 | 50代以上が約24% | 73歳 |
| 社労士 | 50代以上が約27% | 81歳 |
| 中小企業診断士 | 50代以上が約21% | 71歳 |
ご覧のとおり、どの法律系資格でも合格者の4〜5人に1人は50代以上です。最高齢の合格者は71〜81歳と、まさに年齢を感じさせない結果となっています。
さらに、これらの資格のほとんどは実務経験、学歴などの受験資格がありません(社労士を除く)。実際に、伊藤塾の受講生のなかにも、毎年のように60代・70代で難関資格に合格する方がいらっしゃいます。
3−2.定年がなく、開業すれば一生涯にわたって働ける
合格すると、定年がなく長く働けることも、法律系資格がセカンドキャリアに最適な理由です。会社員なら65歳、70歳で定年を迎えますが、法律系の資格職(いわゆる「士業」)には定年がありません。
体力的な負担が少ないので、70歳、80歳で活躍している方も実際にたくさんいます。健康である限り、自分のペースで働き続けることができるのです。
さらに、法律系の資格を取得すると、独立開業という選択肢も生まれます。
開業といっても、パソコン1台あれば自宅で開業できるので、飲食店などと比べるとハードルは低めです。「会社員のまま終わりたくない」「50代からのセカンドキャリアで、自分の好きなように働いてみたい」という人にはうってつけでしょう。
3−3.これまでの人生経験が強力な武器になる
「50代という年齢が、ハンディではなくむしろ強みになる」、これも法律系資格がセカンドキャリアに最適な理由です。
実は法律系の仕事でもっとも必要なのは、専門知識ではありません。お客様の悩みを聞き出す「傾聴力」、複雑な法律を分かりやすく説明する「説明力」、そして何より「人間としての信頼感」こそが現場で求められます。これらはまさに、50代が長年の会社員生活で培ってきた能力そのものです。
たとえば、相続、離婚、会社設立などで考えてみましょう。どれも人生の節目となる局面での相談です。そんなとき、お客様は誰に相談したいと思うでしょうか。20代の若手よりも、人生経験豊富な50代の方が頼りになると感じる人も多いのではないでしょうか。
前職での経験、子育ての経験、人生の苦労。すべてがお客様との信頼関係を築く上での財産になるのです。
※こちらの記事も読まれています。
4.【インタビュー】セカンドキャリアで法律系資格を選んだ木村さん(50代・行政書士)
ここで、実際に50代からのセカンドキャリアとして、法律系資格を選んだ人の体験談を紹介します。
32年間勤めたメーカーを辞めて、55歳で行政書士になった木村俊之さんにお話を伺いました。
より詳しい内容は、以下の動画でお話しされています。
→伊藤塾YouTube「セカンドキャリアとしての行政書士 VOL.02 木村 俊之さん」

4−1.行政書士という職業を知ったきっかけ
私は、もともとセカンドキャリアとして、士業をやりたいと思っていました。
そこで、まずは士業の世界に飛び込みたいと考えて、いろいろ調べたところ、一番学習期間が短かったのが行政書士でした。
行政書士になり、それをきっかけに他の資格も取りたいと考えて、行政書士の勉強を始めました。
4−2.会社員を辞めて、半年間集中して学習した
行政書士を目指すと決めた時に会社を辞め、100%受験に時間を使うことにしました。6月に退職し、11月の行政書士試験まで、半年間集中して学習することにしたのです。
会社を辞めた後は、自宅で一日中誰とも話さず学習を続ける生活でした。最初は、会社に行かず勉強できることが楽しかったのですが、3か月ほど経つと「本当に将来につながるのか」と不安になりました(笑)。ただ、不安と戦いながらも、「会社も辞めた以上、前に進むしかない」と思い、ひたすら勉強を続けていました。
4−3.会社員としての経験は、開業もすべての場面で活きる
私は、ずっと会社員でしたが、行政書士としての開業後も、今までの自分の経験が活きる場面が多々ありました。ほとんどすべてが活きるのでは、というくらいです。
まず、開業して自分の事務所を立ち上げる場面。
私は、これまで士業の事務所に勤務したことがなかったので、まず何をやったらいいかも分かりませんし、営業もどうすればよいか分からない状況でした。ただ、「何か課題があって、それを1つずつクリアしていくという流れは、会社員とまったく一緒です。
私自身も、実際に開業してみて、まったく違う仕事を選んだつもりだったのですが、「あれ?仕事、変わったはずだったんだけど、仕事変わっていないな」と思ったことが多々あります(笑)。サラリーマン時代の経験は、行政書士として開業しても、すべてにおいて役立つと思います。
4−4.50代からのセカンドキャリアを探している方へのメッセージ
私は、セカンドキャリアとして行政書士を目指した2年間で人生がドラスティックに変わりました。自分のことを信じて前に進んでいけば、皆さんも成功できると思いますので、頑張ってください。
※木村俊之先生の開業後のご活躍は、以下のページで詳しくお話を伺っています。
5.「50代からのセカンドキャリア」におすすめの資格5選
ここまで、法律系資格が50代のセカンドキャリアに適している理由を見てきました。では、具体的にどのような資格があるのでしょうか。
50代から始めても遅くない、むしろ人生経験が強みになる資格を5つご紹介します。
◉50代からのセカンドキャリアにおすすめの資格5選
・行政書士
・司法書士
・弁護士
・中小企業診断士
・社労士(社会保険労務士)
5−1.行政書士
行政書士は、許認可申請などを得意とする法律職です。
許認可申請などの独占業務に加えて、他の資格で独占されていないものも仕事にできるため、士業の中でもトップクラスに扱える仕事の幅が広い仕事です。
そのため、行政書士になって何をするかは、その人のこれまでのキャリア・得意分野によってさまざまです。たとえば、建設業界にいた人なら建設業許可、介護業界の人なら高齢者の成年後見のように、前職の経験がそのまま武器になるケースも多いです。
どんな業界で働いてきた人でも、その経験を活かせる分野が見つかりやすいのが行政書士の魅力です。50代がセカンドキャリアを考えるときに、最初に検討してほしい選択肢の1つといえるでしょう。
◉行政書士の基本情報
| 学習期間の目安 | 6ヶ月〜2年 |
| 合格者の年齢層 | 50代以上が約27% |
| 就職しやすさ | ★★☆☆☆ |
| 独立開業しやすさ | ★★★★★ |
※こちらの記事もあわせて読まれています。
5−2.司法書士
司法書士は街の法律家とも言われている法律職です。
マイホームの購入(不動産登記)、相続(相続登記)、会社設立(商業登記)など、主に手続き的な側面から人生の節目に関わっていきます。
司法書士試験の合格者の平均年齢は41歳。50代から挑戦する人も多く、60歳でも求人があるほどの売り手市場の資格です。伊藤塾では、毎年多くの司法書士試験合格者を送り出していますが、ほとんどの合格者がスムーズに司法書士事務所などに採用されています。
合格後は、事務所で1〜2年の経験を積んだ後、独立して自分の事務所を構えるのが王道のキャリアプランです。難関試験ですが、合格さえできれば、セカンドキャリアで感じる仕事面での不安は激減するでしょう。
◉司法書士の基本情報
| 学習期間の目安 | 1年〜3年 |
| 合格者の年齢層 | 50代以上が約24% (平均年齢は41歳) |
| 就職しやすさ | ★★★★★ |
| 独立開業しやすさ | ★★★★☆ |
※こちらの記事も読まれています。
5−3.弁護士
弁護士は、法律のプロフェッショナルとして、裁判での代理人や法律相談、契約書の作成など、あらゆる法律問題を扱います。離婚、相続、交通事故、企業間の契約トラブルなど、幅広い分野で活躍できる最高峰の法律資格です。
「50代から弁護士は無理では?」と思うかもしれませんが、実は50代から挑戦して、合格する人は決して珍しくありません。
以下に、実際に50代から弁護士になった方のインタビューをピックアップしたので、興味がある方はぜひ確認してみてください。
→ 51歳・焼鳥オヤジの司法試験合格奮闘記~私が勉強を始めた理由~【杉原さんインタビューPart1】
→【伊藤塾出身】自分らしく生きる~働きながら50代で弁護士になった私の話~
◉弁護士の基本情報
| 学習期間の目安 | 3年〜5年 |
| 合格者の年齢層 | 平均年齢:26.9歳 最高齢:70歳 |
| 就職しやすさ | ★★★★★ |
| 独立開業しやすさ | ★★★★★ |
※こちらの記事も読まれています。
5−4.中小企業診断士
中小企業診断士は、中小企業の経営をサポートする経営コンサルタントの国家資格です。
企業の経営状態を診断し、売上アップの戦略、コスト削減、新規事業の立ち上げなど、経営全般のアドバイスを行います。
この資格の最大の特徴は、これまでの会社員経験がそのまま活かせることです。営業経験があればマーケティング戦略、管理職経験があれば組織改革、経理経験があれば財務改善といったように、どんな職種の経験も武器になります。
合格者の約21%が50代以上です。机上の理論よりもビジネスの現場経験が重視される資格なので、ビジネス経験が豊富な方に適しています。
◉中小企業診断士の基本情報
| 学習期間の目安 | 1〜2年 |
| 合格者の年齢層 | 50代以上が約21% |
| 就職しやすさ | ★★★★☆ |
| 独立開業しやすさ | ★★★☆☆ |
※こちらの記事も読まれています。
→中小企業診断士の仕事内容は?何ができる?向いてる人やキャリアパスも紹介!
5−5.社労士(社会保険労務士)
社労士(社会保険労務士)は、労働・社会保険の専門家です。
企業の人事労務管理、年金相談、労働紛争の解決などを扱っています。働き方改革などによって、急激に需要が高まっている仕事です。
社労士の扱う仕事のなかでも、特に「年金相談」は、50代にとって身近なテーマです。
「いつから年金がもらえるか」「働きながらもらうとどうなるか」といった同世代の悩みに寄り添えるため、顧客から信頼を得やすいでしょう。
合格者の約27%が50代以上、最高齢合格者は81歳と、年齢を重ねてから挑戦する方が多い資格です。
◉社労士の基本情報
| 学習期間の目安 | 1〜2年 |
| 合格者の年齢層 | 50代以上が約27% |
| 就職しやすさ | ★★★☆☆ |
| 独立開業しやすさ | ★★★★☆ |
※こちらの記事も読まれています。
6.法律系の国家資格を目指すなら伊藤塾がおすすめ
50代からのセカンドキャリアとして法律系資格に興味を持たれた方は、ぜひ当コラムを運営する伊藤塾にご相談ください。
伊藤塾は、1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出してきた法律資格専門の受験指導校です。特に、司法試験、司法試験予備試験、司法書士試験などの難関法律資格で、圧倒的な合格実績を誇っています。
【2024年度 伊藤塾の合格実績】
・司法試験 :合格者1,592名中1,436名が伊藤塾を利用(合格者占有率 90.2%)
・予備試験 :合格者449名中405名が伊藤塾を利用(合格者占有率 90.2%)
・司法書士試験 :合格者737名中433名が伊藤塾を利用(合格者占有率 59%)
伊藤塾を利用して難関法律試験に合格しているのは、一部の限られた人だけではありません。
法律初学者からでも、定年後から勉強を始めた方でも、あるいは介護や家族の世話と両立しながらでも、多くの方が難関法律試験に合格しています。50代、60代の合格者も多数輩出しており、年齢を不安に感じる必要はありません。
さらに、合格後をサポートするさまざまな取り組みを実施していることも伊藤塾の特徴です。
合格したOB・OG同士の同窓会設立など、「法曹」「司法書士」「行政書士」「社会保険労務士」といった士業の方々がつながれる機会を積極的に提供し、合格後の活躍をサポートしています。
※こちらの記事も読まれています。
7.50代からのセカンドキャリア構築に関するQ&A
Q. 50代で退職して資格取得の勉強をする場合、金銭面での不安があります。
A. 独立開業を目指す場合、初期投資や開業後の収入が安定するまでの期間の生活費を考慮した貯蓄計画が重要になります。また、金銭面での不安がある場合には、すぐに退職せずに、働きながら学習を進めることも検討されるとよいでしょう。
Q. 50代で勉強と仕事や家庭との両立は現実的に可能なのでしょうか?
A. 仕事や家庭との両立を目指す場合、限られた時間の中で効率的に学習計画を立てる方法や、時には周囲の理解や協力を得るためのコミュニケーション、そして長期的な学習期間における精神的なサポートなどが重要になります。
詳しくは、こちらの記事で解説しています。
Q. 資格を取得して独立開業した際の成功するコツなどを教えてください。
A. これまでの職務経験を活かした専門分野の確立や、地域のネットワーク、オンラインでの情報発信などが必要です。
詳しくは、以下の記事をお読みください。
8.50代からのセカンドキャリアの築き方・まとめ
本記事では、50代からのセカンドキャリアの築き方と、長く活躍できる仕事の選択肢について解説しました。
以下にポイントをまとめます。
- セカンドキャリアを考えるためには、「これからどんな働き方をしたいかを考える」「これまでのキャリアを棚卸しする」「必要なスキル・資格を身につける」 の3つのステップが重要です。
- 特に、定年なく長く働きたい、これまでの経験を活かしたい、年齢がハンディにならない仕事がしたいという50代共通の願いを叶える選択肢として、「法律系の国家資格」がおすすめです。
- 法律系資格は、合格者の平均年齢が高く(例:司法書士では平均41歳。各資格で50代以上が約21〜27%を占める)、最高齢合格者も70〜81歳と、年齢がハンディになりにくい特徴があります。また、定年がなく独立開業も可能であり、これまでの人生経験が「傾聴力」「説明力」「人間としての信頼感」として強力な武器となります。
- 50代からのセカンドキャリアにおすすめの資格として、行政書士、司法書士、弁護士、中小企業診断士、社労士(社会保険労務士) が挙げられます。
- 「人生100年時代」の今、50代からの挑戦は決して遅くありません。
もしあなたが50代からのセカンドキャリアとして法律系国家資格に興味を持たれたなら、ぜひ伊藤塾にご相談ください。伊藤塾は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出してきた法律資格専門の受験指導校です。
法律初学者の方でも、定年後から勉強を始めた方でも、あるいは仕事や家事と両立しながらでも、多くの方が難関法律試験に合格しています。50代、60代の合格者も多数輩出しており、年齢を不安に感じる必要はありません。
あなたのこれまでの人生経験は、セカンドキャリアで法律家を目指す上で強力な武器となります。ぜひ伊藤塾で、あなたの理想のセカンドキャリアを実現するための第一歩を踏み出しましょう。
伊藤塾はあなたのセカンドキャリア構築を全力でサポートさせていただきます。